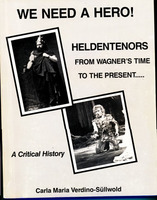WE NEED A HERO 表紙と目次 [WE NEED A HERO 1989刊]
資料3
前書き
1章:ヘルデンテノールとは
2章:ワーグナーの求めた英雄像
3章:最初のヘルデンテノールたち:
ティハチェク、ニーマン、シュノール・フォン・カロルスフェルト
4章:ワーグナー後:ヘルデンテノール・スタイルの登場
5章:レオ・スレザク
6章:ラウリッツ・メルヒオール
7章:マックス・ローレンツ と 苦難の時代
8章:フルトヴェングラーのヘルデンテノール:ルートヴィッヒ・ズートハウス
9章:セット・スヴァンホルム
10章:ヴォルフガング・ヴィントガッセンとニュー・バイロイト
11章:ジェス・トーマス
12章:多様化へ:
サンドール・コーンヤ、ジェイムズ・キング、ジョン・ヴィッカーズ
13章: ベルカント・ヘルデンテノール
ルネ・コロ、
ジークフリート・イェルザレム
14章:ペーター・ホフマンと総合芸術
ペーター・ホフマン、ワーグナーテノール そしてポップスター
レパートリー研究:
No.6 コンサートとイタリアのレパートリーなど
No.7:イドメネオ、タミーノ、ネローネ、オルフェオ、 マックス、バッカス、
フロレスタン、リエンチ、タンホイザー
No.8:エリック、ローゲ、ジークフリート
No.9:ジークムント
No.10:ワルター・フォン・シュトルツィング
No.11:パルジファル
No.12:ローエングリン
No.13:トリスタン
No.14:ポピューラ音楽、あるいはロック・ミュージック
No.15;批評など
No.16
後書き
WE NEED A HERO!
HELDENTENORS FROM WAGNER'S TIME TO THE PRESENT
.......A Critical History
Carla Maria Verdino-Süllwold
1989
ちょっとだけご紹介します〜著者とはメールで連絡がとれて、入手困難な録音をいくつか頂きました。HELDENTENORS FROM WAGNER'S TIME TO THE PRESENT
.......A Critical History
Carla Maria Verdino-Süllwold
1989
前書き
1章:ヘルデンテノールとは
2章:ワーグナーの求めた英雄像
3章:最初のヘルデンテノールたち:
ティハチェク、ニーマン、シュノール・フォン・カロルスフェルト
4章:ワーグナー後:ヘルデンテノール・スタイルの登場
5章:レオ・スレザク
6章:ラウリッツ・メルヒオール
7章:マックス・ローレンツ と 苦難の時代
8章:フルトヴェングラーのヘルデンテノール:ルートヴィッヒ・ズートハウス
9章:セット・スヴァンホルム
10章:ヴォルフガング・ヴィントガッセンとニュー・バイロイト
11章:ジェス・トーマス
12章:多様化へ:
サンドール・コーンヤ、ジェイムズ・キング、ジョン・ヴィッカーズ
13章: ベルカント・ヘルデンテノール
ルネ・コロ、
ジークフリート・イェルザレム
14章:ペーター・ホフマンと総合芸術
ペーター・ホフマン、ワーグナーテノール そしてポップスター
レパートリー研究:
No.6 コンサートとイタリアのレパートリーなど
No.7:イドメネオ、タミーノ、ネローネ、オルフェオ、 マックス、バッカス、
フロレスタン、リエンチ、タンホイザー
No.8:エリック、ローゲ、ジークフリート
No.9:ジークムント
No.10:ワルター・フォン・シュトルツィング
No.11:パルジファル
No.12:ローエングリン
No.13:トリスタン
No.14:ポピューラ音楽、あるいはロック・ミュージック
No.15;批評など
No.16
後書き
Carla Maria Verdino-Süllwold
NewYork 1989
14章 ペーター・ホフマン -16/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ペーター・ホフマンは、まだキャリアの中期にあって、まだ手がけていないワーグナーのヘルデン・テノール役を歌おうとしており、そして、新しいオペラ、ロック、ショー音楽、映画などを探究しようとしているけれど、彼の業績はすでに歴史的遺産であることは間違いない。どのような形で人々の記憶に残りたいと思うかというミヒャエル・レーネルト Michael Lehnert の質問に対して、歌手は、オペラを変えた世代の一員と思ってもらいたいと答えた。ホフマンが、歴史上、最も天分豊かな夢のようなヘルデン・テノールのひとりと呼ばれるようになることは、確実だと思う。歌手の技量は、声楽的にも、様式的にも、そして演劇的にも、英雄役の伝統の中でひとつの分岐点を成している。
ペーター・ホフマンの声は真性テノール echt Tenor と重いテノール schwer Tenor の響きが完璧な融合を見せている。広範囲にわたる音域、継ぎ目のなさ、音色の複雑で多様な表現力など、ホフマンの声は、輝かしさとバリトン的響きの両方を扱うことが可能だ。その歌唱スタイルは、清潔感あふれる、さわやかさを縦糸にして、そこに豊かな豪勢さと装飾のセンスの良さが加わる。ホフマンは、シュノール Schnorr の流れをくみ、19世紀のベル・カント的ヘルデン・テノールの伝統を受け継ぐ、理想的にぴったりと当てはまる存在の化身したものだ。勢い、規模、華やかさ、かろやかで抒情的な音の出し方ができる才能がある。しかし、また、戦後のヘルデン・テノールの室内音楽的繊細さと合わせて、洗練されたドイツ的レガート(この専門分野のための)というメルヒオール Melchior の伝統の良い部分をも継承している。このような中で、彼は、最良の伝統的要素を混合して、全体としては独自の応用範囲の広い声の様式を採っている。
ホフマンはこの分野のレーパートリーで一流の主要な歌手として席巻している。彼は、人為的に分離された、抒情的な声と英雄的な声、そして、ポピュラー音楽とクラシック音楽を隔てる、技術的かつ様式的な障壁をぬぐい去ろうとしている。音楽の価値と作品固有の本来的響きに対する尊敬の気持ちを人の心に知らぬまに忍び込ませつつ、聴き手の嗜好範囲を拡大し、何に耳を傾けるかの決定は、分類表示ではなく、音楽の質のみに基づくべきだと教えている。クラッシク音楽とポピュラー音楽の両方の多様なレパートリーによって、あらゆる年齢層、さまざまな気質の人々を含む広範囲で多様な背景をもつ聴衆を開拓してきた。オペラ愛好家を誘って彼のロック・コンサートに参加させたように、オペラ・ハウスにも新たな観客をもたらし、そこでは、古色蒼然とした役柄に対する、彼の新鮮で生き生きとした、今日的意味をもった解釈は、深い感動を与え、新たな心の琴線に触れた。
ペーター・ホフマンは、他のヘルデン・テノールのだれよりも、英雄的な役を歌う歌手に対する固定観念を壊し、見かけの上でも、個人的流儀の面でも自分のイメージを新たに創り上げ、ヘルデン・テノールの新たな理想形を生み出した。すなわち、すらりとした、スポーツマン・タイプで、視覚的に際立っている。誠実な人柄、気がおけない、独立心が強い、自分の考えを明らかにする、そして、血の通った人間。実際、歌手がオペラの英雄の概念を革命的に変革するのに利用した、彼が発散する魅力に不可欠なものが、こういった人間らしい側面である。19世紀の英雄を、現代的に焼き直すに際して、ホフマンはその神話的永遠性を、現代的感受性に変換した。歌手のすばらしい演奏は昔の英雄を、反逆者、アウトサイダー、寛大な救済者、傷つきやすく思いやりに満ちた人間といった、新たな典型的人物に作り直した。ホフマンは、オペラの伝統であるおとぎ話的物語を保ちつつ、写実的な様相を増幅して伝えた。伝統的な英雄の輝かしさや理想的な美しさを維持する一方で、演奏に独自性と型にはまらない新しさを醸し出している。その結果、彼の演奏は他に類をみないものになっている。
歌手の、舞台と観客の間に興奮の渦を巻き起こす才能は、ヘルデン・テノール史上には、事実上匹敵するものがない。エネルギーあふれる音の震動のうちどんなにささいなものであれ、全てが彼の声と演技の要素である。内奥から派生して観客に到達するや否や、劇場での演劇的体験を、参加体験に変える官能的な音と演技。ホフマンにとって、歌うことは、オルフェが成した不思議を再現する行為なのだ。彼にとってオペラは、演者と観客が、感情的な絆を共有する、終始一貫した完全な演劇でなければならない。ホフマンの手にかかると、音楽劇は、まさにワーグナーが望んだものになる。すなわち、言葉、台本、演技の完全な統合、内面的なドラマと外面的なドラマが結びついて一体となる。
デッカの有名な録音プロデューサーであるジョン・カルショー John Culshaw がかつてこう述べた。ある芸術形式が生き残るかどうかは、ひとつには、ある特定の時代における存在意義があるかどうか、またひとつには、コミュニケーションが成り立つように適応できるかということにかかっている。 カルショーの前提条件を受け入れるなら、ペーター・ホフマンこそは、私たちの時代においてオペラを生き延びさせることができる歌手のひとりであると確信を持って言うことができる。ヘルデン・テノールの歴史が今までに経験した、最大の徹底的な変化のいくつかは、ホフマンが歌う役者として、最初に引き起こした。彼の斬新な舞台動作と映画的リアリズムによって、英雄的演技においてはこれまで未知のものだった自然さを導入した。そして、その結果、オペラの質と分かりやすさに対する観客の期待値を永久的に変えてしまった。
このように、ペーター・ホフマンはヘルデン・テノールの分野に、全面的に生気を吹き込み、活性化したと言っても言い過ぎではない。神話と現代の現実を結びつけ、新たな演劇的標準を創り上げた。彼はこのレパートリーの特殊性と普遍性を共に肯定し、声楽のテクニックと様式によって現在を過去と結びつけた。ペーター・ホフマンは、総合芸術作品というワーグナーの理想を現実のものにしたのだ。ホフマンの芸術において、この言葉は普通以上に重大なこととして受け止められている。この総合芸術作品は、実現可能な純粋に審美的なものであるというだけでなく、完全に体験し共有できる音楽劇の理想像なのだ。
ペーター・ホフマンにとって、歌うことは危険を覚悟の冒険であって、予期せぬ危険に出遭う可能性も、たぐいまれな報いを得る可能性もある。演じる事は、感覚的喜びであると同時に、人間的感覚を超越した、魂を解放する、超自然的な喜びである。ホフマンにとって、音楽における、この開放感と喜びこそが、聴衆に受けとってもらえる贈り物であり、歌手に与えられる贈り物なのだ。歌手も聴衆も共に、この世の、はかなく、微妙で、最高に強烈な美を感じることができるということだ。彼は言う。
自由落下しながら飛ぶこと --- 飛ぶこと、この人間には根本的に不可能なことをすること --- 地球の重力にひっぱられることなく、鳥のように大地から完全に離れる瞬間。自由でありながら、頭のてっぺんからつま先まで制御されている。落ちていくこと、飛ぶこと、何も隠さずすべてをさらけ出すこと。歌うことは、うまくいったときには、この体験と似ている。
14章 ペーター・ホフマン -15/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ホフマン批評、あるいは、ホフマンたたき
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ホフマン批評、あるいは、ホフマンたたき
ペーター・ホフマンは度々マスコミにおいて激しい議論を巻き起こした。その成功の華々しさとその輝かしいカリスマが、時に過剰にジャーナリスティックな表現を誘発した。一方で、若さあふれるジークフリート、おとぎ話の英雄、黄金の声を持った本物のドイツ人の英雄と賞賛され、持ち上げられ、他方で、ロックをやってそのオペラの才能を低下させ、声を酷使していると非難されている。ホフマンの公演は、同じ時の全く同じ公演が、極端に矛盾した論評を受けることも普通である。一例として、1979年のローエングリンの新演出初日の批評を引用しよう。
エルネスト・ニューマンは、ローエングリンの演者は心理学者であると同時に、中世の詩に登場する学生というところだと主張した。ホフマンはこの役が要求するものに合っているとは言えない。彼の歌唱は、ロマンチックでなく、ごく一般的な情熱しかなく、言語表現による説得力が欠けている。終始一貫輝かしい舞台上の人物にふさわしくない。
ペーター・ホフマンは、欠点のない完璧な美しさで歌い、演じた。純粋美学原理さえ、その美しさを前にしては、無価値なものとして簡単に消滅してしまうほどだった。
ほかにも、その対照ぶりが、もっとおもしろいのもある。
彼の声には危険なバリトン的色彩が加わった。彼のローエングリンは、最高の声で響いてはいなかった。すなわち、彼はあまりにも低い声で歌おうとして悪戦苦闘しなければならなかった。 彼は聖杯物語のところで、非常に高い音で歌う傾向があったが、これは怪しい魅力に満ちた恍惚感を損なうことはなかった。
このような見解の多様性は、単なる個人的な好みや聴覚的差異の範疇を超えていることを示唆する。すなわち、隠された言外の意味を暗示している。それは、彼の歌に対する論評が存在するのと同じ分量、この歌手、彼自身に対して主観的に反応している論評があるということだ。
ペーター・ホフマンに対する論評の定式を観察すると、これは、ある程度、ジャン・ド・レシュケ Jean de Reszke、ジェス・トーマス Jess Thomas、ルネ・コロ Rene Kollo においても見られる傾向を映し出している。 評論家は有望な歌手を初めは、熱烈に賞賛し歓呼の声をあげて歓迎した。若い世代のテノールたちのなかでも最高の者といった具合だ。そして、バイロイトで彼を「発見」したことを、大げさに宣伝することに熱心だった。ペーター・ホフマンのパルジファルは、率直に言って、長年の希望がかなった充足感で、腰を抜かすほどだったと書かれたほどだ。1980年代の初め頃、ホフマンの国際的名声と歌う役者としての彼の魅力は、彼を文化的英雄にした。ホフマンは、音楽的、哲学的問題について率直な会話をすることを好み、ジャーナリスティックに作り上げられる「歌手戦争」や、私生活に関するうわさ話に巻き込まれることを避けて、こういった類のでっちあげを警戒して自制し続けていたにもかかわらず、彼の私生活、彼の人柄、彼の名声などは、ジャーナリストたちの興味と関心の的になった。
彼は、かつてこう言った。マスコミのだれかが、多くの聞くべきではない質問はしないという感覚を十分に持っていれば、すばらしいことだと思いますし、そういうことには、すぐ気がつきます。そして、更に付け加えた。賞賛や讃美とは正しく付き合うことができなければなりません。そして、賞賛されることが、人間、ホフマンに関することを、無差別に何でもかんでも、あばきたてることを要求される結果をもたらすものではないと思います。
このように、歌手について書かれた有名人の横顔的記事の多くは、斬新さが興味をひく、率直で、品の良い、控えめな論調だった。彼がロックの仕事に乗り出したとき、マスコミは吃驚仰天した。ホフマンの芸術が示す違いを盛んに書き立てることによって、まずは、この音楽的掟やぶりから利益を得た。例えばこうだ。
パルジファル歌手がロックンロールを歌う・・・ ロック歌手としての契約にサインしたペーター・ホフマンは、7月、バイロイト音楽祭を開幕する予定だ。ワーグナー歌手が、ロッカーとしてCBSとの三年契約にサインしたが、ワーグナー共同体の誰一人として、そのことで彼に反感を持っていない。
しかし、徐々に、この「掟破り」に恐るべき持続力があることが明らかになると共に、落ち着かない気分になる批評家も出て来た。評論家たちはホフマンを二つの世界の間のさすらい人と規定し、ホフマンのロックに関する二つの対照的な批評に、あらわれているように、こういうキャリアの進め方の有効性と賢明さに関する見解ははっきりと分かれた。
ペーター・ホフマンの自らを変化させる才能、未知の分野を探究する明白な勇気、そして、何にもまして、完全なロックの舞台を創造しようとする努力が、ベートーベン・ホールで、多くの拍手で迎えられた。
ジークフリートがエルビスに変身できないというのは本当だ。
ホフマンのロック歌唱への激しい反発は、何人かのオペラ批評家にもあって、彼らは気分を害した。こういう批評家たちは歌手の後を追いかけては、ののしることで復讐した。なんと大量の、客観性の完全に欠如した攻撃的な誹謗中傷キャンペーンがもくろまれたことか。1986年9月のニューヨーク・タイムズにおける、ウィル・クラッチフィールド の記述は、特定の上演を示すことなく、実際に聞かずに判断を下すという、このグループのやり方を証拠だてている。クラッチフィールド氏はホフマンが実際にワルキューレを歌った数日前に、彼がこの指環の連続公演に参加していることは不幸なことだった、なぜならば、昨年のメトで、ホフマンは万策尽きたという感じに聞こえたからだと書いた。そして、ドイツ、マスコミのゴシップ・ジャーナリストのうちの何人かは、さらに酷いデマ屋に身を落として、こんな記事を書いた。
トリスタンの月曜日の再演は、題名役の歌手、ペーター・ホフマンが、歌詞を歌うのが困難で悪戦苦闘しなければならなかったため、大失敗になった・・・ そこで、この上演の終わりに、祝祭劇場の総監督であるヴォルフガング・ワーグナーは、観客の不興から、スター・テノールをかばわざるを得なかった。
(事実は、歌詞は完璧だった。そして、付随的な出来事は不正確な話が参照されたものだった。)
しかし、否定的な反応の最近の背景に対抗して、歌手の業績に対して客観的な評価をしようという変わらぬ動きも生き続けた。多くの主要な新聞とヨーロッパとアメリカのオペラ雑誌によって代表される、この冷静で穏当な判断こそが、主として、歌手の継続的な数々の芸術的貢献を、肯定し、認識し続けている。そして、そういうものが批評する時には、特定の演奏について、慎重な判定が行われている。このようなジャーナリストのうち、卓越して有名な人物には、最近のハロルド・ローセンタール、ハリエット・ジョンソン、エーリヒ・ラップル 、ヨアヒム・カイザー Jなどがいる。彼らは終始一貫、テノールの芸術を擁護している。エーリッヒ・ラップルは、歌手の勝利と成功を楽しげに書いた。たとえば1983年にパルジファルについて、ペーター・ホフマンは、大爆発だった、そして、何とも言えない微妙で不思議な時間だった昨年よりもはるかに印象的でさえあったと述べたが、本調子でなかった公演についても同様に、敏感に反応して、次のように、詳しく記述している。
ペーター・ホフマンの繊細で、バリトン的な声は、リゲンツァの声とは特によく調和するのだが、残念ながら、初日の公演では調子がよくなかった・・・ 三幕で、彼は、だれもが不安になり、いらいらし、凍りついてしまうような状況に陥った・・・ 二幕のもの凄く感動的だった幕切れから、明らかに何も感じとらなかったに決まっている、二、三人のばかなブーイング・マニアは、歌手の状態に異議申し立てをするべきだと思った。これは恥ずべきことだ。というのは、ペーター・ホフマンにその役との類似性が感じられるのだから・・・ 彼の演技にも声にも悲劇が存在する。彼が今晩の公演の困難を一刻もはやく克服できるようにという願いが心からわき起こった。
このような所見こそが、ホフマン批評の典型的な潮流であり、国際的な、大小の新聞にも反映された。この夏、彼のもの凄い大成功だったバイロイト音楽祭のあと、かつて以上に多くの批評家が、あの一派に闘いを挑むかのように、歌手を強力に弁護し始めた。ゲルド・フェーザーは、ジークムント役のために、ホフマンの声質と水準に達するような理想の歌手が発見されるなんてことは早急にはあり得ないと書いた。一方、ヘルムート・ゼーリング は、こう断言した。
ペーター・ホフマンがワルキューレに戻って来たが、それは驚くべきすばらしさだった。(1976〜1980年のシェロー演出以来)彼のジークムントは、この演出のウェルズングに必要な、完璧な力強さ、完璧な輝かしさ、そして完璧な光沢を備えて、光り輝いた。誰もが、長年の時を経たホフマンの声はその絶頂期を過ぎてしまったと心配しているかもしれないが、考え直したほうがよい。彼のテノールは絶好調を示しており、音楽祭の観客を魅了した。さらに、彼の力強く、集中度の高い人物描写は、他の共演の歌役者たちを大いに刺激し鼓舞したので、この上演は、彼の水準に達していた。
こういった賞賛に実質的な評価と支援が加わって、ホフマンは音楽界の主役としての地位を享受した。彼を十年以上にわたってバイロイトのスターにしたヴォルフガング・ワーグナー、1982年にホフマンの規律に対する厳格さと芸術家としての手腕を、このような特別優れた規律感覚や共演者との協調性を今日の歌手に見出すのは難しいと、熱を込めて鮮やかに語ったジェイムズ・レヴァイン、あるいは、ホフマンを世界最高のヘルデン・テノールと呼んだレナート・バーンスタイン。
ペーター・ホフマンのキャリアが批評家たちによってそれほど脅かされないにしても、否定的な論評は完全になくすことはできないから、客観的な歴史研究者が、なんらかの調査、研究を続け、批判的な反論のある主要部分に言及しないわけにはいかない。ホフマンを非難することに熱心な人たちでさえもは、大抵は彼の驚くべき演劇的才能はいやでも認めざるを得ないらしいが、他方、彼の声に対する批判は、主としてビブラートをやり玉にあげるようだ。時に、びっくりするほど幅が広いと言われる。それから、彼の音色に、場合によって、聞き取れる、きめの粗さ、あるいは、ざらつき感が非難の的にされるようだ。彼らはこういうことを、絶え間ないワーグナー歌唱による声の鈍化のせいにしたがる。ホフマンのロック歌唱を前にしても、懐疑主義が大いにまかり通った。ホフマンのロックを非難するポピュラー評論家は、彼のロックはうすっぺらで、お上品だと論評し、それに対して、彼に好意的でないオペラ評論家は、彼はロックのせいで、声を台無しにしつつあるし、加えて、彼のロック歌唱は、オペラ歌手としての信頼性と厳粛さ、言いかえれば、オペラ歌手というものの品格、を傷つけていると主張する。その結果、ホフマンは声を損なう瀬戸際にあり、歌手としての将来性を危険にさらしているとまで言い出すものさえ少数ながら存在する。
一旦このような仮説を表明したからには、そのジャーナリストは、「証拠」を提供する義務があると思うようで、必要とあらば、「証拠」をでっちあげることさえも辞さない。これが実行された、二つのいやらしい例は、1987年7月のトリスタン後の扱われ方と、メトロポリタン歌劇場のジークフリート(「ジークフリート」のと、「神々の黄昏」の)をキャンセル決定をめぐる誇大宣伝だった。前者の場合、歌手は発熱とひどい胃の不調を抱えて歌っていて、医者たちは彼に抗生物質をめいっぱい注射しており、二幕の後では公演を放棄するように忠告したが、ホフマンが参加しなければ、トリスタンの初日はないことになるというわけで、医者の意見を聞かなかった。そして、実際、ブーイングをした妨害者は二人を数えただけで、その二人を除くバイロイトの観客は全員、立ち上がって拍手喝采した。こういう事実にもかかわらず、ドイツのいくつかの新聞には、翌日、「公演は中断」というのから、「歌詞を間違って歌うほどの酷い技術的障害」まで、ありとあらゆることを詰め込んだ大げさな見出しが踊った。最初のは真っ赤なウソで、他のは、アメリカでの同時生中継ラジオ放送を聞けば、間違っていることは容易にわかることだ。重症の気管支炎によるジークフリートのキャンセルの場合は、論評の断片がおおはしゃぎで、根拠のないうわさを振りまいたのだった。あまり評判のよくないドイツの新聞数社は、三幕で「声がかれた」とコメントしたり、「ロックが彼の声をだめにしたのか」と推測したりする記事を載せ、一紙などは、ある声の専門家の女性に意見を求めることまでしたのだが、後に、個人的にインタビューしたところ、彼女は間違った引用をされ、発言を操作されて当惑していると主張した。このようなジャーナリストの悪質な操作は、悲しいことに全くあまりにも普通に行われていることだが、それにしても、怒り心頭だ。
歴史研究者として物事を追究するのと同じように、ペーター・ホフマンの観察者としても注意深く考察するとき、 証拠もなければ、根拠も希薄なこれらの非難は、今なお、ちまたの関心を呼んでいるというか、なぜこういう拒絶症候群が存在するのかという疑問を持つのに十分な理由になるということがわかる。ヘルデン・テノールの歴史上には、似たようなマスコミのキャンペーンの先例が存在するのは確かな事実である。ワーグナーの重い役を歌ったあとのド・レシュケに対する酷い論述、あるいは、スレザークがニューヨークのマスコミと、そのトレモロに関して行った闘い、また、トーマスはその抒情的な声を拡大しすぎているという理論を裏付けようする批評家たちから、そのキャリアの終わりごろに彼が受けた手厳しい批判などを思い出しさえすればよい。要するに、全て偉大な歌手には、彼を悪く言う中傷者の割当が必ずあるものなのだ。
しかし、大げさに騒ぎ立てる種を鵜の目鷹の目で求めているマスコミの一見それとわかる記述や、「古い主役」に飽きて、新しいお気に入りを見つけようとするジャーナリスト的体質、また、声質に対する単なる好みの変化以外にも、ホフマンの場合は、なんらかの別の要素が存在し、これらこそが、議論を加熱させているように思われる。姿形も魅力的なうえ豊かな声の主だったフランコ・コレッリと非常に似通った状況だ。コレッリは、1960年代にイタリア・オペラのテノールのイメージを変えた。テノール役に生気を吹き込み、生き生きとよみがえらせたのだ。彼は、観客とオペラ・ハウスの経営陣のどちらからも同じように賞賛され、愛された。しかし、しばしば批評家の攻撃目標にされた。同じように、ホフマンも、声と姿が一体となった輝かしさを発散して、尋常ならざる雰囲気によって、観客の心を奪ってしまうものだから、一部の批評家は、困惑のあまり、彼の外見と中身が一致しているなんて信じ兼ねるという症状を呈しているのだ。オペラ史上、あれほど姿形がうつくしく、あれほど強力な声を持ち、あれほど人を納得させるように演じる歌手はほとんど存在したことがない。だから、批判的批評をしようとするとき、この魅力的な「セット」に「欠陥」を見つけようとしがちになるのだ。ドナール・ヘナーハン といった、このお仕事に献身している人たちは、極めて用心深く、非難するのは、より主観的な性格をもつ声に限定するように気をつけているのだけれど、歌手の外見にさえ見事に欠陥を見つけ出している。(歌手がメトロポリタン歌劇場にデビューしたとき、タイムズの批評欄には、ホフマン氏はそのほっそりとした体型が災いして、正しいドイツ人的英雄らしく、舞台を牛耳るわけにはいかなかったと書かれていた)
それから、また、ホフマンは、ロック・ミュージックに関わるなど、ヘルデン・テノールとしては、特異であり、私の考えでは、勇敢な決断だと思っているが、これがポピュラー界とクラシック音楽界の間にあって、しばしば両陣営からの十字砲火の標的にされることになった。両陣営とも、歌手の決断が、そのエネルギーを分割することになるのが不満の種だったのだ。最後に、ホフマンの芸術家としての、そして人間としての独立心は、歌手仲間のだれよりもはるかに強い。たとえば、彼は、テノールというものの伝統から、楽しげに逸脱している。これが、一部お偉方の代弁者たちには、まったくもって不愉快にちがいない。ホフマン自身このような攻撃の権威を認めていないのは、まさしく彼の功績であり、名誉である。
ホフマンはこういったことに対して、ユーモア感覚を持って距離をおき、超然とした態度を維持することによって、自分自身に対する批評を、並外れた自己認識と共に読むことができる。
主要な大新聞に無意味な攻撃批評が掲載され、小さな取るに足りない新聞に、私について細かいところまできちんと理解していて、私がうまくできなかったところにちゃんと気がついている人たちがいるということが今までにも、たまにありました。起こった事実を正確に書いてあると、びっくりします。
そして、反応することが必要な場合には、最も非常識な非難に対してさえ、内心の不屈の鉄のような意志とは裏腹に、にこにこしながら無頓着な様子で答えることができる。毀誉褒貶相半ばする論評があった1986年のトリスタンの後、彼はラジオのインタビューに答えた。
だれも批評家のために歌うわけではありません・・・ 批評家に肯定されようが、されまいが、私には関係がないことです・・・ 批評家を喜ばせるかどうかということに、私は影響されません。彼らの意見はなんというかなくてもいいものです。そんなことより大事なことは、私は自分自身のために、そして私を観てくれる観客のために歌うのです。だから、私と観客にとってうまくいけば、これこそが重要なことです。これに関しては、とても運がよかったです。
ペーター・ホフマンは、このインタビューを、批評家が書くことに関するマレーネ・ディートリッヒの発言を、彼の好みでもじって締めくくった。それが真実でない限り、それほど不愉快ではありませんと、彼は、自尊心を損なうことなく、穏やかに反論した。
そして、ペーター・ホフマンは、こういう類の否定的な論評がまったくと言い切っていいほど真実ではないことは確かなので落ち着いていられるというわけだ。彼の仕事のために努力している仲間たちにとって、彼が感動させ、喜ばせ、歌を愛する人に変えた無数の人々や、回想録、映像、録音を通して彼の遺産を客観的に批評することになる歴史研究者たち、そして、これらの、そして他の全ての音楽愛好家にとっては、完全に異なる真実が存在する。そして、その真実は間違いなく肯定的な言葉で語られるだろう。
14章 ペーター・ホフマン -14/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ポピュラー音楽、あるいはロック・ミュージック
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ポピュラー音楽、あるいはロック・ミュージック
ペーター・ホフマンのレパートリーを研究するなら、彼のロック・ミュージックを無視するわけにはいかないだろう。(こういうことを言うと眉をつりあげる人たち
には、ホフマン自身の非常にわかりやすい、「良い音楽と良くない音楽があるだけで、カテゴリーではなく、その音楽の質が違いを決めるのである」という意見を引用させてもらいたい。また、スレザークもメルヒオールもコロもみんなポピュラー音楽を歌っていることにも気づいてもらいたい。ただし、誰一人、ペーター・ホフマンの半分もよくない) ホフマンにとって、ロックやポップ・ミュージックは、歌手の他の多くのレパートリーのうちで、芸術歌唱と同じ位置を占めている。実際、ホフマンにとって、ロックは今日の歌曲Liederなのだ。すなわち、音楽の歴史を築いてきたクラシック歌曲と、現代の精神に語りかけるクラシック歌曲があるということだ。
ペーター・ホフマンのロックを巡る批評には、多くの問題点が浮上する。ロックにクラシックという語を当てはめられるのか。また、もしできるとして、ホフマンのクラシック・ロックは単なる物まねなのか、それとも、独立して成長しうる再創造的取り組みなのか。訓練された声がポピュラー音楽を、それにふさわしく、それらしく歌うことができるのか。あるいは、彼の歌唱はいわゆる「クロスオーバー」音楽なのか。この本はこういう問題を深く論じるものではないとしても、多少の回答は提示するべきだろう。ホフマンは「クラシック」という用語を、いかなる種類の音楽であれ、演奏し続ける価値のある音楽という意味に理解している。ホフマンにとって、クラシックはすべての世代に存在する。ベートーベンだったり、「リング」、あるいは、ロックであったりする。そして、彼は、いわゆるクラシック音楽と現代音楽の和解をもたらし、両ジャンルの音楽の過去と現在の名曲の生きた宝庫を残そうとしている。だが、優れた芸術家ならだれでもそうであるように、ペーター・ホフマンのロック歌唱(そういう意味では彼のオペラ歌唱も)単なる物まねではない。ポピュラー・ソングの、彼の編曲と様式化をオリジナルと比べると、彼がもたらした個性的な創造性の深さがわかる。(実のところ、彼が特にロックに価値を認めるのは、こういう創造の余地故なのだ。なぜならば、オペラ生産の場には、こういう創造力を生かす機会がないことが多いからだ)彼は、ロック・ミュージックの伝統のなかで、まさにオペラの伝統の中で彼がやっているのと同じことをしている。つまり、様式的に必要不可欠なことを学び、その音楽独自の特性をマスターするが、過去の演奏家を無批判に模倣しない。その音楽を消化吸収し、その様式を逸脱しない限界内で作り変え、その後に、聴衆に変化に富んだ新たな音楽的体験を提供する。彼が訓練された声を持っていることは、ポピュラー音楽における彼の成功の妨げではない。というのは、ポップスをまるでグランド・オペラのように歌っている多くのオペラ歌手仲間と違って、ペーター・ホフマンは、その時々の素材にその声を順応させる。すなわち、声量、母音の配置、リズム、フレージングを調節しているし、言語的に完璧に熟達している。(彼の歌の多くは全くなまりのない英語で歌われている)それに、ポップスでは許容される、実験的な試みや音楽的なルバートをためらわない。ロック歌手のホフマンは、あの上品ぶったジャンル、まさにホフマンの芸術と哲学が否定している境界をほのめかす新たな名称であるクロスオーバー・ミュージックの従事者ではない。ポップスをやっているとき 、ホフマンは、自らを「スラミングしているもの」とはみなさない。他のオペラ歌手は時にそのように見える。そうではなくて、ホフマンは、彼のロックを、心の底から好きな独自の表現形式として扱っており、そのための非凡な才能を有している。
ホフマンの段階的に発表されている七つのロックあるいはポップス・アルバムは、発展的挑戦を示している。最初の(ロック・クラシック)Rock Classics(ロック・クラシック 1982年)は、英語の名曲を集めている。二番目のPeter Hofmann2(ペーター・ホフマン2 1984年)は、新旧のバラードと自作のミニ・カンタータであるIvory Man(アイヴォリー・マン)が収められている。Bernstein on Broadway(ブロードウェイのバーンスタイン 1985年)は、デボラ・サッソンと共にナイトクラブのショーにおける表現形式を探究している。1985年のUnsre Zeit(我らの時代)はドイツ語による新しいロック。Peter Hofmann Live '86(ペーター・ホフマン ライヴ’86)は、彼の大ヒットしたツアーの雰囲気を伝える。Rock Classics II(ロック・クラシックII 1987年)はいくつかのスタイルのアメリカのスタンダード・ナンバーをより広い見地から集めている。そして、一番新しいMonuments(モニュメント 1988年)では、未知の分野に分け入った。新たなリサイタルの素材を創り上げることによって、クラシックとポップスの説得力のある融合を達成している。
ペーター・ホフマンのポップスやロックに対する嗜好は折衷的である。エルビス・プレスリー、ビートルズ、その他の重要なロック作品、カントリー・ウェスタン(country western songs)、スピリチュアル(spirituals)、フォーク(folk ballads)、キャバレー・ソング(cabaret songs)、新しい曲 - 原曲と権利取得によるもの - を広く含んでいる。彼が気に入っている作曲家も、ジョン・レノンから、ポール・サイモン、レナート・バーンスタイン、ビリー・ジョエル、彼のドイツ人仲間であるローランド・ヘック Roland Heck とゲルド・ケーテ Gerd Koethe まで、非常に広範囲に渡っている。彼のポピュラー音楽制作は、ジャズ、ソウル、50年代と60年代のロック、ブロードウェイの曲、電子音楽electronic music、さらには、クラシックの交響曲にさえ、その根を下ろしている。ホフマンにとって、音楽作品の質は、メロディーとハーモニー、効果的な声の流れ、そしてなによりも、その表現性と人の心に触れる力、こういうものが、確実に創り出されているかどうかによって決定される。そして、彼の広範囲な嗜好性にも関わらず、個々の作品の規範に対して敏感である。ホフマンは、聖杯物語と、ラブ・ミー・テンダー Love Me Tender のどちらを歌っても、各作品の独自性を彼が尊敬し、尊重していることは常に明白である。その作品特有の音楽的要求に対する明快な理解、ひとつの歌に内在する美しさを引き出そうとする熱意、演劇的存在としてのロックやポップスの歌Liederを伝える才能などが、ホフマンのポピュラー音楽の演奏者としての特徴である。
ホフマンの今なお成長し続けているポピュラー分野には、無数の歌が存在しているが、彼のロックの歌声の中から、いくつかの宝石に注目すれば、彼の全レパートリーの広がりと、彼の演奏の多様性を洞察できるだろう。
ブロードウェイのキャバレー歌手としては、親しみやすさと演劇性に恵まれている。バーンスタインのウェスト・サイド・ストーリーから抜粋した音楽の録音に接するとき、Bernstein on Broadway(ブロードウェイのバーンスタイン 1985年)におけるホフマンとサッソンの演奏ほど、すばらしい録音は存在しないと言っても過言ではない。オリジナル・キャスト・アルバムと比べてさえそうだ。ホフマンは必要不可欠なジャズのリズムに対する完璧なセンス、欠点のないディクション、息をのむほど美しい最弱音 pianissimi と官能的な色合いを伴う優雅な抒情性を示している。そして、テノールの高音域を楽々と自由に操っている。マリア(Maria)は、喜びにあふれた調子で歌われ、それが永遠に続くように感じられて、いつまでも耳に残って忘れられないほど、軽やかな高い最弱音で終わる。クール(Cool)は、挑発的で生意気な感じだ。サムウェア(Somewhere)には、本当の対話のような演劇的な強度と、その理想主義を納得させる輝きがある。ミサ(Mass)のシンプル・ソング(Simple Song)で、テノールもソプラノも、この聖歌に要求される純粋な音色を表現している。オペラとバーンスタインの劇作品は、類似性が強いとも言えるし、同時に微妙に異質であるとも言える。だから、この音楽の真価であるユニークさを表現するためには、ホフマンたちのような、こういう微妙さを自由に扱える熟練した歌手たちが必要だ。
バラード歌手としても、ホフマンは天性の腕前を披露する。彼は伝統的な英語のフォーク・バラードでも演劇的な語りでも、同等な気楽さを見せる。彼の、キャット・スティーヴンス Cat Stevens のMy Lady D'Abanvilleの技巧的な演奏は、この静かな曲を、オリジナルのフォーク形式を超えるものにしている。編曲部分を挟むことによって、単純な伴奏無しのメロディーから、ロックらしい複雑なハーモニーを持った曲に変わっている。彼の透明感のあるディクションと本物のテノールの音色はその歌の音楽的進行に繋がる連続性をもたらす黄金の糸となっている。The Gamblerといった南西部のバラードで、ホフマンはこの歌にまつわる挿話の世界を完全に構築する。演劇的独白の単刀直入さを伴ったメロディーを伝え、その地域独特の鼻声や地方色を正確に表現する。ホフマンはまた、Salty Dogのような海のバラードには、不気味で耳障りな不協和音と強烈な感情的傾向を与えることができる。それによって、力強い演劇的物語が生み出される。彼は船乗りの何かに取り憑かれたような声を出すことができるから、詩の輪郭の骨組みからほとばしる多彩で微妙な変化と陰影を感じ取ることができる。
カントリー・ウェスタンという表現形式において、ホフマンは、ゆっくりとしたものうげな調子の語りの雰囲気を出すことができるのと全く同じように、そのうねるようなリズムと鼻にかかったなまりを完璧に再現することができる。例えば、Please Come to Bostonは、細部に渡る豊かな表現がぎゅうぎゅう詰めになっていて、各節が歌手の旅の縮小された一章みたいだ。
スピリチュアルの歌い手として、ホフマンはその土地に生まれ育ったネイティブの歌い手たちにある「黒い響き」がないと批判されている。しかし、こういう見方は「霊魂 soul」という語を、限定的に解釈しているように思われる。この極めて宗教的な音楽で、ホフマンは「 霊魂 soul」という語の真の意味の核心を成す情熱と友愛の情を引き起こすことができる。彼の豊かな、力強い声が、He Ain't Heavy, He's My Brotherの中で、リード・ゴスペル・シンガーの白熱感で歌い上げるとき、テノールのすばらしいリズム感とこの歌の源が19世紀にあるという特殊性を超えた普遍性を伝える彼の才能に気づかされる。だから、ホフマン版のSailingも、苦悩から、神の愛と人間的な愛に対する信仰へと旅路を辿るさすらい人の独白になるのだ。ジョン・レノンのLet It Beでさえ、ホフマンの手にかかると現代のスピリチュアルになる。彼の澄んで軽快な感情の起伏に富んだ抒情的な長い輪郭線とくつろいだ雰囲気のフレージングによって、彼は単純で力強い肯定的メッセージを際立たせる。
ホフマンはまたより古いポピュラー音楽にも興味を示す。1930年代と1940年代の、大がかりなバンド・スウィング・ミュージックである。つぶやくような歌い方ではなく、甘美で流暢な優雅さで歌われる、彼のまろやかなコール・ポーター Cole Porter 的You're a ladyが、優れた一例である。
ホフマンがロック・シンガーとして、一番有名なのは、多分、エルビス・プレスリーの歌の再創造によってだろう。実際、彼のポップス歴はこの分野から始まり、この分野に深く関わり続けている。(エルビスは我々にとって崇拝の対象であると、ホフマンは聴衆に語っている)ホフマンは、「王たる」エルビスよりずっと豊かなフルヴォイスで、昔懐かしい曲に新しい性格を付与する。ホフマンの朝日の昇る家(House of the Risisng Sun)の持つ、人の感性に訴えるエネルギーは、彼がこの歌を初めてレコードとテレビ番組Hofmanns Trauemereien(ホフマンの夢)で歌ったとき、ドイツの聴衆を嵐に巻き込んだ。テノールは黒の衣装を着て、後ろから光りを当てたので、強烈な眼光だけがぎらぎら輝いていた。彼がマイクをぐいっとつかむと、そのライオンのように挑発的な動きに伴われて、攻撃的な音の洪水が押し寄せた。ホフマンの声は、うなり声、いとおしむ感じ、そして、高らかに響く音色から、その内奥からわき起こる貫き通すような叫び声へと、けだるく、ものうく発展しつつ、くすんだ感じになったり、地声になったり、セクシーになったりと代わる代わる、めまぐるしいほどに変化する。ホフマンは、朝日の昇る家(House of the Risisng Sun)でも、監獄ロック(Jailhause Rock)と同じように、荒れ狂い、むせかえるニューオリンズの熱気を、その演奏のエロチックな熱狂で彷彿とさせる。彼の歌は、音と抵抗し難い視覚的魅力を伴う身体表現が融合した、荒々しく生々しい創造活動だ。この二つの歌のあらわで、生々しい感情表現と野性的な強いリズムの対極として、エルビスのトレードマークである有名な、Love Me Tenderは、歌曲(Lied)のように歌われる。究極の誠実さと優しさを備えた声で、無伴奏で歌うとき、ホフマンの痛切な歌が、ひとりひとりの心に触れているような感じがする。
母国語でポピュラーを歌うことで、ドイツの聴衆に彼の魅力を直接的に伝えるという側面が加わる。1985年のアルバムUnsre Zeit(我らの時代)の個性的な珠玉(おおくはHeckとKoetheの作品である)のひとつひとつが、バラード形式に作曲された、ロックとジャズのリズムで縁取られた現代の吟遊詩人の詩だ。まとめられたものは、実質的に、時という複数の顔を持ったテーマに関する一連の瞑想になっている。ホフマンは、有名人であるがゆえ、ますます貴重なものになった時というものの、連続的でありながらつかの間のはかなさを探究する過程で、変化する様々な人格の仮面を身につける。ホフマンは、ひとつひとつの音による詩を、小さなドラマに仕立て、表情豊かに、現代的状況下における人間の心を探究する。中でもその感情的衝撃度と旋律線の明瞭さが際立つのがテノール自身が作曲したWenn ich ein Niemand warだ。この中で、歌手は自分の本質が愛されることを求めている。
しかし、ホフマンのオリジナル作品のなかでもっとも印象的なのは、彼のロック・ファンタジー、Ivory Manだ。これは、彼が「台本」を構想し、デボラ・サッソンがセンスのいい、高尚な英語の詩を書き、ローランド・ヘック Roland Heckと ゲルド・ゲート Gerd Koetheがその歌詞を複雑な楽譜に整えた。対話と説明から成る、このミニ・ロック・オペラは、宇宙飛行士の物語だ。アイヴォリー星が核兵器で滅びたあとに、たった一人生き残った宇宙飛行士が、滅亡の危機に瀕する地球にたどりつき、同じ運命から人類を救おうと努力する。この作品は複雑な構成を持っている。つまり、五つの声部に分かれていて、主導歌手と合唱の対話として演じられる。音楽は聖歌、スピリチュアル、フォーク・バラード、律動的なロックが織り交ぜられている。ホフマンは、愛は不可解なことではないこと、そして、だれもが自由なものとして生まれた、そのままに、だれもが自由な世界を創り上げることができると信じるキリストに似た、親切な救済者である中心人物を歌い、その関わり方によって、この作品の深い衝撃的な意味を納得させる。Ivory Manで、ホフマンとサッソンは、その歌の才能で現代的問題に立ち向かい、同時代人に向けて心から話しかけ、仲間である人々に、正気を保ち、愛と非暴力の哲学を受け入れるよう迫る。テノールが1984年のツアーで、このカンタータを歌ったとき、聴衆は手を取り合って、彼とともに、Paradise Shuffleを歌った。ホールの雰囲気は幸福感にあふれ、Ivory Man(アイボリー・マン)の予言する理想は単なるファンタジー以上のものになりうるのだという希望が目の前に見えているようだった。
ペーター・ホフマンはその最初の六つのポピュラー・アルバムのひとつひとつにおいて、自分の時代の歌をクラシックにしようと考えている。その七番目にリリースしたモニュメント Monumentsで、ある意味、初期の試みではレコードのB面的に見なされている基本路線に真っ向から取り組んでいる。モニュメント Monumentsでは、原曲に、現代的表現法で作られた変奏曲を移植して、クラシック音楽を大衆化しようとする。その結果、音楽的にも歌詞的にも革命的な融合を果たした、激しく鋭い議論を呼ぶアルバムができあがった。古いクラシック音楽を新しいやり方でする、ホフマンの演奏は、単に、編曲してポップスらしい詩を付け加えた以上のものを生み出している。実際のところ、それらは全く新しい創造的表現形式になっている。前時代の音楽は新しい曲--- 主題の変奏曲と言ってもいい ---を書くために、 役立つ主題を与える素材として求められている。つまり、モーツァルトのバッハ変奏曲と同じように有効であるし、ホフマンのクラシック・ポップスの全ての作品と同じように音楽的に刺激的である。時に、これらの変奏曲は、忠実に演奏されるクラシック作品に、たとえば、古いアリアに技巧的で、新鮮なカデンツァを付け加えるという形を取っている。また、時には、旋律と歌詞の両方を含めての聴覚的次元を増幅させるために音楽に詩を加えたりもする。多くは、原曲に対する良心的態度によって、原曲に非常に忠実でありながら、同時に原曲から根本的に逸脱している。人当たりのよい穏健なクロスオーバー・ポップスでは、決してない。イージー・リスニング的クラシック音楽でもない。そうではなくて、時代を超えたテーマを扱った独特の再創造作品であり、生きているクラシック音楽の、ホフマンによる定義を、まさに耳で確認できる形で示しているアルバムだといえよう。
このアルバムに収録された八つの歌は、すべて愛に関係があり、それが重層的に表現される。神聖な愛、人間的な愛、喜びにあふれた愛、悲しい愛、個人的な愛もあれば、集団的な愛もある。ホフマンは様式感のある、めくるめくような声で、彼の独自性の非常に強い、凝縮度の高いアルバムのうちのひとつと認められる作品を創り上げている。そこにはすばらしいメッセイージが一貫して込められている。すなわち、ベートーベンの「人間は互いに愛し合うべきものだ」という言葉に含まれるメッセージである。しかし、そこにはまた、型破りの選曲から生まれる卓越した音楽的一貫性が存在する。電子楽器と伝統的な楽器が、現代的オーケストラとして融合している。複数の声楽的スタイルも混ぜ合わされて驚くべき調和をみせる。音楽的正確さと果敢な再創造が併置されている。モニュメント Monumentsは、敬虔であると同時に聖像破壊的である。伝統に敬意を払う一方で、伝統に反逆している。鋭いレーザー光線で音楽間の壁を粉砕している。晴れやかに輝かしく、コンサート会場を良い音楽はひとつの言葉を歌うというペーター・ホフマンの信念を強烈に証明するように、深い感動で満たす。
レコードでは、前にも述べたように、さらにトスカとリゴレットのアリアのための巧みに考案されたカデンツァに加えて、ベートーベンの喜びの歌とバーンスタインのサムウェアの新たな編曲も歌っている。第九交響曲の音楽で、ホフマンはよりゆっくりしたテンポと英語の歌詞を選択して、聖歌的単純さを優先するために、ベートーベンのオーケストレーションの壮大さをある程度放棄している。彼の本物のテノールの声は合唱が喜びに満ちて舞い上がるのを数回に渡って助長する。ルバートをかけるわずかな機会を楽しみ、確かな、オペラ的高音で締めくくる。歌唱スタイルは、フォーク的聖歌からクラシックのコンサート・アリアまでの広がりの中で展開され、木管楽器群による純粋な昔の音楽の響きを強調するキーボードとパーカッションの混合的な楽器使いは、時代を超えた人間の兄弟愛を歌い上げる説得力あふれる新しい曲を生み出している。バーンスタインのサムウェアで、ペーター・ホフマンは、シンセサイザーのクレッシェンドと重いパーカッションで前奏を始め、place for us(私たちの場所)のイメージが想起されるときに、彼のピンと張った鋼のようなヴォーカル・ラインが、やっと穏やかに静まるという方法を採っている。豊で、まろやかな音色を、時にセクシーな黒人的響きに結びつけ、ゆっくりとしたテンポから、快活で激しいテンポへと変化する。非常に正確に精巧に造形された、心から納得できる願いを伝えようとして、彼が生み出すジャズ的なリズムと滑らかなレガートのリズムが交互にアクセントをつけて雄大に響く。
このレコードにはまたクラッシック音楽にポピュラーの詩をつけた三つの曲が入っている。なかでも最も強い印象を与えるのが、ホルスト作曲のThe Planets(惑星)から、木星の部分の最初の二つの動機に詩をつけたJoybringer/Sunrise(快楽の神〜木星)だ。ホフマンの最初の動機では、シンコペーションによって、二番目の動機では、対照的にゆっくりとした抒情的なテンポをとることによって、音楽的に明らかに変化が生じている。この希望への情熱的なメッセージのために、ホフマンは光沢のある朗々とした音色を当てている。ラフマニノフのピアノ協奏曲第二番のアダージョの主題では、E.Carmen の詩、All By Myselfで、壊れた関係と失われた時が、鼻にかかったバラードとして、歌われる。ホフマンにかかると、歌い手、つまり語り手が、痛切な感動を呼ぶ、実在の、孤独な老人として実際にそこに浮き上がって見えるように、歌は、効果的に性格づけて表現される。その低く太く、セクシーで、悲しげな、完璧なSprechgesang(話すように歌うこと)の抑揚は、人間の感情の思いつく限りの微妙に変化する色合いを生み出しており、だれもが納得してしまう。ショパンのプレリュード第20番ハ短調による、Barry ManilowのCould It Be Magicでは、ホフマンのロマンチックな声が、楽器群の醸し出す旋律の連続性を維持している。ここでは、キーボードとギター伴奏から、伝統的オーケストラ編成までの楽器が用いられ、キーボードとギター伴奏によるフォーク・バラードから、伝統的オーケストラ編成によるロマンチックなジャズのテンポまでの、変化に富んだ強弱感を生み出している。そして、そこに旋律のはっきりした声の流れが重なる。この曲でも、すべての曲と同じように、ホフマンの、考え抜かれた対照的なスタイルの選択の仕方はこのアルバムを貫く思想を強化している。
モニュメント Monumentsで、ペーター・ホフマンは、彼の好みのテーマを響かせるための、わくわくするような刺激的な新しいカギを発見した。すなわち、ポピュラー音楽とクラシック音楽の区分は人為的なものであること、音楽のすばらしい傑作、名曲は時代を超越していること、「クラッシック音楽」は聖遺物ではなく、生きている、さまざまな形で演奏されうる芸術作品であること、演奏家はこのソロ・リサイタルのような適切な場において、実験的なことをする権利があること、つまり、当然、独創的でなければならないが、聴衆に対して、挑戦的に新しいものを示し、進むべき新たな方向を探り、新たに鍛え直した音楽言語で彼らと交歓する権利が
あるということだ。
演奏会を開いて、聴衆を自らのロックとポップスに巻き込む彼の才能は、その一挙手一投足が、人を惹き付ける。それは彼がオペラで行うコミュニケーションと同じだ。三度のツアーでは、二時間半のショーを行ったが、照明と音響デザインは技術的に感嘆させられるもので、楽器の演奏者と合唱を歌う歌手の選択においても音楽的に非常に優れており、演出も振り付けもダイナミックで、趣味のよいものだった。同時代の多くのロック歌手たちと違って、ホフマンの最大の魅力は音楽的価値にある。すなわち、その感動を呼び起こす声と彼の編曲と伴奏の優秀さである。そのプログラムは目新しい企画とか、おしゃべりではなく、あくまでも歌が中心になっている。彼の舞台は直接的取り組み、つまり、あれこれ言い訳せずに、私たちの時代の歌であると彼が信じる「新しい音楽」を提供する者としての歌手独自の方法である。
ホフマンのロックは、この歌手の音楽的人格の重要な要素のひとつである。そのロックに、彼はオペラの舞台で学んだ技術を一部持ち込んでいる。すなわち、歌詞に対する鋭敏な感覚、聴き手の感情に訴える朗唱の鋭さ、演劇的な信憑性、そして、豊かな広がりをもった並み外れた声。彼は、ロックから、オペラに、彼のコミュニケーション・スタイルにある親密感、現実の世界との関連性、現代性をもたらす。彼は、両方の分野で、聴衆を獲得している。彼は、聴衆の聴くものに対する好みの幅を広げ、聴衆の音楽的固定観念を破壊し、あらゆるジャンルの質の高い作品に対する、聴衆の鋭い感性に気づかせる。ホフマンはロックのせいで声をだめにすると主張する偏狭な人たちは、否定し難い証拠によって正直な判断をしているのではなく、自分たちが達成できるかもしれない予言能力を信じる必要にかられているにすぎない。16年以上にわたって、自らの声で職業経験を積んで来ており、自分の声にある天賦の才能を大事にしている、テノール自身こそ、その声の使い方を決定する資格があるし、少なくとも歌を歌わない評論家よりは、はるかに適任であることは間違いない。そして、彼はこう主張する。ロックでは、ストレートな旋律だけが歌われます。しばらくこれをやるのは、歌の練習のようなものです。そして、確かに、ジェイムズ・レヴァインのような、非常に立派な音楽の専門家の見解こそが、このつまらない議論においては、重視されるべきだろう。指揮者は1982年にこう言った。
ロックとペーター・ホフマンに関する限り、彼の技術は確実でゆるぎない状態なので、ロックをやっても問題ないと思う。ロックが彼の声を駄目にするという考えは間違っている・・・ ロックではマイクを使うのだから。静かに穏やかに歌うことができる。そうすることは容易なことだ・・・ 彼は何であれ自分のすることを自分で決めるだけの知性を備えている・・・
ホフマンはロックを歌うことによって高尚な文化を貶めている、と主張する伝統主義者は、彼が20世紀のクラッシク音楽に含まれる歌唱文学を保存し普及させるために果たした重大な歴史的貢献を見落としている。
ルドルフ・ビングはかつてこんな皮肉を言った。世界的に優れた歌手たちはブルー・ジーンズがなかなか似合わない。しかし、ペーター・ホフマンにとっては、ジーンズが似合うかということは全く難しい問題ではない。むしろ、時代遅れのテノール的固定観念に合わせることのほうが難題だ。彼は自分自身と折り合いをつけて、うまくやっていくためには、常に聴き手に挑戦的に問いかけ続ける必要があるのだ。そのレパートリー、ライフスタイル、そしてキャリア、どれをとっても、彼が非常に大事にしている音楽の目標に忠実であり続けている。つまり、こういうことだ。音楽の意義は、人と人の間に、世代間に橋を架けられるということだと、私は確信している。これこそが私が歌う理由である。
※ ※ ※
14章 ペーター・ホフマン -13/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
トリスタン
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
トリスタン
ホフマンの役としてよく知られているヘルデンテノールの役のうちで、トリスタンはテノールに最高にやりがいのある難題をつきつける。ホフマンのこの作品の経験は1981年バーンスタインのコンサート形式上演にまでさかのぼるが、実際に舞台でトリスタンを演じたのは1986年からにすぎない。それでも、短期間のうちに、歴史に残るこの役の優れた演奏者たちのひとりであることを立証した。
![ワーグナー : 楽劇「トリスタンとイゾルデ」(演奏会) (Wagner : Tristan und Isolde / Leonard Bernstein | Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) [Blu-ray] [Live] [輸入盤] [日本語帯・解説付] ワーグナー : 楽劇「トリスタンとイゾルデ」(演奏会) (Wagner : Tristan und Isolde / Leonard Bernstein | Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) [Blu-ray] [Live] [輸入盤] [日本語帯・解説付]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/5102hisjadL._SL160_.jpg) ホフマンが三幕を一幕ごと、ライヴで、テレビ用に録画、録音するという企画で、はじめてのトリスタンを歌ったとき、(バーンスタインの公演は、テレビ用のビデオ撮りとレコード録音しながら、聴衆を前にして舞台で歌われた)ヨアヒム・カイザー Joachim Kaiser はこのように書いた。
ホフマンが三幕を一幕ごと、ライヴで、テレビ用に録画、録音するという企画で、はじめてのトリスタンを歌ったとき、(バーンスタインの公演は、テレビ用のビデオ撮りとレコード録音しながら、聴衆を前にして舞台で歌われた)ヨアヒム・カイザー Joachim Kaiser はこのように書いた。ペーター・ホフマンはこの十年間の偉大なトリスタンの仲間入りをした。彼はねたましいほどの若さだ。元気いっぱいで、エネルギーにあふれ、情熱的だ。楽譜の難しい部分も臆することなく表現した・・・ 凄いことだ。
そして、1983年にレコードが発売されたとき、ハロルド・ローゼンタール Harold Rosenthal は オペラ誌(Opera)批評で、この レコードは、棚にしまうときは、メルヒオールの隣に並べるべきだとまで述べた。
ヒルデガルト・ベーレンス、ベルント・ヴァイクル、イヴォンヌ・ミントンなどと共演したバーンスタインのトリスタンは、今までに作られたこのオペラの最高によくできたもののひとつだ。あえての極めてゆっくりとした速度、歌手たちのレガートと呼吸に支えられて、そのテンポを維持することが可能になり、指揮者はこの世のものならぬ官能的な、めったにないような美しさを備えた世界を創り出した。初のトリスタン役のホフマンは、この役の歌の美しさを強調した。最初の音から最後の音まで、非常に優美に歌うと同時に、複雑な心理描写をしている。バーンスタインの指揮の透明さと繊細さに併せて、ホフマンの声は月光のようなきらめきを示し、息をのむほどに抑えた強弱感を創出。この演奏は、暗い運命にとらえられた英雄を浮び上がらせる。はじめは、極端に抑圧された願望に悩まされているが、ついには、罪のうちに解放され、死に抱かれて恍惚のうちに、その願望は、成就する。
後に、ホフマンが1986年と1987年、バイロイトで出演した、ジャン・ピエール・ポネルとダニエル・バレンボイムのプロダクションでは、音楽的にも演劇的にも、強弱のつけ方は多少変化している。ここで、ホフマンは精力的な力強いテンポを維持し、様々な音楽的解釈が対立しているなか、あえて、トリスタンの武人的たくましさ、衝動的、反抗的側面を非常に強調している。カール・シューマン Karl Schumann はこの違いについて、バーンスタインのときは、その軟弱なトリスタンに合わせたため、ホフマンはあまり退廃的ではなかった。ポネルの刺激的な演出には、完全にはまっている と述べた。完全な舞台上演ということが、聴覚的にも視覚的にも、衝撃度の違いを生じさせた。いつでもそうなのだが、劇場の照明の下でこそ、ホフマンは、より刺激的に光り輝き、歌唱と演技が融合して、まばゆいほどの白熱した人物像を具現する。こうして、彼は新鮮で、成熟したトリスタンを創り上げた。それは、世界的に一流のトリスタンだった。アントニオ・リヴィオ Antonio Livio は、ペーター・ホフマンを含むバイロイトのキャストは、全体的に調和のある効果的な舞台を創り上げたが、特に演技と歌唱の調和は完璧であると評した。また、Opernweltは、いくつかの疑問点や不安な部分はあるにしても、ペーター・ホフマンはわずかの技術的修正で、バイロイトの歴史上、この役の偉大な演奏者のひとりになれるだろう・・・ 三幕は、非常に充実しており、生きて歌っている限り、ホフマンは輝く・・・と書いた。
1986年と1987年のラジオ放送を聴くと、彼の演奏が年々深まり続けているのがわかる。抒情的な旋律は、歌詞に対する感覚の鋭さと輝かしい陰影の付け方が強まっている。この役に、公演ごとに、いったいどのぐらい新しい色合いを見つけることができるのか、毎回驚かせられるほどだ。三幕、もの凄い恍惚感、大家の雰囲気、朗唱の輝かしさ、透明感を維持しつつ変わることのない強度、心を捕らえてはなさない確信に満ちた信念で、彼はこの役に没入する。そして、これが観客をカタルシスを伴う感情の波に巻き込み、押し流す。
声、身体、精神、これらの放つ輝きのまれな結合、これをホフマンは、この役に、もたらすことができる。そして、これこそが、彼を、トリスタン歌手の歴史において、独自のユニークなトリスタンにしている。いつもと同じように、ひとつひとつの音、ひとつひとつの言葉、ひとつひとつの動作、ひとつひとつの演劇的な刺激が、最大限の衝撃を引き起こすために、計算され尽くしている。スヴァンホルム、ローレンツ、ヴィントガッセンもそうだが、ホフマンは、声を表現力の限界まで持っていくことを恐れない。演劇的に強烈な効果を上げるために、単に美しい音にこだわることをしない。迫真の舞台のために必要とあらば、苦痛に、うめき、あえぎ、叫ぶ。しかし、先輩たちよりも激しくそういうことをしても、彼の生来の豊かな音色のお陰で、このような赤裸裸な演劇的真実の瞬間の破綻は相殺され、よりバランスのとれた声楽的演奏を示している。加えて、全体的な詩情にも違いが見られる。
一幕で、ホフマンは男性的な雄々しい騎士だ。マルケ王の友としてふさわしい。このときはまだ、彼にとって名誉と栄光こそが、何よりも重要だ。彼は、イゾルデから遠ざかり、よそよそしく振る舞うことで、彼女を恋する感情を隠す。しかし、語られることのない心の底の感情は、登場時の一節、Was ist's, Isolde? (何? イゾルデ?)で、彼女の名前を発する、その声の調子に明らかに示される。アイルランドの王女の非難をかわすために、自分の態度は慣習のせいにして、Frage die Sitte(しきたりです)と、即座にすげなく答える。イゾルデに呼ばれて、黙って従うときの、Begehrt Herrin was ihr wunscht(望むことを命じてください) は、音色は暗いが、金属的な基礎の上に暖かみのある、英雄的な響きを載せて、調子よく快活でさえある。シラブルごとに、ホフマンの複雑多様な側面を持つ彼の声の微妙な色彩感が、心の奥に潜む愛情と情欲をさらけ出す。水夫たちの声に、我に返ったトリスタンは、Wo sind wir?(ここはどこだ)と驚いて叫ぶ。そのとき、彼は男として、あらぬ空想に我を忘れたことを恥じている、名誉を忘れていたことを恥じている。彼は部下たちに慌てふためいた感じで、大声で、軍隊的な命令を発する。イゾルデが飲み物を差し出すと、死による救いを強く望む彼は喜んでそれを受けとる。死こそが心の内奥の苦悩から解放してくれる。ホフマンはTristans Ehre(トリスタンの名誉)の一節を、誇り高い、威厳あふれる響きで始めるが、全体を通して、感情がわずかに表面に現れるに任せている。例えば、hoechste Treu(最高の誠意)のところの小さなトレモロの中に、ホフマンのトリスタンは、対立する愛と義務に板挟みになっている葛藤を表わす。Trug des Herzens, Traum der Ahnung(心をあざむき、予感を夢見る)の愛撫するような弱音にのせて、彼は魅惑的な死の誘惑を伝える。二人は飲み物を口にする。二人はしばらく身動きもせずに立ち尽くす。彼は、究極的な傷つきやすい繊細さで、彼女の名前を、甘くやさしく歌う。それから、官能の衝動の暴力的な爆発が起こり、ホフマンのトリスタンは、強烈な金属的な音色で Seligste Frau!(至福の女性よ)と叫ぶと、カップを投げ捨て、イゾルデに突進する。短い終幕の愛のデュエットが無理なく、情熱的に歌われる。バレンボイム指揮のオーケストラの激しい荒れ狂うようなテンポに対抗して、ホフマンは、確実でゆるぎないイントネーションと高く舞い上がる旋律を保って、声楽的クライマックスへと上昇する。この狂喜乱舞の音楽にのって、ホフマンのトリスタンは、自らの愛欲によって混沌に突き落とされたように見える。そして、突如、狂ったような激しい自己肯定の爆発のなかで、彼の口から、O Wonne! toller Tuecke! O truggeweihtes Glueck(おお、無上の喜び。敵意に満ちた喜び。おお、錯覚に任せたこの至福) が流れ出る。この幕は、トリスタンのdas Wunderreich der Nacht und des Todes(夜と死の国)との運命的な関わりの最高潮で終わる。
第一幕、ホフマンはトリスタンの葛藤をまさに人間的に描写する。二人の愛のきわめて抽象的な様相を強調することを好むコロとは違って、ホフマンのトリスタンは完全に血と肉を備えた人間であり、彼の決断は、その結果を完璧に認識した上で行われる。ホフマンのトリスタンは、彼の演じるジークムントと同じように、愛のためにあえて破滅への道を選択するのだ。
二幕のうっとりするほど美しい音楽、愛の夜Leibesnachtで、ホフマンは申し分なくその義務を果たし、演劇的意味がしっかりと込められた美しい音色を生み出している
。狂おしくも激しいIsolde, Geliebte!(イゾルデ、愛する人!)と共に、舞台に走り出て、この幕のために、声をエネルギーの激しいほとばしりに合わせる。活気に満ちた、無分別な、あからさまな情欲、甘いLiebeswonne ihm lacht(愛の喜びが彼に微笑む)から、Dem tueckische Tage(ねたみ深い昼)に至るO dieses Licht! Wie lang verlosch es nicht!(おお、この光! この光が消えるまでにいったいどれほどを要したことか!)の繊細なエロティシズムまでの広がりの中で、微妙に変化する色合いで、明らかにされる情欲。O sink hernieder(ああ、降りて来い、愛の夜)の部分におけるホフマンの歌唱は、申し分なく美しい音楽性を示して、比類ない。最弱音で始め、柔らかい音色の確実な流れにのって半分の声mezza voceまで高まっていきながら、途切れるころのない、長いフレーズを保って、歓喜にあふれるSelbst dann bin ich der Welt(そして、私自身こそが世界だ)でクライマックスに達する。彼のso stuerben wir um ungetrennt(そして、私たちは共に死のう)は、弱音に満たされ、暗い響きに彩られ、軽々とした
最高音はきらびやかで、催眠術にかけられたように、魅惑的だ。ホフマンは、その力を示す瞬間に向かってのびやかに進むと、抑制していた力を誇示し、何とも美しく、響き渡るEwig!(永遠に!)で締めくくる。
この幕の終わりの部分の扱い方は、深い感動を呼ぶ。ホフマンが、その独白、Ah Koenig(ああ、王よ)によって、伝えることができる、威厳、優しさ、良心の呵責、超越感などは、まさに彼の演奏を特徴づける。彼は、あたかも、あの世から響いてくるような、ベールのかかったような声の弱音で歌い始める。まるで、彼の世界の基盤が足下で崩れ、友情と名誉に対する裏切りの支離滅裂な言い訳をつぶやくことしかできないかのように、半分の声mezza voceで続ける。トリスタンのマルケ王に対するうそ偽りのない忠誠心が、ホフマンの演奏では、はっきりとわかる。しかし、彼はまた、この独白をこの役の二度目の転換点を際立たせるために利用する。ホフマンは、その歌を壮大な挽歌に組み立てていくとき(これこそ、ワーグナーがシュノールのトリスタンに関して、もっとも賞賛した性質である)、罪悪感から自由になる。不朽不滅の愛の偉大さと悲劇的ジレンマの崇高さが、それ以外の思いを無意味なものとして消し去る。彼は、その愛の大きさを物語る、涙にぬれたような音色で、ob sie ihm folge?(彼女は彼に従うか)と、イゾルデの誠意を問う。弔いの陰うつさと奇妙にうっとりとさせる美しさで、Wunderreich der Nacht(夜の国)への旅を語る。(広範囲にわたる弱音と表現力豊かなレガートで)次第に威厳を増し、死の決意に向かう恍惚感のうちに高揚しつつ、dem Land das Tristan meint(トリスタンの思う国)の魅惑的なイメージを紡ぎ出す。何ものをも超越する力に鼓舞されて、心の底にうずまく失望感に満ちた怒りをあらわに、彼の純粋な思いに異議を唱えるメロートに向き直る。Wer wagt sein Leben an meiner?(私と命のやりとりをするのはだれだ)、彼は光沢のある鋼のような音色で叫ぶ。mein Freund war er(彼は私の友だった)は、苦々しいさげすみの気持ちと、弱々しい非難に満たされる。自分の犯した罪に対して、自己正当化を図るとき、トリスタンの血は煮えたぎっている。den Koenig den ich verriet(私は王を裏切った)は、自分の裏切りに対する恐れでいっぱいになって、あえぐように歌われる。ホフマンのトリスタンは、不誠実だった友への憎しみをみなぎらせて、Weh dir,Melot!(行くぞ、メロート) と歯ぎしりするように怒鳴ると、敵の刃に我が身を投げ出す。
ホフマンは二幕で、トリスタンという人物の心理的な側面をより深く洞察して見せる。はじめは、二種類の愛が完璧に表現されるのを見る。私たちは、苦しいほどの恍惚感の内に描き出される姿に、情欲に身をまかせすべてを焼き尽くすようなエロティシズムと理性的で力強い純粋な愛、この二つの愛の姿を、体験し、彼が選ばざるをえなかった悲劇を共有する。
三幕、どのすばらしいトリスタンにとってもそうでなければならないように、ホフマンも、そのもっとも優れた舞台を創り上げる。残酷な肉体的苦痛に正気を失い狂乱しながらも、失われることのない詩情あふれる思いによって、最終的に美しく昇華するトリスタンが描き出される。ヴィッカーズやトーマスと同じように、ホフマンも肉体的苦痛を、激しく現実的な感じでみせつけることができる。しかし、彼らと違うのは、彼はこの残酷な苦痛の描写に奇妙な美しさを醸すことができるということだ。すなわち、そのうっとりさせられる魅力は、英雄性が、退廃度を多少しのいでいること、より純粋な王国に対する肯定的な思いのほうが、否定すべき情欲より、多少まさっていることにある。
ホフマンはDie alte Weiseを、疲れ果て意気消沈した呈で、暗い、静かな、ものうい音色で始める。Wo war ich? Wo bin ich?(私はどこにいたのだ。 ここはどこなのだ)は、茫然自失、鈍く、抑揚のない単調さで歌われるが、Meine Herde(私の領民)では、混乱しつつも、多少意識が回復した感じだ。Wie kam ich her?(どうやって来たのか)には、消え入りそうな生命のぞっとするほど陰うつなはかなさが感じられ、このトリスタンは死の体験からゆっくりと回復しながら、目にしたものを途切れ途切れに思い起こす。Ich weiss es anders, doch kann ich dir nicht sagen(私は違うように思うが、話すことはできない)は、最弱音ではじまり、肉体から分離したような、死んだ人のような音色がDie Sonne sah'ich nicht(私は太陽を見なかった)の不吉な前兆となる落ち着いて憂うつな気分へと沈んでいく。Ur-Vergessen(究極の忘却)の弱音のフレーズには、透明な悟りがある。そして、weitem Reich der welter Nacht(世界の夜のはるかな王国に)の最弱音を超えるほどの超弱音は、厳かな畏敬の念を呈する。そのイメージがどんどんと高まっていき、Isolden scheint(イゾルデが輝いてそこに見える)で、ついに力強い調子で声になってほとばしる。それから、Verfluchter Tag mit deinem Schein(光り輝く、ねたみぶかい昼)で、自己を引き裂く苦しみに至る。そこは、呪いそのものが広く広がっていくような響きで歌われる。次に来るのは、墓場のように陰うつで、悲哀に満ちた、自責の念にさいなまれるBrennt sie Ewi diese Leuchte(この光は永遠に光り続けるのだろうか)だが、これは、優しく穏やかな旋律、Ach, Isolde, suesse Holde(ああ、美しく、たおやかなイゾルデ)へ、そして、半分の声mezza voceの、子どものように無邪気なwenn wird es Nacht im Haus?(ここはいつ夜がくるのか)へと変化していく。このように、ホフマンは最初の死から目覚めてからの一連の独白を、驚くほどの無邪気さと純粋さで、再び死に向かいあって、締めくくる。
二番目の独白は、言葉と音の狂気に満ちた奔流だ。Isolde kommt! Isold naht!(イゾルデが来る。 イゾルデが近づく)が、彼の口からほとばしるとき、しばしば美しさと耳障りな粗いざらつき感が見事に融合した音色が効果をあげている。O treue!(おお、なんという誠実さ)は、雄大でゆるぎない。クルヴェナルの友情に対する喜びにあふれた賛歌は、熱っぽい愛の表現だ。それは、das kannst du nicht leiden(あなたは、私の苦しみを体験することはできない)の、抑え難い極限の苦しみに縁取られている。ホフマンは、現実的に体力が消耗してくずおれる瀬戸際が訪れるときには、その声が弱まり、引いていくにまかせ、再びエネルギーを補給する。イゾルデの船を幻覚のうちに見て叫ぶDort streicht es am Riff! das schiff!(船が座礁しそうだ、ほら、あの船が)は、苦痛に満ちて耳障りに響く。鋼のように引き延ばされる旋律、疲れきってあえぐ最後の言葉、Kurvenal, siehst du es nicht?(クルヴェナル、おまえには見えないのか?)のうちに、声を使い尽くす。
三番目の独白で、ホフマンはトリスタンの高まる疲労困憊ぶりと譫妄状態をみせてくれるが、それは疲労困憊というものを徹底的に究明して見せているのであって、声の弱さではない。最後の官能的な一節、sehnen und sterben(憧れて、死ぬ)を長く引き延ばすとき、彼の愛からエロティシズムが完全に失われたことが、表現される。この後に続く、Sehnen! Sehnen!(あこがれる、あこがれる)は、悲哀と自責の念に満ちた、魂の苦悩の雄大かつ激烈な爆発だ。そして、この後、彼の思いは、アイルランドの乙女に対する甘くせつない気持ちへと戻っていく。はかなく傷つきやすい愛とあこがれの気持ちが再び死を目前にした幻覚の中に忍び込んでくる。ホフマンのトリスタンは、あの薬を呪う直前、幸せなころを身を切られるようなせつなさで思い起こす。Der Trank! Der Trank!(あの飲み物)の下降する叫びは、幻覚のもうろうとした状態を貫いて響き、この苦悩の人を、苦痛に満ちた現実の世界へと呼び戻す。この独白の最後の三分の一の、狂乱し、疲れ果て、うわ言へと移行しつつ、ホフマンはO dieser Sonne sengender Strahl(おお、この燃えるような太陽)を、怒りに満ちた非難の調子で、未来をはっきり見ているように歌う。彼はわめきちらし、口ぎたない言葉を吐き出し、犬のように歯をむいてうなり、金切り声でさけび、歌う。そうやって、彼の運命を定めた神々に対して死に物狂いの非難を浴びせる。最後の力を振り絞って、Verflucht sei fuerchtbarer Trank!(かの飲み物よ、のろわれてあれ)を、砕け散りそうな強さで叫ぶと、あたかもおおかた緊張から解放されたかのように、次の節、Verflucht wer dich gebraut(その薬を作った者こそのろわれよ)で、沈みこむように声の調子をおとし、力尽きて、気を失って倒れたとたんに、その声は、虚無のうちに消え果てる。悪夢から覚めると、ホフマンは、四番目の独白に優しく愛撫するようにとりかかる。波を越えてイゾルデがやってくる優美でたおやかな幻想を目の当たりにする独白。Wie selig hehr und mild gewandelt(彼女の
なんと穏やかに、美しく、優しく見えることか)での弱音の限りなく微妙な陰影のつけかたは、非常に美しく魅力的だ。そして、Ach! Isolde! Wie schoen bist du!(ああ、イゾルデ! あなたはなんと美しいのか!)で、美しく弧を描いて高まっていくクレッシェンドで、クライマックスを迎える。
ホフマンは刻々と移り変わる気分を生き生きと表現する。ひとつのフレーズのうちに、多様な感情のすべてを込める。そして、トリスタンの気分が高揚するたびに、この英雄に死がそれだけ近づいているという合図を送っている。船が視野に入ると、彼はDie Fragge(旗)と二度叫ぶが、二度目の声は、最初の活気あふれた声の、青ざめて疲れ果てた残り香のようだ。トリスタンの感情は、その負傷した身体がどれほど傷ついているかを思い知る。しかし、その混乱した頭の中で幻覚がいっそうはっきりとしたイメージを持つとき(ポネルの演出では、すべて熱にうかされた夢だ)、ホフマンは、再び、勇敢な騎士らしい英雄に立ち返る。彼は、その死に瀕した身体の深みから、引きちぎるようにして、船乗りの命令を、狂ったように叫ぶ。幻覚に見た船がその視界から消えると、Verloren!(失われた)と、暗い、長く引き延ばされた叫び声をあげる。そのsiehst du es endlich?(やっと見えたのか)は、あまりにも真に迫っているので、彼と共演するクルヴェナルは、トリスタンの狂喜乱舞の呈の喜びの声を否が応でも反映しないわけにはいかない。
死の思いに励まされるように、ホフマンは五番目の、すなわち最後の独白、O dieser Sonne(おお、この太陽)へと突進する。彼はここにトリスタンの自尊心、名誉、尊厳、そして、情欲の全てを注ぎ込む。これこそは、究極の皮肉に満ちた自己肯定、つまり、狂気のうちに、喜んで運命を選び取ることなのだ。彼は、身体的にも役と同一化しつつ、Tristan der Held in jubelnder Kraft(喜びに満ちた力強さを備えた英雄、トリスタン)では、鋭く下降するひとつひとつのシラブルに、幻想と現実を、激しく対比させる。Mit blutender Wunde bekaempf ich einst Morolden(かつて血を流してモロルドと闘った)で、その栄光に満ちた過去を回想するとき、彼は、この記憶を新たな啓示へと変化させる。本能的な直感のうちに、自分の出生、苦しみ、傷、そして愛の全てを、自己の避け難い運命である、死へとつなげる。Mit blutender Wunde erjag ich mir heut Isolden(血を流す傷によって、今イゾルデのもとへ飛び立とう)と、包帯を引きちぎりながら、狂気錯乱して叫ぶ。ホフマンは、傷が開いたこと、そして、沸き立つような血潮が流れ出ていることが、はっきりとわかる声で、愛する人の名を低くうめくように発する。彼は、昇華された苦痛の恍惚のうちに、舞台を横切ってよろめき進みながら、荒々しい、明らかにそうとわかる情欲に身をまかせた様子で、Heia mein Blut! Lustig nun fliesse!(さあ、我が血よ。 喜ばしく流れよ)を吐き出す。最後のフレーズは美しくないが、その迫真の呈は、心に強く訴えかけ感動的だ。破綻した声で、皮肉を込めて、die Leuchte! ha!(光りだ)と金切り声で叫ぶ。その我慢できないほどの耐え難い苦痛が死のめくるめくような輝きを見せているようだ。勝ち誇ったように、次第に強まり、クレッシェンドしていき、弱音の悲劇的なzu ihr!(彼女のもとへ)へと沈み込む長いフレーズのうちに、ホフマンのトリスタンは、隠された障害を超えて、あのめったに行き着くことのない王国へと全力を出し尽くす。その動かなくなった身体から、彼の最後の言葉、彼が幻覚のうちに見た救済者に対する呼びかけが、あふれ出る。イゾルデと、彼女の名前は次第に弱まり消えて行く、ディミヌエンドで発せられ、心臓の鼓動のようなつぶやきが、しずかに優しくゆっくりと途切れて終わる。
ペーター・ホフマンのトリスタンは、記念碑的創造物である。壮大な悲劇性、人間的直観に満ちている。直ちに畏敬の念をおこさせる、傷つきやすく繊細な英雄。哀調に満ちてはいるが、決して哀れっぽくはない人物。ロマンチックでありながら、現実的な次元に存在する騎士。反抗的で、探究心にあふれ、苦悩し、孤独にさいなまれながらも、不屈の精神的理想の故に負けることを知らない現代人。ホフマンのトリスタンの秘密、すなわち、彼の演奏を歴史上の他の演奏と区別しているものは、おそらく、このオペラの音楽的、哲学的核心に、教義にとらわれることなく率直に向かい合えるという、テノールの能力にあるのではないだろうか。ホフマンは、ヴィッカーズやコロと違って、このオペラの「危険なエロティシズム」を避ける必要性を感じていない。彼は、スヴァンホルムがやったように、中世騎士道で化粧することによって、この英雄の複雑な心理を体裁良く、美化してごまかすことをしないし、ヴィントガッセンがやったように、分裂した心の葛藤のせいで精神的に破綻をきたした人間として描くこともしない。彼は、むしろ勇敢にも、トリスタンの罪は、もしそう呼ぶ人がいるとすれば、崇高であり、トリスタンの自己認識では、すべてが勝利、死ぬことさえも勝利であるという、そんなトリスタンを描き出している。
このヘルデン・テノールの完全な分析において、ペーター・ホフマンは完璧な芸術家としての手腕と能力を示している。英雄的なスタミナ、強力な声楽的テクニック、先見的な演劇的集中度の強さ、台本に対する的を得た鋭敏さ、豊かな音楽性。この通過すべき役をやり遂げたことによって、ホフマンは、不朽のヘルデン・テノールたちの仲間としての場所を確保した。
14章 ペーター・ホフマン -12/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ローエングリン
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ローエングリン
パルジファルにおいて、ホフマンが生じさせることができる真実、精神性、感動は、彼のローエングリンの放つ輝きと存在感の成就にも貢献している。多くの先輩たちに比べて、ホフマンはローエングリンをより人間的な存在と見ることにしているから、彼のローエングリンは時に激しい論争を引き起こす。彼には白鳥の騎士の神々しさが欠けているとか、彼には奇妙に覚めているのが明らかな瞬間が見られるとか、非難している批評家も少数だが存在する。しかし、こういった見解は彼の役に対する考え方を誤解しているように思える。ペーター・ホフマンはローエングリンを人間性を希求する神の如き存在としてとらえる。初めから、その素性と気質のとらえどころのなさにだれもが気がつくが、同時に、この神の人間性を求める強い力を確信させられる。 ローエングリンの神の如き有り様と、道徳的な心理状態の間で彼が保つ緊張感はホフマンの舞台に著しい劇的な力を与える。すなわち、情熱的な人間の感情と、人間の世界とは隔絶した霊的な世界へと引き返す冷静さが、交互に示されるのを目にする。 歌手はローエングリンを異次元からの来訪者として描き出す。つまり、ローエングリンは、人間の愛の形の中で自らが救済されることを求めて、救済者たらんとする者なのだ。(テレビ番組、ホフマンの夢の中で、歌手はスーパーマン・ローエングリンを創作した。その場面はこの二つのお話の現代的な類似点を映し出していた。彼はアイヴォリー・マンIvory Manでも似たようなことをしている。)
多くの論争は、ローエングリンを歌うのに必要とされる「正しい種類の声」ということにも焦点が当てられる(一般的にイタリア的な方法対ドイツ的な方法に分けられる)。Donal Henahanのような人たちは、ホフマンの声は軽すぎると思っている。その一方で、反対に、彼の声は、抒情性が不足していると非難している人たちもいる。あまりにもヘルデン・テノールでありすぎるというのだ。これらの見解は、両極端を示す批評の面白い例として、ヘルデン・テノール史研究者としての著者の興味をひく。私の耳にとって、ホフマンは理想的なローエングリンの声、すなわち、十分な重さ、本当に英雄だと思わせてくれる英雄的な信憑性、さらに、この英雄を誇り高いドイツ人にするいかにもドイツ的な歌い回し、そして、同時に、ワーグナーが要求したベル・カント的な柔軟で豊かな音色を備えた声を持っている。
ホフマンはバイロイトでは、1979年ゲッツ・フリードリヒ演出で、初めてこの役を担当した。当時、Rudolph Joeckle ルドルフ・ジェックルはホフマンを若く、共感を呼ぶ、まさに人間的なローエングリンとして賞賛した。Erich Rappl エーリッヒ・ラップルはペーター・ホフマンはこの役に、立派な落ち着いた男らしさと同時に、純潔の輝かしさと若者らしい情熱をもたらし、舞台で演じられているのだということを忘れさせるほどだった。彼の生き生きとして活気にあふれる、柔軟なテノールは、抒情的な優雅さに満ちている・・・ と、熱狂的に書いた。 Richard Bernstein リチャード・バーンスタインは、圧倒的な批評の熱狂をこんなエピグラムで端的に総括した。ペーター・ホフマンこそが、まさにローエングリンなのだ。
バイロイト音楽祭で、この役を始めて歌った1979年、高音を出すときに、多少構えるような感じが聞き取れたにしても、その声は、甘い優しさ、明瞭なフレージング、彼の演奏の特徴である劇的な陰影などを、示していた。1980年には、ホフマンの声にはもうどんな「破綻」も聞き取れなかった。新たに統合され輝かしさを増した声は、今や、ローエングリンの難しい音域tessituraで、楽々と鳴り響いた。高いAの音も易々と出ていた。そして、1981年にこのプロダクションは録画され、各種の賞受賞作品となるクラッシク音楽映画を、ホフマンは創り上げた。
ホフマンは、バイロイトでの三シーズンに渡るフリードリヒ演出に加えて、世界中のあらゆる主要オペラ・ハウスで白鳥の騎士を引き受けた。ほとんどが、彼のために企画された新演出だった。1980年1月24日のメト・デビューに際して、Speight Jenkins ジェンキンズはニューヨーク・ポストに、ペーター・ホフマンはローエングリンとして印象的なデビューを果たした。彼の息をのむほど表現力にあふれた、「はるかな国に In fernam Land」、そして、非常に強い印象を与えたエルザとの別れ。その最後の高いAの音は、最初のそれと同様に新鮮だった。と書いた。彼は、ハンブルクでもマンチェスターでも(1981年)同じような感じで賞賛された。1982年にはこの役でパリのガルニエ宮のシーズン開幕公演に出演、チューリッヒとモスクワでも新演出初日を飾った。1983年、ベルリンとスカラ座にローエングリン・デビューした。カラヤンは彼を1984年のザルツブルクに招いた。1985年から1986年にかけて、アウグスト・エヴァーディングの新演出でニューヨーク、メトロポリタン歌劇場。1986年と1988年にはマンハイムとウィーンでこの役を歌った。1987年にはヴェネチアはフェニーチェ座の特別なワーグナー記念公演で、熱狂的な拍手喝采を巻き起こした。Corriere della Sera は、このときのことを、こう書いた。ペーター・ホフマンは、非常に説得力のある白鳥の騎士だ。声楽的には完璧。白い衣装をつけた姿といい、理想的な人間の物腰といい言うべき言葉もないほどだ。
たくさんある声だけの記録に合わせて、二つの映像を研究すれば、彼の演劇的な考えの発展経過がわかる。ホフマンの演奏は、1979年のバイロイト・デビュー以来、視覚的にも成長している。詩情あふれる美しさと器量の大きさが増している。1980年バイロイトの白鳥の騎士は、最近のものに比べて、より厳しく、より怒りっぽく、激しい。その後、より円熟した優しさと底流にあるより大きな苦しみに満たされるようになった。それに、彼の成熟した声の芸術性がスコアの中により繊細なニュアンスを見出すようになった。さらには、微妙な強弱感に加えて、ホフマンは神話が人間の姿をとった息をのむほどにロマンチックな人物を
完璧な状態に仕上げて見せた。あらゆる意味で、ペーター・ホフマンが描き出すローエングリン像は、神とみまごうばかりだ。
声楽的にも演劇的にも、ホフマンは題材を完璧にコントロールしている。彼は、この役を自信たっぷりに演じるが、これがローエングリンに不可欠である畏敬の念を、納得ずくで、生じさせる。歌う役者としての彼の集中振りは、これは常に傑出しているが、ローエングリンでは特に顕著である。その独唱は、全体に対しては非常に個性的な主張となり、二重唱は真の対話になる。その動作には無駄がなく、大げさに動くことがないにも関わらず、その動作の意味が、力強くはっきりと伝わってくる。特に、そのほっそりとして表現力豊な手を用いて、多くを伝える。彼は、冷たく抑制的であると同時に激しく情熱的なオーラを強烈に放つ。彼が放つ純潔さと官能性が、彼の白鳥の騎士を卓越したレベルにまで高めている。
きらきら光る白い鎧を身にけた、その輝くばかりの登場の瞬間から、おとぎ話が現実となって、目の前に出現する。舞台奥で、Nun sei bedank と、白鳥への別れを告げるとき、その柔らかい黄金の輝きに満たされた声は、完全に劇場中へと伝わっていく。音色は、純粋で、節度が保たれ、抒情的であり、磨かれた金属のような鋭さに彩られている。粗さはなく、充実している。哀愁があり、優雅である。この異世界からの訪問者はゆっくりと向きを変え、まるである種、神がかった恍惚状態で、この世における自らの道を探るかのように、魔法にかけられたように、ほんのしばらくじっとたたずむ。それから、彼は勇気をふるって、エルザを探し求める。 (演出によって、目だけで求めたり、あるいは、直接彼女のそばに行く) そして、最後に国王ハインリッヒに向き直り、著しく注意をひく声で、あいさつする。彼の全体的な物腰こそは、貴族的崇高さの典型を示している。すらりとした直立の美しい立ち姿、誇り高く、穏やかで優しく、好戦的なところはなく、内面的な輝きがあふれている。テルラムントに対する挑戦には敵対心はまったく見られない。それは、敵対心ではなく、無実の罪を着せられた乙女を守るという、彼の使命を誠実に表明するものだ。ホフマンはここで無私無欲のローエングリンを描き出す。実際のところ、彼のエルザに対する態度には気後れさえ見られる。より深い愛の源泉の存在を示しつつ、情熱の目覚めを感じつつ、二人は控えめに視線を合わせる。穏やかに優しく、しかし、断固とした調子で、Nie sollst du mich befragen. . . .(決して尋ねてはならぬ・・・)という言葉を彼は発する。命令を繰り返すとき、声はより強く響き、目には神秘的な炎が燃えている。エルザが、命令に従うことを誓うと、ホフマンの顔には言いようのない喜びの表情がひろがる。敬虔で冷たい輝きが緩んで、太陽の光のような人間的な暖かさがのぞく。彼は、Elsa, ich leibe dich(エルザ、私はあなたを愛す)と、柔らかく、愛撫するかのように歌う。その優しい弱声、mezza voceメッツァ・ヴォーチェは、彼が感じている幸福を示す。テルラムントとの闘いは、写実的な場合も、様式化されている場合も、英雄的に鳴り響く勝利宣言Um Gottes Sieg(神の勝利によって)は、常に威厳を失わない。テルラムントを許すところから、一幕終了の合唱を通じて、ホフマンは二つの世界に立つことになった英雄の気持ちを伝える。彼を導く神の助けを賛美し、その一点を見つめる眼差しは、この世の混沌とテルラムント一味の嘆きではなく、彼方にある聖杯の王国を見ているのだと感じさせられる。それでも、愛情に満ちた人間的な関わりのはじまりを示す甘いおののきも味わっている。一幕の終わりまでに、ホフマンのローエングリンは、彼がブラバントに来ることになった奇跡を達成し、エルザを守ることに成功するが、彼もまた奇跡の体験者となる。すなわち、彼自身が人間性を獲得するきっかけを与えられることになる。
二幕では、ローエングリンは後半まで登場しないけれど、オルトルートの告発騒ぎのただ中への彼の登場は、その場を静まり返らせるような輝きをもたらす。was ist's?(一体何事か)、彼はいらだった様子でこう尋ねるが、その、暴力に対する嫌悪感によって封じ込められた激しい怒りは、その鋼のような青さできらめく眼差しと、その声の金属的な鋭さに、現れるだけだ。彼は、軽蔑の念に満ちた声で、オルトルートに立ち去るように命じる。Was seh'ich! Das unsel'ge Weib bei dir!(私は一体何を見ているのか。あの汚れた女があなたと共にいるとは)と、エルザに対して嘆きを表わし、さらに、オルトルートに向かって、steht ab von ihr!(彼女から離れろ)と命じる。それから、再びエルザに向き直り、疑いの心をおこす毒が、彼女の心に入らなかったかと尋ねる。その声の感情の高ぶりを示す音色と彼の物腰の奇妙な親密感には、彼の恐れがはっきりとあらわれている。テルラムントを阻止して、彼はエルザに優しく問いかけ続ける。In deiner Hand, in deiner Treu, liegt alles Glueckes Pfand(あなたの手の中でこそ、あなたの誠実さによってこそ、私の喜びは保証されるのです)Laesst nicht des Zweifels Macht dich ruh'n. Willst du die Frage an mich tun?(疑いの力に捕らえられないでほしい。私に質問したいのですか) 再び、一人の異邦人として二つの世界の間で、苦悩に氷ついたように立ち尽くし、彼女の答えを待っている。彼女が否定し、その愛情を再確認すると、彼の人間の心が再び息を吹き返し、彼女に優しく手を伸ばし、涙にぬれた彼女を慰め、元気づけるように微笑みかけ、穏やかに彼女を愛撫する。彼の愛撫の汚れのなさは、強烈なエロティシズムと紙一重だ。彼のHeil dir! Nun laesst vor Gott uns geh'n(さあ、エルザ、共に神の前へ行こう) は、ゆっくりと、荘重に行われる。彼女の名前のところで、非常に美しく魅力的に、徐々に弱められ、最弱音に至り、つづく旋律では、弱音が維持される。それは、快い確信、神と神による美しい被創造物に対する深い敬愛の念、そして、壊れやすい幸福を表わす響きだ。柔らかに歌われる理由は、大声で吹聴するには、あまりにも貴重な感情だからだ。次に続く合唱の中でさえ、そのように明示してあれば、ホフマンは柔らかく歌う。彼のローエングリンは出来事を内省的に熟考する。劇的に適切な瞬間には力強く強まっていく声で、美しく調和した音の満ち引きを創り出す。このような最高の瞬間において、彼と比較できる者はまず存在しない。そもそも、その複雑に絡まった思考網も、やはり異邦人のものだ。合唱が完了すると、このローエングリンは手を伸ばして、威厳をもって、エルザを教会へと導く。オルトルートが最後のチャンスとばかり彼らの行く手を阻むとき、ホフマンのローエングリンは片手を一度振って彼女を追い払う。小さいが、強制力を感じさせる、有無を言わさぬ動作だ。
三幕、花嫁の部屋の場は、まさにホフマンの傑作、彼の名人芸が見られる。ワーグナーの有名な結婚行進曲のメロディーが始まると、彼が登場する。輝くばかりにゆったりとした気楽さを備えた人間らしい生き生きとした雰囲気をまとっている。ホフマンは、エルザに対する徹底的な集中状態とその魅惑的な身体によって、抑制された性欲の持つ刺激的な感覚を生じさせる。純潔によって抑えられている情熱と粗野な本質が新たに見えてくる。彼は、Das suesse Lied verhalt; wie sind allein(甘い調べも消えて、私たちは二人きりだ)を、抒情的に愛情いっぱいに始める。優しく、彼女の瞳、彼女の顔、髪、全身を、突き刺すような憧れの眼差しで探っている。ホフマンは、恍惚感を含むフレーズで、mezza voce, piano, pianissimoなどの弱音を多用する。エルザが禁じられた問いを発する前、あふれるような詩情をたたえて歌われるAtmest du nicht mit mir die suessen Dufte?(甘くかぐわしい香りを感じないのか)において、ありったけの愛を、喜びの気持ち全開で、高らかに宣言する。怒りと悲しみに打ちひしがれて膝をついてくずおれる前の崇高な瞬間、彼は、彼女の口を閉じようとして手を伸ばす。それは、愛を守ろうとする死に物狂いの行動だ。すべてが失われた苦痛を感じつつ、両手で頭を抱え込むが、猛烈な苦しみを抑えることはできない。目には涙があふれる。彼のHoechstes Vertrau'n(私は深く信頼した)は暗く、困惑に満ちて、とても説得力がある。激しい非難としては、愛情に欠けていないし、理解さえ示している。しかし、痛みを和らげることはできない。エルザが差し出した剣を受けとるために機械的に振り向いたとたん、感情の失せた自動的な動作で押し入ったテルラムントを切り捨てる。そして、力なく立ち尽くす様子は、内面的な崩壊をまざまざと表わし、Weh' nun ist all unser Glueck dahin(ああ、今や私たちの幸福はすべて失われてしまった)で、彼の英雄的な声は悲しげなつぶやきに変わる。
ホフマンの演奏では、この瞬間から、ローエングリンは、人間と愛し合いたいという激しい欲求故の永遠の悲しみを知ってしまったにもかかわらず、その人間的な愛の喜びを、彼は得ることができないことを知っている。心をかき乱され、空虚な気持ちを抱えつつも、はるか彼方からもたらされる墓場のように陰気な落ち着きが彼を支配する。彼はブラバントの貴族たちにテルラムントの亡骸を運び出すよう威丈高に命令し、寛大な態度で、エルザの侍女たちを呼ぶ。そして、これが最後とばかり花嫁を振り返って、限りなく穏やかに立ち去る。
エルザの要求に答えるべく、王の前に再び現れたとき、ホフマンのローエングリンは、苦悩に傷ついた様子を示している。まばゆい衣装を身につけてはいても、(ゲッツ・フリードリヒの演出では彼の苦悶を強調するために極めて不吉な黒い鎧だが、エヴァーディングの演出では銀色と金色の衣装)その明らかに落ち着かない態度と合わせて、顔の表情もその不安感を伝える。彼は、苦悩に満ちて、檻の中の動物のように舞台を歩き回る。己の運命と向かい合う力を死に物狂いで求めるかのように舞台上を大股で歩き回る。エルザの前で止まったとき、彼は自らが必要としていたものに気がつく。そのとき、彼の怒りは緩み、全てを許す愛に変わる。身体をぴんと伸ばしすくっと立って、非常に威厳のある態度で、ホフマンのローエングリンは、最高の瞬間、Vor aller welt, vor Koenig und vor Reich, enthuelle mein Geheimnis(全世界と王と王国の前で、秘密を明かす)を、極めて軽い弱音で、はっきりと明瞭に歌う。
聖杯物語の前にある静寂の数秒間は、ホフマンの舞台では、常に特別な感動を呼ぶ。この突き刺すような静寂の中に、卓越した詩人の孤独感を漂わせる。目を閉じ、勇気を奮い立たせ、彼が出発してきた霊的な王国との超自然的な交信を求めつつ、神々しい魂の苦悩と栄光を表わすように、「遥かな国に」を歌い始める。傷ついた死すべき人間の状態から、崇高な神性を備えた状態へと、フレーズを一つずつ微妙に積み重ねて構築しつつ、移行していく。ホフマンにとって、聖杯物語はローエングリンの自己無罪評決、ブラバント王国に対して、自らの正義の力と聖なる出自を証明するもの、挫折したエルザに対して、自分の無傷を正当化すること、愛のうちに、その中の一人として生きようと望んだ人間の共同体に向けて発せられる威厳に満ちた最後通告なのだ。しかし、さらには、それは彼自身の霊性の証、聖杯が彼を見捨てていないことを明示するもの、その神に由来する力が、まだ彼の内にあるということ、その純潔が彼の人間への憧れを許すということなのだ。ホフマンの内的な確信の強さと集中力が彼の音楽に流れ込む。甘く優しい黄金のように輝く弱音mezza voceで、彼は始める。独特な透明で、充実した響きの中で、モンサルヴァートに関する宣言は、異次元世界の光に包まれる。Taubeというところは完璧な弱音pianoである。そこには、彼がその霊的確信に触れ、恩恵にあずかる力を取り戻したことを暗示する説明し難いとらえどころのない感情が込められている。それから、徐々に高らかに響く終わりの部分へと盛り上がっていく。Mein Vater Parsifal traegt seine Krone; sein Ritter ich -- bin Lohengrin gennant(父は王冠をいただくパルジファル、私はその騎士、ローエングリン)と、誇らしく名乗りをあげるのだ。歓喜にあふれる音楽が渦巻くように高まっていくとき、ホフマンは忘我の一瞬、目を閉じ、我に返って目を開ける。そして、上空に視線をさまよわせ、聖なる兄弟愛への再編入の印である白鳥の影を求めて、傷つきやすい雰囲気を漂わせて、祈る。白鳥が目に入ったとき、彼の目には厳粛な炎がきらめく。白鳥が登場しないエヴァーディングの演出では、これが唯一の印である。彼は向きを変えて去ろうとするが、再び戻らざるを得ない。エルザとの悲しみにあふれた別れはローエングリンの深い悲劇性を物語る。死すべき人間に混じってのつかの間の滞在でローエングリンが得たものは苦痛に満ちた思い出だけだ。それでも、エルザへ向けての情熱的な旋律でこの思い出を語るとき、涙を抑えて歌うフレーズで、All meine Gedanken(私の考えのすべて) と断言するとき、最後の抱擁のあと頭を上げて、Leb'wohl!(さらば)と声を振り絞るとき、ホフマンは、ローエングリンの悲劇とは、すなわちローエングリンのすばらしさでもあると信じさせてしまう。はるか彼方の、孤独な、神の如き騎士が人間の心を手に入れたのだ。
舞台奥に大股で進むと、輝くような別れの歌が歌われる。その登場と同じように、黄金色に輝き、甘美で流れるような歌だが、今度は感情的な陰影が深まっている。音質の、肉体から魂が抜け出たような異次元的な感じは弱まって、私たちと同じ次元に立つ、より現実的な存在という感じが強まっている。オルトルーのあざけりを含む呪いの言葉に、彼は突如霊感にうたれる。ゴットフリートにかけられた魔法を解こうと、全身全霊を込めた黙祷によって、ホフマンのローエングリンは聖杯にへりくだった気持ちで祈願する。それは、いわば後ろ髪をひかれる思いで、地上の愛の証をやっとのことで後に残して、再び救済者として旅立つ、過ちをおかしたさすらい人の嘆願なのだ。
ペーター・ホフマンは常に最高のローエングリンのひとりとして舞台に立つ。 すなわち、我々の時代つまり、冷笑的な雰囲気の支配的な時代に通用する、現代人である私たちの心に訴える、並外れて非凡なローエングリン像を見せてくれる。どうしようもないほど頑固で疑り深い人でさえ、信じさせてしまうほどだ。彼のローエングリンは、不思議な人ではあるが、超自然的というよりは、むしろ人間的だ。ローエングリンは奇跡ではないと、ホフマン自身がたびたび語っている。ローエングリン自体が奇跡というよりはむしろ、テノールの考えによれば、ローエングリンの地上への旅を奇跡にするのは、白鳥の騎士の能力なのだ。すなわち、彼は、愛し、犠牲を受け入れ、救済することができる。
14章 ペーター・ホフマン -11/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
パルジファル
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
パルジファル
シュトルツィングが巧みな人間的な演奏を要求するとすれば、パルジファルは、傷つきやすい繊細さを持ったヒーローであることを納得させるだけでなく、霊感を受けた神々しさと同時に人間らしさを備えたヒーローを創造するというほとんど不可能なことに対する挑戦である。ペーター・ホフマンがパルジファルと関わった経歴は膨大である。実際、多くの批評家や観客にとって、彼こそは、私たちの時代のパルジファルその人である。私にとって、彼こそが、空前絶後のパルジファルだ。
今日のワーグナー・テノールのうちで、一体だれが彼と同じように役と一体化できるだろうか、ファビアン・ガステリアー Fabian Gastellier は、1985年のジェームズ・レヴァイン指揮のバイロイト音楽祭公演のレコードを 聴いたあと、こう問いかけた。1980年、ヘルベルト・フォン・カラヤンの復活祭音楽祭のあと、Opernwelt誌は、我々はザルツブルクで、何年も待ち望んでいた、そのパルジファルを得た。ペーター・ホフマンはパルジファルとして、私たちを納得させた・・・ 彼はこの役の造形の仕方を完璧に知っている。
 ホフマンがはじめてパルジファルを歌ったのは、1976年、四ヶ月の間に三つの新演出で歌うという空前の状況だった。同年のバイロイト音楽祭、ヴォルフガング・ワーグナー(ゲッツ・フリードリヒと書いてあるが、明らかな間違い)演出の公演のラジオ放送は、彼の豊かで、暗い、力強い声を示している。同じ年のジークムント同様、弱音の微妙な陰影感はまだ十分とは言えないが、すでに役との内面的一体感と説得力は十分だ。三十歳代の、情緒あふれる、優雅で、前途有望な男の、完璧に洞察力に満ちた舞台だ。これらの特質は、その声の微妙さと歌詞に対する鋭敏で的を得た感性と併せて、ホフマンがこの役を歌い続けた13年を通して深まっていくことになる。
ホフマンがはじめてパルジファルを歌ったのは、1976年、四ヶ月の間に三つの新演出で歌うという空前の状況だった。同年のバイロイト音楽祭、ヴォルフガング・ワーグナー(ゲッツ・フリードリヒと書いてあるが、明らかな間違い)演出の公演のラジオ放送は、彼の豊かで、暗い、力強い声を示している。同じ年のジークムント同様、弱音の微妙な陰影感はまだ十分とは言えないが、すでに役との内面的一体感と説得力は十分だ。三十歳代の、情緒あふれる、優雅で、前途有望な男の、完璧に洞察力に満ちた舞台だ。これらの特質は、その声の微妙さと歌詞に対する鋭敏で的を得た感性と併せて、ホフマンがこの役を歌い続けた13年を通して深まっていくことになる。1980年、カラヤンはホフマンをザルツブルクの清らかな愚か者にと招き、この公演を録音した。このレコード録音は、カラヤンの芸術作品としてだけでなく、歌手の芸術作品として、特別に重要な仕事を記録している。この音盤はGrand Prix du Disque、Grand Premio del Disco、Tokyo Record Academy Prize、Orphee d'Or、Grammyなど、各種の賞を受け、このオペラの古典的な解釈となっている。ホフマンは、カラヤンがいかに歌手たちを巧みに導き、二幕を一気に通して録音したかということ、そして、終わったときには目に涙を浮かべていたことを、畏敬の念をもって回想している。実に、またとないような唯一無比の経験だったと歌手は思い出を語った。この録音の張りつめた集中度と声楽的美しさはホフマンの数あるすばらしいオペラの録音のなかで、このレコードを特別なものにしている。歌手の声は1980年までにほのかにきらめく微妙な輝度を獲得しており、レガートのなめらかなフレージングはこの上なく美しく、今までに録音されたもっとも繊細なパルジファルのなかでも、その強弱感のダイナミックさは際立っている。
同じ年、ホフマンはコヴェント・ガーデンの、テリー・ハンズ Terry Hands の現代に時代を移した演出で、パルジファル役を演じ、1982年4月には、ニューヨークに登場した。ニューヨーク・ポストの故ハリエット・ジョンソン Harriet Johnson は熱狂的に語った。非常にすぐれた歌手兼役者、ホフマンはオペラに対する熱狂を煽り立て、あれこれ思考することなど忘れさせ、ただひたすら、要するに、彼はすばらしい! としか言えない状態に陥らせるだろう1982年7月、歌手は、ジークムントでそうだったように、バイロイトの百年記念上演でパルジファルを歌うという特別の栄誉を与えられた。ゲッツ・フリードリヒの演出で、ホフマンは再び個人的な成功を収めた。ヨアヒム・カイザー Joahim Kaiser は次のように評した。
フリードリヒの手のうちで、ペーター・ホフマンは魅力的で、元気のいいパルジファルであるだけでなく、(天真爛漫さにもかかわらず)もの凄く貴族的な、避け難い宿命的な性質を醸している。ということは、徹頭徹尾完全に理想的なパルジファルだということだ。
この演出の公演は、録音され、レコードとして保存されたが、ホフマンの最高の舞台に数えられる。特別の公演である1982年7月27日のものは、ラジオ放送されたが、これはオペラにおけるヘルデン・テノールの歴史を通じて、対抗できる者はないと確信する。技術的にとてつもなく完璧であり、役柄が非常に深く知覚され、はっきりと示される。ということは、決して消え去ることなく記憶されるオペラ上演のひとつであることは間違いない。
ヴェネチアのフェニーチェ劇場も、1983年、この都市のワーグナー百年記念に、あの純な愚か者を再現するためにホフマンを招き、ホフマンは、その活発に元気いっぱいに、恍惚感に満ちて歌われる英雄らしさ故に、再び激賞された。(ピエール・ルイジ・ピッツィの演出で、歌手は、骨の折れる二幕を歌う前に、エネルギッシュな激しい振り付けで、クリングゾールの手先たちとの闘いを演じた)
それ以後も歌手は世界中の主要なオペラ・ハウスでパルジファルを歌い続けている。1984年、1985年、1988年には再びバイロイトで、1985年ボンで、1986年ニューヨーク、1987年ハンブルク、1988年ウィーンとバルセロナで。ジークムント同様、この役は特別に彼のものと言える。彼はこの役に声楽的深さと、人の心を揺り動かさずにはおかない演劇的美しさをもたらす。
ホフマンのパルジファル観は(ジークムントと同じように)次第に成長し、強調するところが移行している。もっとも最近の公演は、深い感動を呼ぶ最後の聖杯の奉仕の場面まで、緊張を保って、演劇的クライマックスを遅らせることで、三幕に演劇的重要性を加えている。一幕では武器を捨てる天衣無縫さを、二幕ではむせかえるような男っぽさの性的魅力を、保ちつつ、三幕に、以前に増して賢者らしさと人間らしい精神性を与える。彼の舞台は、ワーグナーの創造した世界の崇高さを発見させ、観客をこの作品の共同体的神秘を共有しているという気分にさせる。
ホフマンの演じる人物の声楽的かつ演劇的な微妙な変化を概観しよう。
パルジファルは一幕で歌うところは少ないが、ホフマンはここで、この役の性格に注意を集中させようとする。オーケストラの弦楽器の競走するような音でパルジファルの登場が知らされる瞬間から、その圧倒的なエネルギーを感じさせられる。舞台に飛び出してくるホフマンは、元気で強情そうな少年を私たちに見せてくれる。Gewiss! Im Fluge treff'ich was fliegt! (当たり前さ。飛んでるものならなんだって射るよ) ときっぱり言うとき、ちょっと生意気な感じがする。若きジークフリートと同じように、このパルジファルは、ちょっと尊大な感じがする。困難に出会ったことがないのだ。しかし、グルネマンツに優しく諭されると、すぐに心を動かされる。穏やかに柔らかく発せられるDas weiss ich nicht(知らなかった) は、すでにこの少年が変わったことを示している。彼は驚き、動揺して、深い後悔の念と謙虚さを感じている。ホフマンは必ず、この自己認識の瞬間を、彼が射殺した白鳥に向けた身体的反応をもって強調する。その物体に触れるのをいやがって、後ずさりする。この真実を拒否する様子は、表面的なものにすぎず、彼の内面では良心が目覚めたことがわかる。グルネマンツとクンドリーとの母親についての会話では、自立と愛着が奇妙に入り交じっているのがわかる。hoch geboren(高貴な生まれ)のパルジファルの性質が、その時、示される。彼はIch habe eine Mutter(母がいる)と、自分の出自を誇らしく述べる。そして、ジークムントのような大胆さで、母ヘルツライデと別れて、森での自立した生活を詳しく物語る。それでもまだ、クンドリーが母の死を語ると動物的な怒りの発作を起こし八つ当たりする。Tot! Meine Mutter! Wer Sagt's(お母さんが、死んだって。だれがそんなことを言うんだ)と、怒って叫び、こどもっぽい、力任せの拒絶の態度をとる。グルネマンツに押さえつけられたとき、ホフマンのパルジファルは感情の高まりに打ちのめされている。彼のIch verschmachte(気が遠くなるような気持ちがする)は、身体的衰弱を表現するのではなく、感じやすい傷つきやすさを、静かに厳かに告げている。聖杯について、グルネマンツに尋ねるいくつかの質問は、まるで子どものような単純さで歌われる。たとえば、Wer ist gut?(善い人とはだれですか)は、完全の無防備さ故に、聴き手の心に直接飛び込んでくる。本当に少しの旋律と動作で、ホフマンはこの無邪気で罪のない若者の矛盾した言動、穏やかさと攻撃性、幼稚さ、愛と霊的なものに対する探究心など、を表現する。
場面転換の場面とそれに続く聖杯儀式の場面で、ホフマンは完璧な存在感を保持する。たとえば、森を通り抜けて行く箇所は、彼の不思議そうに、星のように輝く眼差しと堂々とした足取りがまぶしい。聖杯の聖堂内、ホフマンは驚きで声も立てず、訳が分からず、惚けたように見つめる。聖杯が高く掲げられ、アンフォルタスが苦痛のため息をもらす瞬間の動作は極めて印象的だ。ホフマンは片手を杯に伸ばすが、即座にその手をひっこめ、孤独感と疎外感の突き刺さるようなに苦痛のうちに、はっきりと形をとらない知識を捉えようと身悶えする。こういう決定的な場面における、ホフマンの身体表現は全て、パルジファルの子どもらしい性質が殻を破ろうとしていることを伝える。(ゲッツ・フリードリヒの演出では、少しの間、胎児に後退した姿勢を取る) 聖杯秘義が終わると、このパルジファルは完璧に変化している。ジョセフ・キャンプベル Joseph Campbell の言葉を借りれば、彼は、英雄を冒険へと招き寄せる呼び声を聞いたのだ。冒険の旅に出発する準備が整ったのだ。
ホフマンは、花の乙女たちのところに現れるとき、大人の男らしさが目覚めようとしている雰囲気を醸す。闘いで、そして、その色気で、彼はその魅惑的な男らしさを見せつける。花の乙女たちの最初の誘惑に対する戸惑いには、一部のテノールにあるような不感症さは全くない。それは、むしろ未知の異質な感覚に対する、甘い、穏やかな受容の気分を呈する。母の面影はまだ非常に強い感覚で存在しており、so nannte traumend mich einst die Mutter(母がかつて夢の中で私をそう呼んだ) を、ホフマンは柔らかな暖かい感じで紡ぎ、弱音で終わる。初めてクンドリーの呼びかけに応えるとき、その豊かな響きは無意識のうちに性的魅力を醸し出す。ヘルツライデの記憶と、現実の身体を持ってそこにまざまざと存在するクンドリーの間で、彼は引き裂かれ、混乱する。彼は陰うつな悲しみと深い感情のこもった声でWehe! Was tat ich? Wo war ich?(ああ、私は何をしたのか。私はどこにいたのか)と、後ずさりする。Mutter, koennte ich vergessen?(母を、私は忘れたのか) を、柔らかく、瞑想的に歌う。一番最後の音節を、彼は後悔の気持ちを込めてつぶやく。クンドリーの誘惑の効果は、彼の身体表現と彼が放つ強い心理的表現によって、視覚的に示される。エロチックな感じが伝わってくるのが感じられる。彼の四肢の震えと微妙に変化する顔の表情に、パルジファルの本能的衝動と自我の悶えが表現されているのが見て取れる。Amfortas! Die Wunde!(アンフォルタス! あの傷!) は、突き刺すような叫びだ。魂から直接にほとばしるその響きの奔流は、充実した声で長く保持される。嘆きというものをまさに発見した叫びだ。Hier! Hier!によって、身体と霊魂の両方にある、その傷を、猛烈な激しさではっきりと指し示していることを表現する。続く独白の部分は、各節とも非常に美しくなめらかなレガートで形成される。(特に指揮者、レヴァインのゆったりとしたテンポに合わせて引き延ばされる) 強烈で、苦悩に満ちたO Qual der Liebe(おお、愛の痛み)、あたたかで、穏やかな、畏敬の念にうたれたDas heil'ge Blut ergluht(聖なる血潮が輝く)、知に目覚める苦痛に満ちたつぶやきのEs starrt der Blick dumpf(私は黙して見つめた)、はらわたをえぐるような苦痛に身をよじるようなすさまじい悲痛ゆえに、言葉さえも震えるdie Klage, ach die Klage(叫び声、ああ、叫び声)、これら各節の中から生まれる響き。その感情の爆発するund ich der Tor, der Feige(そして、私は、愚かな卑怯者)の苦悩の様は、聴き手の心を揺さぶり、続いて、このテノールの構築する気高い祈りは、対抗できるテノールは一人もいないほどだ。Erloeser, rette mich(救い主よ、私を救ってください)では、loesの部分の高いFの音から、erともうひとつrette michの部分の高いEの音まで、美しく弧を描いて次第に弱くディミヌエンドしていく。情緒あふれる声で、あたかも不滅の自己の存在をはじめて見出したかのように、hier in die Seele(ここ、私の魂の中へ)とつぶやく。恍惚とした請願の声、Heiland, Herr der Huld(救済者よ、憐れみの主よ)は、罪の意識と、苦痛と情熱に満ちた音色を維持して高く響く。そのフレーズの彫刻されたような息づかいに、パルジファルに同情心が生まれるのが感じられる。それこそが、クンドリーの時間に打ち勝つ同情の心Mitleidなのだ。Ha! Dieser Kuss(ああ、この口づけ)を、ホフマンは、彼女の抱擁をふりほどいて、激しい嫌悪感と共に吐き出す。彼自身の弱さを知ること、クンドリーに対する嫌悪の念と同じだけの自責の念が、彼を退かせる。一部のパルジファルたちと違って、この転換点から先、ホフマンは自分の行動に全責任をとる。彼はひとりクンドリーだけに責任を転嫁して、厳しく非難することをしない。彼のAuf Ewigkeit waerst du verdammt mit mir(お前も私も共に、永遠に罰せられるだろう) は、非常に穏やかな警告であり、罪のあがない、すなわち救済の約束だ。彼はクンドリーが怒り狂って彼を引き止めようとするとき、彼女から逃れようと格闘するけれど、Ein anders ist(それは違う)と、自分の使命を説明するとき、他の一部のパルジファルより我慢強い。Vergeh' unseliges Weib!(私から去れ、呪われた女よ)は、以前にまして、死に物狂いの様相を呈する。それは、今や彼女の誘惑に完全に気づき、自分自身の弱さを恐れる男の嫌悪感に満ちた反発である。身体的な力と声の力を爆発させて、ホフマンはクンドリーを突き飛ばして、クリングゾールの槍を奪い取る。(バイロイトでは、フランツ・マツーラが投げたその武器を、彼は実際に受け止めた) そして、Mit diesem Zeichen bann'ich deinen Zauber(この印によって、私はお前の魔法を解く)と高らかに歌う。それは、trugende Pracht(妖しい力)の大きく広がるGの音で、オーケストラの上を飛翔して終わる。悲しみに満ちた様子で、穏やかにクンドリーを振り返ると、彼女に与えた苦痛と、それに自分も関わっていることを謝罪し、Du weisst wo du mich wiederfinden kannst(どこで私を見出すか、あなたは知っているはずだ)と、彼女がそう望むなら、新たな関係を結ぼうと申し出る。ホフマンの二幕は、覚醒と成長のゆっくりと進行する過程を描き出す。すなわち、少年は青年になったが、まだ完全な大人にはなりきっておらず、これからさらに成長していくことになることを示している。
三幕で、しばしば黒い甲冑を身につけた姿で再登場するとき、その足取りの極度の緩やかさ、落とした両肩 、考えに沈んでいるようなゆっくりとした動作から、彼がどうしようもないほど疲れきっていることと、 彼が知を得たことが、はっきりとわかる。Heil dir, dass dich wieder finde(神に感謝します。再びあなたに会えたことを)と言う、グルネマンツに対する最初の挨拶から、その声に強烈な気品と成熟した大人らしさがあふれているのを耳にする。そこには輝かしさも存在する。陰うつな気分、罪の意識、そして苦痛が深い意味をもった魂の苦悩に変化している。放浪、修養、探求がこのパルジファルを円熟させ、柔らかで暖かく、さらに長い旋律線を伴うフレージングは、新たに見出した内面性を示唆する。彼の感性はより深まっている。アンフォルタスの最初の叫び声に対する身体的共感は、永遠の直感的告解となっている。ホフマンのパルジファルは、罪の意識を鋭く強調する、刺し貫くように金属的な高いAの音は、Und ich bin's der all dies Elend schuf(そして、私にこそ、この全ての悲惨の責任があった)と宣言したあと、次第に穏やかな悲しみへと静まっていく。letzter Pfad nur schwindet(最後の小道も今は消えてしまった) 彼の嘆きに、自己憐憫の跡は一切なく、むしろ、犯した過ちに対する深い悲しみと永遠に終わることのない疲労困憊し、mir schwindet(気が遠くなる)と、一瞬気を失いそうになりながらも、諦めずにしつこく最後の希望にすがる気持ちを強調している。
クンドリーに水を恵まれて、パルジファルは元気を取り戻し、彼の旅が終わりに近づいていることをゆっくりと喜びのうちに感じはじめる。Werd' heut' zu Amfortasich noch geleitet?(今すぐ、アンフォルタスのところに連れていってもらえるだろうか)と、驚くようなきっぱりとした問いかけで、実際のところ、探して求めて得られないものを罪のうちに見出したのだという認識を得ようとする。断固として潔い態度で洗礼を受け、誇りもって、聖杯の騎士の地位を受け入れることを表明する。彼の身振りと声からは、彼があふれるような愛と喜びに目覚めたことが伝わってくる。Du wuschest mir die Fuesse(あなたは私の足を洗ってくれた)という言葉によって、彼女の変わりように衝撃をうけながらも、謙虚な気持ちでクンドリーに感謝する。謙虚に、誇り高く、Als Koenig er mich gruesse(私は王として、彼の挨拶を受けよう)と、彼は召命を受諾することを宣言する。ホフマンは、パルジファルの気分と、目的意識を非常に美しく伝える。夢が現実になったようで、なかなか信じられないほどだ。寛容さと優しく感動的な動作で、彼はクンドリーに洗礼を授け、うっとりする非常に美しい最弱音に向かって次第に弱まっていく一節で、Glaube an den Erloeser(救い主を信じよ) と、彼女に命じる。ホフマンは甘い尊敬の念と深い兄弟愛に満ちた雰囲気を醸し出すことができる。聖金曜日の場面を肯定し納得できる気分で満たす。その英雄的な声を、輝かしく抒情的な声に変えて、ワーグナーのとんでもなく難しい弱音と最弱音を際立たせる。Blueten und Blumenの弱音、so lieblich traut zu mirと、trauern und weinenでの最弱音、そして何にもまして、du weinestの、危険な声の転換点におけるF#の音の、すばらしく美しい漂うような音色は、裏声(ファルセット)ではない、真の最弱音(ピアニッシモ)である。
感情の波に乗って、野原の愛に満ちた共同体は聖杯寺院の強烈に霊的な雰囲気へと移っていく。ホフマンは、このクライマックスの時にこそ、緊張状態を構築する必要があることを、猛烈に意識している。霊感に満ちた熱意をもって、飢餓感に狂乱状態の騎士たちに立ち向かい、アンフォルタスの脇腹を槍で厳かに触れ、Nur ein waffe taugt(ひとつの武器だけが役に立つ)と、予言者的な癒しの力と共に、唱える。高らかに聖杯の覆いを取ることを宣言して、魔法の言葉を紡ぎ出す。Sei heil, entsuendigt, und entsuehnt(祝福されよ、癒された、罪のないもの)は、息を継ぐことなく、一気に高まる旋律で歌われる。Den heil'gen Speer ich bring'ihn euch zurueck(私が聖なる槍を取り戻す)は、高いGの音の弱音で締めくくられる。多くの公演で、この最後の旋律もまた,弱音で歌われる。きらめくような畏敬の念をもって、ホフマンは、oeffnet den Schrein(聖櫃を開け)と命じる。感情の高まりを示す微妙なトレモロが弧を描いて、息をのむほど美しく柔らかく終わりを迎える。彼は、夢見心地の呈で聖杯を高く掲げ、跪く騎士たちに、厳かに顕示する。鳩が舞い降り、容易に消えることのない、高まる恍惚感に満ちた雰囲気のうちに、幕が下りる。
14章 ペーター・ホフマン -10/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ワルター・フォン・シュトルツィング(ニュルンベルクのマイスタージンガー)
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ワルター・フォン・シュトルツィング(ニュルンベルクのマイスタージンガー)
ワルター・フォン・シュトルツィング役のキャリアはたった五年だが、すでに熟練した人物描写を達成している。最近のボンの上演について、こんな批評があった。ペーター・ホフマンは、舞台上の最高のワルターの一人である。1985年2月22日、メトロポリタン歌劇場の初ワルターについて、ドナルド・ヘナハン Donald Henahanは、彼はまさに本物のガラハッド、信じられないほどの風格と優美さを備えた俳優だと評した。(ガラハッド(Galahad). ケルト神話、 アーサー王伝説に登場する、騎士ランスロットの息子。パーシヴァル、ボールスと共に聖杯の三騎士の一人) 1988年のバイロイト音楽祭の後には、大概の批評は、熱狂的なものになった。ペーター・ホフマンのシュトルツィングは、その姿は光り輝き、歌はほとんど完璧だった。あるいは、ペーター・ホフマンは声の調子もよく、その歌は、燦然と光り輝き、シュトルツィングを情熱的に演じた。といった具合だ。重いテノール schwer Teorsのなかで、この役をやって成功する歌手は少ないが、ホフマンはその一人である。彼がこの役を初めてやったのは1984年チューリッヒで、続いて、1985年にニューヨークで、1988年には、ボン、マンハイム、そして、同年の夏には、ついにバイロイトに出演した。この役に関するホフマンの見解は彼独自のユニークなもので、批評家たちは、ホフマンがこの役に付与した独自の刻印を、即座に看て取った。
ペーター・ホフマンは、ルネ・コロの熱い反抗的なシュトルツィングとは、明らかな違いを示した。彼は人間的成熟に至る道筋を成長過程と関連づけたと、マンハイム・モルゲン紙は書いた。さらに、一連の Morning Dream の歌は音楽的に完璧だったと、彼の声楽テクニックを賞賛した。
テノールは、1983年にオペラからの抜粋を集めたリサイタル盤を録音した。Fanget an! (はじめよ!)と Preislied(優勝の歌)は、どちらもわくわくする。伸びやかな歌い回し、みずみずしい声、若々しく、熱烈だ。そして、それぞれ、違いがはっきりと特徴づけられている。Fanget an! (はじめよ!)の荒削りの直情に対して、 Preislied(優勝の歌)は、計算され、技術的に確実であるにもかかわらず、恍惚感をもたらすのを感じる。後者では、彼のなめらかなレガートはクライマックスの durch Sanges sieg gewonnen Parnass und Paradis(歌の勝利によって勝ちとったものはパルナスの山とエデンの園)へ切れ目なく舞い上がる。ひとつひとつの節を独特の陰影で彩り、この歌を詩による自己発見への旅にしている。
近年、ホフマンの役への同化は深まり続けている。ヘルツ誌のインタビューに対して、中世の騎士に対して感じる近親感は、親方歌手たちの古くさい制約に対するシュトルツィングの反抗と、自分自身の芸術観に正直であろうとする彼の孤独な苦闘によるところが小さくないと説明した。こういう探究心を擁護したのは、ザックス一人だったわけだが、ホフマン自身、それを、観客に求めていた。ほとんど彼の自伝とも言えるような類似点が、彼に非常に情熱的かつ説得力のある騎士を描き出させたと言える。
歌手は、高慢なシュトルツィングではなく、独特のオーラを放つシュトルツィングを描き出した。ある観客はそれを、本当の意味で貴族的な雰囲気と表現した。それはすなわち、めったにこういうことができる人はいないのだが、ホフマンは、貴族的であることと粗野であることという二分された側面を伝えることができるということだ。シュトルツィングはザックスを自分の師として選ぶが、それは、彼がザックスのうちに同じ精神を見ているからだ。だからこそ、彼はザックスをその他大勢の中で唯一人、分かり合える友として大切に思うのだ。しかし、このシュトルツィングは、彼自身の独自の自意識を終始保っている。彼はすばらしく成長し、規律、寛容、そして、町の人々に対して淡い優しさのようなものさえも身につけるが、 Preislied(優勝の歌)は、荒々しいほどの独立心を持って歌われる。それはたとえそうすることが、ニュルンベルクの人々の拒絶を誘発するものだとしても、自分の芸術的立場を主張し、エーファを獲得するのだという強い意志を表わしている。彼が月桂樹の冠を拒否したのは、論理的帰結である。それにもかかわらず、彼はザックスの知恵と、彼によって喚起されたドイツの芸術に対する賛歌に同意する。それは、彼の心のうちに、もうこれ以上の反抗を不必要とする、人間的な深い共感と理解と安心感がわき起こったからだ。反抗ではなく、和解こそが、彼の幸福と満足の喜びにあふれた主張となる。
1988年8月3日のバイロイト音楽祭公演の放送は、ホフマンのワルター・フォン・シュトルツィングの複雑さを洞察させてくれた。この役を演じた多くのテノール仲間たちよりも、わくわくさせられるし、何と言っても演技性がすばらしい。ホフマンは彼のシュトルツィングに、言葉の力強い説得力、深い音楽性、優雅な歌い回し、そして、高い音域には心地よい英雄的強さを付与している。
開幕時の登場から、楽譜が要求する演劇性に順応するテノールの才能に驚嘆させられる。ジークムントやパルジファルの悲劇的重々しさはどこにもなく、それに代って、このブルジョア的内容にふさわしい、軽快な自然さが際立つ。彼のエーファに対するせっかちな第一声 Mein Fraeulein, sagt(お嬢さん、こたえてください) はごく自然な会話になっているが、それにもかかわらず、彼の懇願には極めて人間的な性急さがあらわれている。このシュトルツィングは正真正銘の若い娘に恋する正真正銘の若者だ。大げさな感じもなければ、軽卒な印象も受けない。彼が貴族階級だということは、ニュルンベルクのブルジョア階級に受け入れられたいという彼の願望の障害にはならない。
ホフマンのシュトルツィングは、横柄な印象を与えることなく、マイスタージンガーになるための、ダーヴィッドの助言に耳を傾ける。彼は真剣に学びたいと望んでいるし、とても熱心にそのための課題に取り組むことを承諾する。2、3度は不愉快な気分になる。Hier in den stuhl?(この椅子に?)と、うさんくさそうに指定の椅子に座るときは、明らかにそうだが、Fuer dich, geliebte, sei getan (愛する人よ、あなたのためにやるぞ) とロマンチックな慰めを持って、気持ちを鎮める。テノールの本来的な響きの持つ安定した力強さは決断と冷静な自信を示し、断固とした落ち着いた調子で、最初の歌 Am stillen Herdを歌い始め、それは静かに進んで、ちょっと後には、成功の手応えで盛り上がり、最後には、柔和でロマンチックで情熱あふれる詩の世界へと広がっていく。
シュトルツィングの歌のそれぞれの節を、いちいちはっきりと区別して際立たせる才能、すなわち、各節に異なる音の色彩と、俳優としての行動理由を付与する才能、これがホフマンのシュトルツィングを素晴しいものにしている一因である。これはまたFanget an! (はじめよ!)と、一幕の終わりのアンサンブルでも、明らかになる。彼は、この歌を力強く始め、最初の節を完全に軽々と歌う。審判の最初のチョークの音に妨げられるとき、彼の声は冷静でいようという決意を示すように、多少硬くなる。チョークで印をつけるベックメッサーの引っ掻き音はどんどんひどくなるが、彼は全神経を歌に注ぎはじめ、彼の声はけんか腰の気分を突き通して輝かしい詩となる。Doch, fanget an! (とにかく、やらせせてくれ!)は、大上段にふりかぶった反駁だ。そして、まずはやぶれかぶれのこだわりで、それから、大騒ぎの騒音の最中で集中力を保とうとする恐ろしいまでの荒々しさで、まっしぐらに最後の節に突進する。マイスターたちが耳を傾けようとしないのが明らかになると共に、彼のいらだちと怒りは最高潮に達する。指揮者ミカエル・ショーンバットの熱狂的なテンポに応じ、英雄的な自分自身を保ちつつ、合唱とオーケストラの圧倒的な爆発の中、ホフマンのシュトルツィングはメタリックに明るく響き渡る叫び声、die hehre Liebeslied(偉大な愛の歌)でその歌を締めくくる。彼は、ゴールを見据えた戦士だ。しかし、同時に忍耐力と持続力を厳しく試されるひとりの人間でもある。 wie fraget ihr?(なせそんな質問をするのか)と、彼は本気で腹を立てて叫ぶが、即座にHoert doch, zu meiner frauen Preis(女性を讃えるところを聞いてください)と、自分は不当に攻撃されているけれど、(実際、騎士である紳士に対して考えられないことだ)負けはしないということを示す調子で、気持ちを抑えて受け流す。Blieb ich von allen ungehoert?(だれにも聞いてもらえないままになるのですか)は、苦しい抵抗だが、最終的な混乱状態に再突入する前に、恐ろしい現実に直面する最後の言葉において、その反抗心は微妙に弱まっている。最後の数節で、ホフマンは混乱の最中、耳を傾けてもらおうと劇的な朗唱で訴えかける。この抒情性から台詞的な歌への移行は、華々しく進み、シュトルツィングの冷静な心の崩壊を示唆する。部屋から駆け去る前、もう終わりにしようと決心して、Ade! ihr Meister hienied'!(さらば、マイスターのみなさん) と高らかに響き渡らせる歌が、このシュトルツィングの最後の音楽的言葉だ。すなわち、ひとりの歌手として、説得力を示すべきなのだ。そして、そのようなホフマンのシュトルツィングはもの凄く勇敢で大胆だ。凡俗な批評家たちの中にあって、唯一の、皮肉のきいた、破壊されえない声なのだ。
二幕のシュトルツィングは爆発だ。Ach, du irrst(ああ、あなたは間違っている)は、通常の狂乱状態の激しい非難よりも、怒りと軽蔑でさらにほの暗く燃えている。彼は自分が関わる事になるコンテストの大きな意味を大いに認識している若者だ。慣習のばかばかしさに抗しようとして、Ein Meistersaenger muss es sein(マイスタージンガーでなければならない) を、彼は苦々しい思いであざける。Wahl に置かれるアクセントを苦い思いで理解しつつ引き延ばしながら、Keine Wahl ist offen(選択肢はない) に、抵抗する。テノールの朗唱は力強く、ひとつひとつの言葉は、注意深い陰影で彩られ、各々のリズムは、巧みに変化する。その声は充実し、その最高音は安定している。このワルターはくじけることを知らない。世の中の法則に、ただちょっと幻滅しているだけだ。戦術こそ変更せざるをえないが、エーファを獲得する方法を見つけようとしている。あまりにも強烈な確信を持っているからこそ、彼は愛する人がそんなにもはやく自分になびいたことにある意味驚いている。愛情に満ちた畏敬の念をもって、優しくDu fliehst?(一緒に逃げてくれるだろうか)と歌う。この幕の他の多くの部分で、この優しさは、彼の男らしさのなかにあって目立っているが、甘い声はエーファのためにとってあるのだ。Welch'toller Spuck(なんとすばらしい夢)は柔らかい、表現力豊かな弱音で、その場面の月光に照らされた恋愛物語が、テノールの歌を覆っているようだ。最後の時には、騎士らしく挑戦的に立ち上がると、ロマンチックな堂々とした態度で、愛する人を守るために、剣を抜く。その動作に、怒りの気持ちはなく、ただひたすら献身的な愛だけが存在している。
大騒ぎの翌朝、ザックスの家で目覚めたとき、ホフマンのシュトルツィングはこの職人との間に完全な人間関係ができたと感じる。ザックスの家は居心地がいい。シュトルツィングの警戒心はゆるみ、昨夜の夢を打ち明ける。マイスタージンガーになることによって、エーファを勝ち取ることはできるとザックスに励まされて、ホフマンのシュトルツィングは和解こそ賢明な道であることを認める。ザックスに対する尊敬と他の狭量なマイスターたちに対する反感とを、ワルターが区別しているのがわかる。そして、彼はザックスの助言に注意深く耳を傾け、恋の喜びの詩 Ich lieb'ein Weib(私は一人の女性を愛しています) で応え、歌って彼女を得ることを約束する。
靴屋の居間の場面で、ホフマンは優勝の歌の各節の制作過程をたどって、ワルターが体験していく創作の進展と、心理的展開のゆっくりとした過程を演じる。最初の数節は支持を求める軽い調子だ。二連目はあたかもテノールが作曲しつつ、ゆっくりと自信を深めていくかのように穏やかに歌われる。三連目では、まるで各節が試行錯誤から生まれた喜びあふれる着想であるかのように、より長い旋律線を維持し、装飾を施し始める。四連目のNaechtlich undaemmt(夕闇が忍び寄り)の一節で、ホフマンはその声を弦の暗い響きに合わせ、なんとも美しい混合的な響きを創り出している。詩人はここで弟子から学ぶことになる。そして、その飛翔し、広がり、弧を描いて完全に弱まっていく、Im Lorbeerbaum (月桂樹の) では、シュトルツィングの芸術の力強さと優雅さを共に証明している。
Wo faend ich die? Genug der Wort(それがどこで見つかると言うのですか。もう言葉はたくさんです)のところでは、ザックスの批評に過敏になって、ちょっとけんか腰になるが、この人間的な反応はすぐに師に対する信頼感を新たにする結果となり、さらには、エーファの姿をとらえて気持ちが高まり、作曲(in Liebestraum愛の夢)は活気に満ちた肯定的な終わりへと向かう。シュトルツィングは、今や愛する人を前にし、友人の賢明な作戦によって、柔らかな美しい歌い回しで歓喜の五重唱に参加する。この録音における、ペーター・ホフマン、ルーシー・ピーコック、ベルント・ヴァイクル、ウルリヒ・レス、マルガ・シムルの声の混合した全体的響きは申し分のないすばらしさで歌われ、アンサンブルとして見事に調和している。
シュトルツィングの心は、すばらしい問題解決に、晴れやかな気分でいっぱいになって、Preisleid(優勝の歌)を準備するために退場する。みずみずしい合唱の響きを先触れに、彼が輝くような白い衣装を身につけて、豪華な装いのバイロイトのキャストの真ん中に進み出るとき、それはまさに息をのむ瞬間だ。畏敬の念を込めたつぶやき、礼儀正しい緊張に満ちた沈黙、そして、彼は歌い始める。
Morgenlich leuchtend(朝は薔薇色に包まれ)は確信的にロマンチックに歌われる。このシュトルツィングは課題のために準備したのだ。報いられた愛が彼に与えている強さがエーファの名を発音する優しい弱声のなかと、心地よく響く言葉、im Paradisのうちに聞かれる。テノールは続けて第二連を、前の部分とは違う強さで歌詞を表現し、愛の告白das Muse des Parnass(パルナス山のミューズ) にdas Muse des Parnass最大限効果的に到達する。最後の連は、テンポも情熱もますます高まり、ホフマンのシュトルツィングはあらゆる思いを最後の瞬間に注ぎ込む。これは勝つか負けるかの賭けだ。マイスタージンガーたちも観客も、テノールが無事に輝かしくParnas und Paradis(パルナス山とエデンの園)と歌い終わると同時に、シュトルツィングこそ、勝利者だと思ったに違いない。彼はめくるめくような感動の瞬間に、規則を超越する歌を創り出していた。新たな明快さと輝きによって、再創造したのだ。詩というものは、その芸術性を主張するなら、個人の内的真実に根をおろしていなければならないし、知性を備えた成熟によって育てられなければならないし、神から霊感を与えられなければならないし、人間的関わりによって作られなければならないということだ。彼の明るく響くNicht Meister! Nein!(いいえ、親方はお断りです)は、こういう気持ちから出た拒否なのだ。孤独な芸術家の、断固として誇り高い、しかし、敵意のない拒否。彼は、もっとやわらかい Will ohne Meister selig sein(私はマイスターにはならず、しあわせでいたい)という言葉で、拒絶の調子を抑えて、個人的に排他的市民になるのは好まないということはすなわち自分の独立心の問題であるということを、 穏やかに説明しようと試みる。ザックスの個人的かつ愛国的な感動を呼ぶ訴えかけに従うのは、靴職人の友情と評価に心を動かされたからで、そして、それはまた誠実で、分別のある理解ゆえでもある。つまり、自分の文化的背景と和解した芸術家は、更に賢明さと確かな独立性を身につけ、真にユニークでの総体的な表現を産み出すということを理解したからなのだ。
このオペラ全体を通して、特にこの勝利の最後の幕で、ホフマンは三次元的なワルター・フォン・シュトルツィングを創り上げることに成功している。彼のシュトルツィングは暖かさと注意深い細心の洞察力をもって、孤立した創造者も社会全体の中に融和的に取り込まれるのだという、ワーグナーの成熟したメッセージを伝えている。ホフマンは、ワルターを暖かい人間性を備えた、完全に思いやりのあるヒーローとして演じる気迫と同時に、この作品に要求される喜劇を演じる天賦の才能も備えている。彼の演劇的に豊かな才能は理想主義的な、複雑な心理傾向を備えた若者像を描き出す。彼の放つ輝かしい存在感は観客を圧倒する。マンハイムの観客の一人はこんな感想を述べている。「三幕、上から下まで真っ白の衣装を身につけ、疲れなどみじんも感じない、若々しいすばらしい声のペーター・ホフマンは、夢のようなヒーローだった・・・」
14章 ペーター・ホフマン -9/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ジークムント(ワルキューレ)
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
ジークムント(ワルキューレ)
このように、ホフマンは、そのレパートリーにさらにジークフリートを加えることを計画するだろうが、すでに160回以上演じた、彼のジークムントは、彼の芸術の頂点に立っている。ミヒャエル・レーネルトの言葉を借りれば、彼には競争相手がない役だ。
ホフマンは、1976年のシェローのプロダクションの前におよそ40回ウェルズング役を歌っていたが、彼のキャリアにおいて、シェローの公演こそが 、重要な段階だったと彼は今でも考えている。1976年7月26日のホフマンのバイロイト・デビューの放送録音は、鮮やかな声の重いテノール schwer Tenorの、中音域における濃い、チョコレートのような色合いの響きを明らかに示している。ホフマンはまだ究極的に安定的で落ち着いた強弱感を達成していないが、すでに 切れ目のないレガート、官能的なフレージング、演劇的な明瞭さははっきりと表わしている。プロダクションが解散される1980年、録音、録画が行われるまでには、ホフマンの声は完璧に融け合った完成の域に到達していた。いまや、その響きには透明感ときらめきがあると同時に、豊かで、暗い音色を備えている。そのうえ、美しい最弱音で陰影をつけることができる。ピエール・ブーレーズの室内楽的強弱感を持った指揮のおかげで、ホフマンが究極的に微妙な陰影をつけることを可能にし、ここでは、歌手はワーグナーをあたかもモーツァルトであるかのように歌うことができている。さらに、最高に美しい響きを紡ぎ出す好機を逃してはいない。その響きは抒情的であると同時に正真正銘英雄的である。ホフマンが創り上げた多くのワルキューレのなかで、もうひとつの画期的な公演は、1983-1985年、ニコラウス・レーンホフ演出のサンフランシスコでの上演だった。このリングで、ペーター・ホフマンのジークムントは、世間から見捨てられて放浪する、野性的な若者だった。1983年6月、Opernweltは、この演出の性格描写は彼にぴったりだ。ホフマンは声楽的にも絶好調で、実に見事な舞台だった!と書いた。1986年、ホフマンは、ジェームズ・レヴァイン指揮の新演出リングのジークムントとして、メトロポリタン歌劇場のシーズンの幕を開けた。ロバート・コペルマンは、ペーター・ホフマンは、全く疲れを見せない声でジークムントを演じた。正真正銘のドイツの英雄だった。その本物らしさは、並外れている と評した。それから、また1988年3月19日、ニューヨーク、同演出での相手役、レオニー・リザネクのジークリンデさようなら公演でもまたジークムントを演じた。私自身、この非常に熱のこもった感動的なエネルギーのあふれた公演についてOpera Internationalに批評を書いた。
ペーター・ホフマンのジークムントは大成功だった。声楽的にも絶好調だったし、その歌唱の情熱的な抒情性、その朗唱の正確さ、見事な呼吸(ブレス・コントロール)、これらは 、ジェームズ・レヴァインの、切れ目のない響きを維持する、ロマンチックなテンポと見事に調和していた。彼の声は、暗めに響き、中音域と低音域は豊かさが際立っていた・・・・ 例えば、彼が死を迎える激しい苦痛のうち仰向けに倒れたまま、逃げさっていくジークリンデを、愛に満ちた眼差しで必死に追うとき、ホフマンに反応しないでいることは不可能だ。
1988年7月28日、ホフマンはバイロイトの、ダニエル・バレンボイム指揮、ハリー・クプファー演出の新演出リングで、再びジークムントを歌った。十年以上前、シェローの演出で、この役に対する評判を築いたように、再び、この役は、彼のものであって、今までに存在した他のどのテノールのものでもないということを大成功のうちに証明した。彼の舞台は、ますますエネルギーにあふれ、さらに深みをましており、その洞察力の新鮮さと迫力で、観客を吃驚仰天させ続けることを立証していた。ヨアヒム・カイザーは、彼の衝撃的な舞台について次のように述べた。
ペーター・ホフマンは高度に集中力のある演技によって、ジークムントを、絶望して憂うつな気分の追放者に、そして、社会ののけ者として描き出した。彼はなかなか自分の幸福と愛を信じることができない。疑いと敵意でいっぱいになっては、なんども両手で頭を覆う。彼は傷つきやすいだけでなく、すっかり落ち込んでいる。
1988年6月、クプファー演出のワルキューレの初日を迎える一ヶ月前、ジェノヴァのジークムントに関して、イタリアのある批評家は、彼を、私たちの時代の最高のワーグナーの声のひとつと評した。
こういうことからしても、彼が常に最高にすばらしいジークムントであることは疑いようがない。この役に関するホフマンの考えも声楽的な微妙な陰影の付け方も彼の17年のキャリアの間に少しづつ発展、進化してきた。 ジークムントに関する総合的な考え方は多少穏やかになってきている。初めのうちの、より憂愁に満ちた、生意気な反逆者という雰囲気に、成熟に伴って、彼の演奏は、次第により深い人間性とより大きな受け入れ能力を備えるようになってきた。彼は傷つき、追放されていても、繊細な感受性を持った核心部分を決して失わない。そして、最近のクプファー演出でのように、彼の不信感がゆっくりととけていくときでさえ、劇的緊張とその英雄らしさを高める結果にしかならない。私自身、最近のニューヨークの上演で、より孤独で反抗的なその外面性を和らげている無邪気な一面を感じた。厳しくつらい人生を送りながら、一貫して、ロマンチックな感覚や、希望、理想、そして優しさを保っている主人公がそこにはいる。こういう隠れた自我が、ジークリンデによって目覚めさせられ、そのときの彼の反応こそが、感謝の気持ち、畏敬の念、エロティシズム、そして無限の優しさを醸す。ホフマンのジークムントは、あらゆる眼差し、あらゆる接触が、その行動が意識的であること、その行動にある迷いと美しさを認識しているということ、そして、その運命が達成されることを妨げようとするものに対する激しい反抗心を持っていることを明確に表わしている。 彼は、その愛と死が運命的なものだということを知っているが、それでも、彼は生きるために、自分の選択できる道を意識的に決定し、その反抗心を意味のある人間らしい行動へと転換するべく、並外れて強い精神力を行動によって示す。
各演出によって演劇的な陰影の付け方は変化するにしても、ホフマンのジークムントに対する性格付けの核心は一貫してその独自性を保っている。この役の先輩たちとの違いを際立たせているのは、現代的な意味で直感的に伝わる彼の英雄らしさと、彼の歌唱と演技にある感電させられそうなエロティシズムである。シェローの演出から今に至るまで、ホフマンは、感情をはっきり示すジークムント、生来の官能性と精神性が混合して白熱の輝きを生むジークムントを創り上げてきた。言い換えれば、社会から疎外されたアウトサイダーとしての、普遍的かつ現代的な態度のジークムントだ。彼の存在そのものの疎外性、その完璧な男らしさ、現代的な魂の不信感と信頼感に対するその情熱に任せた向こう見ずな関わり方。これこそが彼が意図するところなのだ。我々の仕事は物語の「時代」を問い、我々の時代に通じる橋を架けることだ。そうでなければ、我々はいかにして感動できるだろうか というわけだ。 この役では、ミュンヘン、ロンドン、シュツットガルト(1978年)、バルセロナ、ベルリン(1984年)、トリノ(1987年)、そして、さらに前に挙げた場所等々の、あまりにも数多くの出演を果たしてきているので、それぞれの公演を分析するのは難しいが、録音と劇場の生の舞台の両方における、ホフマンのジークムントの特徴の一部を取り上げて、詳細に検討することは可能だと思う。
一幕、登場のときから、彼はペースを決定する。部屋に猛烈な勢いで駆け込み、もの凄い疲労のせいで崩れるように倒れ込む。疲れきって、肉体的苦痛の中で歌われるWes Herd muss dies sei(だれのかまどだろうが)は、バリトン的で荒々しい。ジークリンデに目を留めた瞬間から、情欲と愛情が目覚める。そして、この気持ちを必死で隠そうとしているのがはっきりと見て取れる。フンディング登場の前に、二人は密かな愛撫を交わし、その後は、彼の視線は彼女から決して離れることがない。その眼差しは、彼女に対する同情と思いやり、彼女を守ろうとする気持ち、そして、二人の間を隔てるものに対する憤りなどを伝えている。フンディングが腹を立ててジークリンデをにらみつけるとき、"Willst du dein Weib umschelten?(自分の妻を責めるのですか)と、彼は雄々しくもいらだつ気持ちを抑える。疑いつつ、不安な気持ちで、彼の過去を話題にしようとするフンディングに立ち向かう。初めはいい加減な作り話をするが、徐々にお互いの敵対関係を察知すると、彼の物語は誇り高い挑発の様相を呈するようになる。ホフマンはこの長大な物語をひとつひとつの言葉を際立たせ、的を射た辛辣さで歌う。リズムの正確さも、レガートのなめらかさも、全く損なうことなく、最大限効果的に、言葉を強調する。彼がden Vater fand ich nicht(私は父を見つけなかった)といったフレーズに哀感を込めるやり方は、Lag sie tot(彼女は死んで横たわっていた)の 深々と響く正真正銘のバリトン的な低いCの音と同じように、心に残る。彼は、Nun weiss du, fragende Frau, warum ich Friedmund nicht heisse(知りたがりのご婦人も、これでおわかりでしょう、私がフリートムントと呼ばれないわけが) と物語を締めくくるとき、Friedmundのところで、驚くほど確実に漸次弱音化 diminuendoを実行し、そのフレーズの他の部分を弱音で紡ぐ。Ein Schwert verhiess mir der Vater(父は私に剣を約束した) は、常に激しい情熱の発露として抒情的に歌われる。一部のヘルデン・テノールがするように、絶対に怒鳴ったりしないし、不自然なスタッカート唱法を採用したりもしない。ホフマンは、このクライマックスを楽々と歌う。Waelseの叫び声は終始高らかに舞い上がりひとつひとつがなめらかに徐々に強く、クレッシェンドしていくが、指揮者のテンポに従って、音価を固守する。(レヴァインの指揮では、音価は長く、他の指揮者の場合はそれほど長くない) Winterstuerme(冬の嵐)は、ホフマンの演奏においては、常に詩を歌う歌曲Liedだ。彼のレガートは強烈で、このロマンチックな旋律に対する彼の気持ちは、対話的だ。そして、この愛の歌の情熱と官能的な脈動が全体を通してあふれている。この歌が終わった瞬間から、ホフマンはジークリンデを鼓舞して、共に痛いほどに愛情と歓喜あふれるこの幕のクライマックスにむかって盛り上がる。彼の身体言語表現はしなやかで、官能的であり、彼の声は生き生きと、響き渡り、飛翔する。彼はジークムントの栄光の瞬間に向かって迫力を増しつつ突き進む。剣のつかをつかむべく跳び上がるとき、恍惚状態でSiegmund heisse ich und Siegmund bin ich!(我が名はジークムント、我こそはジークムント) と、力強く歌いながら、彼は剣を抜くという難事に現実的に取り組む。あの非常に重要な断念の動機renunciation motif の長い旋律線を、途切れることのない、しっかりと支えられた、暗く不吉な、あふれるような響きでやり遂げる。彼はその剣をノートゥングNotungと名付け、運命を受け入れる気持ちと公然の反抗心が、金属的な輝きの中で入り交じって響くzu mir(私の元へ)という叫び声と共に、木の幹から剣を引き抜き、元気いっぱい頭上で振り回す。このときのホフマンの喜びとそれに続く部分は、非常にはっきりとしてわかりやすく、ずっと同じように表現されている。彼の笑顔はきらきらと観客席を照らし、彼のエネルギーはあたかも伝染力があるかのように人々に伝わる。ジークリンデと観客を押し倒す彼の力強さは、ぞくぞくするほどの興奮を体験させてくれる。最後の節で、よく通る高いA音を疲れを見せずに投げ上げて、世界に対して喜びにあふれた挑戦をたたきつける So bluehe denn Waelsungen Blut!(かくして、ウェルズングの血よ、栄えよ) は、性的絶頂の恍惚感を伴っている。一幕の終わりは、演出家によるとしても、大概は愛するジークリンデと情熱的に、実際にしっかりと抱き合うホフマンを見ることになるのであって、それは、性的な意味合いのない軽い抱擁だったり、キスのまねごとだったりすることはなく、まさに映画的な説得力を持つ、刺激的な愛撫だ。拍手喝采のうちに幕が降りる。
このようなぞくぞくするような一幕を超えるのは間違いなく容易な仕事ではないが、ホフマンは二幕でも常に衝撃的な忘れ難い舞台を出現させる。彼のジークムントは短い愛の過程で成長しつづける。彼の魂は成熟して花をつけ、悲劇性も英雄性も共に増して行く。一幕よりも、さらに知恵を得て、より優しさを増し、人生に対してより肯定的になる。その絶望ゆえに何事も恐れずより勇ましくさえなり、差し迫った目的に駆り立てられ、愛する人を守ろうと全力を尽くす。逃走中、彼女の後を追いながら、愛情のこもった身体接触によって彼女を落ち着かせようと試み、心地よい声で彼女を慰め、その恐怖感を和らげ、苦悩するジークリンデをなだめて寝かしつける。そのSchwester, Geliebte(姉妹よ、愛する人よ)は常に変わらず美しい。この一節は、柔らかいmezza voceではじまり、持続される透明な弱音の音節へ向かって弱まっていく。ホフマンにかかると、死の告知の場面は、寒気がするほどの霊気に満たされる。ブリュンヒルデが死者を覆う白布で男らしく落ち着いているジークムントを包むという、シェローの死の儀式は非常に印象的な手法だった。だが、数えきれないほどのもっと現実的で、写実的な演出(シェンクの演出のような)でも、ホフマンは手足の震えと不安げに見つめる彼の凝視の警戒の色で死の戦慄を伝える。彼はブリュンヒルデに、Wer bist du, sag (あなたはどなたですかと)、穏やかに挨拶する。彼女が死に定められた者のみが彼女を見ることを許される(Nur Todgeweihten taugt mein Anblick)のだと告知するまで、彼は目をふせている。そして、絶望的な勇敢さで、ゆっくりと振り向いて彼女と視線を合わせる。しばしば、彼は彼女に歩み寄り、明らかにそれとわかる動作で死を拒む。ホフマンのジークムントはまたブリュンヒルデの放つ輝きを感じていることを示す。彼は、彼女がワルハラで彼のために酒を注ごうという時、騎士のような礼儀ただしさで微笑むが、ジークリンデに対する献身の気持ちに静かに立ち返る。安定した、感情を抑制した声で、ホフマンは、情熱のかすかな兆候を最後のフレーズ、So gruesse mir Wotan und alle Helden. Tu ihnen folg' ich nicht.(それから、ヴォータンと全ての英雄たちにわたしからよろしくとお伝えください。彼らのところに、私は行きません) に加えつつ(Heldenの部分にごく小さなトレモロ)、全てを断念しはじめ、断固とした冷静な決心に至る。それから、この選択に興奮して、彼はジークリンデを自らの身体で守るために、おそらく最後のキスをするために、ブリュンヒルデに対して、So lang Sieglinde bleibt in Leben……(ジークリンデが生きているかぎり・・・) と、断固として、悲しみに満ちた正直な気持ちを披瀝した自分の決心を正当化するために、急ぎ駆け戻る。ブリュンヒルデが彼を説得しようとするとき、彼は自暴自棄に陥り、反抗的にHella halt mich fest(地獄よ、私をとらえよ) と、叫んで、誇りをかなぐり捨て、くずおれ、汗と涙にまみれた顔を両手で覆って、この最後の拒絶に伴う、傷つきやすい感情の爆発に一瞬身を任せる。ジークリンデとまだ生まれていない子どもを殺すという彼の決心は単なる脅しではない。その恐ろしいほどの怒りと、犠牲の精神をホフマンは確信させる。ブリュンヒルデは彼の手から剣をたたき落とさねばならないほどだ。彼女のほうこそが、説得されてしまい、彼と共に反逆に加わることを約束することになる。ホフマンのジークムントは、ほんの短時間だが、自分が救われたことを信じる気持ちになる。彼は、ブリュンヒルデの祝福を受け入れ、戦士としての熱狂的な気分をあらわにするが、ブリュンヒルデが見えなくなったとたんに、その気持ちは萎えてしまう。彼の筋肉のつかの間の興奮と萎縮が、これは裏切られるに違いない見せかけの夢なのだという恐れの気持ちをさらけ出す。
彼はジークリンデに向き直って別れのキスをし、生死にかかわらず、彼女との切っても切れない絆を断つことはできないことを確認して、自らを慰める。ホフマンは Zauberfest gesendt dein Schlaf (あなたは魔法にかかったように眠っている) を、微妙な強弱感で優美に歌う。その Umfried dich der Freude (喜びがあなたに平和を与えますように)は、曰く言い難い優しさに満ちている。その弱音と mezza voce の柔らかい音は、ほのかにきらめき、フンディングに闘いを挑む叫び声の虚勢を張る様と鋭い対照をなす。ホフマンは、この闘いを、常に現実的に本物のように表現する。彼はフンディングを挑発し、偽りのない純粋な勇気と無理矢理に希望を膨らませた大げさな勇敢さで自らを駆り立てる。ホフマンは、ジークムントの死に関して、実際的な残忍さと猛烈な暴力性を示さずに済ますことは決してない。彼は本当に苦痛を感じているかのように、身体をよじって身もだえする。突き刺さった槍をつかんで起き上がろうともがき、すっかり動かなくなって横たわるまで、気分が悪くなるほど真に迫ったけいれんをおこして身をよじる。汗にまみれた顔ををジークリンデのいる方向に向け、生気が失われていく目で彼女の姿を追い、ブリュンヒルデが彼女を連れ去るのを声もたてたられない激しい苦痛のうちに見つめる。確実に訪れようとしている死は彼が 声を出すことも手を伸ばすことも妨げる。シェローの演出以来、ホフマンのジークムントのもうひとつの特徴は、ヴォータンに対するほとんど究極的な寛大さである。神、ヴォータンが十字架から降ろされたキリストを抱く聖母像、ピエタのようなやり方で、ジークムントを抱き上げるとき、ホフマンは自分が神の息子であるということを直感した喜びと、神を父として認識したことを示す。シェンクの演出では、微笑みさえ見せ、がっくりと頭が後ろに倒れる寸前、手を伸ばして父の顔に触れようとする。彼の死のかすかな吐息は、夢心地で没入している注意深い、心の底から感動している観客の耳にはっきりと響き渡る。
ホフマンのジークムントを体験することは、この役の複雑さを徹頭徹尾理解すること、別の言葉で言えば、正真正銘の神話的次元で絶頂感とカタルシスを体験することだ。たった一度でも、彼のウェルズングを目撃すれば、ワーグナーの音楽劇が到達しうる高みをついに体験した当事者であることを感じるはずだ。
14章 ペーター・ホフマン -8/16 [WE NEED A HERO 1989刊]
14章 おじいちゃんのオペラは死んだ:
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
エリック(さまよえるオランダ人) 、ローゲ(ラインの黄金)、ジークフリート
ペーター・ホフマンと総合芸術の仕事
エリック(さまよえるオランダ人) 、ローゲ(ラインの黄金)、ジークフリート
ホフマンはさまよえるオランダ人のエリックにも同じ力強さと魅力を与えて、ワーグナーが要求したように、捨てられた求婚者を、オランダ人の、説得力のある引き立て役にすることができる。ホフマンはヘルベルト・フォン・カラヤンのために、ドゥニャ・ヴェイゾヴィチのゼンタ、ジョゼ・ヴァン・ダムのオランダ人との共演で、録音した。彼は情熱的で魅力的で自信あふれる、エリックという若者を描き出す。彼のゼンタに対する報われない愛は、オランダ人の要求に対して、見事な均衡を与える。彼の声域はこの役の高い音域に楽々と適合し、繰り返される高音部分を、やすやすと見事にやり遂げる。それは、楽々とした華麗な抒情性を要求されるときと全く同じだ。最初の登場のときから、最後に幕が降りるまで、注目を集めるエリックがいる。
二幕でエリックがゼンタとはじめて向かい合うとき、彼は自尊心と決断力を示す。このエリックは哀れっぽくもなければ、脅迫的でもない。彼は自らの強い気持ちとかつての愛情から生まれる誠実な感情をぶつけてゼンタを取り戻そうとする。ホフマンの歌う、生々しい夢物語は、忘れ難い。彼は変化に富んだ多彩な音色を駆使して悪夢の物語を紡ぐ。ホフマンがその官能的な声で物語る悪夢にはぞっとするほどの具体性を帯びる。彼は、ゼンタをおびえさせようとしているのではなく、自分自身が気にかかっていることを彼女と共有したいがために、夢の話をするのだ。 その存在の奥底から絞り出される、ホフマンの暗い、切望的な叫び声 Mein Traum sprach wahr!(あの夢は正夢だった) には、彼の喪失の悲しみの苦痛に満ちた現実が貼り付いている。それでもまだ彼は、愛のために、すなわち、自分自身の愛のため、そししてゼンタのために、闘おうと決心する。三幕の彼のカヴァティーなとフィナーレの合唱では、愛する人を助けようと全力を尽くして奮闘する。ホフマンのエリックは、最後の悲痛きわまりない叫び声、Verloren!(失われた!)に至るまで、希望を捨てない。結果的に、聴き手はエリック個人のドラマに、彼と同等のレベルで関わっているような気分に浸る。ホフマンのエリックは独特の寛容な雰囲気があり、好感が持てる。他の大勢の演奏者に比べて、ホフマンはエリックの多様な感情のうち、自己憐憫の気持ちを排除し、代りに、私たちにオランダ人に対する激しい同情心を起こさせる感情、つまり、苦しみを強調する。
ニーベルングの指環の中の役のうち、ホフマンは現在のところジークムントでもっとも有名だが、幻惑されかねないほど魅惑的なローゲの役も歌っているし、もうすぐ両ジークフリート役もするだろう。ホフマンのごく初期のワーグナーでの成功のひとつは、1975年2月ドルトムント、ハンス・ペーター・レーマンの創意あふれる演出でのローゲ役だった。
ケーテ・フラム Kaethe Flammは、熱狂的な批評を書いた。
若いペーター・ホフマンは、一夜にして大評判になるほど魅力的だ。もの凄い天賦の才能に加えて、それ以上にすばらしいテクニックを身につけた、若さあふれるヘルデン・テノール(彼はたったの30歳で、これが初めてのローゲ役の舞台なのだ)、彼はこの役を驚くほどの熟練振りと洗練された精巧さで演じ、この役の究極の微妙な雰囲気を徹頭徹尾、直感的に具現化した。
舞台写真を見ると、敏捷な雰囲気を醸すホフマンがいる。ちらちら燃える火のようにアップにした髪型、奇抜な化粧、曖昧な感じで身を横たえ、湾曲した指は無関心を装った疑い深さを示している。複数のレポートが、彼の堂々とした身体的美質、顔の表情の微妙な変化、細かで、無駄のない、はっきりと明瞭な一連の動作などについて語っている。ホフマンのローゲの、微妙な陰影の付け方の精妙さは、豊かで複雑な歌唱と併せて1976年10月15日のウィーン国立劇場の公演を記録したテープでも、明らかだ。
ホフマンはヴィントガッセンを手本としており、従って、正統的なヘルデン・テノールのスタイルでこの役を歌っているが、音色の美しさと華麗で英雄的な声質という点で、この偉大な先輩をはるかにしのいでいる。この役は中音域から低音域が要求されているのだが、ホフマンはそのバリトンが基礎になっている声で輝かしい響きを巧みに操り、旋律をしっかりと浮き上がらせる才能を示す。Ihr da im Wasserが、このように一気に弧を描くような壮麗さで歌われるのを私は耳にしたことがない。彼のローゲは、威厳があり、知的で、高貴でさえある。そして、何にもまして、鋭い直感力を持っている。一見して理性が勝っているとわかる火の神がここにいる。その炎のような口調は、彼の機転の利いた詭弁を反映している。その冷静な推論の裏には、神々の妥協と同様に、彼自身の妥協に対する軽蔑と皮肉が隠されている。彼は無関心を装うなぞめいた仮面をつけて、感情的に距離をとっている。 その寒々とした現代性は畏敬の念をおこさせ、 そのいかがわしさは人を魅了する。たとえば、このローゲは神々と合意することに嫌気がさしてきているように思えるし、彼が最後に虹の橋を渡ることを拒否するのは、彼が目が覚めた印なのだと感じる。Ehrem Ende eilen sie zu(彼らは終わりに向かって急ぐ) は苦い洞察に満ちている。それでも、ラインの乙女たちに対する彼の忠告 in der Goetter neuem Glanze sonnt euch selig fortan(さあ、神々の新たな栄光のうちに憩うがよい) は、横柄で威圧的に響く。それはまさに、あたかも神の命令のようにもっともらしいものだから、彼は結局のところ、常習的同調者じゃないのかなと感じる。ローゲの内省的な問いかけ、 Wer weiss was ich tue? (私がこれからすることが誰にわかるだろうか) は一瞬、弱く、それから、否定的に響くが、ジレンマに対する答えにはならない。むしろ、永遠に理解し得ない不可思議な人物像を、腹が立つほど、完璧に描き出す。最後まで、ホフマンのローゲの炎のような思考回路は不可解なままだ。堕落と道徳的清廉さの間にあって、安易な選択を拒否することによって、また、その性格の可能性を制限することを拒否することで、ホフマンはローゲの謎めいた不可解さを保っている。そして、そうすることで、観客の想像力を刺激する。ホフマンはこの役はそれほど頻繁に歌っていないけれど、それにもかかわらず、ローゲに関するヘルデン・テノールの歴史に、ひとつの叙事詩的に偉大な演奏を残した。
同様のことが、両ジークフリート役に関しても、間違いなく実現するだろう。歌手はこれらの役を綿密にきちょうめんに学び終えている。1983年のリサイタル盤の鍛冶の歌の録音がなんらかの証拠になるならば、ホフマンのジークフリートは、耳にも、そして演劇的にも、ぞくぞくわくわくするものになることは間違いない。彼はこの難しい歌を天衣無縫の奔放さで歌う。突き刺すような迫力の金属的響きと官能的な俗っぽさが溶け合ったその声は非常に魅力的で、大いに好奇心をそそられる。音の移動は流れるようだ。高いAへと、問題なく、きちんと、不安なく駆け上り、力強さと官能的な魅力は明白だ。彼が、オペラ全体を演じれば、この歌にあるのと同じ身体的特徴、ロマンチックな雰囲気、エロティシズム、気品、感受性の強さなどの要素によって完璧な人物像を描き出すであろうことを確信させられる。歴史上の他のどのテノールよりも、ホフマンはジークフリートの英雄性の本質を具現するだろう。オペラ・ニュース Opera Newsのインタビューで、ジークフリートの準備に関して、歌手は、このように話した。私は身体を駆使する歌手です。自分の身体をその役の状態にしなければならないと思っています。そうでなければ、ただ単にドラマのなかであっぷあっぷするしかありません。オペラ界は、ホフマンがこの役でデビューするのを期待して楽しみにしている。最近の他のどのテノールも、声楽的にも視覚的にも、ワーグナーの正真正銘の英雄としての彼の存在感に挑むことができるなどということはありそうもない。