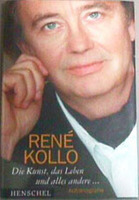ルネ・コロ自伝 [ルネ・コロ自伝]
資料4
RENE KOLLO
Die Kunst, das Leben und alles andere. . .
Autobiografie
2004
Die Kunst, das Leben und alles andere. . .
Autobiografie
2004
抄訳
pp.9-18 :生い立ち
pp.87-97:カラヤンとの関係(ザルツブルク1976年、ローエングリン)
ザルツブルク1974年、ストレーレル演出の魔笛、カラヤンvsストレーレルなど
pp.98-106:バイロイト音楽祭1977年、ジークフリートでW.ワーグナーと衝突!
pp.161-168;1981年スカラ座開幕公演のローエングリン事件
pp.169-172;1981年バイロイト音楽祭トリスタンとイゾルデ
pp.172-176;1985年バイロイト音楽祭タンホイザー
pp.9-18 :生い立ち
pp.87-97:カラヤンとの関係(ザルツブルク1976年、ローエングリン)
ザルツブルク1974年、ストレーレル演出の魔笛、カラヤンvsストレーレルなど
pp.98-106:バイロイト音楽祭1977年、ジークフリートでW.ワーグナーと衝突!
pp.161-168;1981年スカラ座開幕公演のローエングリン事件
pp.169-172;1981年バイロイト音楽祭トリスタンとイゾルデ
pp.172-176;1985年バイロイト音楽祭タンホイザー
1985年バイロイト音楽祭 [ルネ・コロ自伝]
1985年、バイロイトで最後の大役、すなわちタンホイザーを歌うことになっていた。他の大役はバイロイトですでに全部歌っていた。早世したジュゼッペ・シノーポリの指揮、ヴォルフガング・ワーグナーの演出だ。
サンフランシスコで親しい歌手仲間のヒルデガルト・ベーレンスたちと一緒に、『ニーベルングの指環』に参加していたので、サンフランシスコからバイロイトへ飛んだ。五週間ほどの練習期間だった。
サンフランシスコの公演でかなり参っていたうえに、花粉症が出始めていた。体調は最高だったが、ただ粘膜だけがかさかさに乾いていた。従って、当然声の調子もよくなかった。はじめはまだ大した問題にはならないと希望的観測をしていた。
バイロイトで借りていた家には素晴しく美しいテラスがあった。このテラスの上に桜の木がいまいましい薄桃色のつぼみをつけた大きな枝を広げていた。
桜は花を咲かせ、私はくしゃみをした。
一週間過ぎ、二週間、三週間が過ぎ去った。私はくしゃみをし、桜は咲いていた。私は毎日、毎日、今はまだ健康上の理由で自分の役を歌うことができないが、明日は状況は絶対に改善するだろうと、希望的観測を述べてシノーポリをなだめていた。
だが、状況は良くならなかった。
私は医者に行って、花粉症の薬を注射してもらった。しかし、効果はなかった。適切な音を出すどころか、私はくしゃみをし続けていた。幸いヴォルフガング・ワーグナーもジュゼッペ・シノーポリもとても冷静で、こういう状態にもかかわらず、私に対して好意的だった。幸いリチャード・ヴァーサルが練習期間中代役を務めてくれていた。それでも、オーケストラ練習は、自分で歌おうと頑張った。しかし、すぐに喉はまだ完全にからからにひからびていて、そういうひどい重圧に反応した声しか出ないことがすぐにわかった。
そこで、ついに、評判のいい私の耳鼻咽喉科専門医、ラインハルト・キュルステンに見てもらうためにウィーンへ行く決心した。私は操縦士免許を持っていたので、自家用機でウィーンへ行き、すぐに治療してもらった。(ついでに言うと、もうひとりの私の喉の専門医がベルリンのテオドール・リュッファーだ。彼にはこの十年困ったときに助けてもらっている) さあこれですべてがよくなると私は思った。一両日もすれば、声はまた元通りになるだろう。
医者に行ってからはかなり良くなっているように感じていたが、ゲネプロもヴァーサルに引き受けてもらい、シノーポリとワーグナーにプレミエには歌うことを確約した。
プレミエの日、11時ごろ祝祭劇場に行った。歌ってみると、驚くほど、楽々と声が出た。二十分ぐらい歌って、いい気分で朝食をとるために食堂へ降りて行った。そのあと、また練習のために戻った。
へなへなと膝をついて崩れ落ちてしまった。
また声がひあがってしまったのだ。
高音はもの凄い努力をして、やっとのことで絞り出さなければならなかったし、それも長くは続かないことに気がついた。
大恐慌!
どうするのだ?
五時間後には、初日の幕が開く。私はさらに試してみた。そして、当然うまくいかなかった。私はうなり、大声で叫んでいた。
その間にも、一休みするためと、何か飲んで喉の渇きを潤すために、何度も食堂に行った。しかし、無理矢理に数小節歌うことができるだけだった。その後にはすぐにまた声が出なくなる。昼の二時ごろには、私はすっかり疲れきってしまい、三時半に事務所に電話をかけて全力を尽くしてもだめだということを伝えた。私がどんな気持ちでそうしたか、だれもが自ずと理解してくれることを願うのみだ。
なんともタイミングが悪かった。
父は、まだバイロイトに来たことがなかったし、ワーグナーを崇拝してもいなかったが、タンホイザーのプレミエに来ると知らせてきていた。父は、上演の前に、楽屋で私に会いたいと思ったが、私がそこにいなかったので、守衛に尋ねた。不機嫌な感じを与えるフランケン方言で、守衛は父の質問に答えた。「コロさんは、そこにはいません・・・」
「なんだって。どうしてだ。冗談を言ってるのか。彼はきょうタンホイザーを歌うのだ」
「違います。多分もう車で行ってしまいましたよ」
息子が父をワーグナーに近づけ、ワーグナーのオペラを見せることができる機会は失われてしまった。というわけで、私のキャリアにおいてこれ以上ないほどの最低の最低というだけではなかった。
バイロイトの緑の丘を恐慌状態であとにしてから、アパートにあった物をまとめて、車で去った。アウトバーンに入ったとき、祝祭劇場からの生中継が始まったのをラジオで聴いた。
今なおバイロイトのことを考えると、今まで全く見過ごしていたことに突然気がつく。テラスに向いていた寝室は古い絹の壁紙だった。午前中はいつも声が出なかったけれど、花粉症だけでなく、壁紙も関係があったとは全く考えもしなかった。
頭の中で口ずさみながらハンブルクに向かった。妻が新たに授かった小さな娘、フローレンスと一緒にいる病院の前に車を止めて、エンジンを切ったちょうどその瞬間、タンホイザーの生中継放送の最後の音が鳴っていた。
病院の階段を上って、上の階に行き、妻の部屋に急いでいたら、年配の夫婦が廊下の壁添いのベンチに腰掛けていた。二人は一緒に沈み込むような感じでぼんやりと前を見ていた。二時間後、妻と別れて帰るとき、またあの年寄り夫婦の前を通った。今度は両手が震えており、蒼白のおちくぼんだほほを涙が流れていた。通り過ぎながら、より大きな悲劇があるのを意識した。すべて相対的なものなのだ。
この現実認識は、ただちに追いかけてきたマスコミとの関わり方においても、助けになった。大概のジャーナリストの頭には私がプレミエを前に不安に駆られてキャンセルしたのだろうし、要するにタンホイザーは歌えないのだろうと報道することしかないのだ。
そして、私の状況をもう一度説明し、健康を取り戻せば、残っている最後の三度の公演を引き受けられるであろうと言うためにヴォルフガング・ワーグナーに手紙を書いた。返事はどちらかと言うと、誤解と偏見があったようだった。以来、私たちの関係はと言えば、お互いに気分を害したままだ。
花粉症けんかというところだ。
タンホイザーは、ジェノヴァ、ハンブルク、ミュンヘン、ベルリン、ケルン、ロンドン、東京で歌い、成功している。
サンフランシスコで親しい歌手仲間のヒルデガルト・ベーレンスたちと一緒に、『ニーベルングの指環』に参加していたので、サンフランシスコからバイロイトへ飛んだ。五週間ほどの練習期間だった。
サンフランシスコの公演でかなり参っていたうえに、花粉症が出始めていた。体調は最高だったが、ただ粘膜だけがかさかさに乾いていた。従って、当然声の調子もよくなかった。はじめはまだ大した問題にはならないと希望的観測をしていた。
バイロイトで借りていた家には素晴しく美しいテラスがあった。このテラスの上に桜の木がいまいましい薄桃色のつぼみをつけた大きな枝を広げていた。
桜は花を咲かせ、私はくしゃみをした。
一週間過ぎ、二週間、三週間が過ぎ去った。私はくしゃみをし、桜は咲いていた。私は毎日、毎日、今はまだ健康上の理由で自分の役を歌うことができないが、明日は状況は絶対に改善するだろうと、希望的観測を述べてシノーポリをなだめていた。
だが、状況は良くならなかった。
私は医者に行って、花粉症の薬を注射してもらった。しかし、効果はなかった。適切な音を出すどころか、私はくしゃみをし続けていた。幸いヴォルフガング・ワーグナーもジュゼッペ・シノーポリもとても冷静で、こういう状態にもかかわらず、私に対して好意的だった。幸いリチャード・ヴァーサルが練習期間中代役を務めてくれていた。それでも、オーケストラ練習は、自分で歌おうと頑張った。しかし、すぐに喉はまだ完全にからからにひからびていて、そういうひどい重圧に反応した声しか出ないことがすぐにわかった。
そこで、ついに、評判のいい私の耳鼻咽喉科専門医、ラインハルト・キュルステンに見てもらうためにウィーンへ行く決心した。私は操縦士免許を持っていたので、自家用機でウィーンへ行き、すぐに治療してもらった。(ついでに言うと、もうひとりの私の喉の専門医がベルリンのテオドール・リュッファーだ。彼にはこの十年困ったときに助けてもらっている) さあこれですべてがよくなると私は思った。一両日もすれば、声はまた元通りになるだろう。
医者に行ってからはかなり良くなっているように感じていたが、ゲネプロもヴァーサルに引き受けてもらい、シノーポリとワーグナーにプレミエには歌うことを確約した。
プレミエの日、11時ごろ祝祭劇場に行った。歌ってみると、驚くほど、楽々と声が出た。二十分ぐらい歌って、いい気分で朝食をとるために食堂へ降りて行った。そのあと、また練習のために戻った。
へなへなと膝をついて崩れ落ちてしまった。
また声がひあがってしまったのだ。
高音はもの凄い努力をして、やっとのことで絞り出さなければならなかったし、それも長くは続かないことに気がついた。
大恐慌!
どうするのだ?
五時間後には、初日の幕が開く。私はさらに試してみた。そして、当然うまくいかなかった。私はうなり、大声で叫んでいた。
その間にも、一休みするためと、何か飲んで喉の渇きを潤すために、何度も食堂に行った。しかし、無理矢理に数小節歌うことができるだけだった。その後にはすぐにまた声が出なくなる。昼の二時ごろには、私はすっかり疲れきってしまい、三時半に事務所に電話をかけて全力を尽くしてもだめだということを伝えた。私がどんな気持ちでそうしたか、だれもが自ずと理解してくれることを願うのみだ。
なんともタイミングが悪かった。
父は、まだバイロイトに来たことがなかったし、ワーグナーを崇拝してもいなかったが、タンホイザーのプレミエに来ると知らせてきていた。父は、上演の前に、楽屋で私に会いたいと思ったが、私がそこにいなかったので、守衛に尋ねた。不機嫌な感じを与えるフランケン方言で、守衛は父の質問に答えた。「コロさんは、そこにはいません・・・」
「なんだって。どうしてだ。冗談を言ってるのか。彼はきょうタンホイザーを歌うのだ」
「違います。多分もう車で行ってしまいましたよ」
息子が父をワーグナーに近づけ、ワーグナーのオペラを見せることができる機会は失われてしまった。というわけで、私のキャリアにおいてこれ以上ないほどの最低の最低というだけではなかった。
バイロイトの緑の丘を恐慌状態であとにしてから、アパートにあった物をまとめて、車で去った。アウトバーンに入ったとき、祝祭劇場からの生中継が始まったのをラジオで聴いた。
今なおバイロイトのことを考えると、今まで全く見過ごしていたことに突然気がつく。テラスに向いていた寝室は古い絹の壁紙だった。午前中はいつも声が出なかったけれど、花粉症だけでなく、壁紙も関係があったとは全く考えもしなかった。
頭の中で口ずさみながらハンブルクに向かった。妻が新たに授かった小さな娘、フローレンスと一緒にいる病院の前に車を止めて、エンジンを切ったちょうどその瞬間、タンホイザーの生中継放送の最後の音が鳴っていた。
病院の階段を上って、上の階に行き、妻の部屋に急いでいたら、年配の夫婦が廊下の壁添いのベンチに腰掛けていた。二人は一緒に沈み込むような感じでぼんやりと前を見ていた。二時間後、妻と別れて帰るとき、またあの年寄り夫婦の前を通った。今度は両手が震えており、蒼白のおちくぼんだほほを涙が流れていた。通り過ぎながら、より大きな悲劇があるのを意識した。すべて相対的なものなのだ。
この現実認識は、ただちに追いかけてきたマスコミとの関わり方においても、助けになった。大概のジャーナリストの頭には私がプレミエを前に不安に駆られてキャンセルしたのだろうし、要するにタンホイザーは歌えないのだろうと報道することしかないのだ。
そして、私の状況をもう一度説明し、健康を取り戻せば、残っている最後の三度の公演を引き受けられるであろうと言うためにヴォルフガング・ワーグナーに手紙を書いた。返事はどちらかと言うと、誤解と偏見があったようだった。以来、私たちの関係はと言えば、お互いに気分を害したままだ。
花粉症けんかというところだ。
タンホイザーは、ジェノヴァ、ハンブルク、ミュンヘン、ベルリン、ケルン、ロンドン、東京で歌い、成功している。
1981年バイロイト音楽祭 [ルネ・コロ自伝]
1『それでも、ライラックはなんと良い香りがすることか』
バイロイト音楽祭 ポネルのトリスタンpp.169-172
バイロイト音楽祭 ポネルのトリスタンpp.169-172
1981年、二年振りに再びバイロイトに来た。すでに書いたが、ミュンヘンでのエヴァーディングとのトリスタンが終わっていたので、暇だった。今度のトリスタンはバイロイトのヴォルフガング・ワーグナーの依頼で、ジャン・ピエール・ポネル演出、ダニエル・バレンボイム指揮だ。
ポネルは当時世界的にひっぱりだこだったオペラ演出家だったが、私はまだ共働したことがなかった。そこで、リハーサルの前にミュンヘンで会って一緒にお昼をした。彼は演出上の考えを少し話してくれた。二時間後、私たちは満腹し、それぞれ満足し、二人とも、この公演が楽しみになった。
こうして、夏には大好きなバイロイトに再びいたというわけだ。二年行かなかった間に、大勢の新しい歌手たちが加わっており、たぶんだれも私のことを知らなかった。本稽古はうまくいったが、初日は全くの期待外れだった。
うまくいかなかったことはむしろ励みになり、私を発奮させ、今度は完璧にやろうと意を強くした。私にとってただ受け入れられることほど退屈なものはない。その場合、すべての喜びはすでに過去のことだ。とにかく丸一日かかる本稽古では本格的には歌わなかったが、ゲネプロはそうはいかない。しかし、初日に備えるために、ゲネプロでも全部を感情を込めて本格的には歌いたくはなかった。こうすることは、バイロイトでトリスタンをカットなしで全部通して歌うときには、特別に重要だ。1980年、初トリスタンだったチューリッヒでは、有名な『Tag- und Nacht-Sprung』がカットされた通常の版を歌った。このカットはワーグナーも認めている。(バイロイトでは全ての役をカット無しで歌った)
チューリッヒでの経験から、トリスタン役は粘膜がひどく乾いてしまうことがあるということがわかった。そういうわけで、バイロイトのトリスタンの準備では天才的なことを思いついた。舞台担当職員に言って、三幕の二カ所、演出の希望によって私が倒れなければならないところの、舞台の床下に、自転車乗りが持っているような水のボトルを埋め込んでもらった。すべてのボトルに小さな穴を開けて、それぞれ緑色のストローを差し込んだが、草のように見せた舞台では全く気づかれなかった。そうして、例えば三幕でクルヴェナルが歌っている間に、その水によって、すばらしくさわやかな気分になり、声も回復することができた。
この種の妙案は私だけが思いついたことではない。カルーソーは衣装に小さな瓶を幾つか隠した。その中に普通の塩と油と水を混ぜたものが入れてあった。声が枯れたら、気づかれないように、観客に背を向けて、極めて優雅に瓶の中のものを喉に流し込んだ。ヴォルフガング・ヴィントガッセンもその種の作戦を話してくれた。彼は、もちろん私もだが、長年世界中の舞台をそうしたちょっとしたことで切り抜ける方法を心得ていた。彼は舞台にいる間ずっとガムのようなスグリ味の飴をほっぺたの片方に入れて、恒常的に少量の水分が酷使されている喉に注ぎ込まれるようにしていた。(しかし、これはバイエルンのリビニという名前の飴でなければだめだ。というのは、ほっぺたの裏にしっかり吸い付いたみたいになって決して動かないのはこの飴だけだからだ)それから、私の新人時代からの魅力的な相手役ゲルティ・ツォイマーはトラック一台分の丸いのど飴をなめて、そののど飴みたいにぽちゃぽちゃになった。
一部の歌手ともめたにしても、ポネルとバレンボイムとの練習期間は私のキャリアの中で最高だった。気楽にのびのびできた。何度か、ポネルは私が彼の演出意図に従っていないことに気がつくと、自ら私のところにやってきて、家に招待して、問題点について話し合った。彼はワインを飲みながら、私の反論に心を開いて耳を傾けた。そして、幾つかは彼にとっても納得がいったように見えた。私は少なくともその時まで、主要キャストとオペラについて楽しく語り合い、その考えを考慮する演出家に出会ったことがなかった。自分のやっていることをほんとうによくわかっている芸術家だけが、寛大かつ賢明な態度をとることができる。
ポネルはすでにミュンヘンで会ったときに、このオペラの結末の新しいアイディアのことをほのめかしていた。これは私の解釈と完全に一致していた。彼は、トリスタンの死後、イソルデを登場させないつもりだった。
最後の幕で、トリスタンは彼の周囲の出来事はすべて高熱による幻覚、いわば、昏睡状態における夢だと思っている。その結果、観客は古びた大作オペラに改めて対峙させられることになる。すべてはまさに考えであり、哲学にすぎない。全ては超越的になり、永遠の宇宙に溶け込んでしまう。マルケ王とブランゲーネを乗せた船の到着、全ての戦闘の叫び声、クルヴェナルの死などはもはやまったく存在せず、いわば、ただ単に時間が経過しているにすぎない。
私は、ワーグナーが五十年長く生きていたとしたら、あの最後のところは全く書かれなかったであろうと確信している。当時はオペラの結末は従来の様式に従って作曲しなければならなかった。しかし、今なら彼はあらゆることを、超越的かつ形而上的領域の中で経過させただろうし、何であれ現実的必然性に配慮することはなかっただろう。おそらく今日天上の響きと言われているのと、かなり似たような音楽的手段を使っただろう。
残念なことに、ポネルはゲネプロの直前になって、通常の演出と異なる結末にすることに決めたので、その考えを完全に実行に移すには遅すぎた。ヴィーラント・ワーグナーも、その祖父の作曲した結末で、似たような困難を経験している。彼はトリスタンの死の直後にイゾルデの愛の死、「穏やかに静かに」をつなげたいと常に思っていた。
![ワーグナー:楽劇《トリスタンとイゾルデ》 [DVD] ワーグナー:楽劇《トリスタンとイゾルデ》 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51nk75d5N7L._SL75_.jpg)
目次
1981年スカラ座開幕公演 [ルネ・コロ自伝]
1981年12月7日 ミラノ・スカラ座シーズン開幕公演 ローエングリン
クラウディオ・アバド指揮、ジョルジュ・ストレーレル演出pp.161-168
クラウディオ・アバド指揮、ジョルジュ・ストレーレル演出pp.161-168
ローエングリンに関しては、1980年代のはじめには、トリスタンに対するような興味はもはや持っていなかった。とにかくあまりにも頻繁に歌いすぎていた。そのころまでに、百回以上歌っていた。だから、ちょっと休みたかった。だが、ジョルジョ・ストレーレル(Giorgio Strehler)とクラウディオ・アバドという組み合わせは、魅力的だったので、1981年にミラノへ行った。ミラノのスカラ座がドイツ・オペラで開幕されたことはまだなかったということもあって、こういう面からも名誉ある仕事だった。私は、イタリア的なメルヘンチックで軽やかなローエングリンを期待していた。だから、この仕事は、とにかく楽しみだった。それが、思いがけないことになってしまった。
ゆっくり休んで、元気満々で、私はこの北イタリアの大都市に到着すると、すぐホテルからスカラ座へと乗り込んだ。演出家も共演者たちも全員集合していた。エルザは魅力あふれるアンナ・トモワ・シントウが演じた。ストレーレルはいつものように叫びまくりせわしげに走り回っていた。ザルツブルクのときから、すでにこういうことは知っていたから、今更驚きもしなかった。
彼はまずローエングリンの登場場面について、その思いつきを説明した。それはいまだかってないほど、ユニークなものだと、彼は非常に誇らしげに告げた。舞台上には、直径およそ1.5メートルの黒く塗った柱が数本、二列に向かい合って立っていて、これは、ローエングリンの到着に際して、左から右へ、そして、逆に右から左へと動くことになっている。ローエングリンは、前面にある一本の柱のかげに、隠れていて、人々に気づかれずに、その隠れ場所から歩み出ると、突然、舞台前面中央に、輝かしい光に包まれて立っているというわけだ。
非常に美しい登場の仕方だ。ただ、とても残念だったのは、作品の論理に添って、はめ込まれておらず、作品の内容に合った感覚が犠牲になっていたら、最高にすばらしいギャグも私を納得させないということだ。合唱が数小節歌った後で、私は後ろ舞台に向かって歩かなければならない。つまり、30ないし35メートルの距離を進むわけだ。壁にプロジェクターで映し出された白鳥に挨拶して、再び国王のいるところまで前進。特に不明確だったのは、それならば、実際のところローエングリンがその場所に現れる必要があるのかということだった。私は、彼はいつも聖杯のつけた護衛と共に登場しなければならないと思う。それなのに、柱の間から登場したあと、白鳥にむかって30メートルも後方に走っていかなければならないというのは、一体、どういうことなのだろう。とにもかくにも、その白鳥こそが聖杯がつけた護衛なのだ。
私は、自分がこういうことにあまりにもこだわりすぎるのはわかっている。いずれにせよ、失望が顔に出てしまったのだろう。ストレーレルは、私の演技をそのように解釈した。ただちに、私たちの間に壁ができ、雰囲気が壊れた。他の歌手たちと話し合ったとき、彼らは私にこう説明してくれた。数日来、ここのところではぼんやり立っているが、そもそも何のことやら意味がつかめないから、実際のところどうするべきかさっぱりわからない。
その後10日間がこんな具合で過ぎた。ストレーレルは、ひたすら、彼の柱をいじくりまわし、私たちを無視した。彼の機嫌が多少いい時を見計らって、私は彼に、実際のところ、あの場面は何を意図しているのか、質問した。その日まで、すでに一週間以上過ぎていたにもかかわらず、私たちは演出意図が全然わからなかったのだった。
彼は、血わき肉おどるという感じのいかにもイタリア人らしいイタリア語で説明してくれた。ローエングリンは、いわゆる『ドイツ的な聖人たち』 といった種類のものとは無関係だし、エルザの存在も全然知らなかったのだ。彼はただ単に彼女に出会ったにすぎない。なぜならば、彼は、戦争に際して国王を助けて戦うために、天上から降りてきたのだから。「戦士らしく」「これで十分だ。(Porco - basta!)」
ローエングリンはエルザをはっきりと知っていたし、彼が地上に降りたのは、人間になって、人間の最高の特質であって、冷厳とした聖杯騎士団には存在しない愛を望んだからなのだと、私は遠慮がちに反論した。彼は、叫んだ。君たちドイツ人はいつも、一種の『聖人』 を欲しているようだ。だが、そんなものはくそくらえだ。まったく、くだらない。ローエングリンは「戦士」であって、「国王と共に戦うために、地上に」降りて来たのだ。
やれやれ、そして、こういう具合になった。合唱団はプロシャ式の膝を曲げない直立歩調で行進しなければならなかった。こんなのは、プロシャ軍にとってさえ、多大な努力を要するものだから、ミラノ・スカラ座の合唱団にとっては全くもって不可能なのは目にみえていた。一方、歌手たちは第二次世界大戦のドイツ軍の鉄兜をかぶらされた。それは、真っ黒で、SSと書いてあった。ドイツ人はみんなナチで、ワーグナーに全ての責任があるというわけだ。
そのとき、私たちのところでどれほどファシズムが横行していたかを、イタリア人に非難させてよいものかと、思った。イタリア人だってファシズムに陥り、少なくとも多少はファシズムに貢献したのだ。それなのに、よくも安易にそういう演出ができるものだ。
二日後、最初のドレス・リハーサルがあった。ストレーレルの舞台監督 Ezio Frigerio が責任者だった。私は武装した騎士の衣装を身につけさせられた。それは、中世の勇士だってだれもあんまりうれしくなかったにちがいない格好だった。私も全然うれしくなかった。背中のひもをきつく締められたあとは、息もできなかった。だれでもわかるように、息ができなければ、歌う事はできない。Frigerio は間違いなく、こんなことをただのドイツ人ひとりに対して考えつくとは全く思えないのだが、イタリア人テノールに買収されて、私を殺そうとしたに違いないと確信したほどだ。そういう具合に締め付けられたものだから、声に影響が出た。やれやれ、言葉もない。私はFrigerio氏に、難しい役を歌わなくてはならないのだし、全部が鉄とブリキで出来た、30キロ以上の重さの重装備の甲冑を身につけていたら、良くできないと思われるから、違うのにしていただきたいと、非常に丁重にお願いした。
彼はいかにもイタリア人らしい微笑みを見せたので、わかってくれたと思った。ところが、次の日、試着室へ行くと、まったく同じだった上、さらにその上に、当時はまだ婚約者だったベアトリーチェが持ち上げることができないようなマントを羽織ることになっていた。私は再び直してもらいたいと伝えた。私はこの重装備の武具を身につけたくないし、さらに付け加えれば、何よりも重要な事は、私はコートスタンドとしてではなく、ローエングリンとして契約したのだ。確かに武装はしていなければならない。ストレーレルはローエングリンは戦士であるという点に立脚しているのだ。私はそうは思わない。私は「戦士」ではない。非常に広い意味ではそうだろうが、私はがらくたを身に着けるつもりはない。
さらに二、三日、そのままけいこを続けた。声はさらに酷くなった。このようにして、総稽古の前日になった。朝、スカラ座に行ってみたら、毛ほども軽くなっていない、不寛容そのものみたいな、相変わらずの甲冑に出会った。
共演者のひとりが、私の衣装部屋にやってきて、これは前代未聞の最大の破廉恥行為かもしれないと言った。しかし、それは私の衣装のことではなくて、全く別のことを言っていたのだった。彼は私にイタリアの新聞を読むようにと手渡した。大きな文字の見出しはこうだった。「太鼓腹の銀行家、ローエングリン」 私はこのプロダクションの直前に、ダイエットしていたものだから、この一文は特別ショックだった。私は甲冑と新聞記事ををひっつかむと、舞台へ突進した。
まさに「戦士」が目覚めたのだ。
ただちに時の声をあげて舞台に登場した。みんな、あっけに取られて声もなかった。私は甲冑を聖なるスカラ座の舞台に叩き付け、Frigerioとストレーレルとアバドにはもちろんのこと、客席に座っている連中全員に新聞を示して、舞台上から怒鳴った。「プレミエ開幕前に、職員が歌手を誹謗するインタビューに応じるような劇場にもはや用はない!」
私は荷物をまとめると、ベアトリーチェと一緒に、Ascona にある、母から相続した、小さな家に車で行った。ただちに白熱した電話が飛び交うことになった。私は、完全に鼻づまりだったので、電話に出なかったから、電話の応対は、かわいそうなベアトリーチェが全部引き受けざるを得なかった。
翌朝、とうとうスカラ座の監督が自ら電話をよこした。私としては、まだ劇場と縁を切るべきたとは思っていなかったから、劇場が関わっていないくだらない話は忘れてもいいところだった。
マエストロ・アバドからも電話がかかってきた。これは彼の最初のローエングリンなのだ。とにかく彼はこの件には全く無関係だし、彼を喜ばせるためなら戻ってもいいと思った。明日のゲネプロ(最終総稽古)には戻ると約束した。
こういうわけで、翌日午前十時ごろには、再び劇場に行った。私の甲冑にまだ変化はなかったが、もしかしたら、恥ずかしさですでになんだか相当さびているようだったが、とにかくそれを身につけるしかなかった。共演者がまた最新の新聞を持ってきた。もういくつか新しい記事があって、私が一方的に非難されていた。私は何も言わなかった。なぜなら、イタリア式になだめられるだけだから。
ちゃんと声も出ず、不機嫌に、ゲネプロを終えて、ホテルに戻ると、再び荷物をまとめて、Ascona に行った。ついに、翌日、ベアトリーチェに、私の代理として、キャンセルを伝えてもらった。
ただちに電話が熱く鳴り響いた。ストレーレルはローエングリンの演出から離れていた。彼はジャーナリストにもう演出はやれない、それに関して何もすることはないだろうと話した。私がこのプロダクションにいるかぎり、彼はたしかに何もできなかったという点では、彼の言ったことはまったく正しい。引用した文章以外に、演出意図について、全期間を通して、なんと、何一つ説明を受けなかった。わたしは左へ行くべきなのか、右へ行くべきなのかということさえ、わからなかった。そして、最近十日間は、彼はもはや劇場に姿も見せず、助手の女性にけいこを任せきりだった。
私たちはドイツに車で戻りたかったので、プレミエの日に、預けてあった残りの荷物を取りにミラノへ行った。ホテルはいわばスカラ座のセンター事務所だということを知っていたので、無用な騒ぎを起こさないために、ベアトリーチェがひとりで車でホテルに行った。その間、私は別のホテルで待っていた。そのホテルで、私はジャーナリストのGudrun Glothと会うことを約束していた。彼女は客演に関する大作を物にしたいと望んでいた。後で、ハンブルクから来ていた、私の録音プロデューサーのKlaus Laubrunnが合流した。彼はプレミエを見たいと思っていたのだ。彼は私に、とにかく歌うべきだとしつこく迫った。そうすることによって、一般の観客に感銘を与えるのであって、そうでなければ、みじめなだけだ。私は決して破滅型の人間ではないし、彼の言う事はもっともだったので、気持ちが和らいだ。
後退したり、前進したりで、へとへとになりながらも、私は初日をそこそこのレベルでこなした。私にとって最高の舞台ではなかったが、観客は大喜びの大成功だった。そして、幕が降りた後、ストレーレルとFrigerioも突如舞台に登場して挨拶をした。私たちはほとんど目を合わさなかった。ちょっと気がついたこと。この公演は音楽的にも問題があった。ローエングリンで、このときのミラノのようなバラバラの合唱は一度も聞いたことがない。歌い始めるのが早すぎる歌手たちがいても、他の歌手たちはそれを止めようともしないのだ。当時、このプロダクションが失敗だったことからも、アバドはまだ指揮者として秩序を維持する事ができなかったことがわかる。
翌日の新聞には、天才的なストレーレルの演出がいかなるものだったか、そして、ローエングリンの新たな世紀が始まったと書かれていた。私としては、この新たな世紀には、もう歌う必要もないのを単純にうれしく思っている。
目次
バイロイト音楽祭1977年 [ルネ・コロ自伝]
「はじめよ!と、判定役が叫ぶ」
バイロイトとテレビ番組 pp.98-106
1977年バイロイト音楽祭「ジークフリート」ピエール・ブーレーズ指揮、パトリス・シェロー演出
バイロイトとテレビ番組 pp.98-106
1977年バイロイト音楽祭「ジークフリート」ピエール・ブーレーズ指揮、パトリス・シェロー演出
1973年、ヴォルフガング・ワーグナー演出のマイスタージンガーに出演。エヴァちゃんはまたハンネローレ・ボーデで、ザックスは、その当時は初役だったカール・リッダーブッシュだった。彼はあまりにも早く亡くなってしまった。凄い配役は、ベックメッサーで、クラウス・ヒルテだった。
マイスタージンガーの二年後の1975年はパルジファルの新演出で、非常にやりがいがあった。二十年来ずっとバイロイトの唯一の演出だった、独創的で忘れ難い、ヴィーランド・ワーグナーのパルジファルのあと、はじめての新演出だった。ヴォルフガング・ワーグナーの新演出も良かったと思う。マスコミにも受け入れられた。
このシーズンの終わりに、ヴォルフガング・ワーグナーは、私に、ジークフリートを歌うことができるかどうか質問した。もちろん喜んでやりたいが、同時に「神々の黄昏」をやることはまだできないというのが、私のこたえだった。はじめから両者をやるのは負担が重すぎるだろうと思った。
そして、この指環は全部若いフランス人が演出することになっており、指揮はピエール・ブーレーズだといううわさだった。この天才少年はパトリス・シェローという名前で、パリではすでに世間をあっと言わせるような大成功をおさめていた。うわさをきいて、私はシェローと会いたいと言った。それは、彼が、別のものではなくて、まさに「リング」を演出したがっているのだということを確信するためには、彼の演出構想について知りたかったからだ。ここ数年、残念ながら、少なからぬ演出家に対してそういうことを確認せざるを得なかったことがままあった。
私は、繊細で、非常に神経質な、かつ、何よりも自信にあふれているくせにまったく自信がないようにも見える若い男と出会った。彼が私に話したことは非常に説得力をもっていることがすぐにわかった。彼の演出は、一部の人たちが即座に悪意を持って解釈したように、政治的な意図しか持ち得ないというよりは、非常に演劇的だったと思う。シェローは、動き、人間関係、演劇的な時を演出した。それは、まさしくシェイクスピアの演劇だった。100%シェローと考えが一致したわけではないにしろ、良い演劇なら、不都合はすぐに忘れて、妥協できるから、シェローと、相手役のギネス・ジョーンズ、ハインツ・ツェドニク、ドナルド・マッキンタイヤーと仕事をするのはとても大きな喜びだった。
後に、シェローは「リング」に関する自著の中で私のことをこう書いた。私は非常に才能があるが、同時に多少怠惰なところがある。これは正しい観察だ。ただし、私の怠惰さというのは、歌手としての自己防衛に起因するもので、よく考えた結果なのだ。彼のような演劇の演出家の要求する事を歌手が全面的に実行に移したら、あっという間に声がだめになってしまうだろう。(若い世代に警告しておく!) オペラという芸術形態は、演劇とは全く異なる身体の扱い方が必要なのだ。ここのところをよく考えるべきだ。歌うということはとにかく緊張をはらんだ停止状態でこそ成り立つのだ。その状態でなければ、美しく歌うことはできない。
オペラと演劇はどこが違うか、ちょっとした出来事を紹介しよう。これは、バイロイトのジークフリートで起こったことだが、脚を骨折したとき、薮の陰に隠れて歌うように求められた。
そこで、私は、私用の薮の後ろのバー用の腰掛けに座り、前には楽譜を立て、時々ちょっと喉をうるおすために、あめ玉とコカコーラをその上に載せておいた。観客からは私は見えなかった。その公演では、ただ私の声だけが聞こえていたのだ。私の役、つまり、ドイツの伝説の勇士の役は、演出家シェローおんみずから演じた。南国の黒髪の男が私の金髪のかつらをつけると、とてもおかしく見えた。それで、落ち着かない雰囲気だった。まったくひどく誇張して、身振りはやたらに大きく、細かいところまで感情豊かだった。私たちとのリハーサルのときは、とても美しくて感動的だったのだが、あの晩は全体的に私の趣味ではなかった。
(この時の写真がバイロイトのHPにあります。とても小さい白黒写真ですが、こちらです)
一幕の後、彼は汗まみれになって二人の共用の楽屋に入ってきた。私は気の毒そうに彼を見て、言った。 「親愛なるパトリスくん、ご自分の演出がどんなに骨が折れるかわかったかな。私の場合はその上に歌わなければならないんですからね」 それから、私は彼が誇張しすぎているということも説明した。「そう。わかっていますが、どうもひどくあがってしまって」
オペラと演劇の違いが非常にはっきりとした、面白い思い出だ。演劇は完全に身体を使い尽くすことが可能だ。それに対してオペラは歌唱のために静止した状態が必要なのだ。だから、動きと静止に関して、正しい認識を持つことが、歌手の為すべき仕事なのだ。またこういう場合もある。相手役のギネス・ジョーンズと、最後の二重唱 "Ewig war ich, ewig bin ich""の最後の音を、楽譜に全然書かれていないのだが、2点ハ音で歌った。しかし、これは、その時はひどく走り回ったりせずに、一度試してみただけだった、動きが激しい場合にはこんなことは所詮できはしない。バイロイトで「ジークフリート」の稽古の開始に際して、ピエール・ブレーズと一度会う約束をしていた。その日は、ハンブルクまで車を運転して行かなければならなかったので、なんとなく落ち着かなかったのに、ブーレーズは約束の時間を何度も遅らせた。四時間も遅れて、やっと彼はやって来た。彼は楽譜を車のトランクルームからつかみ取り、私たちは、コレペティトールと一緒に練習室に行った。
その時、かなり驚いたのは、指揮をはじめると、明らかにまだあまりスコアを知らないということがわかったことだった。彼は常に拍子をとっていた。最初の稽古で演奏に関する希望を全く言わなかったのにも、驚いた。練習期間中を通して、一秒も彼と「リング」に関して何一つ語り合わなかった。彼は常にとても魅力的だったが、まさにバイロイトで、共にひとつの作品を創り上げるのなら、何かもっとそれ以上のものを期待するところだ。あるいは、少なくともそうあるべきだと思うのだが、残念ながら、今日では芸術的な熱意や願望を披瀝しないのが常識になってしまったようだ。ひょっとしたら、自信がなかったのか? 歌手仲間でも、以前に比べると、今日では芸術上の専門的会話や真剣な議論はほとんど行われなくなってしまった。
Ich lade gern mir Gaeste ein (千客万来)というのは、私が1977年に始めたテレビ番組だ。ZDFの制作で、生放送番組だった。録画撮りを再生するのではなく、常に同時放送だった。それに、ちょっとしたシーンを演じることになっていた。実際のところ、私は本当に一度は俳優になりたいと思ったことがある。その上、喜劇役者のオッティ・シェンクを獲得するという幸運が得られた。彼は全ての放送に出演してくれた。
最初の放送はバーデンバーデンで、ずっとベルリンでジャーナリストをしていた友人のヘンノ・ローマイヤーが制作することになった。二度目の録画の後、三日間、新シーズンの初ジークフリートを歌うように求められているのであるから、私はヴォルフガング・ワーグナーに数日間バイロイトを留守にする許可を求めた。
彼の承諾を得て、最初の稽古を気にする事なく安心してバーデンバーデンへ行った。放送の準備のために、およそ一週間あった。一日中、録画が行われることになっていたバーデンバーデンのホテルで、台本の修正に携わった。もうひとつ認識しなければならないことがある。歌手にとって、その種のホールにおける空気不足は、絶対的によくない。何故かと言えば、そうなると、粘膜がかさかさに乾いて、声が損なわれるからだ。(歌手は常に新鮮な空気を必要としている) 私の声は即座に最初の疲労症候群を示したが、各放送においては相当量を声を消耗せざるを得なかった。実際、相当な負担だった。私は次第にいらいらしてきて、初日の公演が心配になってきた。
それ以後、全部で十回の番組を制作したが、これらには最高に有名なスターたちが参加して、立派なものだった。このように制作された各放送はおよそ数千マルクの制作費がかかたっと思う。こんなことは今日ではもはや不可能だし、当時も文化的、芸術的放送としては異例の大金が投じられていた。世界的に有名なバイオリニスト、ユーディ・メニューイが共演者のステファン・グラペッリと共に出演したし、偉大なクラリネット奏者のバンドリーダー、ベニー・グッドマン、歌手仲間のビルギット・ニルソン、シェリル・ミルンズ、ブリギッテ・ファースベンダー、ルチア・ポップ、ジュリア・ミゲネス・ジョンソン、あるいは、喜劇役者のヴィクター・ボルゲといった人々がいた。要するに、最高の人たちの中の最高の人たちが集まっていた。
それに、時には、何もかも完全に違ってしまったりもした。生放送だったから、だれかが言ったように、足が冷たくなった等という理由で、ほんのちょっと前でさえ、出演者がキャンセルすることもあった。当然、適当な代りの人をすぐに探して、見つけたが、私は仕事の前に立ち止まって、出演者Aのために書いた台本を大急ぎで忘れて、新たな出演者Bのための台本を覚える。これはいつも簡単というわけにはいかなかった。というのは、特別の場合、デュッセルドルフのキャバレー"Komoedchen"の仕事仲間の台本が来て、私のところに回ってくるのが相当遅いのだ。そして、とにかくすでに完全に頭痛がしてきている私は、声が最悪になりそうだという心配のために、さらに負担が重くなるというわけだ。
そういうわけで、1977年のある土曜日には、最悪の状況に陥っていた。ありがたいことに、観客をとても迅速に参加させることができて、骨が折れるが、楽しい2時間の後、最後の音が消えた。汗だくになって、完全に疲れ果ててグロッキーで、ホテルにはうようにしてもどった。軽く食事をして、ビールを飲んで、ベットに転がり込んだ。というのは、次の日は、二つの公演が立て続けにあって、なんだか危ない感じがしていたからだ。
次の朝、目が覚めて、コーヒーを部屋まで持って来てくれるように注文しようとしたが、私の声は、まるでゴビ砂漠みたに干上がっていた。歌手は他の人たちよりこういうい状況には慣れているから、まずは落ちついてコーヒーを飲んでから、軽くウォーミングアップをやってみるために劇場に行った。非常に慎重にやった結果、もう数分後には再び声が出た。その声は私の耳にも相当酷く聞こえたが、他人の耳には絶対にずっと酷く聞こえたに違いない。それでも、声は徐々に戻ってきた。30分後、私はホテルに戻って、朝食を取り、その後、美しい公園を散歩して、いい空気をできるだけいっぱい吸った。だが、何か衰弱感があったので、バイロイトのヴォルフガング・ワーグナーに、とりあえず最初の警告をしておくほうがいいだろうと思った。「ジークフリート」は間違いなく大丈夫だと思ったが、歌手の仕事と、さらにもうひとつ放送が迫っているから、数日中に行けるかどうかは保証できなかった。特に、ジークフリートの適当な代役が大勢その辺を走り回っているなんてことはあるはずがない。そこで、私はヴォルフガング・ワーグナーに、「ジークフリート」の公演は間違いなく大丈夫だが、緊急の場合に備えて、代役を準備しておくのが望ましいという趣旨のことを書き送った。
数時間後、バイロイトから電報がきた。その電報は私には理解できない不可解な口調だったのでびっくりした。「貴殿が月曜日の稽古に参加しない場合は、重大な結果を自ら招くものである.........」とかなんとかだった。最近のテノールにおける大きな成功は全部私がもたらしたもので、私たちはお互いに非常に親密で友好的な関係を保っていたところだったから、私はこの内容に度肝を抜かれ、吃驚仰天した。私としては、彼が喜ぶようにしたかったのだ。それに対する、お返しがこれだとは! 通常は、上演の日の正午までに病気によるキャンセルを通告すれば十分なのだ。それをいったい何をしようというのだろうか。あの公演のためにもう新たなジークフリートを確保したとでもいうのだろうか。しかし、どんなに困難でも、本気で、素直な気持ちで私は彼のためになりたかった。
そこで、月曜日にバーデンバーデンで二つの仕事をこなした後、疲れきって、よれよれになって、バイロイトへ行った。私は、当時、バイロイトに小さな住居を持っていた。そこで、侮辱された。私が家に着くや否や、もう、当時ヴォルフガング・ワーグナーの秘書だったタウト夫人、そして、私たちの忘れ難い合唱指揮者のピルツ夫人までが、私に電話をよこした。二人は私に事を重大に考えるようにと、しつこく迫った。「時にはあんなふうな反応がかえってくることは、あなたもご存知でしょう」 しかし、私は幻滅するだけだった。私は思った。私は舵取り、エリック(さまよえるオランダ人)、ローエングリン、シュトルツィング(マイスタージンガー)、パルジファル、そして、ジークフリートとしても、並外れた成果をあげたではないか。私の監督に何かそれ相当の協力的配慮を期待することはできないというのか。
そういうわけで、この精神的圧迫によって私の声は、この時まさに間違いなく決定的な損傷を受けた。だから、私はシェローの演出は複雑で難しいから、私が舞台で歌うふりをしながら演じ、歌のほうは、テノール仲間のひとりが、オーケストラ・ピッチで代りに歌うというのを提案した。つまり、プレイバックのようなものだ。ありがたいことに、ジャン・コックス が引き受けてくれた。
これがヴォルフガング・ワーグナーとの最初の軋轢だった。実にばかばかしいきっかけだったと思う。その後数年以上も私たちの関係は改善しようがなかった。ヴォルフガング・ワーグナーはおそらく、ジークフリートでの衝突の後、私が彼に対して悪感情を抱いているとずっと思っていたに違いない。私は性格的にも、他人を傷つけよう等という気は毛頭ないというのに。多分、彼には誤解があったのだ。私は結局のところ、彼の演出や芸術的野心に感銘を受けて触発されたことはほとんどない。しかし、バイロイト祝祭劇場とそこで彼のために働く芸術家たちにとっての、仲間として、そして公明正大な監督としては、常に高く評価している。
********************************
註:シェロー演出のジークフリートにおける、コロとW.ワーグナーの衝突は、We Need A Hero では1979年のことになっています。
目次
カラヤンとの関係 [ルネ・コロ自伝]
1976年ザルツブルク復活祭音楽祭 ローエングリン カラヤンvsコロ
1974年ザルツブルク音楽祭 魔笛 カラヤンvsストレーレル その他 pp.87-97
1974年ザルツブルク音楽祭 魔笛 カラヤンvsストレーレル その他 pp.87-97
カラヤンとの共働についてはすでに書いたが、もう一度、当時、大騒ぎになって物議をかもした1976年の事の経緯に戻って話したい。
 それはローエングリンだった。ザルツブルクでの公演の前にベルリンでレコード録音をしたが、はじめから、悪い星回りだった。カラヤンは我慢できないほどの背中の痛みに悩まされていた。これは録音期間中にどんどんひどくなり、録音が半分進んだところで、中断、カラヤンは手術するために入院した。
それはローエングリンだった。ザルツブルクでの公演の前にベルリンでレコード録音をしたが、はじめから、悪い星回りだった。カラヤンは我慢できないほどの背中の痛みに悩まされていた。これは録音期間中にどんどんひどくなり、録音が半分進んだところで、中断、カラヤンは手術するために入院した。数週間後、私達はザルツブルクでの舞台稽古で会った。ものすごくいらいらして神経の高ぶった雰囲気が支配していた。カラヤンは必死で我慢していたけれど、ひどい苦痛を隠すことは不可能だった。カラヤンは、後三ヶ月は休むようにという医者の言葉を聞かなかったのだ。
稽古では常に様々なことが起こる。全ての関係者に同じように目を配ることは不可能だ。衣装やメーキャップの問題、演出上の問題等々。
さて、カラヤンは三幕の「あなたは私と共にかぐわしい香りを感じているのではないのか」というところで、私に、美しい花々の咲き乱れる庭で実際にその香りをかごうとするかのように、後方に行くように求めた。その時、私は髪の毛が逆立った。ワーグナーによるピアノ用スコアには当然そう書いてあるが、現代の精神分析的時代においては、ワーグナーが思ったのとは、ちょっと別の解釈をする必要があると思う。ローエングリンは美しい言葉で、エルザの気分を換えて、質問したいという強い願望から気をそらそうとしているのではないだろうか。それはこう読み替えられるのだ。「あなたは私と共に、人間の持つ素晴らしさのうちでも最高に人間的なもの、すなわち愛を感じてはいるのではないか。私は人間になるためにあなたのところに来たのだ」ともかく、私にとって、庭でヒアシンスの香りをかぐという意味ではないし、そうであるべき根拠など全くないと思う。
私はカラヤンと議論しようとしたが、無駄だった。そういうわけで、私は権威に屈して、香りをかいだということだが、不満は隠せなかった。
確かにヒアシンスの嫌なにおいのせいばかりではないが、ザルツブルクの厳しい東風をかいだせいで、不愉快きわまりない急性扁桃炎(アンギーナ)になってしまったのは、間違いがない。私ののどは慢性的に炎症を起こしていたし、けいこのとき、ちゃんと歌う必要はなかったが、事実、体調が悪いのだから、当然ひどく神経質になっていた。空き時間には、何度か列車でウィーンまで行って、歌手のための伝説的な耳鼻咽喉科の専門医のReinhard Kuersten先生のところへ通った。少なくとも往復5時間はかかった。先生は毎回、たくさんの飲み薬を出し、注射をしてくれたが、病気はしつこくて、容易に回復しなかった。
本稽古(Hauptprobe)の日が来た。その数日前に、私とカラヤンの共通のエージェントのEmil Jucker のところへ行って、カラヤンに、本稽古は演技ばかりかちゃんと歌うつもりもないということを伝えてもらいたいと頼んだ。半分は録音していたから、私がどう歌うか、カラヤンに分かっていることは間違いないし、一方、私のほうもカラヤンのテンポはわかっている。
カラヤンはそのことに同意してくれて、問題はなかった。彼としては、稽古のためにすぐに別の歌手を連れて来るほうが好都合だった。
数日後、急性扁桃炎(アンギーナ)は多少良くなり、間もなく最終リハーサル(Generalprobe)だった。私としてはちゃんとやるつもりで、何も言わなかった。朝、祝祭劇場に行って、守衛に私の練習室の鍵を出してくれるように頼んだところ、そこにはすでに他の歌手がいて練習しているという。あの本稽古で代役をした歌手が最終リハーサルにも予定されていたのを、だれも私に知らせてもくれなかった。私としては全くうれしくなかったが、この強制休養は、急性扁桃炎(アンギーナ)にとってはよい効果を与えることは間違いない。だから、苦情も言わず、もっと回復して、初日に備えるためにホテルに戻った。
二日後まではそうやって過ごした 。
初日(プレミエ)の午後、祝祭劇場に行った。この公演で、ローエングリンを歌う歌手が決まっていないとはまだ知らなかった。私の練習室はまた占領されていた上、私の衣装ダンスにあの歌手の衣装がかかっているのを見て、私はうんざりもし、がっかりもした。劇場は安全策を講じて、病気のコロのほかに、健康な歌手を雇う必要があったということは、もちろん私にもわかる。しかし、ちょっと電話して、私の具合を聞いてくれることを期待してはいけないだろうか。私は怒り狂って、衣装を身につけ、初日を歌った。
翌日と翌々日は休みだった。初日の翌朝、カラヤンの親友のAndre von Mattoni から、マエストロが今夜会いたいのだが、ローエングリンのピアノ譜を持って来るようにという電話があった。奇妙な話だと思った。何の為にピアノ譜を持って来いというのだろうか。しかし、それ以上深くは考えなかった。私としては、お互いの花の香に関する小さな意見の相違について、話し合うことができることを望むだけだった。というのも、そのときまで極めて楽しく、創造的かつ生産的だった私たちの共働をよりよいものとするためには、私にとって、まさに好都合なことだったからだ。
エレベーターのところへ行く通路で彼に出会った。彼の顔色は悪く、恐ろしいほど青白かった。高い襟の、真っ黒のコートを羽織った姿は、E.T.A.ホフマンの小説に登場する奇妙な病気の人物を思わせた。
私たちは黙って、貨物用エレベーターで最上階の練習舞台へ行った。彼は私の手からピアノ譜を乱暴にひったくったあと、ピアノの前に座ると、不機嫌な手振りで、私は部屋のずっと奥のほうに立つようにほのめかした。そして、ピアノ譜のある部分を開いて、もはやしなやかとは言えない指で弾きはじめた。「歌ってください」と私を怒鳴りつけた。
私はこの行動にどんなに侮辱されたことか。彼は私もまた病気だということを知っているに違いないのに、私が今ここで全く無意味に歌うべきだと言うのか。私はピアノのところに歩みよって、私も目下病気で、次のローエングリンの公演を前にして、絶対に声を休ませておく必要があるのだということを、説明しようとした。それに、とにかく彼は私がどう歌うかということは先刻承知しているのだ。
そこへ、最高に無神経な言葉が耳に届いた。私の全キャリアにおいてこんな言葉は、耳にしたことがいまだかつてなかった。カラヤンは、「そもそもあなたがまだ歌えるかどうか、私としては全くわからない」と、その生来のがらがら声で文句を言ったのだ。
突然、私たちの音楽的関係は終ったことがはっきりした。私は、自分のピアノ譜を楽譜立てからひったくると、それをぱたんと閉じて、もうチェックする必要はありませんと言い返した。それから、練習舞台を後にした。
外廊下に出ようとしたとき、まるでイタリアのオペラ・ブッファみたいな場面が繰りひろげられた。
ヴェルディのレクイエムの稽古のためにカラヤンと会うことになっていた、まさに三人の大歌手、ルチアーノ・パヴァロッティ、ミレッラ・フレーニ、ニコライ・ギャウロウは、どうやらドアのところで盗み聞きするチャンスを得てのその誘惑に抗し難かったようだった。びっくり仰天した彼らは、あわてて、私に背を向けた。あたかもタンホイザーの二幕でのローマへ巡礼に行かなければならない合唱団みたいだった。
夜、荷物をまとめた。もちろんローマへではなく、ハンブルクへだ。この仲たがいがもたらす結果について、よいこともあり得るなどという幻想は一切持っていなかったが、こうする以外にいったいどんな可能性があっただろうか。
ところで、出発前に、数社の新聞記者から電話をもらった。翌日、一社を選んで会った。プレミエ後より大きな扱いだった。ついにマエストロも登場させられていた。一面に、なんと写真入りの、太字の見出しだった。
私のキャンセルで、新聞という新聞が大喜びするなんてことがなかったのがうれしかったということは否定し難い。
しかし、大衆紙の大見出しは実際のところ私のもくろみ通りではなく、反カラヤンでは全くないのは確かだった。
病気は常にそこにあり、そこに関わってくる医者も、私の生活において、重要な役割を果たすわけだが、1970年代の終わりごろに、耳鼻咽喉科の医者と一緒に体験した大いに不思議な出来事についてこれから話したい。ミュンヘンに滞在していたとき、声の調子が非常によくなかった。のどがひりひりして、声帯の具合は最悪になりはじめていた。ミュンヘンの近くに診療所を持っているある医者を強く勧められた。そこで、その先生のところへ車で行った。こんばんはとか決まりきったあいさつのあと、拷問台さながらの診察台に座った。
医者は私ののどを診た。
しつこく何度も、どんどん奥のほうまで眺めて、一分ぐらいしてから、ため息が聞こえた。
「ええと・・う・・」
彼はもう一度しっかりと私の声門を観察して、頭を振った。
「ちょっと待っていてください。やっぱり助手に手伝ってもらいます」と言った。「かまいません。待っています」数分待ったあと、助手がやってきた。そこで、二人で私の声門を詳細に観察して、頭を振った。二人でまた頭を振っている。
「ところで、先生はどう思いますか」
「はい、私としては・・めったにない症例だと・・」
二人は繰り返し肩をすくめて、当惑の呈。
数分後、最初の医者が口を開いた。「今日のところは何か薬を出しますから、今晩飲んでください。そして、あさってもう一度来てください」
私は処方箋をもらうと、途方に暮れて、ベッド数の多い大病院を後に、再びミュンヘンに戻った。二日後、約束通り、またその病院へ行った。
「そうですね・・う・・・ん・・」
「先生のご意見は?」
「そうですね・・実際のところ、わかりません・・」
二人とも、私がだんだん落ち着かなくなっているのはわかっただろう。
「一体どうなっているのか、いい加減に言えないんですか」
私はいらいらしてきた。いい加減に私の声門にどんな不思議なことがあるのか、知りたかった。とにかく私の健康、私の声、私の声門なのだ。
しかし、説明はしてもらえなかったが、もう一度口を開けるのは許してもらえて、また別の医者にしばらくの間診察された。
診察がとても長引いているということは、手術をしてたくさんある病院のベッドのひとつを埋めようとしているのではないかという疑いが突然わき起こった。
私がうれしくなるような見込みは全くなかったので、私は両先生にさようならして、大急ぎでそのひどい場所を後にした。
車を運転しながら、頭にあったのはこういうことだ。「要するに」と私は思った。「声帯の癌にかかっているとしても、とにかくバイロイトへ行くのだ」
あと四日でけいこが始まる。
私はバイロイトへ行って歌った。
そして、今日もまだ歌っているというわけだ。
だが、私があの二人の医者の言う事に耳を傾けていたとしたら、もしかしたら、もう長くはやれなかったところかもしれない。大病院をやっていくためには経済性を追求する態度は当然必要だが、そうはいっても、あのようなやり方をするのは、何かあまりにも卑しい感じがしてみっともないことだと思う。
話をカラヤンに戻そう。もうひとつのカラヤンとの共働は、ミラノ・スカラ座とオペラ演出家のジョルジョ・ストレーレルとのザルツブルクで体験できた。ストレーレルは当時非常に有名で、ひっぱりだこだったから、カラヤンが彼を見過ごすことなく、1974年ザルツブルク音楽祭に招いたのは必然的なことだった。二人が一緒のところを見た人は、カラヤンがこのイタリア人を招いたことを必ずしも喜んでいるわけでないことがわかっただろう。二人とも似たような体格で、どちらも黒い服を身につけ、シルバーグレイの髪をしていた。遠くから見ると、どちらがどちらだかはっきりわからなかったほどだ。
こういうのはまずうまくいかない可能性が高いに決まっていた。魔笛の新演出が計画されており、ストレーレルの舞台装置家、Luciano Damiani が舞台装置を担当した。演出家は私たちを自分のところに毎日拘束して、モーツァルトについて何時間も講義した。一方、カラヤンは、St.Tropez の自宅で休暇を過ごしていた。そのときストレーレルが私たちに話したことは、もう以前にモーツァルトについては聞いたことがあったことだったが、実に最高にすばらしかった。講義は延々と何時間も続いたが、それもまたとても楽しかった。私たちはまもなくモーツァルトに関する事で知らないことは何もなくなったほどだが、どこから舞台に出るかとか、どこから舞台を去るべきなのかは、まだ知らなかった。カラヤンは相変わらず遠いフランスにいて、毎晩、電話でザルツブルクの状況に関する情報を得ていた。だから、彼はつんぼさじきにいたわけではなかったが、実際のところ何もおこらなかった。
三週間後、カラヤンは日焼けして、最高の体調で休暇から戻り、すぐに最初のオーケストラ稽古が行われた。乱暴な悪態をつきまくる傾向のある、ストレーレルは、客席や舞台の上を大げさな身振りをしながらしょっちゅう走り回り、乱暴なイタリア語で舞台で働く人たちと一緒に叫びまくっていた。カラヤンはこのときとばかり、オーケストラの演奏を止め、その相当に大きな手で指揮台をたたいて、ストレーレルを怒鳴りつけた。「今ここではオーケストラ稽古をしているのだ!」ストレーレルは青くなって、まるで壁の前に立たされた小さな子どもみたいに、今度は決してしゃべりませんと言った。その後は助手の女性が演出を続行した。
私は魔笛はまだ歌ったことがなかったから、とにかく完全に満足してはいなかった。当時は、タミーノと言えば、尊敬する先輩の、フリッツ・ヴンダーリヒとペーター・シュライヤーが声的には理想だとみなされていた。そして、私はと言えば、当然のことながら、声としてはすでにかなりドラマティックになっていた。うまくいって、喜ばれることが可能だろうか。
プレミエの日が来た。「なんと美しい絵姿」のアリアがはじまったとき、はじめの調子をとったあと、カラヤンは指揮棒を手に持って、観客の方を向いた。私が舞台で歌い続けている間、カラヤンは最前列に座っているザルツブルク音楽祭の支援者たちにあいそを振りまき、私の立っている方向を激しい身振りで示していた。オーケストラは勝手に演奏を続けていた。
当然のことだが、私は自分のことにしか関心はなかった。彼は私の歌がいかによくないかを示しているのだと思った。けれども、あるときわかった。彼は演出のことを言っていたのだ。そして、観客にストレーレルの酷い演出は、彼には何の影響も与え得ないということを言いたかったのだ。
カラヤンは自分の目標を達成した。イタリアから来たカラヤンの一卵性双生児みたいなストレーレルは、まさに舞台装置家 Damianisのお陰で この先も天才的な演出をやり続けることができたけれど、次の年に再び現れることはなく、彼の魔笛は二度と再演されなかった。
ロシアのことわざに曰く、「16キロの塩を共に食べないうちは、人間は自分を知る事はない」
私はカラヤンとは一度ステーキを一緒に食べただけで、しかも塩味ではなかった。さらには、カラヤンの自家用機に一緒に乗って、ザルツブルクからエジンバラへ飛んだ。こういうわけで、私は彼の事を知らないし、本当に彼のことを知っている人はひとりもいないと思う。
いつだったか彼に、ベルリンの古いホテルから、ケンピンスキーに移るように提案したことがあった。それはあのローエングリンのずっと前だった。そこにはプールがあって、彼の背中の病気にもとてもいいと思ったのだ。私たちの共通のエージェントであるEmil Jucker が私の提案を早急に実現してくれたので、カラヤンは毎朝6時には完全にひとりでプールを占領してすごくいい気分にひたっていた。
そういうことがあったからかもしれないが、数ヶ月後、ケンピンスキーで Jucker と一緒に、カラヤンと夕食を共にする約束をした。私たちは6時にすでに出会ったので、レストランに座っているのは、完全に私たちだけで、およそ一時間の食事中、私たちの会話は二つか三つの文章だった。私はもともとおしゃべりではないし、その上、その晩は注目を浴びたくなかった。Jucker は、くつろいだ雰囲気にするために、できるだけのことをした。しかし、カラヤンの態度は冷たいままで、何かにつけて神経過敏だったから、私たちは黙って、ステーキをかみしめながら、この悪夢が早く終わる事だけを望んでいた。
私は、ヘルベルト・フォン・カラヤンが苦手だったが、おそらく彼も同じ思いだったのかもしれない。私たちが一緒に仕事をした年月が私の人生においてもっともすばらしい、そして音楽的にもっとも満足できた時期だということは否定するつもりはない。あのころが私の思い出にあるのはうれしいことだ。それに、すごいことに、音沙汰のなかった数年後、私の50歳の誕生日に突然とても細かくいろいろと書かれた電報を受けとった。彼は私の誕生日だけでなく、私の成功のことも当然耳にしていて、そのことも祝ってくれていた。もはや得られることがあるなど思ってもいなかった友情の証は、だからこそ、一層感慨深かった。
人間は誰しも多くの顔を持っている。ヘルベルト・フォン・カラヤンも同じだ。私にとって、彼は子どもの心を持ったマキャヴェリだった。そして、だれかが私たちから去ったとき、カラヤンの場合はその死後だったのだが、その人が私にとってほんとうにどういう存在だったかということがはっきりすることがなんと多いことだろうか。そのプロイセン的勤勉さ、そのとてつもない才能、演奏の軽々とした瞬間、素朴な正直さと誠実さ、こういうことを私は非常に高く評価している。そしてまた、カラヤンこそが、私がその墓に一本のばらの花を置き、そうすることをうれしく思う、ただ一人の人だ。
目次
生い立ち [ルネ・コロ自伝]
先祖が残してくれた古い本
先祖が残してくれた古い本
母、マリールイーズ・コロは 旧姓ハーティングで、北フリース人の血筋である。もっとも、母は南のフレンスブルク出身だが、ルーツは北フリース諸島だ。母は「ローエングリン」に出てくるあの領主の娘、オルトルートとは姉妹のような関係だということもありうるわけで、同じように頑固な上に、同じように偉大だった。平穏な生活は母には似合わないように見えた。例外的な状況の中で母はきわめて有能であることが実証されていた。その上、戦争中には、そのような状況が多かったのだ。戦争末期の逃避行では、少なくとも、外面的には、すばらしい威厳と冷静さを示していた。
普段は、いわゆる優雅な生活を、たいてい、不機嫌に、不満そうに、北方人的冷たさで見ていた。鉱山労働者のような体格。Luettenを飲んだときはだけは、ほんとうに打ち解けて、陽気になった。母が愛したものは、私たち、姉と私だった。すべての感情表現を抑制することに時代や教育がどんな影響を与えるかということを理解するためには確実に世代を遡らなければならない。多分フリース人だということも関係するだろう。 私自身も、まだ若いころ、「とてもよくしゃべり、よく笑う人」はドイツ人にはうさんくさく思われるのだということを耳にしていた。「そういう人は不誠実だ」「隠すべきことがあるはずだ」と北欧の人は言う。 北欧ではめったなことではにこりともしないし、必要最小限しか話さない。ある冗談がこういうことをとても適切に示しているので、そのまま引用するのが一番いいと思う。この冗談は、私の希望としては全く冗談抜きではないこの本にある唯一の冗談でもある。
ひとりのフリース人「や!」
もうひとりのフリース人「やあ、やあ」
はじめのフリース人が妻に「おいで、行くよ。この人はしゃべりすぎる」
このようなとても楽しいとは言えない地方で母は育った。今ではもちろんはるかに気楽になっているようだ。なぜなら私たちは今はちょっとほほえんで、何度も何度もキスをして、おしゃべりは果てしなく続く。
女性はみんな車の運転が下手だというのは、楽しいおとぎ話だが、母は運転が物凄く上手だった。子ども時代に、母と一緒に数回イタリアのガルダ湖に滞在したことがある。最高のレストランをみつける絶対確実な勘で、田舎の見知らぬ町に入っても最高にすばらしいレストランに、迷うことなく行きついたものだ。まさにどうしてそんなことができるのかは神のみぞ知るというところだった。要するに母はホテル経営者の娘だったということなのだ。
たくさんの見込みのありそうなレストランを通り過ぎてから、やっと止まったところには格別しゃれてはいなが、そんなに高くなさそうな、ほんとうに簡素なトラッテリアがあった。
母は「あなたは車にいなさい」という意味で、私のほうを振り向くと、「ちょっとのぞきに」行った。それは母がそこのトイレに行ったということを意味していた。
これですべて決まりだった。
トイレが清潔で手入れが行き届いていれば、これは当時のイタリアではほんとうに珍しかったのだが、テストに合格で、母は私に中に入るようにと目で合図した。トイレがひどく汚い場合は、私たちはそのまま先へと進んだ。このやり方で私たちはいつも最高の食事と最高のワインのある場所に行き着いた。
母は頻繁に体調不良に悩まされていた。人の話によると私を産んだときにはあやうく死にそうになったということだ。医者はすでにあきらめていたが、母の意志も母のフリース人の血も計算に入れていなかった。母は牡羊座だ。母は冷戦沈着に最悪の事態を乗り切った。
母の星座牡羊座には、ちょっとあぶない話がある。今なら多分話しても大丈夫だと思う。母は『総統』と同じ四月二十日が誕生日だった(ちなみに二日後はレーニンの誕生日だが、たぶん知っている人は非常にすくないだろう)さてヒットラーの誕生日には、ベルリン中の窓には鈎十字の旗が掛けられていた。義務だったのか、あるいはそうでもなかったのだろうか。その当時、父が姉と私を連れて一緒に通りを歩いていたとき、父は旗を指して私たちに言った。「ちょっとあれを見てごらん、全部ママのためなんだよ」
その後、母は六十五歳で重い病気にかかり、そのせいで、慢性的な不安定とぎこちなさが確実に大きな部分を占めるようになった。しかし、それについては後にしよう。
母は自分の生い立ちについて話してくれなかったので、それはもう霧のかかった過去の中にしかない。いつのころか若い娘だったころ、母はフレンスブルクからベルリンへ出て、映画界を目指したが、結局のところ、私たちの父と結婚したのだ。
父が後に話してくれたのだが、そのころの母は、父がそれまでに見た最高に美しい女性たちのうちのひとりだったそうだ。父はそのころにはもうものすごく大勢の美しい女性たちを知っていたのだ。父は魅力的で、相当の有名人だったから、あらゆる点で、ご婦人たちに頼りにされていた。それにしても、父がおそらく最終的に交際していた女性は、素朴なフレンスブルクで想像できた以上に、相当大勢いたのだろう。だから、結婚式の直後に、二人の関係には大きな亀裂が生じた。
父はスラブ系である。父の両親はケーニヒスベルクの出身だが、その前はワルシャワ出身だった。父も回顧録を書きはじめたが、ほんの数ページだけで、そのあと、若いころのところで行き詰まっている。奇妙なことに、父はそれを書き続けることもなければ、終りにもしていない。だから、私がここで、家族の年代記の中でコロ家の先祖について少し振り返ってみたいと思う。
ウィリ・コロは1904年、ケーニヒスベルク、すなわち <Tragheimer Ausbau> で生まれ、そこの教会で洗礼を受けた。そして、私の後の人生に影響を与えた全ての事は、すでにここにその根があるように思える。この教会で、リヒャルト・ワーグナーとミンナ・プラナーが、結婚式を挙げている。ワーグナーが好きでもない指揮者の職につくべくリガに赴任する旅の途中だった。だから、この教会の記録簿には、二人の作曲家の名前が記入されているのだ。私たちの家族だって、ワーグナーとコロの芸術的相違はしっかりと認めているにしてもである。私にとってはそれだけでも不思議な気がする。ここが、ワーグナーとコロという二つの名前が、初めて、本当にすぐ近くにあった場所なのだ。
父は三歳まで、石油ランプの下で、祖母に育てられた。父はその明かりがすばらしいと思っていた。『なぜならば、それはとっても暖かくて、とてもいいにおいだったのだ』 祖母の死後、そこから冷たいガス灯の照らすベルリンの両親のもとに戻ってきたのだが、両親は父のことをかまわなかった。父は、自ら書いているように、まったく見ず知らずの人々に出会ったのだった。その父、ワルター・コロは、その当時コレペティートル兼まだ無名のカペルマイスター(指揮者、楽長)として働いており、母のマリー・プロイスはスウブレット歌手で、芸名をミッツィ・ジョセッティと言った。両親とも他のすべての人間同様稼がねばならなかった。
この辺のことについては、女性ジャーナリストのグドルン・グロスが録音した私的な会話をのぞくことにしよう(こういう理由で、文章は、書かれたもののようには、洗練された表現になっていない)
『とにかく私にとっておもしろい時代だった。私はひとりの紳士と向き合っていた。それは父で、言うまでもなく私は父が大好きだった。父は生来とても親切で、とても物静かで柔和で、善良だった。母はちょっとヒステリックで、父ほど付き合いやすくはなかった。父はいつもとてもいい香りがしていた。整髪料やポマードや、それに間違いなく香水のにおいだと思う。父はいつも身なりに非常に気を遣っていた。そして、私は、父が初めてピアノで『どんなにお星さまがたくさんあるか、知っているか』を弾いてきかせてくれたとき、あまりにもたくさんの美しい音色に、茫然自失の呈で、天にも昇る心地だった。
ボツダム通りの私たちの賃貸家具付住居には、その後歴史に名を残した人々が出入りしていた。例えば、クララ・ヴァルドフは、上がって来たり下りて行ったりしていた。彼女は四階に住んでいて、いつも私たちの客だった。ハインリヒ・ツイレは家族全体の友人だった。クララ・ヴァルドフと父は、いつも閉じこもって、二人で面白い小話をしては笑い声をたてたので、母はドアの前に立ってやきもちをやいていた。母は、二人が恋愛関係にあるのではないかと信じていたのだった。このころクララ・ヴァルドフは、どちらかと言えば、父とよりはむしろ母と恋愛関係にあったのではないだろうか。しかし、その当時はまだわからなかった。そのころはまだ知られていなかった』
祖父のところには、オットー・ロイター、ロバート・シュタイデルといった歌手やコメディアンのような人々も出入りしていた。オットー・ロイターは『いつも壁に沿って Immer an der Wand lang』を歌った歌手だ。これはワルター・コロが最初に大成功をおさめた歌だ。
『私の父、ワルターは、当時、今日のドイツではまったく想像できないぐらい有名だった。その名はそのころすでにアメリカまで届いていた。そもそも私は父のことを当然ながら長い間、あらゆる時代を通じて最高の作曲家だと思っていた。そして、学校の音楽の授業ではじめてシューベルト、モーツァルト、ベートーベンのような人たちもいるのだということを知ったのだった。私がそのときまでこの人たちを全然知らなかったのは、私の父ほど有名じゃないということだということもわかった。』
父の録音テープのおしゃべりはあとでもう一度たっぷり紹介する。
祖父ワルターは後に、大きな成功をおさめたとき、自分の音楽出版社を設立し、さらに今日のドイツ音楽著作権協会(GEMA)の創立者の中心人物だった。当時、GEMAができる前は、音楽家はだれでも人気のある音楽作品を演奏することができ、それに対して一文も払う必要はなかった。しかるに、GEMAの登場によって、その後、音楽家はいわゆるGEMA名簿に記入しなければならなくなった。そして、それからは、公開で演奏したいということで音楽作品を使うときはその都度、各レストランやナイトクラブなどがGEMAに対して小額の寄付金を支払うことになった。
ワルター・コロが創立メンバーとして重要だったのは、コロを演奏しないということは、当時の音楽家にしてみれば、誰一人としてできない相談だったからだ。多くの作曲家に関しては演奏を断念することもできたが、『今もまだ菩提樹の木陰で Solang noch untern Linden』、『小さな女の子はおやすみの時間 Kleine Maedchen muessen schlafen gehen』、 『もうちょっとだけ待って Warte, warte nur ein Weilchen』、『若い娘が殿方を知れば Wenn ein Maedel einen Herren hat』、『ねえお前、私はよく眠れない Kind, ich schlafe so schlecht』、『菩提樹の木陰を少女が散歩中 Unter'n Linden, unter'n Linden gehen spazieren die Maegdelein』などや、その他たくさんの歌をなしで済ませることはとても出来はしなかったのだ。その絶大な人気によって、彼はGEMAの事業の成功のための偉大な保証人となったのだった。
もちろん賛同者ばかりではなかった。大勢の音楽家たちが猛烈に抵抗した。あらん限りの抵抗があったが、政治的な側面から法的解釈がなされた。そして、GEMA が音楽家たちにワルター・コロの演奏は絶対に許可しないと言えば、即刻、支払い契約が結ばれた。
祖父については、父が数年にわたって話してくれた以上の思い出はほとんどない。
祖父は教会音楽家として始め,『いつも壁に沿って Immer an der Wand lang』に行き着いた。
私は『ハロー、メリー・ルー Hello, Mary Lou』で始めて、タンホイザー、そしてトリスタンに行き着いた。
ドイツにおいて、一部の純粋主義者にとって、前者は芸術的転落であり、後者は芸術的上昇である。ただしかし、同時に、何にしろ再現芸術というものは、着想を得てそれに適切に手を加えることに比べて、はるかに創造的でないと考えるべきだろう。というわけで、『今もまだ菩提樹の木陰でSolang noch unter Linden』や『彼女が春に夢見ること Was eine Frau im Fruehling traeumt』あるいはアメリカ人のオペレッタ専門家、クルト・ゲンツルの意見では、全てのベルリン歌曲の中で「最も心のこもった、最も優しい」歌である『五月にシェーンベルクで Es war in Schoeneberg im Monat Mai』などをまず第一に作曲しているはずだ。
その後さらに本当の流行歌も書いている。『私のオウムは固い卵は食べないMein Papagei frisst keine harten Eier』、『マックス、それを押し出して Max, du hast das schieben raus』、『ちょっと来て回すのを手伝ってKomm, hilf mir mal die Rolle dreh'n』などである。最後の歌は、父も書いているように、衣料品店のショーウィンドーに置いてあった重いアイロン仕上げ用ローラーのことを知っている人にしか理解できない。太いバラ色の腕をした、たくましい女中のベルタでさえ、その仕事をひとりでは絶対こなせなかった。その結果、女中としては、昔の「プロシャ軍の兵舎」から喜んで家中の洗濯物を圧縮機にかけてくれる、とても従順な「マスケット歩兵」を調達する必要があった。そして、晩には、彼はベルタの台所で数切れのバタートーストと一杯のビールを振る舞ってもらった上、その後、彼女と楽しむことさえできた。父が『人手不足の職業』のひとつとして、詳しく説明してくれたものだ。
私には、祖父にしてみれば、あまり気に入らない癖があった。今は、シェーンベルガーの住居の窓には、案内板が取り付けられていて、大層なダマスク織りの制服を着た守衛が立っている。ところで、私の大きな楽しみは、ターザンのように大声で叫びながら、窓の左から右へ、右から左へと、はずみをつけて飛び移ることだった。それはとても大きな窓だったので、一方から、もう一方までの距離は飛び移りがいがあった。もちろん守衛はいなかった。窓は壊れて、元通りに取り付けるのには相当苦労がいった。両親がほんとにたまにしか呼ばれなかったのはこのお陰だということは間違いない。そして、やむを得ない場合は、私抜きで、とはっきりいわれるようになった。
しかし、それにもまして、祖父はとても魅力的な人だったにちがいない。なぜなら、祖父の友人の群れは巨大だったのだから。ちなみに、債権者もまた群れをなしていた。祖父は、ベルリンの設計者で画家のハインリッヒ・ツィッレと非常に親しかった。この人が引いた一本の線は、そのどれもが『その線』だということが再確認できるといわれていた。二人は、その筋のベルリンの居酒屋ではどこでも有名だった。祖父は一晩中飲み明かしたあと、馬を馬車から外して徒歩で戸口まで馬車を引っ張ってくるのを何回か目撃されたことさえあった。ベルリンには、長い道と大勢の目と友情があった。
祖母は、私が生まれたあとすぐ祖父と別居したので全然知らない。二人の結婚生活は不幸で楽しくなかったにちがいない。怒鳴りあいのけんかはしょっちゅうで、父は二人の間に立って、どちらの側にも捕まりたくないと思っていた。父は自ら望んで、ハルツ地方のブランケンブルクの全寮制の学校に入った。この学校にいたひとりの高校教諭が父の人生に大きな影響を与えた。『西洋の没落: Der Untergang des Abendlandes 』という有名な本を書いたオズワルド・シュペングラー である。この本は全ての人に推薦できる。この本に書かれていることは、今日、すでに真実であることが証明されていると思う。
父は両親のところで、子どもとして、不幸な結婚生活のひどい不利益を我慢しなければならなかったのだから、その中から、自分の将来や子どもたち、つまり私たちのために何か学ぶところがあったはずだとほんとうは期待できるところだ。父はそういことから何も学んでいない。あるいは、戦争とその間の様々の状況もそういうことを学ぶよい機会にはならずに済んだ。父が私たちの母と共に送った結婚生活は、スウェーデンの作家、ストリンドベリなら、大成功間違いなしの新しい作品を書くのではないかといった様相を呈していた。ドアというドアは、鍵がめちゃめちゃに壊され、母の最高音中の最高音でわめきちらす金切り声が響きわたった。そういう時、父はたいていは家から逃げ出して、数時間後に戻ってきた。そういうことのあと、母は一言も話さず、座っていた。家には氷のように冷たい沈黙だけがあった。
註:スウェーデンの作家ストリンドベリ(1849-1912)
<続き>
目次