2003年刊の伝記:表紙と目次 [2003年刊伝記]
資料2
マリタ・ターシュマンは、この芸術家との緊密な共同作業によって、オペラの舞台とロック・コンサートの間を往復したスターの波乱万丈の半生を描いている。ホフマンのパーキンソン病との闘いについても詳しく述べている。
マリタ・ターシュマンは、ハンブルクで音楽学とドイツ文学を学び、出版関係の仕事をしている。この本は数年にわたるペーター・ホフマンとの共同作業によって完成をみた。
目次
*ペーター・ホフマン、輝ける男 ヴォルフガング・ワーグナー
*「ほんとにジークムント? まさにジークムントだった」ペーター・ホフマンとの初めての出会い
*「自分の人生が、おそらく音楽に関連して、何か特別なものになるような気がしていた」マリエンバートからバイロイトまで 1 2 3
*世界をまわって ローエングリン、フロレスタン、そして、初めてのトリスタン
*オペラ歌手でロック歌手に、矛盾なし 1 2 3
*「この病気は私には似合わない」パーキンソン病の診断 病気と共に生きる
*「ドイツ人はペーター・ホフマンを誇りに思うべきです」アンナ・マリア・カウフマン談
*謝辞
*パーキンソン病とは何か
*ペーター・ホフマン・パーキンソン病研究プロジェクト
*ディスコグラフィ
『成功を可能にするためには、夢中になる何かがなければならないと、私は確信している。今日、それ以外に成功する道はない。人は多くの困難や退却を乗り越えなければならないが、他人の意見に依存するのは望ましくない。時には難しくても、人は自分自身をこそ信じるべきである』ペーター・ホフマン
音楽は私の初恋
そして、最後の恋
未来の音楽
そして、過ぎ去った日の音楽
音楽のない生活
自分の音楽を持たず生きることはできそうもない
荒れ狂う世界の中で
私の音楽が私を導いてくれる
(J・マイルズ)
Marita Türschmann
PETER HOFMANN
Singen aus Leidenschaft
2003
外見がワーグナーのオペラの主人公たちの姿とこれほど合致するテノールは二人とはいないのではなかろうか。ペーター・ホフマンは、声の力と豊かさによってだけでなく、抜群の存在感によっても、大評判になった。その存在感こそが世界中のファンを魅了したのである。ヘルデンテノールとしての世界的キャリアのクライマックスは、バイロイト音楽祭への出演であった。バイロイトでは1976年以来感銘を与え続けた。そのほかに、1982年以降、ロック・ミュージシャンとしてのキャリアを開始し、この二つ目のキャリアでも成功をおさめた。PETER HOFMANN
Singen aus Leidenschaft
2003
マリタ・ターシュマンは、この芸術家との緊密な共同作業によって、オペラの舞台とロック・コンサートの間を往復したスターの波乱万丈の半生を描いている。ホフマンのパーキンソン病との闘いについても詳しく述べている。
マリタ・ターシュマンは、ハンブルクで音楽学とドイツ文学を学び、出版関係の仕事をしている。この本は数年にわたるペーター・ホフマンとの共同作業によって完成をみた。
マリタ・ターシュマン著
ペーター・ホフマン 歌への情熱
2003年3月 ヘンシェル出版 ベルリン
ペーター・ホフマン 歌への情熱
2003年3月 ヘンシェル出版 ベルリン
目次
*ペーター・ホフマン、輝ける男 ヴォルフガング・ワーグナー
*「ほんとにジークムント? まさにジークムントだった」ペーター・ホフマンとの初めての出会い
*「自分の人生が、おそらく音楽に関連して、何か特別なものになるような気がしていた」マリエンバートからバイロイトまで 1 2 3
*世界をまわって ローエングリン、フロレスタン、そして、初めてのトリスタン
*オペラ歌手でロック歌手に、矛盾なし 1 2 3
*「この病気は私には似合わない」パーキンソン病の診断 病気と共に生きる
*「ドイツ人はペーター・ホフマンを誇りに思うべきです」アンナ・マリア・カウフマン談
*謝辞
*パーキンソン病とは何か
*ペーター・ホフマン・パーキンソン病研究プロジェクト
*ディスコグラフィ
『成功を可能にするためには、夢中になる何かがなければならないと、私は確信している。今日、それ以外に成功する道はない。人は多くの困難や退却を乗り越えなければならないが、他人の意見に依存するのは望ましくない。時には難しくても、人は自分自身をこそ信じるべきである』ペーター・ホフマン
音楽は私の初恋
そして、最後の恋
未来の音楽
そして、過ぎ去った日の音楽
音楽のない生活
自分の音楽を持たず生きることはできそうもない
荒れ狂う世界の中で
私の音楽が私を導いてくれる
(J・マイルズ)
読書の後で-2 [2003年刊伝記]
ご紹介した2冊の伝記を読むにあたって、直接的に参照したわけではないのですが、潜在的に参考になり、理解の間接的助けになったと思われるのは、今までに読んだ、内外の出版物、LP、CD、LDなどのリブレット、いわゆる掲示板のようなものに投稿されたものを含むインターネット上の記事などからの情報です。外国のものは、ほとんど英語で書かれたものです。ごく一部のネット上で見つけた新聞、雑誌の抜粋記事、リブレットの一部がドイツ語です。国内の出版物は、音楽関係の書籍のほかに、雑誌は「音楽の友」「レコード藝術」「グランド・オペラ」「ライジング(新書館)」「音楽現代」などが主なところです。以下、読んだ本のうち、わかる範囲のものを並べてみました。順不同。順序には何の意味もありません。ただ単に整理できていないだけです。
「年刊ワーグナー」 福武書店
「栄光のオペラ歌手を聴く!」 音楽之友社
岡村喬生 「ヒゲのオタマジャクシ世界を泳ぐ」 新潮社
堀内修 「はじめてのオペラ」 講談社現代新書
堀内修 「ワーグナー」 講談社現代新書
堀内修 「 オペラと40人のスターたち—歌手・指揮者・演出家、スターで愉しむオペラの目録」 音楽之友社
R.チェレッティ「テノールの声」西村勝訳 本の風景社
塚本邦雄 「世紀末花傳書」 文藝春秋
米山文明 「声と日本人」 平凡社
木之下晃、堀内修 「これだけは見ておきたいオペラ」 新潮社
本間公 「思いっきりオペラ」「続・思いっきりオペラ」 宝島社
中島啓江 「きょうも元気だ、オペラがみたい」 星雲社
ピエール・マリア・パオレッティ 南條年章訳 「スカラ座の人」 音楽之友社
石戸谷結子 「マエストロに乾杯」 共同通信社
石戸谷結子 「オペラ歌手はなぜモテるのか?」 文藝春秋
「三枝成彰のオペラの楽しみ方」 講談社カルチャーブックス
三枝成彰 「知ったかぶり音楽論」 朝日新聞社
「オペラ辞典」 音楽之友社
黒田恭一 「オペラへの招待」 暮らしの手帖社
「オペラハンドブック」 新書館
押尾愛子 「オペラ・ワンダーランド」 青玄社
出谷啓 「CDで聴くクラシック名曲・名盤」 日本文芸社
野崎正俊「オペラ・ディスク・コレクション」 東京音楽社
ドナルド・キーン 中矢一義訳 「ついさきの歌声は」 中央公論社
「アリアで聴くイタリアオペラ」 立風書房
ラルース音楽大辞典 福武書房
「バーンスタインの生涯」 ハンフリー・バートン著 棚橋志行訳 福武書店1994年
「オペラへの招待」 ジョン・ルイス・ディガエターニ著 細川晶訳 新書館 1994年
「オペラ・ビデオ・ガイド」 新書館
「諸井誠のクラシック試聴室 ベストレコードはこれだ」 1985 音楽之友社
「このオペラを聴け!」 洋泉社
吉田秀和 「オペラ・ノート」 白水社
吉田秀和 「音楽 展望と批評」 朝日文庫
片桐卓也 「悦楽クラシック音楽講座」 KKロングセラーズ
三浦淳史 「演奏家ショート・ショート」 音楽之友社
三浦淳史 「続・演奏家ショート・ショート」 音楽之友社
竹原正三 「パリ・オペラ座 フランス音楽史を飾る栄光と変遷」芸術現代社 1994
「クラシックの自由時間」 立風書房
「オペラの饗宴」 泉洋社
玉木正之 「音楽は嫌い、歌が好き」 毎日新聞社
「オペラの発見、キャラクター・テーマ事典」 立風書房
「ウィーン・オペラの名歌手 II」 音楽之友社
マイリオン&スージー・ハリーズ 「オペラのすべて」 筑摩書房
志鳥栄八郎 「大作曲家とそのCD名曲名盤」 音楽之友社
music gallery 「バイエルン国立歌劇場」 音楽之友社
music gallery「バイロイト音楽祭」「バイロイト音楽祭 II」 音楽之友社
music gallery「ベルリン・ドイツ・オペラ」 音楽之友社
music gallery「ウィーン国立歌劇場」 音楽之友社
「対決!カラヤン対バーンスタイン」 音楽出版社
R.オズボーン「ヘルベルト・フォン・カラヤン」木村博江訳、白水社
成澤玲子 「海外ライヴの贈り物」 共同通信社
三井啓 「コンパクト・ディスク・ベスト100 クラシック」 音楽之友社
齋藤慎爾 「偏愛的名曲事典」 三一新書
永竹由幸 「オペラと歌舞伎」 丸善ライブラリー
朝日新聞学芸部「朝日試聴室」 朝日文庫
三宅幸夫訳 「ワーグナーの上演空間」音楽之友社
三富明 「ワーグナーの世紀」 中央大学出版会
三宅新三 「ヴァーグナーのオペラの女性像」 鳥影社
田宮敬子 「オペラヒロイン物語」 新潟日報事業社
クリスティアン・フォン・クロコウ 「女たちの時」 平凡社
岩間 陽子 「ドイツ再軍備」 中央公論社
渡部昇一 「ドイツ留学記」 講談社現代新書
セバスチャン・ハフナー 「ヒットラーとは何か」 草思社
「ニーベルンゲンの歌」 岩波文庫
「トリスタン・イズー物語」岩波文庫
あずみ椋 「ニーベルングの指環」(漫画)
講談社 里中満智子 「ニーベルングの指環」 (漫画)
中央公論新社 「ニーベルングの指環」 アーサー・ラッカム挿絵 新書館
「ローエングリン」「トリスタンとイゾルデ」「パルジファル」「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」新書館 ペーパー・オペラ・ブック・シリーズ
ドロシー・ハスフォード, 山室 静訳 「神々のとどろき—北欧神話」 岩波書店
マイケル・J・フォックス (著)「ラッキーマン」 入江 真佐子 (翻訳) ソフトバンクパブリッシング (2003)
Johanna Fiedler "Molto Agitato The Mayhem Behind the Music at the Metropolitan Opera"
Carla Maria Verdino-Suellwold "WE NEED A HERO!: HELDENTENORS FROM WAGNER'S TIME TO THE PRESENT.......A Critical History" 1989 ←ちょっとだけご紹介します〜
☆2005年1月~2010年11月30日のインターネット記事
「年刊ワーグナー」 福武書店
「栄光のオペラ歌手を聴く!」 音楽之友社
岡村喬生 「ヒゲのオタマジャクシ世界を泳ぐ」 新潮社
堀内修 「はじめてのオペラ」 講談社現代新書
堀内修 「ワーグナー」 講談社現代新書
堀内修 「 オペラと40人のスターたち—歌手・指揮者・演出家、スターで愉しむオペラの目録」 音楽之友社
R.チェレッティ「テノールの声」西村勝訳 本の風景社
塚本邦雄 「世紀末花傳書」 文藝春秋
米山文明 「声と日本人」 平凡社
木之下晃、堀内修 「これだけは見ておきたいオペラ」 新潮社
本間公 「思いっきりオペラ」「続・思いっきりオペラ」 宝島社
中島啓江 「きょうも元気だ、オペラがみたい」 星雲社
ピエール・マリア・パオレッティ 南條年章訳 「スカラ座の人」 音楽之友社
石戸谷結子 「マエストロに乾杯」 共同通信社
石戸谷結子 「オペラ歌手はなぜモテるのか?」 文藝春秋
「三枝成彰のオペラの楽しみ方」 講談社カルチャーブックス
三枝成彰 「知ったかぶり音楽論」 朝日新聞社
「オペラ辞典」 音楽之友社
黒田恭一 「オペラへの招待」 暮らしの手帖社
「オペラハンドブック」 新書館
押尾愛子 「オペラ・ワンダーランド」 青玄社
出谷啓 「CDで聴くクラシック名曲・名盤」 日本文芸社
野崎正俊「オペラ・ディスク・コレクション」 東京音楽社
ドナルド・キーン 中矢一義訳 「ついさきの歌声は」 中央公論社
「アリアで聴くイタリアオペラ」 立風書房
ラルース音楽大辞典 福武書房
「バーンスタインの生涯」 ハンフリー・バートン著 棚橋志行訳 福武書店1994年
「オペラへの招待」 ジョン・ルイス・ディガエターニ著 細川晶訳 新書館 1994年
「オペラ・ビデオ・ガイド」 新書館
「諸井誠のクラシック試聴室 ベストレコードはこれだ」 1985 音楽之友社
「このオペラを聴け!」 洋泉社
吉田秀和 「オペラ・ノート」 白水社
吉田秀和 「音楽 展望と批評」 朝日文庫
片桐卓也 「悦楽クラシック音楽講座」 KKロングセラーズ
三浦淳史 「演奏家ショート・ショート」 音楽之友社
三浦淳史 「続・演奏家ショート・ショート」 音楽之友社
竹原正三 「パリ・オペラ座 フランス音楽史を飾る栄光と変遷」芸術現代社 1994
「クラシックの自由時間」 立風書房
「オペラの饗宴」 泉洋社
玉木正之 「音楽は嫌い、歌が好き」 毎日新聞社
「オペラの発見、キャラクター・テーマ事典」 立風書房
「ウィーン・オペラの名歌手 II」 音楽之友社
マイリオン&スージー・ハリーズ 「オペラのすべて」 筑摩書房
志鳥栄八郎 「大作曲家とそのCD名曲名盤」 音楽之友社
music gallery 「バイエルン国立歌劇場」 音楽之友社
music gallery「バイロイト音楽祭」「バイロイト音楽祭 II」 音楽之友社
music gallery「ベルリン・ドイツ・オペラ」 音楽之友社
music gallery「ウィーン国立歌劇場」 音楽之友社
「対決!カラヤン対バーンスタイン」 音楽出版社
R.オズボーン「ヘルベルト・フォン・カラヤン」木村博江訳、白水社
成澤玲子 「海外ライヴの贈り物」 共同通信社
三井啓 「コンパクト・ディスク・ベスト100 クラシック」 音楽之友社
齋藤慎爾 「偏愛的名曲事典」 三一新書
永竹由幸 「オペラと歌舞伎」 丸善ライブラリー
朝日新聞学芸部「朝日試聴室」 朝日文庫
三宅幸夫訳 「ワーグナーの上演空間」音楽之友社
三富明 「ワーグナーの世紀」 中央大学出版会
三宅新三 「ヴァーグナーのオペラの女性像」 鳥影社
田宮敬子 「オペラヒロイン物語」 新潟日報事業社
クリスティアン・フォン・クロコウ 「女たちの時」 平凡社
岩間 陽子 「ドイツ再軍備」 中央公論社
渡部昇一 「ドイツ留学記」 講談社現代新書
セバスチャン・ハフナー 「ヒットラーとは何か」 草思社
「ニーベルンゲンの歌」 岩波文庫
「トリスタン・イズー物語」岩波文庫
あずみ椋 「ニーベルングの指環」(漫画)
講談社 里中満智子 「ニーベルングの指環」 (漫画)
中央公論新社 「ニーベルングの指環」 アーサー・ラッカム挿絵 新書館
「ローエングリン」「トリスタンとイゾルデ」「パルジファル」「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」新書館 ペーパー・オペラ・ブック・シリーズ
ドロシー・ハスフォード, 山室 静訳 「神々のとどろき—北欧神話」 岩波書店
マイケル・J・フォックス (著)「ラッキーマン」 入江 真佐子 (翻訳) ソフトバンクパブリッシング (2003)
Johanna Fiedler "Molto Agitato The Mayhem Behind the Music at the Metropolitan Opera"
Carla Maria Verdino-Suellwold "WE NEED A HERO!: HELDENTENORS FROM WAGNER'S TIME TO THE PRESENT.......A Critical History" 1989 ←ちょっとだけご紹介します〜
※ ※ ※
☆2005年1月~2010年11月30日のインターネット記事
※ ※ ※
読書の後で-1 [2003年刊伝記]
ネットで知り合った方が、フリッツ・ホフマンさんと連絡を取ってくださり、お返事を頂きました。「クリスマスの挨拶と2冊の伝記を日本で紹介したいが、いいでしょうか」との送信に対して、「良い考えです」とのお返事です。
※ ※ ※
ペーター・ホフマン・パーキンソン病研究プロジェクト [2003年刊伝記]
ペーター・ホフマン・パーキンソン病研究プロジェクト
ペーター・ホフマン・パーキンソン病研究プロジェクトは、『パーキンソン病における、成人の幹細胞使用による自己再生医療』に関する具体的な研究計画を援助する。このプロジェクトでは、パーキンソン病治療法研究における、より新しい、将来性のあるアプローチを援助する。ドパーミンの生成にきっかけを与えると推測される成人の脳の幹細胞を研究の中心にすえる。現在新しい自由な研究の試みは経済的な問題と闘わざるをえないことが多い。まず寄付金によって、納得のいく成果をあげるべきである。その後、引き続いて、研究が強化推進されればよい。目的は、可能な限り早く使用できる治療法を発見することである。その治療法は、病気の治癒にいたれば、もっとよいが、多くの患者にはっきりとした病気の緩和をもたらすべきである。
幹細胞とは、細胞分裂で自己増殖し、さまざまなタイプの細胞に発展的に変化しうる細胞のことである。幹細胞は胎児のもの(胚性)と成人のもの(体性)の二種類に分けられる。数年来、殊に胚性幹細胞に対して、治療上大きな期待がもたれてきた。学問的な研究目的は、パーキンソン病の場合に、患者の脳内でドパーミンを生成する神経細胞をつくり出すのに必要十分な量の、移植可能な幹細胞の生産である。それは、理想的にいけば、病気の治癒に相当するものである。しかし、そこまでの道のりはまだずっと遠いし、胚性幹細胞を使っての実験には、倫理的な理由から異論がある。成人の脳や、他の器官にも幹細胞が発見されているので、学問的興味は体性幹細胞に移る傾向が強い。胚性幹細胞を使った研究の場合のような倫理的かつ法律的制限は回避できる。患者自身の幹細胞を手に入れて、適切に増やすことに成功すれば、移植の場合に拒絶反応も起らない。もちろん、体性幹細胞を増やすことや望み通りのタイプの細胞をつくることはもっと難しい。しかし、移植を成功させるためには、両方とも不可欠の前提条件である。それに加えて、脳から幹細胞を取り出すことは、危険がないわけではない。それで、骨髄の幹細胞から新しい神経細胞を手に入れる試みがなされている。これは動物実験ではすでに成功している。マールブルクの大学病院神経科において、研究活動が行われている。マウスによる最初に成果が記録されている。この研究プロジェクトはすべて寄付金でまかなわれている。プロジェクトグループは寄付に感謝している。寄付金の口座を下記に示す。公共の利益目的の寄付に関する領収書を請求できる。この寄付金は税金の控除可能対象である。
寄付金口座:フィリップ大学病院 マールブルク
名義:ペーター・ホフマン・パーキンソン研究プロ ジェクト
口座場所:×××× 口座番号:××××
銀行コード番号:×××× マールブルク・ビーダー コプフ貯蓄銀行
領収書は文書で下記に請求してください
フィリップ大学病院 マールブルク (以下略)
ご協力に感謝いたします。
パーキンソン病とは何か [2003年刊伝記]
パーキンソン病とは何か
パーキンソン病。この病気は、発見者であるイギリス人の医者、ジェームズ・パーキンソンの名前にちなんで、こう呼ばれるようになった。パーキンソン氏は医学だけでなく、社会に積極的に関わる、注意深い観察者だった。彼は『老ヒューバート』というペンネームを使って、産業革命時代のイギリスの恵まれない人々の劣悪な生活条件を公然と取り上げ弾劾した。通りを行く通行人も含まれる、わずかな症例の研究によって、およそ200年後の今日でさえもその説明が完全に正しいと認められるほど正確に病気を記述することを可能にするためにもおそらく優れた観察眼が不可欠だろう。1817年に発表した『震える麻痺に関するエッセイ』と題した論文で、彼はこの病気に最初の名前を与えた。すなわち、振戦麻痺である。この病気の場合、麻痺ではないので、今日では、みんな知っているように、誤解を招く名前だ。フランス人の神経科医ピエール・マリー・シャルコーは、1860年にパーキンソンの記録に、自分自身の観察を補って、この病気に、パーキンソン病あるいは単にパーキンソンという今日使われている名前を与えた。
多くの人はパーキンソン病と言えば、なんといっても手足が意志に反して震える老人の姿と結び付けて考える。だれでも、この病気は、多分たいしたことではないし、薬によってコントロールできると思いたいという誘惑にかられるのに時間はかからない。残念ながら、この考えが間違っていることは明らかで、そういう事態の役に立たないということを、発病したら、いやでも思い知らされることになる。そこで、多くの人は当惑しつつ、自分の状況をもっと理解したいと望む。『理解』とは要するに 『受け入れる』ことにほかならない。それでは、パーキンソン病とは何だろうか。このような病気と共に生きるということをどう想像すればよいのだろうか。ジェームズ・パーキンソンは、すでに最も重大な症状を以下のように記述している。多くの場合、この病気は、手、足、あるいは、指だけということもあるが、それも片側だけの震えで、しかもとりわけ安静状態のときに、始まる。つまり、例えば、リラックスして、座ったり、横になったり、立っていたりするときだ。のちには、身体の反対側にもひんぱんにそういった症状がおこるようになる。動作は次第に遅くなる。歩き方は小刻みになり、患者はバランスを保つことが難しい。シャルコーはのちに、筋肉の緊張が増す結果おこるぎこちなさという典型的な症状に関する観察結果を追加した。始め硬直はたいてい肩凝りや背中の痛みとしてあらわれる。続いて、筋肉の緊張がどんどん増して、最終的には、特徴的な前屈みの姿勢に加えて、腕と手がつっぱったまま固定される傾向がある。因果関係を持って進行する症状に注目すれば、この病気のあらゆる複合症状は明らかである。
このような症状を引き起こす原因は何だろうか。パーキンソン病は、脳内のある特定の神経細胞が徐々に死んでいくことによって引き起こされる運動障害である。私たちの運動は、随意的なものも、多くの不随意的なものも、脳によって制御されている。脳の働きによって、この制御を常に円滑に行うことができる。休むことなく、無数の情報が正しく結合されなければないらないのである。情報の流れは、神経細胞内で電気的に、神経細胞間ではたいていは化学的な手段で生じる。化学的な情報伝達のためには、メッセンジャー物質を生成し、分離し、受け入れ、再び分解する、すなわち、リサイクルすることが必要不可欠である。このメッセンジャー物質がドパーミンである。ドパーミンは、大脳黒質で生成される。細胞の色が黒いためこのように呼ばれている大脳黒質は、中脳の機能的な部分である。中脳は、やはり大脳皮質と共に、脳の機能的な部分に属しているが、黒質は身体の運動を制御している。従って、中脳は、脳の無数の組織と共に、神経接続によって、絶え間なく情報を交換している。ドパーミンを生成している黒色の神経細胞が徐々に死んでいくことによって、脳内のドパーミンの欠乏という状態が引き起こされ、その結果、パーキンソン病の症状が出現する。脳内のその部分には黒色物質を含む細胞がたくさんあって、縞模様があるように見えるところから線条体と呼ばれている組織が、他の脳組織と緊密に連絡をとっている。線条体の中には、ドパーミン受容体がある。これで興奮作用あるいは抑制作用を制御するドパーミンを受け取ることによって、線条体と連絡をつけ、脳内のその部分が活動する。ドパーミンと、ほかにも多数存在する伝達物質との複雑な相互作用によって、脳内の必要部分に興奮と抑制の信号が作られ、送りだされる。これが身体の運動の制御と統括に根本的に関与している。伝達物質が、不十分か、あるいは、もはやまったく働かなくなった場合、この時点ですでに、どんな影響が出る可能性があるか、ぼんやりとだが感じ取れる。興奮作用と抑制作用のバランスと、この作用を使った情報処理とそれに続く情報管理の全プロセスは持続的に阻害される。脳がもはや正常に機能していない場合、脳の性能に対する畏敬の念がたいていまっさきにわき起こる。一度でも酔っぱらったことのある人ならだれでも、いかにたわいもなく複雑な運動進行切り替えセンターの足並みが乱れうるかということを、知っている。私たちの生活はすべて運動である。運動とは、歩くこと、階段をのぼること、自転車に乗ること、乗馬などだが、車の運転でさえ、ものすごい科学技術の進歩にもかかわらず、今も統制のとれた運動を実行する必要がある。書くことも、ピアノを弾くのも、飲むこと、食べること、向きをかえるのも、朝起きるのも、運動である。さらに、笑ったり、驚いた表情をしたり、悲しみの眼差しを見せたりといった私たちの身振りや表情もまた運動である。そして、忘れてはならないのが、話すことと、歌うことも運動だということだ。話すことは、複雑かつ微妙に交錯する調和を要する運動だが、歌うことは、それよりもはるかに複雑で繊細な運動である。パーキンソンによるドパーミン欠乏に関する記述によれば、ドパーミン欠乏が脳内の運動制御の足並みを乱し、最終的には患者の運動のバランスを乱すのである。言うまでもないことだが、これはだんだんひどくなる。一見すると、一方では運動不能や硬直、他方では無意識の震えといった、正反対の症状が出る可能性がある理由は、興奮作用と抑制作用の交替で説明するとわかりやすい。全てドパーミン欠乏の結果にすぎないとすれば、この病気は軽いうちなら投薬によって治療できるはずだと思われがちである。この考えは確かにそれほど的外れではないが、よくあるように、最初に考えるよりも、実生活における現実ははるかに複雑なのである。
パーキンソンやシャルコーの時代には、ドパーミンのことも、ドパーミンが運動の調整に重要な意味を持っていることもまだわかっていなかった。1960年の始め、不足しているドパーミンの代わりをする投薬がはじめて試みられた。幸いなことに、パーキンソン病であっても、ドパーミン受容体は維持されている。しかし、ドパーミンはそのままでは脳内に取り込むことができない。そこで、脳内でドパーミンに変化するレボドパなどの前駆体を使う。ただし、レボドパが脳内に到達する前に、この変化がおこってしまったら、受け入れ難い副作用を引き起こすばかりでなく、薬の適量の決定が困難になる。この早すぎる変化をある物質を加えることによって遅らせれば、投薬は効果的になり、投与量を減らして副作用を抑えることができるようになる。それでも、最善の投与量の決定は、常に難しい問題である。すでに示唆したように、健康な脳においてドパーミンは、情報伝達のためにまさに必要となったその時に、局所的かつ一時的に、限定的に生成される。余った分はただちに分解される。例えば糖尿病の場合、必要なインシュリンの量は、血糖値と供給された炭水化物に基づいて、正確に算出することができるが、そのつど必要なドパーミンの量ははかることができない。情報伝達がおこなわれている千分の一秒という単位の中で、計量することはまったくもって不可能である。一日中、脳には多くのドパーミンが必要だが副作用を避けるためには、可能なかぎり少量しか使用させないようにする必要がある。このために、例えば、胃や腸の中により長く留まって、そこで、徐々にレボドパを発生させる、いわゆる遅効性調合薬剤が使われる。それだけでなく、脳内のドパーミンを減らす薬もある (MAO-B-Hemmer抑制剤)ドパーミンの欠乏が原因で、他の伝達物質が激増するので、これを減らすというよりは、むしろこういう伝達物質の作用を弱める薬もつかうわけだ。最終的には、ドパーミンに似た働きをする物質で、ドパーミンを受容体に的確に導入できるドパ・アゴニストが使われる。治療効果の程度はここで詳しく説明する必要はないだろう。しかし、すべてに共通していることは、神経外科的処置を含めて、対処療法を行うだけで、病気の原因を排除することはできないということである。確かにドパーミンを生成する神経細胞の死滅が起っていることはわかっているのだが、何が神経細胞の死滅を引き起こしているのかは今日にいたるまで解明されていない。パーキンソンの症状を引き起こしうる化学物資がみつかれば、動物実験で試験されて、新しい薬や治療法がみつかるだろう。時には、脳の病気やけがが原因になる。どちらの場合も、対症療法的にはパーキンソン症候群と称している。さらに、パーキンソンの遺伝的素因も見つかっているが、発病に関してそのように説明できることは非常に珍しい。おおかたの患者の場合、本当の原因はまったくわからない。場合によってはさまざまな要素が関わっている可能性がある。とりわけ、環境汚染や、いわゆるストレスによって発生する活性酸素の作用について議論されている。後者については、身体がストレス状態になければ、活性酸素、つまり、高度に反応的な酸素結合と、それによる細胞損傷作用は無害であると言われている。
加齢に伴って、身体が本来持っている自然回復機能の働きは衰える。パーキンソン病にかかる確率は年をとるほど高くなるのはおそらくこれが理由である。大半の患者は、最初の症状が出たときには満60歳をすでに過ぎているが、はるかに若い人でも発病している。また同時に、脳は驚くべき代償能力を有しており、黒色物質内のドパーミンを生成する細胞が、すでに半分以上死滅してしまったときにはじめて、最初の症状があらわれるのだ。この病気のこうした潜行性の経過は、殊に若い患者の場合、早期の正確な診断を困難にすることが多い。残念ながら、病気の進行を食い止めることができる信頼性のある薬もまだない。入手可能な薬が症状を緩和し、最初の恐怖のあといつも通りの活発さをほとんど完璧にとりもどせるのだけれど、脳の中では、細胞がどんどん死んでいっているのだ。時と共に黒色の物質の外側にある別の領域もおかされてきて、脳の機能障害が進行し、そのために、抑鬱状態といった問題が加わり、精神的な能力が弱まり、血液循環障害等々が出現する可能性がある。
パーキンソン病に対する投薬の効き目は何年も持続するものではない。なぜなら、病気のほうも更に成長するからだ。その上、好ましくない副作用がおこる可能性があり、その結果、治療法の調整あるいは、新しい薬の投与が不可欠になる。そして、そのことがさらにまた別の副作用を招く可能性があるのだ。
このようなことから、パーキンソン病には、決定的な治療法は(まだ)ないし、まったく同様に、患者に施される治療法もわずかしかないことがわかる。この病気は、患者によって、ひとりひとりちがった進行の仕方をする。薬の効果も患者によってひとりひとり違うし、投薬の身体に対する負担の度合いも同じではない。薬の効き目は、同一人においてさえ、日によって違う。パーキンソン病は挑戦である。日々、新たな事態に直面せざるをえないし、いつも同じようにうまくいくとは限らない。
私たちの社会はますます高齢化が進んでいる。そしてパーキンソン病患者の数は増えている。彼らはみな、症状を抑えるだけではなく、脳内の損傷を治すことができる治療法に対する強い期待で結ばれている。もしかしたら、幹細胞の利用によって、うまくいくかもしれない。胎児の幹細胞の利用については、意見がわかれるところだろうが、成人のそのような細胞を取り出すことも、可能かもしれない。世界中の研究者が、この病気を最終的に治すのための方法を探している。ペーター・ホフマン・パーキンソン研究プロジェクトの活動もそのひとつである。しかし、真の突破口が得られるまでは、そこにある病気とすこしでもうまくやっていくことがまずは肝要である。ますます多くの細胞が死滅しているということは、パーキンソン病を食い止めることができ、かつ予防する物質の開発こそが、大きな進歩ではないだろうか。この病気をこれまでより早期に、そして的確に、最初の症状が現れる前に診断する助けとなるような手段ならびに方法があれば、これこそが何よりも新たな患者の助けとなり、彼らを多くの葛藤から解放するだろう。 パーキンソン病の確かな原因と、この病気が実際どのようにはじまるかがわかれば、回復までの道筋はもはやそんなに遠くはないだろう。しかし、それまでは、この病気に関する情報水準を改善すること、とりわけ、患者に対するより一層の理解を実現することなど、あらゆる援助が可能である。よりによって若くしてパーキンソン病にかかった人たちは特に深刻である。なぜなら、生活も仕事も現役の最盛期に、病気にかかってしまうのだから。このころは、まず第一に年齢と身体の衰えを結び付けて考える時期でもあり、まだ若さと欠点のない身体こそが最高の財産であるようの思える時代でもある。突然、もはや以前のようには、身体が機能しないということは、受け入れ難い。いったいだれが、業績だけが意味を持つ社会において、自分の弱点を喜んで認めたがるものだろうか。
突然、舞台上にしろ、あるいはカメラの前にしろ、もう二度と立てなくなるなら、外科用のメスが二度と握れなくなったり、エンジンの修理ができなくなったりするなら、なんという事態だろうか。よろめいたり、理由もなくその手が震えたりするのが50歳の人の場合、大半の人は、中枢神経系統の病気よりも、むしろアルコールが原因だと考える。パーキンソン病は未経験の境界線を設ける。当然のことが、挑戦になってしまう。全く思いもしなかったことが、突然困難になる。だが、パーキンソン病は1500年にはすでにまぎれもなく人を破壊していた。その状況が、印象的に、書き残されている。『震える手足は、心の許可もなく、勝手に動いている。心は、全力を尽くしても、その手足の震えを阻止することができない』 いつの日か心と手足を再びお互いに調和させる手段が発見されること、これこそが、まさに待ち望まれていることなのだ。
謝辞 [2003年刊伝記]
謝辞
この本のために、その豊富な体験を提供してくださった皆さんに心から感謝を捧げます。
中でも次の方々に心より感謝致します。
ペーター、多くの時間をこの仕事に割いて全面的に協力してくださいました。
フリッツ、多方面に渡って手助けしてくださり、写真の選出をしてくださいました。
インゲボルク、ホルスト・ウェーバーご夫妻、沢山のアイディアを出してくださり、
なにかと協力してくださいました。
ヴォルフガング・ワーグナー氏、快く序文を書いてくださいました。
アンナ・マリア・カウフマンさん、気持ちよくインタビューに応じてくださいました。
ジャニーヌ・アルトマイヤーさん、電話でユーモアいっぱいに語ってくださいました。
レギーナ・ヴィック博士、パーキンソン病の章に関して専門的に助けてくださいました。
そして、最後に、編集者のマーチン・ルンデル氏、専門家として指導し、辛抱強く協力してくださいました。
アンナ・マリア・カウフマン談 [2003年刊伝記]
「ドイツ人はペーター・ホフマンを誇りに思うべきです」
アンナ・マリア・カウフマン談
アンナ・マリア・カウフマン談
アンナ・マリア・カウフマンは、すでに述べたように、「オペラ座の怪人」のクリスティーン役でのペーター・ホフマンとの共演と、二度の演奏旅行で、彼が高く評価していた歌手である。ペーター・ホフマンとの共演を通して、彼女自身も歌手として大きな成功をおさめている。
「私はハンブルクで『オペラ座の怪人』のクリスティーン役のオーディションを受けましたが、ある日、最終的に私がこの役をやらせていただけることになったことを知りました。本当に幸運でした。その後で、まず私の相手役がだれなのか聞きました。ペーター・ホフマンでした。耳を疑いました。とにかく私はほんとにまだまったく無名でした。キャリアが始まったばかりの新人でした。それが、すごいスターと一緒に舞台にたつことになったのです。大感激でした。実際のところほとんど信じられないという気持ちでした。
初対面は車の中でした。私たちは車で、ホテル四季で行われる記者会見に行くことになっていました。ペーターはすでにリムジンに乗っていて、私は彼のそばに乗り込みました。私はひどく興奮していて、彼に対してどう振る舞うべきかわかりませんでした。でも、彼は私が想像していた世界的スターとは全く違っていました。まったく自然で、ちっとも気取ったところがありませんでした。彼は私がとても緊張しているのに気がつくと、ちょっとした冗談を言って緊張をほぐしてくれました。ホテルにはおよそ200人ものジャーナリストが私たちを待ち構えていたのですから、このような落ち着いた、マスコミ通の同僚がそばにいてくれたことは、私にとって幸いでした。こんなことは、それ以前にはまだ一度も経験したことがありませんでした。その時の記者会見は本当に問題なく進みました。その後続いて写真撮影でした。私には何もかもが新しい世界でした。ペーターは始終気楽に振る舞っていました。そして、私が物おじしないように気をつかってくれました。私がまた元通り硬くなって、自信を失っていることに気がつくたびに、さりげなく腰に手を回してちょっとくすぐるので、私はつい笑ってしまったものでした。この時の写真はケースに入れて飾ってあります。
一緒に仕事をしている間も、あんなに有名な歌手が私たちみんなの中に混ざってごく自然に振る舞うのに、何度も驚かされました。彼はまさにプロでした。いつも親切でしたし、問題があるたびに解決の手助けをしてくれました。音楽が大好きなんです。そして、若くて経験の浅い仲間たちに対して常に助言や助力を惜しまない、すばらしい芸術家です。もしかしたら『スター』然として、舞台経験のない新人を厄介だと感じる『スター』もいるのかもしれませんが、ペーターは違いました。彼と一緒だったおかげで、信じられないほどすばらしい仕事ができました。彼と共演した『オペラ座の怪人』時代は、ただただすばらしかったです。私にとってあの時期こそ、キャリアの土台だと言えます。
ハンブルクでの契約が終わったあとも、縁が切れてしまうことはありませんでした。時々電話で話したりして、同僚としての友情にあふれた専門的な助言をもらったりしたものです。『オペラ座の怪人』に対して、ゴールドCD、プラチナCD、それからダブルプラチナCD等々、RTLの獅子賞その他、さまざまの賞を一緒に受けることができました。そのほかにも私たちは何度か一緒にテレビにも出ました。1994年には、北ドイツ放送交響管弦楽団と共に『ミュージカル・クラシック』の演奏旅行に出かけました。すばらしい経験でした。その上、大成功でした。
ペーターの病気について知ったときは、もちろんショックでした。しかし、彼の病気とのつきあい方には、感嘆するばかりです。彼は運命を受け入れて、自分の道を更に進み続けています。大勢の人々のお手本たりうることだと思います。悲しいことですが、悪意のある人間が存在するのは世の常です。そういう人たちは何であれぶち壊そうとして、悪口を言うのです。ペーターは今もすばらしい歌手です。時に否定的なことを言われたり、書かれたりするのは、たいていは何の根拠もない卑劣な言動にすぎないのです。なぜなら、ねたみからか、もしくはたとえ別の理由があるにしても、彼のことが好きじゃない人たちもいるからです。
1999年に、演奏旅行の同行者として、招かれました。すばらしい時間を過ごしました。病気に関しては、彼はその扱い方をよく心得ていましたから、ほとんど問題はありませんでした。彼は自分のできる範囲を知っていますし、私は常に彼を信頼していますから、彼と演奏旅行をすることに、露ほどのためらいもありませんでした。音楽と舞台、これこそが彼の全人生なのです。彼は全てをやり遂げたのですから、もうこれ以上先に進む必要はないのです。しかし、彼は自分の仕事が好きなのです。そして、今でもまだ第一級の仕事を成し遂げることができるということを証明したのです。
私は、ドイツにおける自分の国の偉大な芸術家に対する扱いは、かなりひどいと感じています。このようなことはアメリカだったら考えられません。モハメド・アリに与えられている尊敬、応援、賞賛などを一度でいいから、しっかりと思い浮かべてもらいたいものです。アメリカ人はモハメド・アリのことを誇りに思い、絶えず応援し続けているのです。
ドイツにとってペーター・ホフマンは実に偉大なオペラ・スターです。生きている伝説です。ドイツ人は彼のことを誇りに思い、彼を大切にし、敬意を表するべきだと思います。」
病気と共に生きる [2003年刊伝記]
「この病気は私には似合わない」
パーキンソン病の診断 ~病気と共に生きる
パーキンソン病の診断 ~病気と共に生きる
「1991年に録音したエルヴィス・ソングのあと、もうひとつの夢を是非ともかなえたいと思った。今度は、カントリー・ミュージックのために、相当期間、ナシュヴィルのスタジオを予約してあった。 私はすでに数年来、『バイエルンのカウボーイ』と呼ばれていた上に、アメリカ西部でたびたび乗馬をしたことがあったり、アメリカ・インディアンと友情を結んでいたこともあって、実際にカントリー・ミュージックは身近な存在だった。カントリー・ミュージックになじんでいるその地で、ゴーサインを出したこと、そして私の歌い方が受け入れられた結果、
 アルバム『カントリー・ロード』が生まれたのはうれしいことだった。アメリカでは、クラシック音楽と娯楽音楽の区別がなかったことがよかった。アメリカでは何であれ、為せば成るだった。このCDは、私の50歳の誕生日だった1994年8月22日にぴったり合わせて発売された。
アルバム『カントリー・ロード』が生まれたのはうれしいことだった。アメリカでは、クラシック音楽と娯楽音楽の区別がなかったことがよかった。アメリカでは何であれ、為せば成るだった。このCDは、私の50歳の誕生日だった1994年8月22日にぴったり合わせて発売された。カントリー・ミュージックもとにかく舞台で歌わなくてはというので、次のツアーを計画した。そのころは、すでに相当前から健康を害しているように感じていたにもかかわらず、この計画に熱中し、没頭していた。ある日のこと、あくびをするたびに右手がふるえるのに気がついた。もっとも、この関連性を初めて意識したのは、相当あとのことだ。とても奇妙な感じだった。そのほかにも、何だか変な感じがしていた。何か説明できない衰弱感があった。『スポーツマンとして、自分の身体はちゃんとコントロールできるのだから、弱さは克服するものだ』と、あのころは思っていた。だから、おかしな感じなどは、さっさと頭から追い払って、気にしないことにした。時々、めまいがしてふらつくような感じがしたり、あくびをした時に手がふるえるのに気がついたりしていたのは、すでに何かの前兆だったのだ。しかし、私はそういうことを深刻に考えず、医者に行って「『あくびをする度に、右手がふるえるんです』なんて言えるものか。そんなことが言えるのだったら、『足を二回踏みならしたら、しゃっくりが出ます』と言い張ってもいいわけだ。気にすることはない。 無視し続ければ、そのうちにおさまるさ」と思っていた。けれども、すでにカントリー・ツアーの練習期間中に、症状は前よりひどくなっていた。動きのぎこちなさが進行しているのは確かだったし、背中がむずむずするような奇妙な感覚があった。その上、時々平衡感覚に変調をきたすようになり、この障害は、身体の動きに重大な影響を与えた。形成外科医に相談したところ、あのオートバイ事故の後遺症で、神経が圧迫されているのかもしれないと言う。確かにそうかもしれないと思った。一応治療はしてくれたが、効果はなかった。 カイロプラクティックの鍼治療のほか、いろいろやってみたが、どれも一時的に症状を緩和するにとどまった。パーキンソン症候群ではないかという話も出ていて、詳しい検査をしたのだが、診断がつかなかった。症状はどんどん悪化していたにもかかわらず、ツアーを中止することは考えられなかった。 およそ50回のコンサートをする予定で、チケットは完売、ホテルは予約済み・・・やるしかない』
観客はもちろん何の予兆も感じていなかった。しかし、ショーが始まると、 一瞬にして楽しい気分は消え去り、会場中に困惑が広がった。ペーター・ホフマンは仮面をつけたようなこわばった表情をして、ぎこちない姿勢で、しゃちごばって、手の震えを抑えようと、肩からかけたギターにしっかりと押し付けて、舞台に立っていた。可能な限り変わったそぶりを見せず、同時にコンサートの進行に集中するには、ものすごい努力が必要だった。ファンは、いつも、無造作そのものだった、すばらしいスターに、一体何が起ったというのだろうかとあれこれ思い巡らせた。居合わせたマスコミ関係者も歌手に問題があることに気がつかないわけがなかった。これはコンサート後のこんな批評からも明らかだ。身体が衰弱してやつれたスターの恐怖の小部屋からは、アルコール中毒から麻薬中毒といった、まあ月並みなものしか出てこないわけで、この辺が、コンサートにおけるペーター・ホフマンの状態の説明としてふさわしい。悪意に満ちた言葉が滝のように浴びせられた。これは、背骨の 神経が圧迫されたことが、歌手の普通ではない状態の原因だと知らされたあとも、終わることはなかった。結局のところ、マスコミは、またしても話題を手にしたのだった。
鉄のような意志で身体を律し、ペーター・ホフマンは全てのツアーをやり遂げた。出演中にもずっと医者の世話になっていたが、最終的な診断はつかなかった。 形成外科や、神経科、その他の専門医にもかかったが、無駄だった。ツアー終了後、何が何でもしなければならないことは唯一、この苦しみの原因を明らかにすることだけだった。
「1994年の『ミュージカル・クラシック・ツアー』のときにはすでに、手が相当にふるえていて、隠せないこともあった。集中するのが困難だった。腕が何となく自分のものではないような感じが続いて、それに対して為す術がなかった。でも、1年後のカントリー・ツアーのときに比べれば、たいていはうまくごまかして、まだ完璧にコントロールできていた。しかし病気はさらにエスカレートした。ほとんど動けなくなったうえ、震えはますますひどくなった。手をギターに強く押し付けたら、手を静かにさせられると思った。時々、ギターを押しつぶしてしまいそうな感じがした。それから、発作的な脱力がおこるようになった。全ての感覚がすこしずつゆっくりと麻痺していって、ただ舞台に上がるだけのためにも、全力を尽くさなければならなかった。こういった身体の問題を把握してコントロールするためには全精神を集中する必要があった。私自身でさえ、一体何が起っているのかわからなかったのだから、コンサートの客は当然なおさらのこと理解に苦しんだに違いない。『何故、彼は動かないのだろうか。何故、彼はこわばったような顔をしているのだろうか。何故、サインしないのだろうか』その通りだった。手が震えて書くことができなかったのだが、このことは特に誤解を招いた。そして、ますますうわさと憶測が広がっていった・・・
もうそのころには、大勢の医者に診てもらっていたし、可能なかぎり、ありとあらゆる自然療法も試してみた。アトランタではアパッチのまじない師のところで数週間以上過ごした。 彼のところでやったことと言えば、完全に彼と生活を共にして、二回ほど一緒に彼らの和解の儀式である平和のパイプを吸っただけで、他には何をしたわけでもなかった。彼は蒸し風呂による発汗治療で有名だったが、私に対してはその方法を使わなかった。数回、その治療法を頼んだが、その都度はぐらかされてしまった。ところが、驚いたことに、家に戻ったときには、苦痛がすっかり消えていた。あれは錯覚だったのか、転地効果だったのか、私にはわからない。残念なことに、それも長くは続かなかった。
病気の診断がついても、そのあとも、仕事はきちんとやりたかったし、早々にあきらめたくなかった。私はアメリカへ行って、評判のよい全ての病院で診てもらうことにした。それでも、はじめは全く成果がなかった。色とりどりの様々な形のビタミン剤やら何やらの錠剤をやたらに処方されたが、当然のように効果はなかった。最後に有名なエムロイ病院のワッツ教授に診てもらった。教授は全ての検査結果を再チェックしてから、動作と反応の検査を実施した。手の動きを再チェックして、私に円と線を描かせた。 全ての検査結果をまとめてはっきりと診断がくだされた。教授は見るからに言いにくそうに『ホフマンさん、残念ながら、パーキンソンです』と診断結果を伝えた。
この告知はもちろんショックだったが、同時に信じられないほどの解放感があった。私の中でおこっていることが、やっとはっきりと分かったのだ。わけのわからない時期が終わったことで、大きな荷物をおろせたのだった。 私はひどく幸せな気分になって、診察室から廊下に走り出て感極まって『パーキンソンだったんだ』と叫んだ。ワッツ教授はあきれてドアのところに立って見ていた。きっとこんな反応は予想していなかったにちがいない。私は教授のそばに戻って、私の身体に起っていることが何なのかがやっとわかったことがとにかくうれしいのだと説明した。 ワッツ教授は、薬に関して必要不可欠な組み合わせを教えてくれ、ドイツのパーキンソン病の専門医に連絡をつけてくれた。教授は私がこの病気とうまくつき合っていることに何度も驚いていた。ほとんど天才的だと教授は言った。こんなふうにパーキンソン病とつきあった患者にいまだかって会ったことがないということだった。これには、私のスポーツ経験が、大きな役割を果していると思う。スポーツマンというものは、自分の身体に対して究極の能力を出すことを要求することが可能だし、敗北や困難な状況とのつき合い方も知っている。スポーツをするたびに、自分にとってより効果的なやり方を発見したものだ。 ところで、自転車で数キロ行けば、その結果、健康な人でもだれでも同じように、当然疲れる。しかし、そのあと、肉体的苦痛がほとんど消えるという感覚がある。できれば、私は、毎日、乗馬やジョギングやゴルフをしたい。スポーツや、身体を使うことなら、とにかく何でもいい。主治医はこの点について私を支持して、『あなたができると思うことなら、とにかくなんでもしなさい』と勧めた。スポーツをしていなかったら、病気はもっとずっと進行していたにちがいないと確信している。
薬の服用を開始したとき、最初は何の効き目も感じなかった。とにかく何の変化もなかったので、ほんとうにがっかりした。そして、およそ3週間後、突然、ほとんど苦痛がないことに気がついた。時々、別の薬にしたり、薬の量を変えたりするのだが、そういう場合には、また同じような現象がよくおこった。もちろんこの薬には、30分以内に苦痛が軽減されるといった鎮痛剤のような効果はない。これについては、繰返し思い知らされたものだ。時間厳守で薬をのむのをたまに忘れると、たちまちその報いがきた。定められた時間を過ぎたら、薬の効果は、分単位で時間きっかりに弱まった。いつだったか愛馬のサニーに乗って外出したとき、森の真ん中でこういうことが起った。私はまるで酔っぱらいのようだった。自分の身体さえ固定できず、馬の動きをコントロールすることは、ほとんどできなかった。サニーはこのことをただちにさとった。サニーは、好き勝手にあちこち走りまわった。実際、行ってはいけないところだろうが、好きなようにした。その時はまだ一瞬強く手綱を引くためには、十分な力があった。幸いなことに、サニーはすぐにまた私の言うことをきいたが、大変なことになり兼ねないところだった。『二度とこういうことが起らないように、時間通りにきちんと薬をのむことを考えなければならない』と猛反省した。
コンサートの仕事に際しては正確な服用計画を作成した。綿密に練り上げ、完璧に実行した。もっとも時には、舞台に出る直前に全く動けなくなって、切羽詰まってしまったこともある。 足は、まるで百キロの石を載せられているような、感じだった。片方の足を前に出すことさえ不可能に思えた。ところが、運のいいことに、時間ぎりぎりになったとたん、動いたのだった。」
ペーター・ホフマンは、あの大変だったカントリー・ツアー、そして、その後のパーキンソン病の診断後も、可能な限り、普通の生活を続けようと頑張った。病気のことを知っていたのは一部の消息通だけで、世間に発表するつもりはなかった。芸術活動も、できる範囲で、やめずに続けるつもりだった。1996年には、新しいCDを録音した。『ロック・クラシック、ラブ・ソング』で、『この素晴らしき世界』や『オンリー・ユー』から、『プリティ・ウーマン』や『ブルー・アイズ』までのすばらしく美しい歌が入っている。制作は、映画音楽作曲家のハロルド・フォルトマイヤーで、彼のスタジオで録音された。
その後、ペーター・ホフマンに対して、バート・ゼーゲベルクから、1997年のカール・マイ劇で
 オールド・ファイアハント役の依頼があった。毎年一人か二人の舞台か映画で知られている『スター』と契約するのがバート・ゼーゲベルクの伝統だった。馬マニアのペーター・ホフマンとしては、『馬に乗って台詞をしゃべる役』は、楽しみでもあり、挑戦のしがいがあった。
オールド・ファイアハント役の依頼があった。毎年一人か二人の舞台か映画で知られている『スター』と契約するのがバート・ゼーゲベルクの伝統だった。馬マニアのペーター・ホフマンとしては、『馬に乗って台詞をしゃべる役』は、楽しみでもあり、挑戦のしがいがあった。 馬は、かなり以前からすでに彼の生活において重要な部分を占めていた。自由時間は全部乗馬に費やし、興味をそそる馬に出会うたびに買ったので、しばらくすると、馬小屋では、11頭の馬がはしゃぎまわることになった。しかし、とにかく膨大な経費がかかったので、次第に数を減らさざるをえなかった。今では、ペーター・ホフマンの馬小屋には、サニーとグリンゴの2頭しかいない。
馬は、かなり以前からすでに彼の生活において重要な部分を占めていた。自由時間は全部乗馬に費やし、興味をそそる馬に出会うたびに買ったので、しばらくすると、馬小屋では、11頭の馬がはしゃぎまわることになった。しかし、とにかく膨大な経費がかかったので、次第に数を減らさざるをえなかった。今では、ペーター・ホフマンの馬小屋には、サニーとグリンゴの2頭しかいない。「毎晩のように馬の夢を見たのがきっかけで、乗馬をはじめた。それは、馬に乗って、遠乗りに出かける夢で、その馬が私とは非常に深い結びつきあるのだと話しかけた。これがある意味で前兆だったにちがいない。 そして、ある日のこと、私は電話帳で厩舎を探し出して、数カ所に電話をかけた。幸運なことに、三番目のところで、乗馬のレッスンが受けられると言う。馬術教師が『とにかく来週にでも一度お立ち寄りください』と言った。彼は、私が何かをしようと決意したら、待てないということを、知るはずもなかった。『喜んで伺います。でも、来週なんかじゃなくて、今すぐにです』と宣言した。彼は了解し、すぐに練習を開始したというわけだ。
最初のレッスンは、どうということもなかった。牧草地の囲いの中を、ちょっと跳ねまわっただけだったので、私は、ぜひとももっとやりたいと思った、しかし、教師は引き続き二時間目のレッスンをすることは、『明朝には、ひどい筋肉痛で動けなくなること請け合いだ。きょうはこれで十分だ』と拒否した。彼の言うことは間違っていなかった。それでも、翌日にはまた出かけていった。三時間目のレッスンのときにはもうどうしても囲いの外へ出たいと言った。それで、もしかしたら落馬するかもしれないとしてもかまわなかった。先生は仕方ないなという様子であきれながらも、私の馬にくくりつけた長い細引きを握って馬に乗り、私の前に立って、先導してくれた。彼は優秀な騎手で、信頼できたが、やはり怖かった。それでも、この遠乗りの間に細引きを外して、その後は、もう乗馬のレッスンに行かなかった。 その代わり、手に入る限りの馬に関する専門文献、特にウェスタンライディングに関するものを読んだ。 こういうことに詳しい人々とのおしゃべりを楽しんだり、短期間牧場で過ごすためにアメリカへ行ったりした。故郷では、ウェスタンスタイルで馬に乗って、『森を過ぎ野を越えて』辺りの風景の中を駆け抜けて行ったのは、多分私が最初で、そのころは、まだ私だけだったと思う。 農家の人たちは仕事の手を休めて、『ホフマンだよ。バイエルンのカウボーイだ』と見送っていた。
興味をひく馬に出会うと、買いたいという気持ちをなかなか抑えられなかった。シェーンロイトの自分の地所に、馬小屋を建てて、乗馬用の円形広場には、まるで王冠のように照明設備をつけて、夜遅くなっても乗馬ができるようにした。そのころは、母が『あなたはいったい何のために家が必要なのかしら。いっそのこと牧草地のそばに小屋を建てたらどう』と勧めたほどだった。私は時に度を越すことがあったから、母がこう言うのももっともだった。しかし、熱意は報われた。1988年に、ミュンヘンでウェスタンライディングの準ヨーロッパ・チャンピオンになった。その後、この世界からはすっかり身を引いてしまった。なぜかといえば、馬の査定、飼育、子馬の売買等々を含めて、要するにこれはお金の問題でしかないということに気がついたからだ。馬と人間の交流は二次的なものにすぎない。しかし、私にとってはそうではなかった。牧草地に行くと、馬たちが遠くから私を見つけて喜んで私の方に駆け寄ってくるのがうれしかった。馬はたまにちょっとなでてやるだけで、喜んでくれる。アメリカでサニーを見つけたときのことを懐かしく思い出す。サニーは個性的で、注意深い雄馬で、裏庭から顔をのぞかせていた。見たとたん、すぐに、私の馬だということがわかった。バート・ゼーゲベルクから連れてきたエル・グリンゴも同じだった。数週間一緒に過ごして、サニーを慣れさせた。部分的にだが、調教もした。もはやサニーを手放す気にはなれない。」
バート・ゼーゲベルクのカール・マイ劇は、もちろん高尚な文化的イベントとは言えない。しかし、ペーター・ホフマンにとって、そんなことは問題ではなかった。要するに今度もまた、今までとは違う場所で自分の限界を探るため、新たな事を試すチャンスだった。それに、練り上げられた演出コンセプトという重荷を背負わずに演じられる役であるということや、無造作な西部劇の英雄を馬に乗って演じること、インディアンとカウボーイの芝居をすること、それを子どもたちが目をまるくし、目を輝かせて見つめてくれることなどが、彼には途方もなく楽しかった。ある子どもが『とってもすごいオペラ歌手がヴィネトウをやってるんだね』と言ったときにはうれしい気持ちがした。加えて、病気の身でありながら、身体全体を使う役、それどころか難しい本物のスタントをやることは、挑戦的だった。彼の病気に関してはまだほとんどだれも知らなかった。2年後、パーキンソン病にかかっていることを公表したとき、この時の共演者たちは、まさに吃驚仰天した。なにしろ、だれ一人そんなことは毛ほども気付いていなかったのだ。正確に薬を服用することによってのみ可能だったのは言うまでもないことだが、身体は機能していた。毎日、燃えるような夏の暑さの中、ゼーゲベルク中を移動しながら、共演者たちと共に、ほこりっぽい野外劇場で自分の役を演じつづけ、小さな『オールド・ファイアハント』ファンたちの求めに応じて、飽きることなく、サインをし続けた。常に規律を保ち、全身全霊を尽くして自分の仕事に没頭した。
もっともマスコミは別の見方をした。 カール・マイ劇と契約した俳優にしろ、選ばれたその他の著名人にしろ、「円形劇場のスター」として登場する際は、非の打ちどころがないと思わせるメーキャップをして、完全な美を見せつけながら、近寄り難い雰囲気で、映画のスクリーンやテレビスタジオの中に存在するのではなくて、砂埃の中 おがくずの上を巧みな身のこなしで動き回る、なによりも「まったく気のおけない」存在であるべきなのだ。あの時のペーター・ホフマンについては、世界的スターの転落した姿にすぎないと言われたものだ。
「馬に乗った」役と言えば、テレビでではあるが、すでに一度やったことがあった。ナミビアが舞台の『道中ご無事で』という連続ドラマの中で、ハンターが角や毛皮を求めて狩りをするのをやめさせようとする農場主の役をやった。馬に乗って息をのむようなスピードで犯罪者を追跡するのだ。
このように芝居の世界をちょっと旅したあと、ペーター・ホフマンは再び音楽に戻った。1998年に、『ラブ・ソング』の成功に続いて同じハロルド・フォルトマイヤー制作による『ロック・クラシック、ユア・ソング』を録音した。これにはエルトン・ジョンからビートルズまでの古典的なポピュラー・ソングが含まれている。健康状態に対する憶測が鎮静化しないため、ペーター・ホフマンは、 1999年8月パーキンソン病にかかっていることを、大手の大衆紙に公表した。
「そのあと、とても気持ちが楽になった。どこでもいかに徹底的に観察されているかということにずっと以前から気がついていた。こういうことに対しては、時がたつうちに非常に鋭敏な勘が養われるものだ。本音を言えば、自分の病気について話したくなかった。同情されたりするのが嫌だったからだ。とにかく徐々に世間から身を引いていきたかった。幸運なことに多くの人々がこうした『撤退』をよしとして受け入れている。ところで、 病気の公表に対する反応は、すごくよくて、相当沢山の好意的な手紙を受け取った。私のことを今こそもっとよく理解できるだろうし、あらゆる催しへの出演が喜びだったと書いてくれたファンの手紙もあれば、同じようにパーキンソン病にかかった人からの連帯を表明する手紙もあった。大勢の人にとって私はいわば見本的役割を果していたのだ。ということは 私の心配は全く根拠がなかったわけだ。
今日パーキンソン病の原因はまだわかっていない。私の主治医は、遺伝ということはほとんどありえないと考えている。頭をひどく打ったことが原因ではないかとの推測も可能かもしれない。原因だったかもしれない時は過ぎ去っている。発病する前、どのぐらい長い間、この病気を抱えてやってきたのか、だれにもわからないのだから。子どものとき一度相当ひどく転落したことがあるから、ひょっとしたらこれが原因かもしれない。それとも、あのオートバイ事故も原因の可能性がある。あらゆる可能性があるが、確かなことはわからない。例えば、ボクサーのモハメド・アリのような人がこの病気にかかっているのだから、頭を強打したことが原因である可能性も、当然あると言えるだろう。
私は可能な限り普通の生活を続けようとしている。すでに述べたように、スポーツはそのために非常に役立っている。十種競技では何度も切り抜けるべき困難に遭遇したものだ。このことがこの数年とても役に立った。十種競技によって自分の身体に全力を出させることと、自分の身体をコントロールすることを学んだ。どん底の状態に陥った場合も、比較的早く回復できる。 私はある程度まで病気に抵抗できると思っているが、どんどんひどくなっていく病気に対抗するためには、時がたつにつれてスポーツマンとしての能力をさらに高めることが必要になってくるようだ。もちろんそんなことは不可能だ。能力訓練のために、すでにやっていることをとにかくやろうとしている。うまくいくこともあれば、必ずしもそうはいかないこともある。その成果は、例えば、パーキンソン病の患者が定期的に行っているテストでわかる。長時間、片足で立っていること、腕を高くあげること、バランス状態を保つことなどは、たいていのパーキンソン病患者にとって不可能なだけでなく、多くの健康な人にとっても不可能である。私はこういうことはずっと問題なくできた。まるでアルコールテストのように、線の上を歩いたり、目を閉じて指で鼻の頭を触ったりすることも問題なくできる。時がたつにつれて、次第に困難になってきているという自覚は、はっきりとある。もっとも一方向に連続的に進行するのではなく、進んだり、後退したりする。時々薬を変えたり、薬の量を調節したりして、最大限効果的な投薬をしなくてはならない。今のところ回復の可能性はない。症状をおさえるよう試みることができるだけだ。つまり、できるのは、症状を緩和すること、病気の進行を遅らせることだけだ。しかし、希望もある。希望を持つだけの根拠もある。研究が進めば、近い将来新しい治療法や手術の方法が発見されると確信している。そいうわけで1999年以来、ペーター・ホフマン・パーキンソン研究プロジェクトを設立し、医者の研究プロジェクトに対して経済的援助を続けている。中でも幹細胞の研究がまず第一にあげられる。これは大いに期待できる。遺伝子研究においても、多くの成果が上がっている。そして、国外ではすでに個々の臓器の複製が考えられている。 いつの日か、主治医が何か新しい事を試してみる機会を得たら、私を自由につかってもらえるようにしてある。こんな病気はとにかく私には似合わない。私は強い意志と全エネルギーでもって、この病気と闘い、将来勝利することを確信している。」
1999年8月にパーキンソン病であることを公表したあとは、この病気のことを、世の中に知らせることも、ペーター・ホフマンの仕事になった。そして、ペーター・ホフマン・パーキンソン研究プロジェクトの設立によって、パーキンソン病研究を積極的に援助している。この財団は、寄付金を、この悪性の病気の克服に貢献する学問的プロジェクトに対する助成金として提供し続けている。だが、寄付だけではなく、例えば『ベスト・オブ・ロック・クラシック』のようなCDの発売も基金として役に立っている。病気に妨害されながらも、ペーター・ホフマンは引き続き音楽活動に対して積極的だった。というわけで、1999年の10月と11月には自信を持って、新たなツアーに出かけた。『オペラ座の怪人』で相手役だったアンナ・マリア・カウフマンと共に、20以上の都市で、『ミュージカルとポップスからのハイライト』を歌った。彼は自分の肉体的な苦痛の扱い方をよく心得ていたため、舞台上の彼を見た人は、病気についてほとんど何も感じなかった。観客は彼の勇気に感嘆し、このような困難な状況においても完璧なショーを催してくれたことと、そのすばらしい成功に対して敬意を表した。そして、とりわけ、ファンは、かつてと変わらず美しい、独特な声を楽しんだ。
しかし、このツアーのあと、最終的に歌手活動からは引退して、よりプライベートな生活をするようになった。病気の悪化を可能な限り先に延ばすために自分の体力を節約したかったのだ。スポーツは引き続き規則正しく行っている。自転車に乗ったり、乗馬をしたり、ゴルフをしたり。これは彼にとってとても重要なことだ。ゴルフは『オペラ座の怪人』でハンブルクに滞在したときに新たにはじめたのだが、それ以来、ずっと夢中だ。「イーグルズ・ヒャーリッツ・ゴルフ・クラブ」のメンバーとして、以前同様、このスポーツを積極的にやっている。そして、このクラブでは、大勢の著名人が、慈善の目的のために尽力してくれている。この方面では、自分の財団のために、ゴルフ・トーナメントを組織することさえできた。
 2000年のバイロイト音楽祭の練習期間中に、1970年代と1980年代を通して、たくさんの公演でジークリンデやイゾルデとして、ペーター・ホフマンの相手役だったジャニーヌ・アルトマイヤーが、ひさしぶりにバイロイトを再訪した。最初の心のこもった出会いで、二人は間近に迫った『神々の黄昏』のゲネプロに一緒に行くことに決めた。フリッツ・ホフマンは、兄に、サインカードを何枚か持って行くように助言した。ペーター・ホフマンとしては、さしあたりそんなことは全く余計なことだと思っていたのだが、それでも、結局のところ、弟の忠告に従った。十倍のカードを持ったほうがよかったかもしれなかった。というのは、昔の『ウェルズング・ペア』は、祝祭劇場に入るや否や、感激した大勢の人々に取り囲まれ、地元の新聞は、大見出しでこの出来事を伝えないわけにはいかないと感じたほどだったからだ。この二人のペアはオペラの歴史に残っている。シェロー演出のリングは、とっくの昔に『歴史的演出』のレッテルを貼られていて、このころにはバイロイト音楽祭開始に続く『はじめの』百年の里程標としての評価がすっかり定着していたにちがいなかった。南ドイツ新聞に載ったある『ワルキューレ』公演に関する記事を以下に紹介しよう。
2000年のバイロイト音楽祭の練習期間中に、1970年代と1980年代を通して、たくさんの公演でジークリンデやイゾルデとして、ペーター・ホフマンの相手役だったジャニーヌ・アルトマイヤーが、ひさしぶりにバイロイトを再訪した。最初の心のこもった出会いで、二人は間近に迫った『神々の黄昏』のゲネプロに一緒に行くことに決めた。フリッツ・ホフマンは、兄に、サインカードを何枚か持って行くように助言した。ペーター・ホフマンとしては、さしあたりそんなことは全く余計なことだと思っていたのだが、それでも、結局のところ、弟の忠告に従った。十倍のカードを持ったほうがよかったかもしれなかった。というのは、昔の『ウェルズング・ペア』は、祝祭劇場に入るや否や、感激した大勢の人々に取り囲まれ、地元の新聞は、大見出しでこの出来事を伝えないわけにはいかないと感じたほどだったからだ。この二人のペアはオペラの歴史に残っている。シェロー演出のリングは、とっくの昔に『歴史的演出』のレッテルを貼られていて、このころにはバイロイト音楽祭開始に続く『はじめの』百年の里程標としての評価がすっかり定着していたにちがいなかった。南ドイツ新聞に載ったある『ワルキューレ』公演に関する記事を以下に紹介しよう。「この『ワルキューレ』に、音楽的にも演劇的にも、全体的雰囲気として、欠けているのは、興奮である。抱擁の陶酔もなければ、身振りやしぐさと感情の混沌として分かち難い結びつきもない。そう感じた瞬間、シェロー演出の天才的な『リング』におけるジャニーヌ・アルトマイヤーとペーター・ホフマンの記憶が、我知らず、強烈に甦る」
ジャニーヌ・アルトマイヤーは、バイロイト音楽祭での再会のあと、ペーター・ホフマンとの感動に満ちた共演について、次のように語ってくれた。
「ペーターと私は、いっしょにすばらしい仕事をしてきました。私たちはものすごく調和がとれていました。いつもよく理解しあっていました。だから、あのころはすばらしかったです。私たちは二人ともまだとても若かったけど、あんなに素敵な共演は二度と経験できませんでした。ぺーターは今でも私にとって最愛の同僚です」
2000年の12月、ペーター・ホフマンは、ソフィア・ラジオ・シンフォニーオーケストラと共に『2000年、聖夜』のクリスマス・ツアー を行って、再び舞台に立った。彼のクリスマスの歌をはさんで、コンサートのはじめと、終わりには、喜びにあふれながらも瞑想的なクリスマスの物語が、彼の友人である俳優のアーサー・ブラウスによって、朗読された。その日の新聞には、ペーター・ホフマンに関することが載っていたが、さらにたいていはパーキンソン病関連の記事が載っていた。マイケル・J・フォックスや、モハメド・アリや、ローマ教皇に関する、数えきれないほどの記事のすみにペーター・ホフマンも「運命の仲間」として名前が出ていたが、ひとりの人物として、芸術家として扱った記事はほとんどなかった。ジャーナリストのアクセル・ブリェッゲマンが2001年10月の『日曜日の世界』誌に書いた記事は賞賛に値する例外と言えよう。ブリェッゲマンは『ペーター・ホフマン 英雄の人生』と題して、客観的に、しかし同時に、思いやりを持って、歌手の引退生活を、感情を交えず伝えている。
「ペーター・ホフマンは、何度も繰り返し、こんな夢を見ている。大勢の人々から逃げて、高層ビルのてっぺんに向っている。大勢の人の群れが彼を追いかけてくる。ビルの上に到着し、立ち止まって、『止まれ』と叫ぶ。そのあと『見るがいい。私に何ができるか』と叫んで、そこから飛ぶ。それでおしまいだ。そのあと、目が覚める。
並はずれた才能を持つヘルデンテノール。その彼が、レザー・ルックのジークムントとして、甲冑に身をかためたローエングリンとして、オペラ座の怪人として、その上、カントリー・コンサートでは、自信に満ちたエルビス・プレスリー歌手として、舞台に立っていたその時は、昔のまま、色褪せることはない。
2年前ペーター・ホフマンはパーキンソン病であることを公表した。モハメド・アリと同じ病気である。ホフマンはバイロイトの近くの村の古い学校の校舎を買って、改装して住んでいる。今はインタビューもない。新聞もない。トークショーもない。(略)しかし、今もなおその瞳にはユーモアの喜びが揺らめいている。それは、かつて圧倒的な紋切り型のワーグナーの枠からはみだした時と同じユーモアの感覚である。庭の二羽の白鳥にターザンとイゾルデと皮肉っぽく名付けている。何よりも愛したワーグナーをユーモアいっぱいにたたき壊そうというわけだ。それは、マスコミが彼をおおげさに祭り上げようとした、青い目で金髪の体格のよい『メイド・イン・ジャーマニー、ドイツ製』のジークムントといった、くそまじめなステレオタイプに抵抗したのと全く同じだった。
実際のところ彼は今はもう自分の昔の録音を聴きたいとは思わないが、『そうは言っても、やっぱり時には誘われて、思いがけず部屋の入口に立ちどまって、往時を思い、すばらしかった時をもう一度味合う』と語った。彼は依然として現代的なジークムントのままだ。病気にもかかわらず、今も馬に鞍を置く。オーバープファルツ地方の静けさの中で、思い出を整理しようとしているのだ。そして、閉じた幕のうしろで、病気と闘っている。ビリヤード台の前で、ゴルフ・トーナメントの会場で、あるいは、朝霧の中を草原を越えて馬を駆けさせながら。そんな時、年はとっていても、また昔通りの飛び抜けた奴のように見える。まるで、夢の中で迫りくる人々の群れを逃れて高層ビルから飛び去るときのように、軽やかに見える。」註:
•カール・マイ劇:毎夏ドイツのバート・ゼーゲベルクで行われる野外劇。子供向けの人気西部劇物語の作者がカール・マイで、この人の物語が、バート・ゼーゲベルクという温泉地で、毎夏野外劇として演じられているとのこと。この野外劇では、毎年一人か二人の舞台か映画で知られている『スター』と契約するのが伝統だそうです。
•カール・マイ(1842-1912)ドイツの作家「カール・マイの冒険小説はドイツの少年に愛されています。ネイティヴインディアン、インカ帝国、クルド(現在、トルコで独立運動をしている)地域など様々なドイツ人にとってエキゾチックな場所を題材に書かれています。」
オペラ歌手でロック歌手-3 [2003年刊伝記]
オペラ歌手でロック歌手に、矛盾なし ・・・3
 「 私の好きなシュトルツィング役を、バイロイトで歌うことができたということは、すばらしいことだった。この役は、ヴォルフガング・ワーグナーの演出で、私は、ライナー・ゴールドベルクとジークフリート・イエルザレムが歌った後を引き継いで、全く新しいものを作り上げようと試みた。すべての練習をやり遂げるためには、もちろん とても厳しい規律に従って仕事をしなければならなかったし、綿密な計画を立てる必要があった。結局、パルジファルに加えて、クプファーの新演出でのジークムントも歌うことになったので、この年のバイロイトの夏は実に挑戦的であった。 私は祝祭劇場でずいぶん長時間過ごしたので、それなら結局のところ劇場に泊まってもさしつかえないほどだった。多くの練習によって声に過大な要求をしたくなかったので、部分的には声を出さずに歌うふりだけをしようと決心した。これはイタリア・オペラのテノールたちはまったく普通にやっていることだが、ドイツ物ではめったにないことだった。しかし、朝から晩まで、しかも、別々の指揮者と演出家と共に非常に異なる三つの役を練習する場合、一日にせいぜい一つの役しか感情をこめて歌い切ることはできない。そこで、パルジファルとジークムントは交互にフル・ヴォイスで歌い、私にとって一番軽い役であるシュトルツィングはもっぱら歌うふりをするだけに決めた。しかし、マイスタージンガーの指揮者だったマエストロ・ショーンバットはこれが全く気に入らなかった。彼はそのことに注文をつけて、『ホフマンさん、あなたのシュトルツィングが心配です』と言った。私は『ご心配にはおよびません。この役は私にとても合っていますから、自然にやれます』と答えた。ショーンバットは『そうかもしれないが、とにかく一度聴かせてもらいたいものだ』と応じ、私は『初日か、もしかしたら、その前にゲネプロで全部お聴きになれます』と返事をした。彼は満足しなかったが、私は態度を変えなかった。結局のところこれは私の声の問題であって、私としては絶対に危険を冒したくなかった。三つの難しい大きな役で最高の業績をあげることができるように、自分の力をどのようにうまく配分するべきかは、結局、ひとり私しか判断できないことだった。彼は数回にわたって、せめて一度か二度ちゃんと感情を込めて歌うように説得しようとしたが、私は自分の考えを貫いた。 ゲネプロが近付いてきたころには、私は相当いらいらしていた。というのは、毎日6時間の練習をしていたにもかかわらず、役を演技面で再構築するためには、とにかく時間が足りなかったからだった。要するに 何かをなんとか考え出さなければならなかった。私は演出で予定されていたのと全く違うことをしようと決意し、実行した。私は、全く失礼な態度でマイスターたちの前に現れた反抗的で、強情で、生意気な若い騎士を演じた。声に関しては絶好調だった。だからマエストロ・ショーンバットはもうそのことを心配することはなかった。譜面台の前の彼がどんどんリラックスしていくのに気が付いて、とにかくすごくいい気分だった。靴屋の居間での夢物語は実にかっこよく、優勝の歌は、大喜びで歌った。舞台の同僚はみんな、拍手喝采どころか、足を踏みならしさえし、観客は熱狂した。翌日、ヴォルフガング・ワーグナーと会う約束になっていた。今回は大目玉を食らうぞ、何もかも計画と違うことをやったのだから、きっと首だな、なんだか具合の悪いことになったな、などと考えていた。会議室では、ワーグナーのアシスタントであるティゲラー氏が、山のように積み上げられた書類を持って、すでに待っていた。彼は、演出計画から逸脱したことについて、何もかも書き留めているに違いなかった。恐ろしいことが起こりそうな予感がした。その時、ヴォルフガング・ワーグナーがやってきた。彼は書類の山をつかむと、机の上に投げ出して、 『ティゲラーさん、こんな紙屑は全部捨ててしまってください』 と、言った。それから、私を抱き締めて、『とてもよくやってくれました。みんなとても喜んでいます。これからもぜひともこの調子で続けてください。見事な舞台でした。声もすばらしかったです』と、褒めてくれた。議論して戦おうと身構えていたのだが・・・無用なことだったわけだ。
「 私の好きなシュトルツィング役を、バイロイトで歌うことができたということは、すばらしいことだった。この役は、ヴォルフガング・ワーグナーの演出で、私は、ライナー・ゴールドベルクとジークフリート・イエルザレムが歌った後を引き継いで、全く新しいものを作り上げようと試みた。すべての練習をやり遂げるためには、もちろん とても厳しい規律に従って仕事をしなければならなかったし、綿密な計画を立てる必要があった。結局、パルジファルに加えて、クプファーの新演出でのジークムントも歌うことになったので、この年のバイロイトの夏は実に挑戦的であった。 私は祝祭劇場でずいぶん長時間過ごしたので、それなら結局のところ劇場に泊まってもさしつかえないほどだった。多くの練習によって声に過大な要求をしたくなかったので、部分的には声を出さずに歌うふりだけをしようと決心した。これはイタリア・オペラのテノールたちはまったく普通にやっていることだが、ドイツ物ではめったにないことだった。しかし、朝から晩まで、しかも、別々の指揮者と演出家と共に非常に異なる三つの役を練習する場合、一日にせいぜい一つの役しか感情をこめて歌い切ることはできない。そこで、パルジファルとジークムントは交互にフル・ヴォイスで歌い、私にとって一番軽い役であるシュトルツィングはもっぱら歌うふりをするだけに決めた。しかし、マイスタージンガーの指揮者だったマエストロ・ショーンバットはこれが全く気に入らなかった。彼はそのことに注文をつけて、『ホフマンさん、あなたのシュトルツィングが心配です』と言った。私は『ご心配にはおよびません。この役は私にとても合っていますから、自然にやれます』と答えた。ショーンバットは『そうかもしれないが、とにかく一度聴かせてもらいたいものだ』と応じ、私は『初日か、もしかしたら、その前にゲネプロで全部お聴きになれます』と返事をした。彼は満足しなかったが、私は態度を変えなかった。結局のところこれは私の声の問題であって、私としては絶対に危険を冒したくなかった。三つの難しい大きな役で最高の業績をあげることができるように、自分の力をどのようにうまく配分するべきかは、結局、ひとり私しか判断できないことだった。彼は数回にわたって、せめて一度か二度ちゃんと感情を込めて歌うように説得しようとしたが、私は自分の考えを貫いた。 ゲネプロが近付いてきたころには、私は相当いらいらしていた。というのは、毎日6時間の練習をしていたにもかかわらず、役を演技面で再構築するためには、とにかく時間が足りなかったからだった。要するに 何かをなんとか考え出さなければならなかった。私は演出で予定されていたのと全く違うことをしようと決意し、実行した。私は、全く失礼な態度でマイスターたちの前に現れた反抗的で、強情で、生意気な若い騎士を演じた。声に関しては絶好調だった。だからマエストロ・ショーンバットはもうそのことを心配することはなかった。譜面台の前の彼がどんどんリラックスしていくのに気が付いて、とにかくすごくいい気分だった。靴屋の居間での夢物語は実にかっこよく、優勝の歌は、大喜びで歌った。舞台の同僚はみんな、拍手喝采どころか、足を踏みならしさえし、観客は熱狂した。翌日、ヴォルフガング・ワーグナーと会う約束になっていた。今回は大目玉を食らうぞ、何もかも計画と違うことをやったのだから、きっと首だな、なんだか具合の悪いことになったな、などと考えていた。会議室では、ワーグナーのアシスタントであるティゲラー氏が、山のように積み上げられた書類を持って、すでに待っていた。彼は、演出計画から逸脱したことについて、何もかも書き留めているに違いなかった。恐ろしいことが起こりそうな予感がした。その時、ヴォルフガング・ワーグナーがやってきた。彼は書類の山をつかむと、机の上に投げ出して、 『ティゲラーさん、こんな紙屑は全部捨ててしまってください』 と、言った。それから、私を抱き締めて、『とてもよくやってくれました。みんなとても喜んでいます。これからもぜひともこの調子で続けてください。見事な舞台でした。声もすばらしかったです』と、褒めてくれた。議論して戦おうと身構えていたのだが・・・無用なことだったわけだ。このようにして、ついにバイロイトにおける『私の』ワルター・フォン・シュトルツィングを作り上げることができた。ワーグナーのオペラを相互比較した場合、『マイスタージンガー』をやっているときが、一番快適な気分だったと言わざるをえない。何よりも、すばらしい喜びにあふれたハ長調の響きを楽しんだものだ。 シュトルツィング役はとても歌いやすい。音域は相当高くて、非常に難しい役と見なされているが、私にとって、全く問題なかった。 同僚たちがとても苦労している一方で、私はすばらしい音楽を歌うのを楽しんだ。『マイスタージンガー』の上演予定が立てられたころは、全然調子が悪くなくて、若くて、生意気で、自信満々のショトルツィングを演じるのがとても楽しかった。最後の音が消えて、幕が降りたとき、もう一度全幕通して歌えればいいのにと思うほど気分が高揚していた。
1984年、チューリッヒでのシュトルツィング・デビューの大成功以来、この役に関して、上手く歌うだけでなく、この若い騎士に、演劇的にも全く新しいニュアンスを与えることを常に追求してきた。 自信満々で、どこか高慢な若い貴族を表現したいと思った。彼は自分の生まれに対して強い自負心を抱いており、実際貴族社会で暮らしてきたのだが、しかし、エーファに対する愛から、下層階級である手工業者の親方社会に入り、自分の歌の芸術とそれと結びついているしきたりを喜んで放棄しようと思いながらも、挑発的な態度をとったり、エーファに露骨に色目をつかったりするのだ。一方、親方たちは非常に礼儀正しいので、このような不作法な振るまいは決してしない。この『傍若無人』こそがこの若者の本質なのだということを、私は表現したかった。そして、観客も評論家も私の解釈に賛成してくれた。
騎士、ワルター・フォン・シュトルツィングは、教養と社会階級という点において、手工業者をはるかに下の階級として見下していたし、その親方であるマイスターにも全く魅力を感じていなかった。そもそも彼の考えでは、彼がエーファに求婚した場合、彼女こそがそのことを光栄に思うべきなのだ。しかし、マイスターたちもまた健全な自負心を有しており、彼らにとって、マイスターであって、その上、マイスタージンガー・コンクールで勝利を得た者だけが、エーファの手を取るに値するということは決定事項であるから、そうは問屋がおろさないというわけだ。ま、仕方ないなと、ワルターは考えるのだが、そういうことなら、私がこの『マイスタージンガー』という芝居に参加するのは全く難しいなんてことはあり得ない。シュトルツィングは靴屋の徒弟、ダビットに、歌唱芸術について『少々』と、その規則を手ほどきしてもらいたいと頼んだ。それで、残りはもちろん自分でするつもりなのだ。他の徒弟たちの監督に加えて、歌手の基礎としきたりの紹介もダビッドの務めになった。ダビッドが『騎士さんは、この務めがどんなに大事かということを、何もおわかりでない』と言ったとき、シュトルツィングは徒弟のもったいぶった態度を嘲笑する。
次々とマイスターたちがやってくる。シュトルツィングは、反抗的かつ無礼な態度で彼らと顔をあわせた。彼はマイスターたちに紹介され、自由で恥ずかしくない立派な生まれかどうかなどという言語道断な質問をされて、さっそく剣に手をかけるのだった。なんという侮辱か。彼の知り合いで、彼の保証人を自認しているポーグナー親方が仲裁に乗り出して、彼を落ち着かせ、他のマイスターたちに、コンクールに参加してマイスタージンガーになりたいというシュトルツィングの希望を説明した。その結果、シュトルツィングは『どのマイスターのお弟子でしたか』という質問を甘受せざるをえなかった。彼は尊大な態度で、はるか昔の物語を歌った。
冬のさなかの静かな炉端で、
私の城も館も雪に包まれるころ
かつて、春がいかにやさしく笑い、
また、やがていかに新しく目覚めたか、
いくども私に教えてくれたのは、
先祖から伝わった一冊の古い書物。
ワルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデこそ
私の先生でした。
ハンス・ザックスは、『立派な先生だ』と感嘆し、ベックメッサーは、『だが、もうとっくに死んでいる。その人が、一体どうやって歌の規則を教えたのかね』と異論を唱えた。コートナーが『しかし、あなたはどこの学校で歌の技術を身につけることができたのですか』と質問を続けた。ワルターは反抗的にその先を歌った。
野原から雪や霜が消え、
夏の季節が戻ってくると、
かつて、長い冬の夜に
昔の書物が私に語った情景が、
緑あざやかな森に響き渡り、
その明るい響きを聞きながら、
森の鳥たちの楽園で、
私は歌も習ったのです。
すばらしい作品だった。ベックメッサーはすぐさま高飛車に『おやまあ。アトリやシジュウカラからあなたはマイスターの調べを習ったのですか。それならどうせその程度のものでしょう』と言った。
ワルターはさらに自信満々で歌った。それはマイスターたちをいらいらさせたが、それにもかかわらず、マイスターたちは、彼の歌に耳を傾けるのにやぶさかではなかった。 彼は規則を教えられ、彼の歌を披露するために、歌手の席に座るように求められた。またまた無理強いだ。彼は『あなたのためだ。愛しい人よ。やるぞ』とつぶやいて、不承不承にしろ、強制に屈っするしかなかった。
それから、教養と詩情にあふれた歌を歌ったが、ハンス・ザックスを例外として、マイスターたちはそれを理解しなかった。『騎士殿の歌も節回しもたしかに珍しいが、混乱しているとは、思えなかった』と、ザックスは言った。そして、マイスターたちが、歌の新しい流儀にひどく憤慨している間に、ワルターは誇り高く、軽蔑的な態度で席をたった。彼はもちろん怒っていたが、あきらめてはいなかった。蹄鉄工や鋳掛け屋ごとき者のために、エーファを断念するもりなどさらさらなかった。翌日の夜には、とにかく彼女と駆け落ちしようと思い巡らせていたが、ベックメッサーのセレナーデのせいで隣近所が目を覚したために、この計画は挫折した。しかし、彼にとって、コンクールの結果がどうであれ、エーファを連れて行くことは決定事項であった。彼は引き続き起こるあらゆる問題に、揺るぎない冷静さと優越感で、確信をもって取り組んだ。靴屋の居間での夢物語では、この優越感を表現に加味した。そのために、ベンチに『だらしなく座って』リラックスしていることを誇示した。そのあと、同じように気楽に、自信満々で、何度も、エーファにめくばせしようとしながら、お祭りの草地に行くのだった。こういう態度をとってこそ、優勝の歌を軽々と確信を持って歌うことができた。あちこちの大きなオペラハウスで、シュトルツィングを歌う機会がたくさんあったが、何度でも繰返し歌いたいと思っている。いつも楽しかった。私の解釈に対する観客の熱狂こそが私を納得させてくれたと言える」
その年の後半、ペーター・ホフマンには、たくさんのオペラの上演予定が残っていた。その中には、バルセロナでの『パルジファル』やウィーンでの『ワルキューレ』の深い感銘を与えた上演があった。彼の活動におけるこのようなハイライトが彼を元気づけ、たとえば
 『モニュメント』と題する新しいレコードの録音といった将来の新たな計画のための力を与えた。これは軽い編曲のクラシック・アルバムで、『リゴレット』の『女心の歌』からバッハとグノーの『アヴェ・マリア』にいたるまでの作品が含まれ、ロンドン・シンフォニー・オーケストラの伴奏で録音された。これは、1989年の春にはもう『ゴールド』レコードを達成した。
『モニュメント』と題する新しいレコードの録音といった将来の新たな計画のための力を与えた。これは軽い編曲のクラシック・アルバムで、『リゴレット』の『女心の歌』からバッハとグノーの『アヴェ・マリア』にいたるまでの作品が含まれ、ロンドン・シンフォニー・オーケストラの伴奏で録音された。これは、1989年の春にはもう『ゴールド』レコードを達成した。同年、ペーター・ホフマンは米国と日本での国外公演を行った。バイロイト音楽祭では、13年前に彼を世界に認めさせた役、ジークムントを再び歌った。クリスマスのCD『聖しこの夜』の録音にあたって、しばらくロンドンに滞在していたとき、はじめて、ミュージカル『オペラ座の怪人』を聴く機会を得たが、これは、1990年代のはじめに彼のキャリアに新たな転換を加えることになる体験だった。だが、この時期はオペラの舞台で活躍していて、1992年の春にはマンハイム国立劇場で『パルジファル』を歌った。秋には『魔弾の射手』のマックスとしてボンに出演することが予定されていたが、演奏旅行のためにキャンセルせざるをえなかった。1990年代はじめのレコード録音と公演に関しては、要するにポピュラー音楽とミュージカルが中心になっていたことは明らかだったにもかかわらず、ペーター・ホフマンはクラシック音楽に対してもそれまで同様に忠実だった。
「ウィーン国立歌劇場での数回にわたる『ワルキューレ』の公演のあと、1989年には全く特別な客演に参加させてもらえた。ベルリン・ドイツ・オペラのメンバーと共に、ドイツ連邦共和国存続40周年にちなんでワシントンのケネディ・センターに出演したのだ。そのあと引き続いて日本をまわるコンサート旅行に出発した。この演奏旅行はずっと前から予定されていて、東京の主催者によって物凄く詳細な計画が立てられていた。1年前にはもう、我々の感覚では、もしできるとしても、出演者到着のまさに直前になってはじめて明らかになるようなことに関していろいろな問い合わせがあった。空港まで私を迎えに行くリムジンの色や、ホテルの部屋に置くグランドピアノの種類や、コンサートの合間に私に提供されるはずの自由行動計画等々が公式に決定された。日本人は綿密でこれ以上はないほど完璧であるが、私が確実にひとりになれる時間をほしがっているなどとは夢にも思っていなかった。信じられないことだった。
日本人のメンタリティーは以前にすでに一度体験して知っていた。ソニーの創業者である盛田昭夫氏がバイロイト音楽祭でバイロイトに来たときだ。礼儀正しくて、あらゆることに対して好奇心旺盛で、精力的にバイロイトとその周辺を見てまわった。私の家では専門家として音楽の装置を鑑定し、自分は純粋な技術マニアなのだという話をしてくれた。たとえば、彼はスピード狂でもあるが、日本では猛スピードで飛ばすチャンスはほとんどないということだった。そういうことなら、私は彼にあるものを提供してもいいなと思った。それに、なにしろその名も何と言うか日本語だ。
というのは、私はがっしりとした大きなモーターバイク、ホンダの1200ccを所有していた。日本ではまさに手に入らないものだった。盛田氏は自分では運転したくないということで、私の後ろに乗って、最高瞬間時速220キロを楽しんだ。盛田氏は飛行機操縦免許も持っているというので、アクロバット飛行の世界選手権保持者で、私が飛行機操縦をならっていたマンフレート・シュテッセンロイターに紹介しようかと申し出たところ、とても喜んでくれた。シュテッセンロイターはきっとよろこんで盛田氏と一緒に宙返り飛行をしてくれるにちがいないと、私は太鼓判を押した。盛田氏は感激しながら、勇敢に飛行機に乗り込んだが、しかし、30分後、着陸したときには、膝がふるえて、吐き気を催しているようにみえた。盛田氏も、このときの話を後に彼の著書『メイド・イン・ジャパン』に書いている。
それはそうと、私はといえば、飛行機操縦免許を取得しないまま、練習をやめてしまった。マンフレート・シュテッセンロイターが飛行中の事故で死んだため、当然ながらひどいショックを受けて、その後も飛行機の操縦に取り組もうという気持ちがもはやなくなってしまったのだった。
 ロンドンのアビー・ロード・スタジオで、クリスマスのCD『聖しこの夜』を録音したが、このスタジオで録音するということは、それだけで、ひとつの事件だった。私はノスタルジックな気分になった。部屋には、ここでビートルズが演奏していたままの昔のバンドマシーンが今も展示してあり、『マジカル・ミステリー・ツアー』の録音で使用されたシンセサイザーの一種でその原形であるメロトロンも見ることができた。そして、ビートルズと一緒に仕事をしていた年配の録音技師が当時のことを話してくれた。クリスマス・アルバム『聖しこの夜』もロングセラーになった。このことに対して、聴衆に心から感謝している。
ロンドンのアビー・ロード・スタジオで、クリスマスのCD『聖しこの夜』を録音したが、このスタジオで録音するということは、それだけで、ひとつの事件だった。私はノスタルジックな気分になった。部屋には、ここでビートルズが演奏していたままの昔のバンドマシーンが今も展示してあり、『マジカル・ミステリー・ツアー』の録音で使用されたシンセサイザーの一種でその原形であるメロトロンも見ることができた。そして、ビートルズと一緒に仕事をしていた年配の録音技師が当時のことを話してくれた。クリスマス・アルバム『聖しこの夜』もロングセラーになった。このことに対して、聴衆に心から感謝している。ロンドンでは、まず先に、アンドリュー・ロイド・ウェッバーのミュージカル『オペラ座の怪人』を見た。プロデューサーのフリードリヒ・クルツが私に怪人役を勧めていたので、ハンブルクでドイツ語上演が予定されていることは知っていた。私はミュージカルを歌うつもりはなかったので、当然断っていた。私にとって、ミュージカルと言えば、ただただ盛大なショーであるダンスシーンに結びつくので、私にはまったく似合わないもののように思っていた。ところが、『オペラ座の怪人』を見て、すっかり感動してしまった。怪人役もこの音楽も、オペラを彷佛とさせるものだった。こういうものを歌うこともまあ考えられると思った。再度ドイツ語によるこの役をやってほしいという、芸術的にも、金銭的にも非常に魅力的な申し出があったので、それではということになった。ただし9か月間のみということで、契約にサインした。そのとたん、予想通りマスコミが金切り声をあげた。『ペーター・ホフマンはいったいどうしたというのだ。彼の声はこんどこそ完全にだめになったのか。オペラとロックのあとは、今度はミュージカルなどという低レベルに転落せざるを得ないということか』等々と、ものすごかった。私はこの年にはまだバイロイトで成果をあげており、他の複数のオペラハウスでも歌っていたのだが、そんなことはどうやら全く意味がないようだった。マスコミにとっては、ミュージカルをやることは、新たな『降格』でしかなかった。私がバイロイトを去ったことも、誇張されて、ヴォルフガング・ワーグナーはもはや私をバイロイトに望まない。なぜなら、私はもはや歌えないからであるなどと、書かれたが、事実ではなかった。ヴォルフガング・ワーグナーからの翌年の出演依頼は、すでに机の上にあった。私は変化を求めて努力する人間だった。13年にわたるバイロイトのあと、とにかく違う仕事に没頭したかった。ヴォルフガング・ワーグナーはこのことを理解してくれて、私たちは、互いに友情を損なうことなく、別の道をいくことにしたのだ。
さて、オペラ座の怪人は、パリ・オペラ座の地下に住み、その醜く歪んだ顔を仮面に隠しているのだが、バレリーナのクリスティーンに夢中になり、彼女を立派な歌手に育てる。だが、最後には敗者となっておわる。怪人役のこの最後に、非常に心をひかれた。それまでは、いつも舞台の上では英雄だったが、今度は新しい状況だった。毎日歌わなくてはならないというのも新しい経験だった。そもそもオペラでは、少なくともそんなに長い期間にわたっては、そういうことはなかった。
 このミュージカルのために、そこに集まって知り合った人たちとのチーム・ワークはとても楽しかった。とりわけ、クリスティーンを演じた相手役のアンナ・マリア・カウフマンとの仕事は快適だった。私たちは『オペラ座の怪人』のあとも一緒にコンサートをした。ノイエ・フローラ劇場建設反対のデモ騒ぎにひっきりなしに邪魔されて、苦労の多かった練習期間と上出来の初日のあと、私はおよそ300回の公演で怪人役を歌った。この間に、200万人以上の観客がこの舞台を見た。関連のCDは『ダブル・プラチナ』として表彰された。ついでに言えば、これはミュージカルの分野では比類のないことだった。更にこのミュージカルでRTLの『ゴールデン獅子賞』を受けた。
このミュージカルのために、そこに集まって知り合った人たちとのチーム・ワークはとても楽しかった。とりわけ、クリスティーンを演じた相手役のアンナ・マリア・カウフマンとの仕事は快適だった。私たちは『オペラ座の怪人』のあとも一緒にコンサートをした。ノイエ・フローラ劇場建設反対のデモ騒ぎにひっきりなしに邪魔されて、苦労の多かった練習期間と上出来の初日のあと、私はおよそ300回の公演で怪人役を歌った。この間に、200万人以上の観客がこの舞台を見た。関連のCDは『ダブル・プラチナ』として表彰された。ついでに言えば、これはミュージカルの分野では比類のないことだった。更にこのミュージカルでRTLの『ゴールデン獅子賞』を受けた。たくさんの公演が実現したのは、契約を半年間延長したからだ。だが、これで、もう十分だった。新たに取り組みたい別の計画がいくつもあった。結局、練習期間を含めて1年半、ハンブルクに滞在していた。経営上、私の決心はあまり歓迎されなかった。フリードリヒ・クルツは、この間にステッラに株式会社を売却してしまっており、新しい所有者は、契約によって私がこの役を降りたあともなお収益に関与するのは、全く気に入らないと主張した。残念なことに、私は自分の権利請求のためには、補償金の支払いに対する契約を破棄されたことを、告訴せざるを得なかった。このことはまたまたマスコミにとっては当然最高にすばらしいストーリーをでっちあげるチャンスだった。
 ハンブルク滞在中に、『ワイルド・アンド・ロンリー・ハート』と題する私にとってことさらに特筆すべき、美しく、どことなく憂愁にみちた歌を集めたアルバムが生まれた。情感あふれる歌詞は大勢の人々に、このレコードと私の離婚との関連性を思わせた。1990年の秋、私は妻のデビーと別れた。私たちの結婚解消は、マスコミにとって、7年前の結婚とほとんど同じくらい大きな事件だったが、もちろん今度は、はるかに否定的な観点から報道された。
ハンブルク滞在中に、『ワイルド・アンド・ロンリー・ハート』と題する私にとってことさらに特筆すべき、美しく、どことなく憂愁にみちた歌を集めたアルバムが生まれた。情感あふれる歌詞は大勢の人々に、このレコードと私の離婚との関連性を思わせた。1990年の秋、私は妻のデビーと別れた。私たちの結婚解消は、マスコミにとって、7年前の結婚とほとんど同じくらい大きな事件だったが、もちろん今度は、はるかに否定的な観点から報道された。『オペラ座の怪人』終了のすぐあとで長い間の夢をかなえるためにアメリカに飛んだ。
 ロサンゼルスのキャピトル・スタジオで、エルヴィス・プレスリーの歌を集めたCDを録音したのだ。これは『ゴールド』を獲得しただけでなく、チャートでは15位に届いた。あるジャーナリストは『オペラ歌手が今度はエルヴィスのまねまでもした』とヒステリックに叫んだ。彼が一度でもこのアルバムに耳を傾ける労をとったならば、模倣云々ではなく、演奏こそが重要なのだということにすぐに気がついただろう。この音楽は私にとってとても楽しかったので、また大演奏旅行を計画していた。その前の1992年2月には、マンハイム国立劇場との契約を果したのはもちろんだ。マンハイムではパルジファルだった。私は2年振りのオペラの仕事に以前にも増して熱心に取り組んだ。私の出演に対して あらゆる悲観的な予測が先行していたにもかかわらず、成功だったので、評論家は私の声がまだだめになっていないことに驚いた。」
ロサンゼルスのキャピトル・スタジオで、エルヴィス・プレスリーの歌を集めたCDを録音したのだ。これは『ゴールド』を獲得しただけでなく、チャートでは15位に届いた。あるジャーナリストは『オペラ歌手が今度はエルヴィスのまねまでもした』とヒステリックに叫んだ。彼が一度でもこのアルバムに耳を傾ける労をとったならば、模倣云々ではなく、演奏こそが重要なのだということにすぐに気がついただろう。この音楽は私にとってとても楽しかったので、また大演奏旅行を計画していた。その前の1992年2月には、マンハイム国立劇場との契約を果したのはもちろんだ。マンハイムではパルジファルだった。私は2年振りのオペラの仕事に以前にも増して熱心に取り組んだ。私の出演に対して あらゆる悲観的な予測が先行していたにもかかわらず、成功だったので、評論家は私の声がまだだめになっていないことに驚いた。」このことは、数年来飽きもせずに些細なミスを、ペーター・ホフマンはロックを歌って声をだめにしているという先入観を正当化するために利用している評論家の偏狭さをまたもや証明した。1980年代末以降のマスコミの論調を概観すれば、相変わらず、ペーター・ホフマンという現象が世間を怒らせていたのがよくわかる。ホフマンが娯楽音楽とクラシック音楽を区別する一般的な図式、そして、それと結びついている『高級な文化』対『大衆文化』という価値づけを拒絶したことが許せなかったのだ。ポピュラー音楽の分野におけるレコード発売とライブ演奏の成功、魅力的な外見、俳優としてのマスメディアへの出演などは、現代的なポップ・スターとしてのすべての基準を満たしていた。こういう点で、他のどのポップ・スターにも先んじていたのはもちろん、同時にすばらしいオペラ歌手だったことも事実である。彼の場合、オペラの勉強に挫折して、ポピュラー音楽に転向した歌手と違って、両分野を互いに侵害することなく、むしろ互いに関連を持たせたつつ、プロとして、二つの道を突き進んだ。ポップスの分野において自らのクラシックの背景を隠そうとして強いて声の『サイズ』を縮小することもなく、多くのファンにとって、ポップ・スターのオーラにはヘルデンテノールとしてのイメージが分かち難く結びついていることも気にしなかった。クラッシク音楽評論家の中の純粋主義者を怒らせたのは、彼らが言い立てる何らかの声に関する欠点などではなく、むしろ、自分の微妙な立場を気にかけるどころか楽しんでいた、彼の無頓着さのほうだったのではないだろうか。彼のオペラ歌手としての業績を批判した人は、もっぱら誤った思い込みによる『劣悪な』大衆文化に対する憤りだけに導かれていたことが極端に多く、彼らの目にはペーター・ホフマンこそが、その代表者として映っていた可能性があるのではないかという疑惑が当然生じる。もう一方の陣営の『狂信的な』評論家もやはり、ホフマンは、反逆的かつ非協調主義者的ロックミュージックの『純粋な教義』を信奉していないとして、彼を非難した。彼らに言わせれば、ホフマンは商業主義が生んだまがいものだった。このように、彼はどこにも居場所がなかった。そして、それにもかかわらずか、あるいは、まさにそれ故にか、成功したのだった。
1992年のポップス・ツアーにおいて、ペーター・ホフマンは、ミュージカルからロックミュージックにいたる全領域を、ポピュラー音楽の演奏家として自由に扱えるということを示す機会を持った。
「マンハイムの仕事は、短い幕間劇にすぎなかった。というのは、前に話したツアーが9月には始まる予定で、準備しなければならないことが山のようにあった。 私たちはすばらしいバンドを編成した。多分、今までのポップス・ツアーのなかで最高だった。プログラムは、第一部が、ポップ・ソング、『オペラ座の怪人』からの抜粋、バラードで、第二部が、エルヴィスだった。 バンドのメンバーは、歌もとてもうまかった。そこで、私たちはアンコール曲として、アカペラの歌を練習した。このコンサートは、びっくり仰天するような雰囲気だった。私のオペラ・ファンが大勢やってきていて、反応は抜群だった。ツアーのチケットはあっという間に完売したので、最小限の変更で、1993年の春には再演することに決めた。圧倒的な成功だった。ミュージシャンたちのプロ意識とハーモニーもまたこのコンサートに確かな貢献をした。彼らのうち二人はもう私たちのところにいないということがいまだに信じられない。ポール・サイモン、デビッド・ボーイ、それからマドンナなどと共演していて、とりわけすばらしいバスだった、私が大好きな歌手のブリッツは、このツアーのあとしばらくして心筋梗塞で亡くなった。私たちの音楽ディレクターでキーボード奏者兼歌手のグレン・モッロウは特にクリス・デ・ブルッフとの共演で、人気のあったスタジオ・ミュージシャンでありツアー・ミュージシャンだったが、残念なことに、白血病で亡くなった。
人気というものは両刃の剣だ。 一方ではファンから途方もなくたくさんの励ましの言葉を受け取り、クラシック音楽と娯楽音楽の両方の感激が交じりあうのに気が付くことができた。他方ではこの状況の陰の部分にも直面させられた。 ボンで、コンサートの後、ホテルに戻ったときのことだ。上階には暗証カードが必要なエレベーターでしか行けなかった。部屋に着いて、問題がないかチェックするために、いつものように弟が先に部屋に入ったのだが、戻ってきてこう言った。『兄さんのベットにだれか寝ている』たしかに、泥酔状態の『ご婦人』が、どうやって入ったものか、そこにいた。呼ばれてやってきたホテルの支配人は、このようなことが起こった理由を説明できなかったが、招かれざる客を即刻排除した。この女性は、シェーンロイトで、やはり泥酔して、ある晩垣根をよじ登って入り込んで、朝まで庭のベンチで寝ていたのと同一人物だった。 彼女はそのあと新聞記事になった頭のおかしい婦人の話は私と弟がでっちあげたのだと言って、私をゆすろうとした。こんなことはとにかく無視するしかない。
もう一人の熱狂的な女性ファンは毎年、4、5週間の夏休み中ずっと私の家の前で過ごしているようだった。私は家でゆっくり楽しみたかったが、彼女はそうやって相当多くの時間を全くだいなしにしてしまった。彼女は、 私が 外出するたびに、薮から飛び出したし、遠乗りに出かけるたびに、手を伸ばして手綱をつかもうとしたが、これは絶対に危険なことだった。それから、畑をこえて私を追いかけて走った。
夜、だれかが垣根をよじ登ったり、少なくともそれを試みたりすることは、もっと頻繁にあった。そこで、夕方には家に入れていた犬たちを、外につないでおいたら、それとほとんど同時に彼らはもう現れなくなった。もっと幸せなことに、投光照明設備を設置してからは、そういう騒ぎはおさまった。
いつだったか弟のフリッツが門の扉を開けたまま、芝刈機を使っていたら、数人のカメラを持った人々が敷地内に入ってきて、遠慮なくぱちぱちと写真を撮った。弟がその人たちに一体どういうつもりかと尋ねたところ、『どういうつもりって。あなたのほうこそ一体どういうつもりなんですか。見ての通り、ここで写真をとりたいんですよ』という答えが返ってきた。弟が立ち去るように要求すると、彼らはきわめて非友好的になったので、フリッツはこう言った。『もう門を閉めますから、どうぞここから出てください。それに、もうひとつすることがありますから。警察を呼ぶんですよ。あなたたちが、出て行かなかったら、そのときはね』彼らは悪態をついて、去っていった。
こういうことは、もちろん極端な場合で、ありがたいことに、たまにしか起らなかった。ほとんどのファンは、特に私生活に関しては、概して思いやりがあった。彼らはとてもすばらしい手紙を書いてくれたり、コンサートのあと花や小さなプレゼントを持ってきたてくれりする。ファンの存在はとにかく純粋な喜びである。ジャーナリストや評論家も同様だ。多くは公平かつ客観的で、専門知識がある。しかし、違うタイプも存在する。この人たちは、もしかしたら、ねたみからか、悪意からか、キャリアを積んだ歌手をぐうの音も出ないほど徹底的にたたく。要するに、こういう人たちは、ロック・コンサートの前にインタビューにやってきて、『ホフマンさん、私はジョー・コッカーだけが好きなんですよ』と、あいさつした、いつかの『ジャーナリスト』のようだ。 私は『それはすばらしい。私も好きです。ところで、あなたは一体何をしにいらっしゃったんですか』と答えた。すると、またもや『ジョー・コッカーが好きです』という言葉が戻ってきた。実際もう少しのところで我慢できなくなるところだった。こんな男をインタビューによこすとは、編集長は一体何を考えているのだろうと思った。それで、私はちょっと無愛想になって、『あなたのジョー・コッカーのために、大きな音をたてて、かみそりの刃を食べるつもりはありませんよ。私の声も駄目になりますからね。それで、何をお聞きになりたいんですか』と言ったところ、インタビューはあっという間に終わった。
こんな話もこのくらいで十分だろう。 いくつかのクラシックのコンサートやガラのあと、
 1993 年の秋に、『オペラ座の怪人』でクリスティーン役だったアンナ・マリア・カウフマンと、北ドイツ放送交響管弦楽団と共に、ミュージカルのレパートリーだけを集めた『ミュージカル・クラシック』ツアーに出かけた。プログラムの内容は、ウェスト・サイド・ストーリーから、南大平洋、キャンディード、更に言うまでもなくオペラ座の怪人までのミュージカルで、その中から、最高に美しい曲を歌った。 チケットは瞬く間に売り切れたので、このツアーも、翌年の春に続行することになった。そして、さらにビデオの形で記録が残された。」
1993 年の秋に、『オペラ座の怪人』でクリスティーン役だったアンナ・マリア・カウフマンと、北ドイツ放送交響管弦楽団と共に、ミュージカルのレパートリーだけを集めた『ミュージカル・クラシック』ツアーに出かけた。プログラムの内容は、ウェスト・サイド・ストーリーから、南大平洋、キャンディード、更に言うまでもなくオペラ座の怪人までのミュージカルで、その中から、最高に美しい曲を歌った。 チケットは瞬く間に売り切れたので、このツアーも、翌年の春に続行することになった。そして、さらにビデオの形で記録が残された。」
オペラ歌手でロック歌手-2 [2003年刊伝記]
オペラ歌手でロック歌手に、矛盾なし ・・・2
いまだかってないほど沢山のファンレターが来た。オペラを望むものもあれば、ポップスを求めるものもあった。『ロック・クラシック』に続くレコードに対する希望や、ドイツ語によるポピュラー音楽のレコードを期待するもの、同時にテレビ出演に関する問い合わせ等々、様々な内容だった。ジャーナリストたちは私に何故、オペラというオリンポス山の頂きから、ポップスという低地におりるのかと質問し、私は決して山の頂きから転落したとは感じていないし、同時に『オペラのテノールとロックシンガー』であることが矛盾しているとは思わないと、繰返し説明した。そうまでして多少の金を余分に稼ぎたいのかと非難する者もいた。こういう人には、私にとってこの音楽は楽しいことで、だれもこのような成功をもたらすことなど予想できなかったと、説明した。計画中のロックの演奏旅行に関しては、突然二つになった仕事は、厳密に区別するべきだという立場を堅持した。私としてはこれまで同様、絶対的に大きな情熱は、ポピュラー音楽ではなく、オペラに対して持っているのだから、オペラの舞台で、声に関しても、演技に関しても、今以上に、更に良い状態を示したいと望んでいた。私はオペラが今までと同様大好きだが、ロック・ミュージックは楽しい。私は演出家や指揮者に指示されることなく、創造的になれるし、歌いたいように歌うことができるし、思いのままにリズムに身を任せる喜びを味わうことができた。それに今はもうロックなしで済ませたくはない。クラシック音楽とポピュラー音楽の両方をこれからも続けていきたいなら、両者を厳格に区別するべきことは明白である。つまり、一定期間は、演奏旅行にしろレコード録音にしろ、オペラのような響きにならないように、前もって声をその音楽に合わせておかなければならないから、そのための準備期間も含めて、ポピュラー音楽だけをする。その後は再び切り替え期間だ。ここでは、オペラの舞台でベストを尽くすために、クラシックの歌唱に集中する。二種類の音楽を混ぜ合わせたいとは思わない。私はそのときどきの『二つの仕事』に、つまり、そのときにたずさわっている方にいつも完全に没頭している。『ロック・クラシック』のレコードのあとで、バイロイトでのパルジファルに対する批評がすばらしい結果になって、いままでよりもよいとさえ言われたとき、私にとって、それはいわば御墨付きであった。
しかし、それ以上に、頭を横に振ってあきれるしかないような状況もあった。例えば、ある評論家は、カラヤンとのレコード録音の『パルジファル』について、私の歌唱には声に関する問題がききとれるが、それは『ロックの叫び声』に起因することは疑う余地がないと書いた。もっともこの評論家は、この録音は確かに『ロック・クラシック』のあと、発売されたのだが、そのずっと前に録音されており、しかもその時期に私は、ロックミュージックのことを考えることさえもまったくなかったし、ましてや歌うなどはとんでもないことだったということに気がついていなかったようだ。」
「クラシック」関係者からはペーター・ホフマンのダブルキャリアに対する批判は全くきかれなかった。1983年にバイロイトで指揮したジェームズ・レヴァインは、ポップスを歌ったパルジファルの声に関する成長について確信に満ちた意見を述べた。
「ペーターがロックンロールを歌うことに関して言えば、彼の声楽的テクニックはすでに成熟しているので、声が損なわれるということはまずありえないと思う。疲れたら、マイクを使って歌えるし、拒否することもできる。どのように成長しているのかについては、もちろん確かなことはわからない。しかし、目下のところペーターはどこから見ても好ましい状況にあると断言できる。声は成長する。芸術家としての能力も知性も成長する。こういうことがとにかくいつも力を発揮する。彼が何を歌うかはどうでもよいことだ。」
テレビは「ワーグナーを取り囲むロック」という特徴的なタイトルで「複線」歌手、ペーター・ホフマンのポートレートを撮った。オペラ活動の様子や、スタジオでのポップスの録音風景、「ロック・テノール」の私生活などがその内容だった。ロック・アルバムと対照的な企画としては、
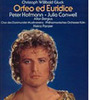 ハインツ・パンツァー指揮、ケルン・フィルハーモニー・オーケストラのグルック作曲『オルフェオとエウリディーチェ』のレコード録音に、ジュリア・コーンウェルと共に参加した。これもまたホフマンの多様性を示している。このオペラでは、それまではあまり望ましくないとされていた豊かな感情表現を、もちろん声によってのみだが、おこなっている。ペーター・ホフマンは、いつも自分自身を概して批判的に扱うのだが、この録音に関しては、自分自身、とても満足しているということだ。彼としてはとびきりの大成功だと考えているそうだ。
ハインツ・パンツァー指揮、ケルン・フィルハーモニー・オーケストラのグルック作曲『オルフェオとエウリディーチェ』のレコード録音に、ジュリア・コーンウェルと共に参加した。これもまたホフマンの多様性を示している。このオペラでは、それまではあまり望ましくないとされていた豊かな感情表現を、もちろん声によってのみだが、おこなっている。ペーター・ホフマンは、いつも自分自身を概して批判的に扱うのだが、この録音に関しては、自分自身、とても満足しているということだ。彼としてはとびきりの大成功だと考えているそうだ。『オーディオ』誌が1984年号で、クラシックの録音を評価して、その結果、演奏のランク付けを行っている。ペーター・ホフマンは、31.6%の優秀な声楽ソリスト・リストの第一位にあがっている。このような評価は心理的葛藤をもたらすことだ。確かに自尊心をくすぐり心地よく響くが、一方、永久に最高業績をあげる義務を課せられることでもある。
1984年2月10日は、ベルリン・ドイツ・オペラでの、ジャン・ピエール・ポネルの印象的な演出による『フィデリオ』の初日だった。指揮はダニエル・バレンボイムで、レオノーレはカタリーナ・リゲンツァ、ペーター・ホフマンはフロレスタン役を歌った。この公演のあとのように、評論家が全員一致で肯定的な結果を出すことは珍しい。ペーター・ホフマンは、不可能なことを成し遂げたに等しいほどの上出来だった。透明感のある表現力に富んだ声で歌いながら、そして、それにもかかわらず、地下牢に一人寂しく、飢えて、死を間近にした人が、横たわっていることを、納得させるに足るものだった。とても濃い化粧をしていたので、よく見ても最初は彼だとわからなかったほどだ。この『フィデリオ』については、オペラの初日などいつもは言及する価値はないと考えている大衆紙でさえ、熱狂的に書きたてた。続いて、ザルツブルグ音楽祭におけるヘルベルト・フォン・カラヤン指揮による『ローエングリン』が、同様の肯定的反響を得た。
 その後、ペーター・ホフマンの胸の中で、もう一方の「心」が再びふくらんでいって、二番目のポップスのレコードである「ペーター・ホフマン2」を録音したが、その中の「アイボリー・マン」は、とりわけ彼自身のアイデアに基づいたミニ・ミュージカルとでもいったものであった。その後、ハンブルクからウィーンまで、20以上の都市を巡る、最初のロック・ツアー「バンドとオーケストラによるペーター・ホフマン 1984年」がスタートした。ライブの伴奏は、フリッツ・ホフマンが、ヴェルツブルクのコンサートを聴いてから、クリス・デ・ブルクのバンドと契約を結んだ。ペーター・ホフマンは、このツアーのプログラムの冒頭で、彼のオペラとポップスという二つの世界間の往復が引き起こすいらだちに対する回答を述べている。
その後、ペーター・ホフマンの胸の中で、もう一方の「心」が再びふくらんでいって、二番目のポップスのレコードである「ペーター・ホフマン2」を録音したが、その中の「アイボリー・マン」は、とりわけ彼自身のアイデアに基づいたミニ・ミュージカルとでもいったものであった。その後、ハンブルクからウィーンまで、20以上の都市を巡る、最初のロック・ツアー「バンドとオーケストラによるペーター・ホフマン 1984年」がスタートした。ライブの伴奏は、フリッツ・ホフマンが、ヴェルツブルクのコンサートを聴いてから、クリス・デ・ブルクのバンドと契約を結んだ。ペーター・ホフマンは、このツアーのプログラムの冒頭で、彼のオペラとポップスという二つの世界間の往復が引き起こすいらだちに対する回答を述べている。「オペラ歌手としての私を見たい人は、オペラに行くべきである。全く異なった傾向をもつ音楽のどちらを選ぶかは、気分次第というのは、わかりきったことだと思う。私も、年がら年中ベートーベンを聴きたい気分でもないのと同様、時にはローリングストーンズのビートは我慢できないと感じることもある。みなさんが私の音楽に合った気分でコンサートにきてくださることを願っている。いずれにしても、音楽のない生活は我慢できないのではないだろうか」
それでも、明らかに別のものを期待していたらしい客もいた。彼らは、ポスターに書いてあった「バンドと・・」という言葉を見落としたにちがいないのだが、舞台上からは見落としようがないほど、その場の雰囲気から浮いていた。
「私は一列目の席に宝石のアクセサリーをつけたイブニングドレス姿の客やタキシードを着た客が数人いるのに気がついた。どうみてもポップスのコンサートを期待しているようには見えなかった。はじめの『ツァラストウストラはかく語りき』の響きが鳴りやんで、私が『朝日のあたる家』を歌いはじめると、彼らがショックを受けた目つきになって、いきなり立ち上がり、ホールを去っていくのが目に入った。舞台上の私たちにとっては、非常に意欲をかきたてられる状況だった。私はその出来事をユーモアで受け止めようと、今からは全てのドアは外側から鍵をかけさせてもらうことにするので、ひょっとしてまだ立ち去りたい人がいないかどうか質問した。けれども、もう誰も出ていこうとはしなかったし、この晩だけでなく、そのあともずっと、私も聴衆もほんとうに楽しかった。15万人以上の観客がこのコンサートを訪れ、大いに楽しんだ。ドイツ第二テレビ放送(ZDF)がコンサートのひとつを録画して6月に放送することになった。そうこうするうちにアルバム『ペーター・ホフマン2』が、チャートで第6位にのり、ゴールドになった。
ツアーの成功で、引き続きこの道を進むという点において、私は意を強くした。どのみち私のポピュラー音楽はすでにある意味で一人立ちしていて、実際のところもはや止められない状況だった。私のところにもレコード会社にも、新しい録音についての問い合わせが山のようだったが、私たちはそういう希望に早急に応じることはとてもできなかった。それにしても、ジャーナリストたちは、相変わらず私の声はポピュラー音楽を歌うには、やはり大きすぎるのに、何故そういうことをするのかと、しつこく質問するのをやめなかった。それに対して、私はそのようには考えていないのだと答えた。いずれにせよロックやポピュラー音楽では、マイクを使うのだから、声の大きさは絶対条件ではない。声が小さければ、技術者が大きくするし、声が大きければ、これも技術者が適正に音量を調節するのだ。適正な調節を遂行することだけが重要なのだ。それとは逆に、オペラの舞台では、せっかくの最高の声もほとんど聞こえないようでは、役に立たないのだから、まず第一に声の美しさと並んで、個性的な声の魅力を引出すためには、声の大きさが重要なのだ。クラシックの分野には、すばらしく美しいが、舞台で歌うには小さいという声の歌手も多いが、その場合、レコードで歌ったり、映画で演奏したりしている。私はオペラが好きだが、この分野では格別創造的なことはできないという感じがしている。もちろん演技や歌唱において十分に個性を発揮することはできるが、私の前に、すでに何百人もの人が歌ってきたことを、指揮者や演出家が望むように歌わなければならない。ポップスの舞台ならすべて私が望むように形作られるのがすばらしい。バンドが何をどう演奏するか、舞台装置、照明、私の身振り等々、全部、自分で決める。そして私が好きなアルバムを収録する場合、その中で、例えば、『アイボリー・マン』でのように、いくつかのアイデアを実現することもできる。そして、ツアーで成功すれば、再びオペラの仕事に、一生懸命、情熱的に取り組みたいという気持ちになる。
もうひとつ頻繁に質問されたのは、声のために不安を感じたことはないのかということである。その点に関してちょっと振り返ってみると、およそ歌手ならだれでも声に関して不安を抱えているものだが、私はそのことを表に出さなかった。とりわけ自分にそういう不安をあえて吹き込まないようにしていた。クラシック音楽か、ポピュラー音楽かは関係ない。『トリスタン』はいつも声にとっては難儀な役だが、それに対して、マイクを使って歌われ、自分の判断で声の音量を絞ることができるポピュラー音楽は害があるなど、全くあり得ないことだ。しかし、どちらの場合も気管支炎にはなりうる。不安があるから、そう思い込むのだと思う。リューベックで新人としてタミーノを歌わないわけにはいかなかったときは、一週間病気だったが、かまわずやり遂げた。こういうわけで、さあ、もう余分なことは考えず、舞台に立って、とにかく歌うのだと自分自身に言い聞かせたら、うまくいった。まさに心理的なものだ。当然のことだが、ウィルス性の気管支炎にかかって、声帯が炎症をおこしたら、どんな歌手でも、舞台に立つことは、ほとんど無理か、絶対不可能だと思う。出演が『ほとんど』不可能な状態の場合は、歌うべきか否かの決定は大問題だ。歌ったら、必然的にいつものようには歌えなくて、観客を大いにがっかりさせたうえ、評論家は容赦のない攻撃に出る。キャンセルした場合も、事態は実際まったく変わらない。私はこういう状況で、たびたび歌って、何と言っても自分が望むように歌えなくて、あとになって後悔した。声帯はその負担でますます炎症がひどくなっているというわけで、さらにひどく傷ついた。ショルティ指揮による『フィデリオ』の録音も、数回の上演も、気管支炎じゃなかったら、もっとよくできていただろう。加えて、気管支炎が慢性化して、決断が鈍ることもある。こういうことはけっこうよくある。今までで、一番大変だったのは、ワーグナーの演奏旅行を病気のために全部キャンセルして、しばらく入院しなければならなかったときだ。会場は借りてあって、全席完売で、オーケストラとも契約済み、とんでもない事態だった。歌手もまたまさしくただの人間だということだ。」
追加コンサート付きのロック・ツアーが成功のうちに終了したあと、ペーター・ホフマンは再びオペラの仕事に戻った。彼のカレンダーは予定がいっぱいだった。
 秋には、ベルリン・ドイツ・オペラで、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ワルキューレ』が予定されていたし、続いて12月にはチューリッヒ歌劇場の再開で、『ニュールンベルクのマイスタージンガー』のシュトルツィング役としてデビューすることになっていた。12月2日のプレミエの直前に、ペーター・ホフマンは、出演が考えられないほどひどく足を捻挫してしまった。ルネ・コロが代役を務めたが、その後、やっと12月23日に、彼にとって一番好きな役になったシュトルツィング役を演じることができた。
秋には、ベルリン・ドイツ・オペラで、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ワルキューレ』が予定されていたし、続いて12月にはチューリッヒ歌劇場の再開で、『ニュールンベルクのマイスタージンガー』のシュトルツィング役としてデビューすることになっていた。12月2日のプレミエの直前に、ペーター・ホフマンは、出演が考えられないほどひどく足を捻挫してしまった。ルネ・コロが代役を務めたが、その後、やっと12月23日に、彼にとって一番好きな役になったシュトルツィング役を演じることができた。1985年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場にローエングリンで出演した。相手役のエルザはエヴァ・マルトンだった。公演はビデオ録画されたが、残念なことに、アメリカでしか発売されなかった。
 ズービン・メータの指揮で、エヴァ・マルトン、マルティ・タルヴェラ、ニューヨーク・フィルハーモニー・オーケストラと共に『ワルキューレ』の第一幕のCD録音もした。続いて夏には、バイロイトでのジェームズ・レヴァイン指揮による1982年の『パルジファル』の再演があったが、今回はこのオペラもレコードとCDに収録されることになった。サイモン・エステスが感銘深いアンフォルタスを歌い、マッティ・サルミネンがティトウレル、ほんとうに何度もペーター・ホフマンのパルジファルのグレネマンツを歌ったおなじみのハンス・ゾーティンが今回も同じ役を歌い、ワルトラウト・マイアーが刺激的なクンドリを演じた。
ズービン・メータの指揮で、エヴァ・マルトン、マルティ・タルヴェラ、ニューヨーク・フィルハーモニー・オーケストラと共に『ワルキューレ』の第一幕のCD録音もした。続いて夏には、バイロイトでのジェームズ・レヴァイン指揮による1982年の『パルジファル』の再演があったが、今回はこのオペラもレコードとCDに収録されることになった。サイモン・エステスが感銘深いアンフォルタスを歌い、マッティ・サルミネンがティトウレル、ほんとうに何度もペーター・ホフマンのパルジファルのグレネマンツを歌ったおなじみのハンス・ゾーティンが今回も同じ役を歌い、ワルトラウト・マイアーが刺激的なクンドリを演じた。ポップスの分野では、今度はドイツ語の新曲による新しいアルバムが「ペーター・ホフマン2」の後に続いた。
 「ファンレターには、ドイツ語の歌によるポピュラー・アルバムを希望する意見が、沢山あった。良い考えだと思った。なんといっても私はドイツ人なのだから、自分の母国語で何かしてはいけないという法はないわけだ。良いチームを組んで、情感にあふれた歌を作り、『我らの時代 UNSRE ZEIT』を録音した」
「ファンレターには、ドイツ語の歌によるポピュラー・アルバムを希望する意見が、沢山あった。良い考えだと思った。なんといっても私はドイツ人なのだから、自分の母国語で何かしてはいけないという法はないわけだ。良いチームを組んで、情感にあふれた歌を作り、『我らの時代 UNSRE ZEIT』を録音した」ドイツ語の歌詞はだれもが好むというものではなかったにもかかわらず、『我らの時代』は成功で、すぐにヒット・チャートにのり、間もなく「ゴールド」を獲得した。ペーター・ホフマンは、当時フランク・エルストナーが司会していた番組「それに賭けろ」をはじめ、多くのテレビ番組で、このアルバムを紹介することができた。ちなみに、賭けに負けたら、その結果、賭け親は結婚式で歌わなければならないことになっていた。彼は教会でのある結婚式でヘンデルの「ラルゴ」を歌って、この賭けの責任を果した。『我らの時代』に最初の二つのロック・アルバムを合わせたものが、ドイツ、オーストリアを巡る1986年の2月と3月のツアーの土台だった。数曲が爆発的にヒットしたことで、気分はますます盛り上がって、この企画は完璧になった。ウィーンでのコンサートはビデオ撮りされ、更にニ枚組のCDに録音された。
5月には、ヴィスバーデンの五月祭でジークムントを歌った。その後、ニューヨークでローエングリン、それから、ジャニーヌ・アルトマイヤーのイゾルデ、ダニエル・バレンボイム指揮の『トリスタンとイゾルデ』の練習のために、バイロイトへ行った。これは、ジャン・ピエール・ポネルによる1981年の演出に手を入れ、より洗練されての再演というものだった。
「プレミエ以前にすでにいくつかの混乱があった。爆破予告があったため祝祭劇場の警備が強化されていたし、私の事務所には、ロックを歌ったという理由で、私に容赦ないブーイングを浴びせるという脅迫があった。陰鬱な『トリスタン』をやるには、全然ふさわしいとは言えないにぎやかな状況だった。
ポネルの演出にはまえまえからとても興味があった。評論家は、ポネルの演出は確かに『イメージに耽溺しすぎている』し、心理的洞察より視覚的表現のほうを、演劇的な感覚より美しいイメージを追求していると、非難していたが、しかし、トリスタンの死に際して、イゾルデの幻覚だけが現れるというのは、それでもワーグナーの意図に近いものは保たれており、舞台上でもとりあえず表現されていた。私としてはそれなりに魅力的な演出だった。あとで公演の写真を見たとき、想像した通り、トリスタンの放心状態、高熱による幻覚が同じようにはっきりと伝わってきた。私としては大きな満足感を味わった上演だった」
ペーター・ホフマンは声の調子も良かった。ミュンヘンの新聞は次のように書いた。
「ペーター・ホフマンは、あらゆる悲観的な予測にもかかわらず、上演の夜を粉砕しかねないほどに懸念された役を、驚嘆に値する調子の良さで乗り切った。彼は実に美しく叙情的な方向を示しており、三幕における安定した声には、唖然とさせられた」
それでも、観客の中の、あの一派はペーター・ホフマンがポップスをやるという「逸脱行為」を断念しようとしないことで、気分を害していることを表明した。
「二、三人がブーイングをした。それよりもたくさんの、足を踏みならし『ブラボー』と叫んでの拍手喝采がそれに応じたが、例のグループは、脅迫をやめなかった。ロック・ミュージックが好きじゃない人は、それを聴く必要はないのだが、脅しによって、私に何か強制しようという試みは、どう見積もっても私に対しては逆効果でしかないと思う。『ブーイング』がすばらしい間奏曲になることもありうるのだが、あの時はそうは思えなかった。それは、1987年に、再びバイロイトでトリスタン役を歌ったときのことだが、初日には、胃の具合が相当悪かった。しかし、身体をコントロールすることはスポーツマン時代にすでに重要な事だったし、歌手にとっても不可欠である。私は自分の職業を実際このようにとらえていた。だから、完全に気分の悪い状態だったにもかかわらずトリスタン役をやり通した。とは言え、なかなか良い出来だったと思う。しかし、最後の音が消えたときはさすがにもう我慢できず、何も考えずに舞台から駆け去ったので、終わりのカーテンコールには出なかった。ヴォルフガング・ワーグナーが幕の前に出て、私に代わって観客に謝罪してくれた結果、私には大きな拍手がおくられた。ところが、おそらくその説明を信じなかったのだろうが、ブーイングも多少あった。相当に奇妙なことだった。
1986年の初日に引き続いて行われたパーティーで、リヒャルト・フォン・ヴァイゼッカーとハンス・ディートリッヒ・ゲンシャーによる興味深い対談があった。ところで、私の隣はフランツ・ジョセフ・シュトラウスだった。『バイエルン人』は大昔から広い視野も持ち、多趣味だったのはまちがいないけれども、そこにはワーグナーの音楽は含まれていなかった。シュトラウス氏は、まずは、その点について、『ホフマンさん、言いにくいのですが、私はオペラのことには全くうとくて、そもそもオペラは全然わからないんですよ』と謝った。そこで、私が、別の話題もたくさんありますからご心配なくと言ったら、緊張がほぐれた。この時から、彼は、公認といった感じで、嫌いな会話に巻込まれないように、あらゆる機会を利用して、私の隣に座った」
一部のマスコミは、言うまでもなく1987年のペーター・ホフマンの初日の不運についてセンセーショナルに報道した。ロックを歌った結果、もうすぐ声がだめになるだろうというせっかちな予測がなされた。彼は何度もこういう主張に基づいたインタビューに直面させられた。かなり挑発的なやり方で行われることも全然めずらしいことではなかった。次の公演で彼が絶好調を示したことには、ゴシップ記者たちはまったく興味を示さなかった。
 ペーター・ホフマンはポピュラー音楽をやめて、彼のそういうイメージを全面的に払拭するつもりがないことを、『ロック・クラシック2』を出すことによって、表明した。このことは、クラシック・ファンの中の「原理主義者」を激怒させた。このCDは1986年の秋に録音され、1987年春に発売された。これは最初の『ロック・クラシック』と直接関連しており、すばらしいロックとポップスの歌が含まれていた。例えば、ジョン・マイルズの『音楽、これこそ初恋の人』とか、バリー・マニロウの『マンディ』などと、そのほかにあまり知られていない歌が数曲というところだが、最初の『ロック・クラシック』に入っている曲と同様に美しい。なかでもプロコル・ハールムの雄大なロック・バラード『しょっぱい犬』は、その編曲とペーター・ホフマンによる感動的な歌唱に関して言えば、珠玉のすばらしさである。伴奏はロンドン・シンフォニー・オーケストラと一流のスタジオミュージシャンから成るロックバンドが引き受けている。3月には「クラシック音楽」に向い、ハンブルクで『パルジファル』、その後、7月にはヴェネチアで『ローエングリン』だった。8月には、すでに述べたように、バイロイト音楽祭での『トリスタン』が加わった。
ペーター・ホフマンはポピュラー音楽をやめて、彼のそういうイメージを全面的に払拭するつもりがないことを、『ロック・クラシック2』を出すことによって、表明した。このことは、クラシック・ファンの中の「原理主義者」を激怒させた。このCDは1986年の秋に録音され、1987年春に発売された。これは最初の『ロック・クラシック』と直接関連しており、すばらしいロックとポップスの歌が含まれていた。例えば、ジョン・マイルズの『音楽、これこそ初恋の人』とか、バリー・マニロウの『マンディ』などと、そのほかにあまり知られていない歌が数曲というところだが、最初の『ロック・クラシック』に入っている曲と同様に美しい。なかでもプロコル・ハールムの雄大なロック・バラード『しょっぱい犬』は、その編曲とペーター・ホフマンによる感動的な歌唱に関して言えば、珠玉のすばらしさである。伴奏はロンドン・シンフォニー・オーケストラと一流のスタジオミュージシャンから成るロックバンドが引き受けている。3月には「クラシック音楽」に向い、ハンブルクで『パルジファル』、その後、7月にはヴェネチアで『ローエングリン』だった。8月には、すでに述べたように、バイロイト音楽祭での『トリスタン』が加わった。合間には、いくつかの慈善ガラ・コンサートがあった。その一部はテレビ録画された。ミュンヘンでのエイズ・ガラ・コンサートとバイエルン国立歌劇場でのマリアンネ・シュトラウス財団のための慈善ガラ・コンサートは特筆に値する。大勢の有名なポピュラー歌手と共に「援助の手」プロジェクトにも出演した。「ようこそ、ミュンヘンへ、映像による夢の都市レビュー」と題する記念番組では、ルートヴィッヒ二世の写真が挿入されたあと、『ローエングリン』からグラール物語を歌った。
秋には50回を超えるコンサートから成る三度目のロック・ツアーが準備されていた。今回は東ドイツの東ベルリン、ドレスデン、それから、かつてのケムニッツ、そして現在はまた再びケムニッツに戻った、当時のカール・マルクス・シュタットで、6回の公演を行う予定だった。
「東ドイツでのポピュラー・コンサートは、西ドイツの芸術家としては、そのときまでは、ペーター・マッファイとウード・リンデンベルクしか許可されたことはなかった。まさに微に入り細に入り、一から十まで、事こまかな計画がたてられた。まず東ベルリンの東ドイツ芸術家エージェントが作成した申請書を用意しなくてはならなかった。その際、完全な歌詞を添えて、演奏予定の歌をいちいち全部提出しなくてはならなかった。報酬は3分の2は東ドイツ・マルクで、3分の1は西ドイツ・マルクで支払われるのだが、いったい東の金をどうしろというのだろう。アメリカ人のバンドと関係者にそんなことは言えなかった。どこにもそんな金を使えるところはないのだから、西の金で支払うしかない。私たちはすばらしい妥協案を見つけた。私たちは、14日間、ズールで無料で自由に使える練習用のホールとホテルの部屋を提供されていた。そこで、私たちは無料の練習コンサートを追加した。この14日間は注目に値するものになった。東ドイツの組織力と世話焼き振りは二度と体験できないほど比類のないものだった。理由は簡単だ。ここには金はなかったが、雇われるべき人間は十分すぎるほどいるのだった。技術者、例えば、電気技師が一人必要になった時には、すぐにいつでも使える人が5人も待機していたし、椅子が数脚欲しかった時には、すぐに会社をあげて手伝いにきてくれた。ホールは昼夜を問わず保安部隊によって監視されていて、保安部隊がそこにいることが可能な限り、どんな希望も彼らの目に留まるのだった。要するに、『西側の人間』に良い印象を与えたいわけだ。ただし、東ドイツの基準から逸脱することを決定せざるをえない場合は、厄介なことになった。そうなると階級制度の序列に従って、次々と上の人にお伺いを立てることになる。
ある日、長い練習の日々が続いたあと、ホテルの中にあるディスコに行こうとしたとき、入口にネクタイ、スーツ姿で立っていたドア係りが私たちの入場を拒否した。ジーンズにスニーカー、おまけにネクタイもしていない私たちは、全くとんでもないことだというわけで、中へ入ることを許されなかった。延々と、無益な議論をしたあげく、結局私たちはほかの服の持ち合わせがないのだから仕方がないということで、最終的には、ホテルの女性支配人が姿を現して、入場を許可するように配慮してくれた。この瞬間から、ドア係りまでがまるで人が変わったようで、意見の相違など何もなかったみたいに、私たちに対して好意的で丁寧な態度をとった。中では、もとは白かったのだろうが、変色して黄ばんだ背広を着たバンドが行儀のよい娯楽音楽を演奏していた。私たちは彼らに、一曲演奏したいので、楽器を貸してほしいと頼んだ。『一曲ですか。アメリカ人に楽器を貸すのですか』と、まずは不信感丸出しだったが、しだいにそれは消えて、何が演奏されるのか興味津々になった。まさに思うつぼだった。ドラマーだけは、高価なバチが折れたときには、相当なショックを受けたが、私たちのドラマーのジェフはいつも荷物を全部持ち歩いていたので、速攻で気前良く変わりの品を調達できた。私たちはディスコに人々を招待して、東の金を気楽につかってしまった。それ以外にその金でするべきことはなかった。もちろんバンドのメンバーのために楽器をいくつか買ったが、それもまた私たちのためではなかった。マイセンの陶磁器も、ヨットやトラバントの車も欲しくなかった。むしろトラクターのほうが頭に浮かんだ。それなら、ひょっとしたら、オーバープファルツの近所の農家のお土産にしたら、喜んでくれるかもしれないと思ったのだが、巨大な怪物のようなものを提供してもらうのは、私たちの意に完全に反していた。
東ベルリンのフリードリヒ宮殿で開催された最初のコンサートはとても奇妙な雰囲気だった。最前列には、無感動で厳格な体制派の党員が無表情で座っていた。その後ろで熱狂した観客が拍手喝采していた。私は舞台から歯に衣を着せず、『本当にいったい何を怒っていらっしゃるのですか。私が何か間違ったことをしましたか』と前の席の人々に向って大声で言った。やはり反応はなかった。彼らは自由で気楽な雰囲気はとにかく好きじゃなかったのだ。ドレスデンでもやはり同じようだった。ドレスデンは『外が見えない谷』と呼ばれていた。というのは、ドレスデンでは、ものすごく高いアンテナを建てなければ西側のテレビを受信することができなかったからだ。私たちのコンサートの直前に、ヘルムート・コールとエーリッヒ・ホーネッカーの会談が行われた。そこで、あいさつの後、いい機会だと思ったので、『私たちの首相であるヘルムートとエーリッヒの直接会談があったわけですが、これによってそのうちに何らかの良い結果がもたらされることを希望しています。ここ、『外が見えない谷』で、私が皆さんに望むことは、いつかここにも光が差し込むこと、そして、もうひとつ、巨大なアンテナが建設されることです』と言った。メッセージは観客に届いた。突然想像できないほどの歓声がわき起こったが、前の方の数列に陣取った人々だけは、あいかわらず妙な具合に顔をしかめ、口をへの字に結んでいた。コンサートの終わりには、いつもバーンスタイン作曲の『サムウェア』を歌ったが、この日の公演ではいつもとは違う意味があった。この『私たちの場所がある。どこかに私たちのための場所がある』という歌詞は、状況にぴったりだった。私はほとんど自分自身に向かって心を込めて歌った。この公演は、感情が爆発し、ものすごく気分が高揚した。
一日後、かつての『カール・マルクス・シュタット』で、私は『こんにちは。ケムニッツの皆さん』と観客にあいさつした。この時はほんとにすごかった。最前列を氷のように冷たい沈黙が支配したが、その後ろの盛り上がりかたはまさに爆発的で、この雰囲気はどのコンサートでも変わらなかった。東ドイツの人々にとって、このようなコンサートは珍しかったので、あきらかに楽しんでくれているのがはっきりとわかった。このツアーには、ギュンター・エマーリッヒの番組『ショーコラーデ』をはじめ、様々なテレビ出演が加わった。
このマンモス・ツアーでは、『従来の』ドイツ連邦州はもちろん、そのほかに、オーストリア、スイス、ルクセンブルグもまわった。私たちはいたるところで熱狂的な観客に出会った。とにかく楽しかった。
チケットは完売、すばらしい観客と山のようなファンレターと共に、私におおきな喜びをたくさんもたらしてくれた三ヶ月にわたるポップス・ツアーのあと、私はうれしい気持ちで再びオペラの仕事に戻った。 それは1988年の春、ボンの『マイスタージンガー』で始まった。そのあと、ニューヨークで『ジークフリート』を初めて歌う予定だったが、ひどい気管支炎のため、残念ながらキャンセルせざるをえなかった。このことは当然マスコミのかっこうのえじきになった。そこには、様々な言い方だったが、要するに『今度こそ、くだらないロックなどを歌ったせいで、声が完全にだめになってしまったのだ』と、書かれていた。それならば『マイスタージンガー』も歌えなかったはずだということは、議論にならなかった。今度もまた、記事ねたを手に入れたということが肝心だったわけだ。」
ペーター・ホフマンはマスコミのセンセーショナルな扱いに冷静さを失わず、いつものように最後には、たとえば、この夏にはバイロイトで、ジークムントとパルジファルに加えて、バイロイトでは初役である『マイスタージンガー』のワルター・フォン・シュトルツィングの三つの役を歌ったのだが、この時も批評は彼に好意的だったといった現実のほうが、正しいと認められるだろうと信じていた。ヴェルト誌は、彼のシュトルツィングとしての初出演を「芸術家として最高のコンディション」を示していたと書いたが、北バイエルン・クリーア誌には次のように書かれていた。
「ペーター・ホフマンのシュトルツィング役はバイロイトでは初めての配役だった。ペーター・ホフマンがこの若い騎士役でまばゆいばかりの人物像を描き出すだろうことが期待されていたことは間違いなかった。だれにしろ、一見して難しい高いA音がたくさんあることで有名なこの役に自信満々ではありえない。それにもかかわらず、ホフマンは、テノールの英雄であることを証明し、この役を立派に歌いきった。 彼の強いトレモロを伴ったバリトン気味な声には、かつてのような安定性はなかった。しかし、うまくコントロールすることによって、効果的にやり遂げることができた。 靴屋の居間での三連の優勝の歌とお祭りが行われた草地での優勝の歌の盛り上がりは、表現力にあふれ、雄大だったし、その力強さは、一、二幕で、ホフマンがこの役のアウトサイダー性を強調して扱っていたことに対応していた」
もしこの公演の録音を聴くことができれば、ペーター・ホフマンの声に関する「強いトレモロ」とか「安定性」の欠如などという評論家の評価を自分で聴いて理解することができるかもしれないが、残念なことにレコードはないので、当然ながら、確かめるすべはない。





