オペラ歌手でロック歌手-2 [2003年刊伝記]
オペラ歌手でロック歌手に、矛盾なし ・・・2
いまだかってないほど沢山のファンレターが来た。オペラを望むものもあれば、ポップスを求めるものもあった。『ロック・クラシック』に続くレコードに対する希望や、ドイツ語によるポピュラー音楽のレコードを期待するもの、同時にテレビ出演に関する問い合わせ等々、様々な内容だった。ジャーナリストたちは私に何故、オペラというオリンポス山の頂きから、ポップスという低地におりるのかと質問し、私は決して山の頂きから転落したとは感じていないし、同時に『オペラのテノールとロックシンガー』であることが矛盾しているとは思わないと、繰返し説明した。そうまでして多少の金を余分に稼ぎたいのかと非難する者もいた。こういう人には、私にとってこの音楽は楽しいことで、だれもこのような成功をもたらすことなど予想できなかったと、説明した。計画中のロックの演奏旅行に関しては、突然二つになった仕事は、厳密に区別するべきだという立場を堅持した。私としてはこれまで同様、絶対的に大きな情熱は、ポピュラー音楽ではなく、オペラに対して持っているのだから、オペラの舞台で、声に関しても、演技に関しても、今以上に、更に良い状態を示したいと望んでいた。私はオペラが今までと同様大好きだが、ロック・ミュージックは楽しい。私は演出家や指揮者に指示されることなく、創造的になれるし、歌いたいように歌うことができるし、思いのままにリズムに身を任せる喜びを味わうことができた。それに今はもうロックなしで済ませたくはない。クラシック音楽とポピュラー音楽の両方をこれからも続けていきたいなら、両者を厳格に区別するべきことは明白である。つまり、一定期間は、演奏旅行にしろレコード録音にしろ、オペラのような響きにならないように、前もって声をその音楽に合わせておかなければならないから、そのための準備期間も含めて、ポピュラー音楽だけをする。その後は再び切り替え期間だ。ここでは、オペラの舞台でベストを尽くすために、クラシックの歌唱に集中する。二種類の音楽を混ぜ合わせたいとは思わない。私はそのときどきの『二つの仕事』に、つまり、そのときにたずさわっている方にいつも完全に没頭している。『ロック・クラシック』のレコードのあとで、バイロイトでのパルジファルに対する批評がすばらしい結果になって、いままでよりもよいとさえ言われたとき、私にとって、それはいわば御墨付きであった。
しかし、それ以上に、頭を横に振ってあきれるしかないような状況もあった。例えば、ある評論家は、カラヤンとのレコード録音の『パルジファル』について、私の歌唱には声に関する問題がききとれるが、それは『ロックの叫び声』に起因することは疑う余地がないと書いた。もっともこの評論家は、この録音は確かに『ロック・クラシック』のあと、発売されたのだが、そのずっと前に録音されており、しかもその時期に私は、ロックミュージックのことを考えることさえもまったくなかったし、ましてや歌うなどはとんでもないことだったということに気がついていなかったようだ。」
「クラシック」関係者からはペーター・ホフマンのダブルキャリアに対する批判は全くきかれなかった。1983年にバイロイトで指揮したジェームズ・レヴァインは、ポップスを歌ったパルジファルの声に関する成長について確信に満ちた意見を述べた。
「ペーターがロックンロールを歌うことに関して言えば、彼の声楽的テクニックはすでに成熟しているので、声が損なわれるということはまずありえないと思う。疲れたら、マイクを使って歌えるし、拒否することもできる。どのように成長しているのかについては、もちろん確かなことはわからない。しかし、目下のところペーターはどこから見ても好ましい状況にあると断言できる。声は成長する。芸術家としての能力も知性も成長する。こういうことがとにかくいつも力を発揮する。彼が何を歌うかはどうでもよいことだ。」
テレビは「ワーグナーを取り囲むロック」という特徴的なタイトルで「複線」歌手、ペーター・ホフマンのポートレートを撮った。オペラ活動の様子や、スタジオでのポップスの録音風景、「ロック・テノール」の私生活などがその内容だった。ロック・アルバムと対照的な企画としては、
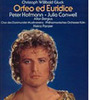 ハインツ・パンツァー指揮、ケルン・フィルハーモニー・オーケストラのグルック作曲『オルフェオとエウリディーチェ』のレコード録音に、ジュリア・コーンウェルと共に参加した。これもまたホフマンの多様性を示している。このオペラでは、それまではあまり望ましくないとされていた豊かな感情表現を、もちろん声によってのみだが、おこなっている。ペーター・ホフマンは、いつも自分自身を概して批判的に扱うのだが、この録音に関しては、自分自身、とても満足しているということだ。彼としてはとびきりの大成功だと考えているそうだ。
ハインツ・パンツァー指揮、ケルン・フィルハーモニー・オーケストラのグルック作曲『オルフェオとエウリディーチェ』のレコード録音に、ジュリア・コーンウェルと共に参加した。これもまたホフマンの多様性を示している。このオペラでは、それまではあまり望ましくないとされていた豊かな感情表現を、もちろん声によってのみだが、おこなっている。ペーター・ホフマンは、いつも自分自身を概して批判的に扱うのだが、この録音に関しては、自分自身、とても満足しているということだ。彼としてはとびきりの大成功だと考えているそうだ。『オーディオ』誌が1984年号で、クラシックの録音を評価して、その結果、演奏のランク付けを行っている。ペーター・ホフマンは、31.6%の優秀な声楽ソリスト・リストの第一位にあがっている。このような評価は心理的葛藤をもたらすことだ。確かに自尊心をくすぐり心地よく響くが、一方、永久に最高業績をあげる義務を課せられることでもある。
1984年2月10日は、ベルリン・ドイツ・オペラでの、ジャン・ピエール・ポネルの印象的な演出による『フィデリオ』の初日だった。指揮はダニエル・バレンボイムで、レオノーレはカタリーナ・リゲンツァ、ペーター・ホフマンはフロレスタン役を歌った。この公演のあとのように、評論家が全員一致で肯定的な結果を出すことは珍しい。ペーター・ホフマンは、不可能なことを成し遂げたに等しいほどの上出来だった。透明感のある表現力に富んだ声で歌いながら、そして、それにもかかわらず、地下牢に一人寂しく、飢えて、死を間近にした人が、横たわっていることを、納得させるに足るものだった。とても濃い化粧をしていたので、よく見ても最初は彼だとわからなかったほどだ。この『フィデリオ』については、オペラの初日などいつもは言及する価値はないと考えている大衆紙でさえ、熱狂的に書きたてた。続いて、ザルツブルグ音楽祭におけるヘルベルト・フォン・カラヤン指揮による『ローエングリン』が、同様の肯定的反響を得た。
 その後、ペーター・ホフマンの胸の中で、もう一方の「心」が再びふくらんでいって、二番目のポップスのレコードである「ペーター・ホフマン2」を録音したが、その中の「アイボリー・マン」は、とりわけ彼自身のアイデアに基づいたミニ・ミュージカルとでもいったものであった。その後、ハンブルクからウィーンまで、20以上の都市を巡る、最初のロック・ツアー「バンドとオーケストラによるペーター・ホフマン 1984年」がスタートした。ライブの伴奏は、フリッツ・ホフマンが、ヴェルツブルクのコンサートを聴いてから、クリス・デ・ブルクのバンドと契約を結んだ。ペーター・ホフマンは、このツアーのプログラムの冒頭で、彼のオペラとポップスという二つの世界間の往復が引き起こすいらだちに対する回答を述べている。
その後、ペーター・ホフマンの胸の中で、もう一方の「心」が再びふくらんでいって、二番目のポップスのレコードである「ペーター・ホフマン2」を録音したが、その中の「アイボリー・マン」は、とりわけ彼自身のアイデアに基づいたミニ・ミュージカルとでもいったものであった。その後、ハンブルクからウィーンまで、20以上の都市を巡る、最初のロック・ツアー「バンドとオーケストラによるペーター・ホフマン 1984年」がスタートした。ライブの伴奏は、フリッツ・ホフマンが、ヴェルツブルクのコンサートを聴いてから、クリス・デ・ブルクのバンドと契約を結んだ。ペーター・ホフマンは、このツアーのプログラムの冒頭で、彼のオペラとポップスという二つの世界間の往復が引き起こすいらだちに対する回答を述べている。「オペラ歌手としての私を見たい人は、オペラに行くべきである。全く異なった傾向をもつ音楽のどちらを選ぶかは、気分次第というのは、わかりきったことだと思う。私も、年がら年中ベートーベンを聴きたい気分でもないのと同様、時にはローリングストーンズのビートは我慢できないと感じることもある。みなさんが私の音楽に合った気分でコンサートにきてくださることを願っている。いずれにしても、音楽のない生活は我慢できないのではないだろうか」
それでも、明らかに別のものを期待していたらしい客もいた。彼らは、ポスターに書いてあった「バンドと・・」という言葉を見落としたにちがいないのだが、舞台上からは見落としようがないほど、その場の雰囲気から浮いていた。
「私は一列目の席に宝石のアクセサリーをつけたイブニングドレス姿の客やタキシードを着た客が数人いるのに気がついた。どうみてもポップスのコンサートを期待しているようには見えなかった。はじめの『ツァラストウストラはかく語りき』の響きが鳴りやんで、私が『朝日のあたる家』を歌いはじめると、彼らがショックを受けた目つきになって、いきなり立ち上がり、ホールを去っていくのが目に入った。舞台上の私たちにとっては、非常に意欲をかきたてられる状況だった。私はその出来事をユーモアで受け止めようと、今からは全てのドアは外側から鍵をかけさせてもらうことにするので、ひょっとしてまだ立ち去りたい人がいないかどうか質問した。けれども、もう誰も出ていこうとはしなかったし、この晩だけでなく、そのあともずっと、私も聴衆もほんとうに楽しかった。15万人以上の観客がこのコンサートを訪れ、大いに楽しんだ。ドイツ第二テレビ放送(ZDF)がコンサートのひとつを録画して6月に放送することになった。そうこうするうちにアルバム『ペーター・ホフマン2』が、チャートで第6位にのり、ゴールドになった。
ツアーの成功で、引き続きこの道を進むという点において、私は意を強くした。どのみち私のポピュラー音楽はすでにある意味で一人立ちしていて、実際のところもはや止められない状況だった。私のところにもレコード会社にも、新しい録音についての問い合わせが山のようだったが、私たちはそういう希望に早急に応じることはとてもできなかった。それにしても、ジャーナリストたちは、相変わらず私の声はポピュラー音楽を歌うには、やはり大きすぎるのに、何故そういうことをするのかと、しつこく質問するのをやめなかった。それに対して、私はそのようには考えていないのだと答えた。いずれにせよロックやポピュラー音楽では、マイクを使うのだから、声の大きさは絶対条件ではない。声が小さければ、技術者が大きくするし、声が大きければ、これも技術者が適正に音量を調節するのだ。適正な調節を遂行することだけが重要なのだ。それとは逆に、オペラの舞台では、せっかくの最高の声もほとんど聞こえないようでは、役に立たないのだから、まず第一に声の美しさと並んで、個性的な声の魅力を引出すためには、声の大きさが重要なのだ。クラシックの分野には、すばらしく美しいが、舞台で歌うには小さいという声の歌手も多いが、その場合、レコードで歌ったり、映画で演奏したりしている。私はオペラが好きだが、この分野では格別創造的なことはできないという感じがしている。もちろん演技や歌唱において十分に個性を発揮することはできるが、私の前に、すでに何百人もの人が歌ってきたことを、指揮者や演出家が望むように歌わなければならない。ポップスの舞台ならすべて私が望むように形作られるのがすばらしい。バンドが何をどう演奏するか、舞台装置、照明、私の身振り等々、全部、自分で決める。そして私が好きなアルバムを収録する場合、その中で、例えば、『アイボリー・マン』でのように、いくつかのアイデアを実現することもできる。そして、ツアーで成功すれば、再びオペラの仕事に、一生懸命、情熱的に取り組みたいという気持ちになる。
もうひとつ頻繁に質問されたのは、声のために不安を感じたことはないのかということである。その点に関してちょっと振り返ってみると、およそ歌手ならだれでも声に関して不安を抱えているものだが、私はそのことを表に出さなかった。とりわけ自分にそういう不安をあえて吹き込まないようにしていた。クラシック音楽か、ポピュラー音楽かは関係ない。『トリスタン』はいつも声にとっては難儀な役だが、それに対して、マイクを使って歌われ、自分の判断で声の音量を絞ることができるポピュラー音楽は害があるなど、全くあり得ないことだ。しかし、どちらの場合も気管支炎にはなりうる。不安があるから、そう思い込むのだと思う。リューベックで新人としてタミーノを歌わないわけにはいかなかったときは、一週間病気だったが、かまわずやり遂げた。こういうわけで、さあ、もう余分なことは考えず、舞台に立って、とにかく歌うのだと自分自身に言い聞かせたら、うまくいった。まさに心理的なものだ。当然のことだが、ウィルス性の気管支炎にかかって、声帯が炎症をおこしたら、どんな歌手でも、舞台に立つことは、ほとんど無理か、絶対不可能だと思う。出演が『ほとんど』不可能な状態の場合は、歌うべきか否かの決定は大問題だ。歌ったら、必然的にいつものようには歌えなくて、観客を大いにがっかりさせたうえ、評論家は容赦のない攻撃に出る。キャンセルした場合も、事態は実際まったく変わらない。私はこういう状況で、たびたび歌って、何と言っても自分が望むように歌えなくて、あとになって後悔した。声帯はその負担でますます炎症がひどくなっているというわけで、さらにひどく傷ついた。ショルティ指揮による『フィデリオ』の録音も、数回の上演も、気管支炎じゃなかったら、もっとよくできていただろう。加えて、気管支炎が慢性化して、決断が鈍ることもある。こういうことはけっこうよくある。今までで、一番大変だったのは、ワーグナーの演奏旅行を病気のために全部キャンセルして、しばらく入院しなければならなかったときだ。会場は借りてあって、全席完売で、オーケストラとも契約済み、とんでもない事態だった。歌手もまたまさしくただの人間だということだ。」
追加コンサート付きのロック・ツアーが成功のうちに終了したあと、ペーター・ホフマンは再びオペラの仕事に戻った。彼のカレンダーは予定がいっぱいだった。
 秋には、ベルリン・ドイツ・オペラで、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ワルキューレ』が予定されていたし、続いて12月にはチューリッヒ歌劇場の再開で、『ニュールンベルクのマイスタージンガー』のシュトルツィング役としてデビューすることになっていた。12月2日のプレミエの直前に、ペーター・ホフマンは、出演が考えられないほどひどく足を捻挫してしまった。ルネ・コロが代役を務めたが、その後、やっと12月23日に、彼にとって一番好きな役になったシュトルツィング役を演じることができた。
秋には、ベルリン・ドイツ・オペラで、ゲッツ・フリードリヒ演出の『ワルキューレ』が予定されていたし、続いて12月にはチューリッヒ歌劇場の再開で、『ニュールンベルクのマイスタージンガー』のシュトルツィング役としてデビューすることになっていた。12月2日のプレミエの直前に、ペーター・ホフマンは、出演が考えられないほどひどく足を捻挫してしまった。ルネ・コロが代役を務めたが、その後、やっと12月23日に、彼にとって一番好きな役になったシュトルツィング役を演じることができた。1985年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場にローエングリンで出演した。相手役のエルザはエヴァ・マルトンだった。公演はビデオ録画されたが、残念なことに、アメリカでしか発売されなかった。
 ズービン・メータの指揮で、エヴァ・マルトン、マルティ・タルヴェラ、ニューヨーク・フィルハーモニー・オーケストラと共に『ワルキューレ』の第一幕のCD録音もした。続いて夏には、バイロイトでのジェームズ・レヴァイン指揮による1982年の『パルジファル』の再演があったが、今回はこのオペラもレコードとCDに収録されることになった。サイモン・エステスが感銘深いアンフォルタスを歌い、マッティ・サルミネンがティトウレル、ほんとうに何度もペーター・ホフマンのパルジファルのグレネマンツを歌ったおなじみのハンス・ゾーティンが今回も同じ役を歌い、ワルトラウト・マイアーが刺激的なクンドリを演じた。
ズービン・メータの指揮で、エヴァ・マルトン、マルティ・タルヴェラ、ニューヨーク・フィルハーモニー・オーケストラと共に『ワルキューレ』の第一幕のCD録音もした。続いて夏には、バイロイトでのジェームズ・レヴァイン指揮による1982年の『パルジファル』の再演があったが、今回はこのオペラもレコードとCDに収録されることになった。サイモン・エステスが感銘深いアンフォルタスを歌い、マッティ・サルミネンがティトウレル、ほんとうに何度もペーター・ホフマンのパルジファルのグレネマンツを歌ったおなじみのハンス・ゾーティンが今回も同じ役を歌い、ワルトラウト・マイアーが刺激的なクンドリを演じた。ポップスの分野では、今度はドイツ語の新曲による新しいアルバムが「ペーター・ホフマン2」の後に続いた。
 「ファンレターには、ドイツ語の歌によるポピュラー・アルバムを希望する意見が、沢山あった。良い考えだと思った。なんといっても私はドイツ人なのだから、自分の母国語で何かしてはいけないという法はないわけだ。良いチームを組んで、情感にあふれた歌を作り、『我らの時代 UNSRE ZEIT』を録音した」
「ファンレターには、ドイツ語の歌によるポピュラー・アルバムを希望する意見が、沢山あった。良い考えだと思った。なんといっても私はドイツ人なのだから、自分の母国語で何かしてはいけないという法はないわけだ。良いチームを組んで、情感にあふれた歌を作り、『我らの時代 UNSRE ZEIT』を録音した」ドイツ語の歌詞はだれもが好むというものではなかったにもかかわらず、『我らの時代』は成功で、すぐにヒット・チャートにのり、間もなく「ゴールド」を獲得した。ペーター・ホフマンは、当時フランク・エルストナーが司会していた番組「それに賭けろ」をはじめ、多くのテレビ番組で、このアルバムを紹介することができた。ちなみに、賭けに負けたら、その結果、賭け親は結婚式で歌わなければならないことになっていた。彼は教会でのある結婚式でヘンデルの「ラルゴ」を歌って、この賭けの責任を果した。『我らの時代』に最初の二つのロック・アルバムを合わせたものが、ドイツ、オーストリアを巡る1986年の2月と3月のツアーの土台だった。数曲が爆発的にヒットしたことで、気分はますます盛り上がって、この企画は完璧になった。ウィーンでのコンサートはビデオ撮りされ、更にニ枚組のCDに録音された。
5月には、ヴィスバーデンの五月祭でジークムントを歌った。その後、ニューヨークでローエングリン、それから、ジャニーヌ・アルトマイヤーのイゾルデ、ダニエル・バレンボイム指揮の『トリスタンとイゾルデ』の練習のために、バイロイトへ行った。これは、ジャン・ピエール・ポネルによる1981年の演出に手を入れ、より洗練されての再演というものだった。
「プレミエ以前にすでにいくつかの混乱があった。爆破予告があったため祝祭劇場の警備が強化されていたし、私の事務所には、ロックを歌ったという理由で、私に容赦ないブーイングを浴びせるという脅迫があった。陰鬱な『トリスタン』をやるには、全然ふさわしいとは言えないにぎやかな状況だった。
ポネルの演出にはまえまえからとても興味があった。評論家は、ポネルの演出は確かに『イメージに耽溺しすぎている』し、心理的洞察より視覚的表現のほうを、演劇的な感覚より美しいイメージを追求していると、非難していたが、しかし、トリスタンの死に際して、イゾルデの幻覚だけが現れるというのは、それでもワーグナーの意図に近いものは保たれており、舞台上でもとりあえず表現されていた。私としてはそれなりに魅力的な演出だった。あとで公演の写真を見たとき、想像した通り、トリスタンの放心状態、高熱による幻覚が同じようにはっきりと伝わってきた。私としては大きな満足感を味わった上演だった」
ペーター・ホフマンは声の調子も良かった。ミュンヘンの新聞は次のように書いた。
「ペーター・ホフマンは、あらゆる悲観的な予測にもかかわらず、上演の夜を粉砕しかねないほどに懸念された役を、驚嘆に値する調子の良さで乗り切った。彼は実に美しく叙情的な方向を示しており、三幕における安定した声には、唖然とさせられた」
それでも、観客の中の、あの一派はペーター・ホフマンがポップスをやるという「逸脱行為」を断念しようとしないことで、気分を害していることを表明した。
「二、三人がブーイングをした。それよりもたくさんの、足を踏みならし『ブラボー』と叫んでの拍手喝采がそれに応じたが、例のグループは、脅迫をやめなかった。ロック・ミュージックが好きじゃない人は、それを聴く必要はないのだが、脅しによって、私に何か強制しようという試みは、どう見積もっても私に対しては逆効果でしかないと思う。『ブーイング』がすばらしい間奏曲になることもありうるのだが、あの時はそうは思えなかった。それは、1987年に、再びバイロイトでトリスタン役を歌ったときのことだが、初日には、胃の具合が相当悪かった。しかし、身体をコントロールすることはスポーツマン時代にすでに重要な事だったし、歌手にとっても不可欠である。私は自分の職業を実際このようにとらえていた。だから、完全に気分の悪い状態だったにもかかわらずトリスタン役をやり通した。とは言え、なかなか良い出来だったと思う。しかし、最後の音が消えたときはさすがにもう我慢できず、何も考えずに舞台から駆け去ったので、終わりのカーテンコールには出なかった。ヴォルフガング・ワーグナーが幕の前に出て、私に代わって観客に謝罪してくれた結果、私には大きな拍手がおくられた。ところが、おそらくその説明を信じなかったのだろうが、ブーイングも多少あった。相当に奇妙なことだった。
1986年の初日に引き続いて行われたパーティーで、リヒャルト・フォン・ヴァイゼッカーとハンス・ディートリッヒ・ゲンシャーによる興味深い対談があった。ところで、私の隣はフランツ・ジョセフ・シュトラウスだった。『バイエルン人』は大昔から広い視野も持ち、多趣味だったのはまちがいないけれども、そこにはワーグナーの音楽は含まれていなかった。シュトラウス氏は、まずは、その点について、『ホフマンさん、言いにくいのですが、私はオペラのことには全くうとくて、そもそもオペラは全然わからないんですよ』と謝った。そこで、私が、別の話題もたくさんありますからご心配なくと言ったら、緊張がほぐれた。この時から、彼は、公認といった感じで、嫌いな会話に巻込まれないように、あらゆる機会を利用して、私の隣に座った」
一部のマスコミは、言うまでもなく1987年のペーター・ホフマンの初日の不運についてセンセーショナルに報道した。ロックを歌った結果、もうすぐ声がだめになるだろうというせっかちな予測がなされた。彼は何度もこういう主張に基づいたインタビューに直面させられた。かなり挑発的なやり方で行われることも全然めずらしいことではなかった。次の公演で彼が絶好調を示したことには、ゴシップ記者たちはまったく興味を示さなかった。
 ペーター・ホフマンはポピュラー音楽をやめて、彼のそういうイメージを全面的に払拭するつもりがないことを、『ロック・クラシック2』を出すことによって、表明した。このことは、クラシック・ファンの中の「原理主義者」を激怒させた。このCDは1986年の秋に録音され、1987年春に発売された。これは最初の『ロック・クラシック』と直接関連しており、すばらしいロックとポップスの歌が含まれていた。例えば、ジョン・マイルズの『音楽、これこそ初恋の人』とか、バリー・マニロウの『マンディ』などと、そのほかにあまり知られていない歌が数曲というところだが、最初の『ロック・クラシック』に入っている曲と同様に美しい。なかでもプロコル・ハールムの雄大なロック・バラード『しょっぱい犬』は、その編曲とペーター・ホフマンによる感動的な歌唱に関して言えば、珠玉のすばらしさである。伴奏はロンドン・シンフォニー・オーケストラと一流のスタジオミュージシャンから成るロックバンドが引き受けている。3月には「クラシック音楽」に向い、ハンブルクで『パルジファル』、その後、7月にはヴェネチアで『ローエングリン』だった。8月には、すでに述べたように、バイロイト音楽祭での『トリスタン』が加わった。
ペーター・ホフマンはポピュラー音楽をやめて、彼のそういうイメージを全面的に払拭するつもりがないことを、『ロック・クラシック2』を出すことによって、表明した。このことは、クラシック・ファンの中の「原理主義者」を激怒させた。このCDは1986年の秋に録音され、1987年春に発売された。これは最初の『ロック・クラシック』と直接関連しており、すばらしいロックとポップスの歌が含まれていた。例えば、ジョン・マイルズの『音楽、これこそ初恋の人』とか、バリー・マニロウの『マンディ』などと、そのほかにあまり知られていない歌が数曲というところだが、最初の『ロック・クラシック』に入っている曲と同様に美しい。なかでもプロコル・ハールムの雄大なロック・バラード『しょっぱい犬』は、その編曲とペーター・ホフマンによる感動的な歌唱に関して言えば、珠玉のすばらしさである。伴奏はロンドン・シンフォニー・オーケストラと一流のスタジオミュージシャンから成るロックバンドが引き受けている。3月には「クラシック音楽」に向い、ハンブルクで『パルジファル』、その後、7月にはヴェネチアで『ローエングリン』だった。8月には、すでに述べたように、バイロイト音楽祭での『トリスタン』が加わった。合間には、いくつかの慈善ガラ・コンサートがあった。その一部はテレビ録画された。ミュンヘンでのエイズ・ガラ・コンサートとバイエルン国立歌劇場でのマリアンネ・シュトラウス財団のための慈善ガラ・コンサートは特筆に値する。大勢の有名なポピュラー歌手と共に「援助の手」プロジェクトにも出演した。「ようこそ、ミュンヘンへ、映像による夢の都市レビュー」と題する記念番組では、ルートヴィッヒ二世の写真が挿入されたあと、『ローエングリン』からグラール物語を歌った。
秋には50回を超えるコンサートから成る三度目のロック・ツアーが準備されていた。今回は東ドイツの東ベルリン、ドレスデン、それから、かつてのケムニッツ、そして現在はまた再びケムニッツに戻った、当時のカール・マルクス・シュタットで、6回の公演を行う予定だった。
「東ドイツでのポピュラー・コンサートは、西ドイツの芸術家としては、そのときまでは、ペーター・マッファイとウード・リンデンベルクしか許可されたことはなかった。まさに微に入り細に入り、一から十まで、事こまかな計画がたてられた。まず東ベルリンの東ドイツ芸術家エージェントが作成した申請書を用意しなくてはならなかった。その際、完全な歌詞を添えて、演奏予定の歌をいちいち全部提出しなくてはならなかった。報酬は3分の2は東ドイツ・マルクで、3分の1は西ドイツ・マルクで支払われるのだが、いったい東の金をどうしろというのだろう。アメリカ人のバンドと関係者にそんなことは言えなかった。どこにもそんな金を使えるところはないのだから、西の金で支払うしかない。私たちはすばらしい妥協案を見つけた。私たちは、14日間、ズールで無料で自由に使える練習用のホールとホテルの部屋を提供されていた。そこで、私たちは無料の練習コンサートを追加した。この14日間は注目に値するものになった。東ドイツの組織力と世話焼き振りは二度と体験できないほど比類のないものだった。理由は簡単だ。ここには金はなかったが、雇われるべき人間は十分すぎるほどいるのだった。技術者、例えば、電気技師が一人必要になった時には、すぐにいつでも使える人が5人も待機していたし、椅子が数脚欲しかった時には、すぐに会社をあげて手伝いにきてくれた。ホールは昼夜を問わず保安部隊によって監視されていて、保安部隊がそこにいることが可能な限り、どんな希望も彼らの目に留まるのだった。要するに、『西側の人間』に良い印象を与えたいわけだ。ただし、東ドイツの基準から逸脱することを決定せざるをえない場合は、厄介なことになった。そうなると階級制度の序列に従って、次々と上の人にお伺いを立てることになる。
ある日、長い練習の日々が続いたあと、ホテルの中にあるディスコに行こうとしたとき、入口にネクタイ、スーツ姿で立っていたドア係りが私たちの入場を拒否した。ジーンズにスニーカー、おまけにネクタイもしていない私たちは、全くとんでもないことだというわけで、中へ入ることを許されなかった。延々と、無益な議論をしたあげく、結局私たちはほかの服の持ち合わせがないのだから仕方がないということで、最終的には、ホテルの女性支配人が姿を現して、入場を許可するように配慮してくれた。この瞬間から、ドア係りまでがまるで人が変わったようで、意見の相違など何もなかったみたいに、私たちに対して好意的で丁寧な態度をとった。中では、もとは白かったのだろうが、変色して黄ばんだ背広を着たバンドが行儀のよい娯楽音楽を演奏していた。私たちは彼らに、一曲演奏したいので、楽器を貸してほしいと頼んだ。『一曲ですか。アメリカ人に楽器を貸すのですか』と、まずは不信感丸出しだったが、しだいにそれは消えて、何が演奏されるのか興味津々になった。まさに思うつぼだった。ドラマーだけは、高価なバチが折れたときには、相当なショックを受けたが、私たちのドラマーのジェフはいつも荷物を全部持ち歩いていたので、速攻で気前良く変わりの品を調達できた。私たちはディスコに人々を招待して、東の金を気楽につかってしまった。それ以外にその金でするべきことはなかった。もちろんバンドのメンバーのために楽器をいくつか買ったが、それもまた私たちのためではなかった。マイセンの陶磁器も、ヨットやトラバントの車も欲しくなかった。むしろトラクターのほうが頭に浮かんだ。それなら、ひょっとしたら、オーバープファルツの近所の農家のお土産にしたら、喜んでくれるかもしれないと思ったのだが、巨大な怪物のようなものを提供してもらうのは、私たちの意に完全に反していた。
東ベルリンのフリードリヒ宮殿で開催された最初のコンサートはとても奇妙な雰囲気だった。最前列には、無感動で厳格な体制派の党員が無表情で座っていた。その後ろで熱狂した観客が拍手喝采していた。私は舞台から歯に衣を着せず、『本当にいったい何を怒っていらっしゃるのですか。私が何か間違ったことをしましたか』と前の席の人々に向って大声で言った。やはり反応はなかった。彼らは自由で気楽な雰囲気はとにかく好きじゃなかったのだ。ドレスデンでもやはり同じようだった。ドレスデンは『外が見えない谷』と呼ばれていた。というのは、ドレスデンでは、ものすごく高いアンテナを建てなければ西側のテレビを受信することができなかったからだ。私たちのコンサートの直前に、ヘルムート・コールとエーリッヒ・ホーネッカーの会談が行われた。そこで、あいさつの後、いい機会だと思ったので、『私たちの首相であるヘルムートとエーリッヒの直接会談があったわけですが、これによってそのうちに何らかの良い結果がもたらされることを希望しています。ここ、『外が見えない谷』で、私が皆さんに望むことは、いつかここにも光が差し込むこと、そして、もうひとつ、巨大なアンテナが建設されることです』と言った。メッセージは観客に届いた。突然想像できないほどの歓声がわき起こったが、前の方の数列に陣取った人々だけは、あいかわらず妙な具合に顔をしかめ、口をへの字に結んでいた。コンサートの終わりには、いつもバーンスタイン作曲の『サムウェア』を歌ったが、この日の公演ではいつもとは違う意味があった。この『私たちの場所がある。どこかに私たちのための場所がある』という歌詞は、状況にぴったりだった。私はほとんど自分自身に向かって心を込めて歌った。この公演は、感情が爆発し、ものすごく気分が高揚した。
一日後、かつての『カール・マルクス・シュタット』で、私は『こんにちは。ケムニッツの皆さん』と観客にあいさつした。この時はほんとにすごかった。最前列を氷のように冷たい沈黙が支配したが、その後ろの盛り上がりかたはまさに爆発的で、この雰囲気はどのコンサートでも変わらなかった。東ドイツの人々にとって、このようなコンサートは珍しかったので、あきらかに楽しんでくれているのがはっきりとわかった。このツアーには、ギュンター・エマーリッヒの番組『ショーコラーデ』をはじめ、様々なテレビ出演が加わった。
このマンモス・ツアーでは、『従来の』ドイツ連邦州はもちろん、そのほかに、オーストリア、スイス、ルクセンブルグもまわった。私たちはいたるところで熱狂的な観客に出会った。とにかく楽しかった。
チケットは完売、すばらしい観客と山のようなファンレターと共に、私におおきな喜びをたくさんもたらしてくれた三ヶ月にわたるポップス・ツアーのあと、私はうれしい気持ちで再びオペラの仕事に戻った。 それは1988年の春、ボンの『マイスタージンガー』で始まった。そのあと、ニューヨークで『ジークフリート』を初めて歌う予定だったが、ひどい気管支炎のため、残念ながらキャンセルせざるをえなかった。このことは当然マスコミのかっこうのえじきになった。そこには、様々な言い方だったが、要するに『今度こそ、くだらないロックなどを歌ったせいで、声が完全にだめになってしまったのだ』と、書かれていた。それならば『マイスタージンガー』も歌えなかったはずだということは、議論にならなかった。今度もまた、記事ねたを手に入れたということが肝心だったわけだ。」
ペーター・ホフマンはマスコミのセンセーショナルな扱いに冷静さを失わず、いつものように最後には、たとえば、この夏にはバイロイトで、ジークムントとパルジファルに加えて、バイロイトでは初役である『マイスタージンガー』のワルター・フォン・シュトルツィングの三つの役を歌ったのだが、この時も批評は彼に好意的だったといった現実のほうが、正しいと認められるだろうと信じていた。ヴェルト誌は、彼のシュトルツィングとしての初出演を「芸術家として最高のコンディション」を示していたと書いたが、北バイエルン・クリーア誌には次のように書かれていた。
「ペーター・ホフマンのシュトルツィング役はバイロイトでは初めての配役だった。ペーター・ホフマンがこの若い騎士役でまばゆいばかりの人物像を描き出すだろうことが期待されていたことは間違いなかった。だれにしろ、一見して難しい高いA音がたくさんあることで有名なこの役に自信満々ではありえない。それにもかかわらず、ホフマンは、テノールの英雄であることを証明し、この役を立派に歌いきった。 彼の強いトレモロを伴ったバリトン気味な声には、かつてのような安定性はなかった。しかし、うまくコントロールすることによって、効果的にやり遂げることができた。 靴屋の居間での三連の優勝の歌とお祭りが行われた草地での優勝の歌の盛り上がりは、表現力にあふれ、雄大だったし、その力強さは、一、二幕で、ホフマンがこの役のアウトサイダー性を強調して扱っていたことに対応していた」
もしこの公演の録音を聴くことができれば、ペーター・ホフマンの声に関する「強いトレモロ」とか「安定性」の欠如などという評論家の評価を自分で聴いて理解することができるかもしれないが、残念なことにレコードはないので、当然ながら、確かめるすべはない。




コメント 0